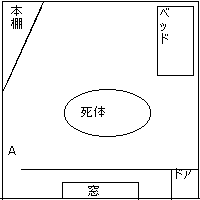Mの悲劇
序
戦国大名、例えば織田信長は野心を持って京へ向かった。シェークスピアの戯曲「マクベス」も様々な汚い手を使って王にのし上がった。さて、今回お話する私が遭遇した事件も金、そして地位を巡る事件である。ちなみに、もう「Hの悲劇」を読んでいる読者はお解り頂けると思うが「マクベス」のMである。
FILE1、懐かしの人
「先輩!」
私は得意先回りの帰りに誰かに呼ばれた。振り向くとそこには十八才位だろうか?背が私よりも幾分低い女性が立っていた。
「えーと・・・」
私は記憶を辿った。しかし、思い出せない。
「また名前、忘れてますね?」
クスッと笑いながら言う。
「ごめんごめん」
私は苦笑しながら謝った。私は人の名前を覚えるのが苦手で、社員の名前もいちいち名前を確認してから用事を頼む事がしばしばある。良くも悪くも個性的な顔ならすぐに覚えられるのだが。
そのためにオフ会で事前に写真送ってもらったにも関わらず名前を訊いたため嫌われてしまった、という苦い経験もあった。
「南川です、今度逢う時にはちゃんと覚えておいて下さいね」
私は名前を言われた途端、急に懐かしいと言う思いが込み上げてきた。
「はい・・・」
「もう。先輩、驚いちゃいましたよ。別に成績も悪くなかったのに急に自主退学しちゃうんですもの」
「ああ・・・」
と言って親友が死ぬと言う忌まわしい事件を思い出し、心苦しくなった。その雰囲気に気付いたのか、機転の利く後輩は話題を変えた。
「あっ、おめでとうって言って下さい。私、婚約してるんです」
「ほう!」
「結婚式、出て下さいね」
と言って招待状を渡された。私は驚いた。まさか彼女が若干十九才で結婚するとは!私のオンラインの友人には十八才で彼氏と同棲すると言う子もいるが、そのことを聞かされた時と同じ位驚いた。
そしてその後に心から、
「おめでとう。」
彼女は私に祝福されたのがよほど嬉しかったのだろう。満面の笑みをたたえた。
「ありがとうございます!」
「それにしても」
私は歩きながら言った。
「まさか結婚するとはねぇ」
「ええ、招待状差し上げようと思ったのですが先輩の住所、解らなくって」
私は苦笑しただけで何も言わなかった。
「でも、君をもらう幸せなロミオは誰なんだい?」
私は道化けて言った。
「ええ、村で一二を争う土地持ちです」
「村?」
私は信じられなくて訊き返した。彼女がそんな大それた所に嫁ぐのもさることながら「村」という単位がまだあるのかということに驚いくのである。
「ええ、東北の辺鄙な村です。コンビニは一軒。バスは一時間に一本・・・」
まるで横溝正史の小説の舞台になりそうな村・・・。私はそう思って苦笑した。
「田舎だと思ってるでしょ?」
「まあね」
私は苦笑した。
「あっそうそう、お願いがあるんですが」
「何?」
「式の一週間前には・・・」
「式っていつ?」
私はあまりの突飛なお願いに訊いた。
「十月三十日です」
「そうすると二十三日からだね?」
「ええ、そうです」
「そりゃ別に好いけど・・・、何だってそんなお願いを・・・」
私は彼女がこれから着るであろうウェディング・ドレスのように白い封筒を差し出された。その封筒から解った事は差出人の名前なし、ただ「南川さくら様」と不自然な程に角ばった字で書かれていた。ちょうど神戸の「酒鬼薔薇事件」のような字体と言えばお解り頂けるだろう。
「これです」
と言う彼女の声が幾分震えていたような気がしたのは気のせいだろうか。
「開けてもいい?」
「はい」
奇妙な緊張。私は彼女の顔色をさり気なくうかがったが強張っている。封筒の封は一回切られており、私に見せるためにセロテープで繋いだのだろう。
「解る事は何かありますか?」
「おいおい、ぼくは魔法使いじゃないんだよ?これから解る事は精々君がこれに怯え、慌てて封をしたと言う事位だろうね。」
私は言いながら封筒の手紙を取り出した。
とてもここには書き表す事のできない、誹謗、中傷、そして卑猥な文句が書き連ねてある。いや、読者諸君のためにも書き記さない方が気分を害さず、いいだろう。放送禁止用語が平気で書かれているのだから。
私は怒りのあまり、
「これは酷い!」
私はどんな女性でも守るべき存在であると言う古風な考え方の持ち主なので、こう言う被害があると酷く頭にくる。誤解されると困るので、一応書いておくが「女性に優しく」というのは下心でしているのでは決してない。
「それで、婚約者の反応は?」
私は怒りを抑えて尋ねた。冷静にならなければ真実はつかめないのである。
「『心配する事はない。』と」
「ほう、それで行くんだね?」
「ええ」
その声には力強さがこもっていた。
「それで、ぼくは何をすればいいの?」
「ただ私の村へ来て、屋敷に泊まってくれさえすれば安心です」
(まだ、彼女はぼくの事を・・・。まさかね)
と言う考えを振り払った。実は私が高校を止める直前、彼女と一緒に遊園地へ行った事があるのだ。もっとも、その時私は友達として行ったのだが、今から思えば私のことが・・・。
いや、昔はどうだが知らないが少なくとも今、彼女には婚約者がいる。だから、私の役にも立たない能力を尊敬の念でしか見ておらず、「愛」と言う文字はない事は確かである。それも寂しい気はしないでもないのだが、仕方のない事と思って諦めよう。
犯罪が絡めば別だが、そう言う事を訊ける程、私は鈍感ではない。この際、萌ちゃんにも来てもらうか。手伝ってくれそうだし。平日は学校があるから帰ってもらって、土日にはもしよかったら来てもらうという形でいいだろう。
「ねえ、相棒つれてってもいい?」
と私は話を切り出した。
「相棒って?」
「浅香優太知ってるだろ?ぼくと仲良しだった。彼の妹だよ」
「浅香先輩の妹さんですか・・・。いいですよ」
「それで心当たりは?こんな手紙を送られるような」
彼女は首を横に振った。
「そう、か・・・。」
奇妙な沈黙が再びあった。そして、私は、
「あっ、これしばらく預からせてくれない?」
私は例の手紙を少し持ちあげて行った。
「いいですが」
「とにかく、今日は本当におめでとう!」
「ありがとうございます」
彼女とは十月二十三日、名古屋駅の生活倉庫前の噴水で待合せた。私がいつもオフ会の集合場所に指定する所である。
FILE2、晩古村(ばんこむら)
十月二十三日、私と萌ちゃん、そしてかの愛すべき我が後輩、南川さくらとともに新幹線で東北の田舎、晩古村という所に向かった。私は愛用のノートパソコンを持っている。
旅日記、そしていささか不謹慎で南川には悪い事だが何か好奇心を引かれる事件に遭遇するという予感がするのである。
新幹線の中では私は連日の仕事疲れのせいだろうか、ぐっすりと寝入ってしまっていたので何が起こったか解らない。が殺人など大きな事が起こらなかった事は確かである。そう毎回、あったらこっちの身がもたないが。
「着いたよ」
と萌ちゃんに体を揺さぶられて、ようやく夢の世界から目覚めたのだ。
岩手駅から更に電車、バスなどに乗り継ぎ、着いたのは名古屋を出て六時間後の事である。
「ここが晩古村の入口です」
と南川は言った。大きな岩のトンネルを百メーターほど行くと、急に視界が開けた。
「このトンネルが崩れたら、戻れないのね・・・」
「おいおい、縁起でもないこと言うなよ」
私は苦笑しながら「妹」に言った。が、南川さくらの話だと事実、そうらしいのである。
「携帯も圏外・・・」
「妹」は溜息をついて言った。私は苦笑するだけだった。
トンネルを抜けた私たちは今、高台にいるのだが見下ろしているのは実に壮大な眺めである。十字に道が敷かれており、その端には大きな建物がある。むろん、道と言ってもアスファルトで固められた道ではない。
まるでナスカの地上絵のごとく緑のパレットに土色の十字架が描かれている。と書けばどんな方でも想像できるだろうか。
(外界から丸切り隔離された村か。こりゃ、ますます金田一耕助の舞台になりそうな村だな・・・)
私はそう思って再び一人、苦笑したのだった。
「ついて来て下さい。案内します」
南川さくらはトトトと土手を下りていった。よく子供が、段ボールの切れ端をソリのようにして遊ぶような傾斜の土手であり、さほど急な土手でもない。彼女に案内され、村の案内をしてもらったのだが、よくこんな辺鄙な所にいるとある意味、尊敬の心を彼女に抱いた。
話は彼女から聞いていたのだがここまで酷いとは想像だにしなかったのである。私は一瞬、戦後まもなくの農村で時代(とき)の流れが止まってしまっていると錯覚したほどである。
少しでも文学的に書くならば、「トンネルは戦後間もなくへと誘うタイム・マシンだった」と書いたら好いのだろうが、私はそこまで思わなかったし、文学的センスのカケラもない一推理マニアだし、乞食が宝冠をかぶるようなもの。高尚すぎて似つかわしくないように思える。
「ほら、この壮大な眺めを味わおうよ」
私は溜息と泣き言を言っている「妹」に苦笑しながら言った。こういう田舎でたまには療養するのもいいかと気持ちを切り替えたのだった。
土手を下りてまず南川に案内されたのは「南」と表札のある屋敷、というか西洋の洒落た感じの貴族が住みそうな館だった。
「こんにちわ」
感じの良い中年女性が挨拶した。私も慌ててお辞儀をする。彼女が通りすぎようとすると南川は引き止めて、
「紹介するわ、南家の家政婦を勤めていらっしゃる、剣崎愛さん」
「いらっしゃいませ」
剣崎は東北訛りが著しい。「妹」も軽くお辞儀をする。
「ミナミって東西南北の?」
家政婦が行ってしまうと私は訊いた。
「ええ、そうです」
「なら『川』が取れただけじゃん」
私は道化けて、あるいは意地悪っぽく言った。
「もう・・・、姓が変わるのだけが結婚じゃないんですよ」
「解ってるよ」
私は苦笑して言った。
「さあ、入りましょう」
と言って私たちは中に入ったのだった。
入ってすぐ萌ちゃんも私も息をのんだ。そして萌ちゃんはうっとりとして、一方私は部屋の中の調度品、家具などの総計を計算して、
(よく、まあこんなものに金かけるな)
と皮肉っぽい敬服を示した。
まるで中世の貴族の館のようである。クラシックな家具で全体が統一されており、照明も豪華なシャンデリア。何坪もある庭は良く手入れされており、エデンの園を想像させる。まさに溜め息の出る美しさだ。
そういう気持ちで私が庭・・・いや、庭園を眺めていると、一人の青年が現れた。気弱そうだが神秘的なこの青年は常識的に考えて南川のロミオだろう。シャム猫がひょいと彼の後ろから姿を見せる。
「シェラカン」
南川はその猫を呼んだ。すると、シェラカンと言う名前らしいその猫は彼女に抱かれた。
「それで、あなたですよね。さくらさんの先輩で日本のホームズと呼ばれている方は。」
青年は低いテナーの声である。
「脅迫状を見せられたのはぼくです。日本のホームズかどうかは知りませんですがね。」
「お話は全て彼女から聞いていますよね?」
私は肯定した。
「ええ、もちろんです。」
「それで、脅迫されるような事は?」
私が知っている限りでは彼女、南川さくらは怨みを買いそうな人間ではないのだが。私は彼女をヨイショするつもりはないのだが慎しく、おしとやかで、美しさがある。
「全然」
「そうですか・・・」
私はもしかしたら、この婚約に原因があるのではと思った。
「この婚約を不快だと感じている人は?」
彼はしばらく考えた後、
「解りませんが、多分いないと思いますね」
「そうですか、今回が初めてですか?このような手紙は」
「いいえ。前に数通、来ております」
実に興味深い問題である。なぜ送って来るのだろう?そういう問題提起をして、第一部は終了したい。FILE3、「東」の邸
私が荷物を置いた後、暇だったので、この村を南川さくらと徘徊する事にした。
「ところで鳥かな?でかい像があったじゃん?あれ何?」
「さあ?」
突然後ろの方で声がした。
「朱雀様じゃよ」
振り替えると白い顎髭の老人が立っていた。
「朱雀様?」
私はおうむ返しに訊いた。老人はしわがれた声で私の問いに答える。
「南を守る神様じゃ」
老人は東菊次郎と言って東家の言わば城主である。
「ちなみにわしの家には、青龍様が飾られておる。今はわしと手伝いの者しかいない。息子たちは皆、街の方へ働きに出ておるのでな」
老人、東菊次郎は哀しげな声で言った。しかし、すぐに
「そうじゃ、お若いの。寄って行きなされ」
と半ば強引に手を引っ張られ連行された。
「おおい。南川さん。何とかしてくれ」
南川さくらはクスッと笑って、
「このお爺さん、若い人が来るのすごく嬉しいらしいんです」
「そ、そんな・・・」
私が泣き言を上げるのをよそに、南川はクスクス笑っている。
「大丈夫です、私も行きますので」
こうして強引に連れて行かれた東の屋敷であるが、流石はご老人、南家が洋風だったのに対し、純和風である。かの藤原頼通が建てた平等院鳳凰堂を想像させる屋敷。宍おどしが、こおんというくぐもった音をたびたび奏でる。日本庭園の典型、もしくは模範的とも言える造りだ。こうして見ると、門の所にある龍の像もなかなか似合っているように思えるのは私だけだろうか。
「どうじゃな、お若いの」
私はここからどうやって逃げ出そうか考えている最中に東に訊かれたのでどぎまぎした。別に老人嫌いというわけではないが陽も西に傾いてきている。それに「妹」もいらぬ心配をしていると思うのでそろそろ、引き上げようかと思っていたらこの老人に捕まったと言う訳である。
なぜ彼女を置いてきたかと言うとぐっすり眠ってしまっていたからである。恐らく旅の疲れだろう。その幸せそうで無邪気な、そして可愛らしい寝顔を見ていると起こすのがあまりにも気の毒に思われた。
こう言う書き方をしていると本多氏の事件のように相部屋だと思われるだろう。しかし、我が幸せな後輩のお陰で別室にしてもらった。私は恋人同士でない男女、肉親以外の男女が同じ部屋に泊まるのを好ましくないと思っているので。例えそれがどんなに親しい友人であろうとも、だ。
「は、はぁ・・・」
感想を述べないと逃れられないようなので私は、
「素敵なお庭ですねぇ」
老人は嬉しそうに満面の笑みをたたえた。
「そうじゃろ、そうじゃろ」
「立ち話もなんじゃから中に入って行きなされ」
(げっ、マジ?!)
と私は途方に暮れた。と言ったら大袈裟だが。
私は南川さくらにアイ・コンタクトで
「助けて」
とメッセージを送った。南川は、
「あら、いいじゃないですか。こういう日本庭園、名古屋じゃメッタに見れませんよ」
と意地悪っぽくクスクス笑って言った。
(こ、この女・・・)
私は彼女をマクダフのように憎悪のこもった目で見据えた。マクダフとはイギリスの偉大な劇作家の書いた戯曲「マクベス」の登場人物の一人で親か息子かを殺されて、マクベスをすこぶる恨んでいた。
「やだ、先輩、そんな怖い顔しないで下さいよ」
後輩、南川さくらは道化けたように言う。
そんなわけでこの老人、東菊次郎の話を延々聞かされる事になった。そのため帰る頃にはもうどっぷり陽も暮れていた。これも我が後輩のせいである。
FILE3、南家での食事
南家の邸に着いた頃にはもう既に星が瞬き、空には中秋の名月が浮かんでいた。田舎の星空はまるで宝石をちりばめたようにキレイである。名古屋では決してこんな星空はお目にかかれないだろう。
「もう夕食の準備はできております」
エプロン姿のメイドらしい女性がそう言って出迎えてくれた。
「遅いじゃないか」
ダイニング・ルームに入ると彼女の未来の義父が優しくたしなめるように言った。
私は南家のダイニング・ルームの広さに息を飲んだ。何十畳もある部屋、広い解放感のある天井・・・・。ホールと同じようにクラシックな家具で統一されている。私はその凄さに思わず溜め息を漏らした。壁にはこれまたクラシックで高そうな絵が飾られている。後で絵の名前と作者は連れの少女に尋ねるとしよう。
「今まで何をしていたんだね?」
彼の名は南章三。この家、というか邸の主である。とうに還暦を迎えているそうだが、とてもそんなふうには見えない。リンカーンのような立派な顎髭の持ち主だ。髪は後頭部が薄めだが、端から見ると気付かないだろう。
彼の傍らには一人の真面目そうな青年が立っている。黒髪を短く切り揃え、マッチ棒なような体格だが、引き締まった顔のせいか、頼もしそうな印象を与える。南川さくらの話だと、彼は南章三の腹心の秘書、原彬だそうだ。
「申し訳ございません。ちょっと先輩に村の案内をしていたものですので」
「そうか、そうか」
解ったようにうなづき、そして彼の息子の方を向き、
「そう言えば、雪子の姿が見えないが・・・」
「ああ、雪子なら自室で小説を書いてますが・・・」
「清明兄さんは?」
「いいんだよ。あんな奴放っておいて」
と笑いながら言ったが言動から彼が長男の事を嫌っている事が解った。
「私、雪子さん見てきましょうか?」
南川さくらがそう申し出ると、大地主は笑って手を振った。
「いや、いいよ。じきに下りて来るだろう。ほら来たようだ」
階段を下る足音が聞こえて、姿を現したのはしなやかな体躯の女性だった。背が高く、ミステリアスな感じのする女性である。
「遅れてすみません」
高いソプラノ歌手のような南雪子の声が室内に響く。
「いや、いいんだ。それにお前が最後ではない」
扉の開く重たい音がした。
「帰って来たようだな」
南清明は目付きの悪い、不良っぽい感じのする青年だった。何もかもが、私や後輩の婚約者である南高明と対照的である。
私を見つけると、
「親父。何だ、こいつらは」
私は腹が立ったが怒りを抑えて自己紹介した。
「探偵?」
清明は探るような目で私を見た。私が「探偵」としてやってきた事が信じられない様子だ。
「すみません。兄は少々酔っているようでして・・・」
高明はそう言った。
「いいんです、慣れてますから」
私は平静を装って答える。
豪勢な食事、美味しいワインや私の好きなシェリー酒の後、ほろ酔い気分で部屋に戻った。実際、ワインもシェリー酒もワイングラス一杯に抑えたものだ。
ここで食事の会話を紹介しておく。何か役立つかも知れないので。
「昔はもっと繁栄していたようですね」
私は微笑して言った。萌ちゃんの言葉を借りるなら“何もかも見透かしたような微笑”である。
「ええ、ええ。」
主は何度もうなづいた。
「ここは昔炭田があったんです。炭田と言っても筑豊炭田(九州の大きな炭田)のように大規模ではありませんでしたが。でも、石炭の時代はもう終わりました」
「それで鉱夫たちも・・・」
「ええ、ここ南家、北家、東家、西家は大きな鉱夫たちの宿舎兼私どもの家でもあったのです」
「それでこんなお邸なのですね?」
「いやはや、少々贅沢しすぎましたかな?」
「いえ!立派なお邸です!」
「妹」は横から口をはさむ。
「そうですか。そう言って頂けると・・・」
主は照れ笑いを浮かべる。
「確かに立派なお邸です」
私も彼女に同感だ。
「特にここが素敵ですね。壁の絵が」
「どの絵が気に入りました?」
「えーと・・・」
私は詰ってしまった。決して絵が気に入っていない訳ではない。名前を思い出せないのだ。いや、見栄を張ってしまった。知らないのである。
「あの絵ですね」
私は女性が腰を屈ませて何かを拾っている絵を指差した。
「ミレーの“落穂拾い”?」
「妹」が囁く。
「そうそう、それそれ」
私は苦笑して、言った。
「先輩」
南川さくらが急に言った。鶏の丸焼きにナイフを入れていた私は目を向ける。
「ん?」
「雪子さんに先輩の活躍談を聞かせてあげて下さいよ。彼女、推理作家の卵なんです」
私は意地悪く、
「本当は南川さんが一番聞きたいんじゃないの?」
「そ、そんなことないですって」
「あはは。じゃ、そう言う事にしておきますか」
と言って、今まで「事件簿」として公開している十件の殺人、一件の誘拐、麻薬取引のうち私が最も気に入っているいくつかの事件を紹介した。私が殺人者の汚名を晴らす事件、アメリカでの出来事などである。
「そういえば、高明さんと清明さんは何をやっていらっしゃるんですか?」
私は訊いた。
「ああ、ぼくは村役場職員です」
「ふうん。ところであなたは?えーと・・・」
私は名前が思い出せないので記憶を辿った。
「清明だよ」
不機嫌そうに言う清明。
「ああ、そうでした」
私は苦笑いをして言った。
「コンビニで働いている」
大地主は吐き捨てるように言った。どうやらまともな定職にもつかない清明が気に入っていないらしい。
こうして楽しく夕食は過ぎたのだが、私は見てしまったのだ。原の南清明に対するあの視線を。ああ!マクダフの視線とは正にあのような視線を言うのだろう。原彬の視線には憎悪、嫌悪、拒絶、拒否・・・そういったあらゆる感情が含まれていた。私はこの物語を書き終った今でも頭から焼き付いて離れない。
ここで、私の泊まった部屋の描写を書いておこう。本棚にはシェイクスピア、ゲーテ、ダンテ、聖書などの小難しい本が並んでいる。本棚と言っても、私の事務所にあるステンレス製のとは違い、威厳のある木製の本棚である。
私はシェイクスピアなら多少、欧米文学を読むに当たっての教養として身に付けている。欧米文学を読むに当たっては、ギリシア神話やシェイクスピア、そして聖書の知識が最低条件なのだ。エラリィ・クイーンの作中ではシェイクスピアの「オセロー」の引用が出てきた事もあったし、「白鯨」のエイハヴ船長の比喩が出てきた事もあった。
そういうわけだからシェイクスピアは多少たりとも読んだ事があるのである。もう随分昔になるが。
私は当時の懐かしさに駆られて、シェイクスピアに手を伸ばした。「マクベス」と英語のタイトルである。私はいつも思うのだが、四大悲劇の中でどうもこれは悲劇と言い難い点があるように思えて仕方ないのである。ここでシェイクスピアについて論じる気なんか毛頭ないのだが。
ノックの音が聞こえた。私は
「は~い」
と言って適当に返事をすると、昼間畦で見かけた中年の女性がエプロン姿で立っていた。彼女は手慣れた手つきで私のシーツを敷いてくれた。名前は剣崎愛と言ったのをおぼろげな記憶を辿って思い出した。
「ありがとうございます」
そう礼を述べた。
「いえいえ」
彼女はシーツを敷きながら愛想笑いを浮かべて言う。私はその純白なシーツと一週間後、後輩が着るであろうウェディング・ドレスの色とが重なって見えてならなかった。そして私は彼女の幸福な結婚生活を予想しつつ、一人笑みをたたえるのだ。
私はベッドの上でごろんと横になって、先程手に取った「マクベス」を読み耽ろうとした。虫の声がちょうどいいバック・グラウンド・ミュージックになっている。しかし私も旅の疲れだろうか、「妹」でないのだが睡魔が襲ってきてまどろんでしまったのだった。
FILE5、彬氏の夢
私の頭からは朝起きてもあの凍りつくような冷たい視線が脳裏を離れなかった。
「おはよう」
私はあくびをしながら隣の部屋から出てきた萌ちゃんに挨拶をした。今日は日曜日。彼女は今日のお昼にはここを立って、名古屋に帰る予定になっている。
「昼ご飯はどうする?」
私が例の広い廊下を彼女と歩きながら尋ねた。彼女はまだ髪を梳いていないため寝癖がある。
「ここで食べる」
萌ちゃんは起きたばかりで眠たそうな声をしている。この彼女の決断が後々、悲劇を招く事になるとは!例の絵のかかっているダイニングへ行き、朝食を取った。朝八時の事だった。
「南川さんと高明さん、後でお話が」
「何ですか?先輩。ここじゃダメなんですか」
怪訝そうな顔をして様子を見る我が後輩。
「う、うん・・・」
私は多少苦笑しながら言った。まさか皆の前でこの家には何かあるのか、とは訊く勇気がない。
「解りました。十時位にお邪魔します」
そう答えたのは高明だった。ギシギシという木の軋む音を響かせて階段を下ってきたのは秘書の原彬氏だった。登り降りしている人の足音を聞くだけでいかにも古めかしい感じのする階段だ。
私は朝だから眠たいのだろうと思って、雪子に
「原さんって寝起きいつもああ言う感じなんですか?」
と訊くといつもは寝起きでも凛とした顔だそうだ。何やら考えごとをしているようにも見える。
「どうしました?原さん」
雪子が高いソプラノで訊いた。
「ちょっと、不思議な夢を見ましてね」
彼は気まずい微笑して言った。
「夢?」
私はおうむ返しに訊いた。
「ええ」
「一体、どんな夢なのです?」
雪子が夢の内容を尋ねた。
「ええ、凄い土砂降りで、雷も鳴っていました。急に生温い風が吹いてきたんです。そうかと思ったら三人の真黒いローブを着ている老婆が現れたんです」
「それで?」
雪子は興味津々といった様子で
「そのお婆さんは何て?」
「『万歳!未来の南家の相談役!万歳、未来の南家の主!』と・・・。」
「不思議な夢ですね・・・」
私が相槌を打つと階段を軋ませながら主の南章三が下りてきた。柔和な顔付きである。
「今日は皆に重大な発表をしようと思う」
その言葉に一同の視線が彼に集まった。
「後継ぎが決まった。皆も知っての通り清明はダメ息子だ」
私はこの場に南清明がいない事に心から感謝した。
「次男の高明に後を継いでもらおうと思う」
南川さくらは歓声を上げた。
「ただし、この縁談を取り持ってくれた原君にも多少はお礼をしておかなきゃいけない」
原の胸の鼓動は大きくなったに違いない。
「息子の相談役になってくれないか」
原は鳩が豆鉄砲を食らったような顔をしていた。一同は驚きの目で原と主人を交代で見た。何も知らない主人、南章三はただにこやかに微笑んでいるだけなのだった。
朝食が終わって、
「相談役って?この人、何か会社でも持ってるの?」
私は南川さくらに訊いた。
「ええ、この村から取れる石炭とそれからできる物を売っているんです」
「へー」
「あれ?知らなかったんですか?」
「ちょっと待ってよ」
私は重大な事に気付いた。
「それじゃあ、社長夫人じゃない?」
「未来の社長夫人です」
「未来の?」
「ええ。あの人が亡くなってからなんです」
「ふうん・・・」
こうして、原氏の何とも不思議な夢は実際に起きたのだった・・・。
FILE6、どろどろした邸
「それで私に用って?」
私の部屋に来た二人は椅子を勧めると
「うん、いやね。あの原さんが清明さんを見る眼差しが尋常じゃなかったからさ」
「ああ。それは父さんが兄さんの事を嫌ってるからなんです」
と後輩の婚約者が言った。
「しかし、それにしたって何もあんな冷たい目で見なくてもいいんではないですか?」
私は率直に言った。
「さあ・・・?その辺の事はぼくにも解りかねます、お役に立てなくってすみません」
「いえいえ」
「失礼します」
私はその声に微かな拒絶を感じた。
「行こう」
と婚約者が誘うと私と思い出話に耽りたいと言ってきたのである。
「そう、解った。気分転換にドライヴしてくるよ。どうも気が高ぶって」
とだけ言って私の部屋を退室した。しばらく彼女の言う通り思い出話に浸っていたが車の発進音が聞こえてしまうと、窓から高明が行ったのを確認。そしてその後、居住まいを正して、
「実は」
と言った。
「さっきの事なんですが少々思い当たる事があるんです」
「何だって?」
私は好奇心に駆られて、もしよかったらその“思い当たる事”を話してくれと頼んだ。
「いいですよ」
難なく承知してくれたのは少し私に取って意外だった。
「この家は嫉妬が渦巻いているのです」
「嫉妬が渦巻いている?」
私は意外さの余り驚いて訊き返した。
「ええ、ええ」
興奮した様子で彼女はうなづく。
「それはどういうことだい?」
「最初、優遇していたのは長男の清明さんでした。もちろんその当時も今と変わらず遊び暮していたのですが、それでも後継ぎとしての第一候補でした。いや、彼以外は後継ぎにする気なんかお義父さんの頭の中には毛頭ありませんでした」
「そりゃ、そうだろうね」
こういう隔離された村ではまるでタイム・スリップしたかのごとく明治時代以降の“長男は後継ぎ”と言う方程式が今、なお根付いている。
「ところが原さんを雇い入れてから、状況は一変しました。というのも原さんは家督より、実力のあるものを次期、会社のオーナーに任じるべきだと近代的な考えの持ち主でした」
「うんうん」
私は原の意見に賛成である。歴史上の王の多くは家督だけで後をついでいるが彼らにはろくな例がない。軍事的天才のナポレオンの甥、ルイ=ナポレオンは独仏戦争で捕虜になってしまうという大失態を演じてしまったし、徳川綱吉は生類憐みの令という極端な動物保護政策を打ち出し、幕府を大赤字にしたのである。
「ぼくは、原さんの意見に賛成だよ」
「それで、そのこと、つまり実力のあるものを次期、オーナーに任じる事を話したのです。もともと原さんは相談役としてここに来られたのですから」
「ふうん、それで憎んでいると」
「多分」
後輩は短く答えた。
「でも待って?章三さんは決意を固めたから今日話したんだろう。清明さんを次期会社オーナーに任じる事を」
「はい」
「だったら時間的に矛盾してると思うけど。だってぼくがあの視線を見たのは昨日なんだよ」
「ええ、恐らくは話した事自体、気に食わなかったのでしょう」
私はなるほど、と思った。確かに原は清明の立場を脅かす存在である。そのためにあの視線を送ったのであろう。
「しかし」
私は呆れ返った。
「なんちゅう家だ。ここは」
南川はただただ苦笑している。
「あっ、ごめん」
私は彼女の苦笑を見て謝った。
「えっ、何がです?」
「ん?愛する人の家を非難してしまった事」
「いいですって、そんなんじゃ私と彼の愛は薄れませんから」
「いいねー」
私は冷やかした。
「そ、そんなことないです」
後輩は恥ずかしがって否定した。
「先輩だってあの子とラヴラヴじゃないですか」
私は顔を真っ赤にして否定した。
「ははは、隠さなくたっていいですよ」
「ち、違う」
「そう言う事にしといてあげましょう」
ノック音が聞こえて先程、噂をしていた少女が入ってきた。
「ジージョ。準備出来たよ」
FILE8、地震
黄色いリュックを背負った萌ちゃんが立っていた。私は
「じゃあ、行こうか」
と言って、食堂に行った。時間は十時と早いのだが、コーヒーを飲みたいのである。私の好きなモカ、もしくはキリマンジャロが出てくるだろうか?
「すみません、コーヒー頂けますか?」
食堂のドアを開けて言った。剣崎が、
「はーい」
と言ってコーヒーをいれてくれたのは良かったのだが、インスタント・コーヒーだったため、あの濃厚な香りは損なわれ、コーヒー独特の苦みも薄れていた。しかし、せっかく入れてもらったのだから残したら家政婦の剣崎に悪いと思っていやいや不味いコーヒーを飲み干すことにした。
「地震?」
天井のシャンデリアがふらふらと揺れているのに気付いて萌ちゃんは言った。私はコーヒーの色をした不味い液体を飲むのを止めて、天井を見あげた。
「ああ、そうかも・・・」
と言っていられるのも束の間、すぐに食堂全体が大きく揺れ始めた。動揺する萌ちゃんの手を引っ張って机の下に押し込めるとすぐに私も机の下に避難した。剣崎も
ガスコンロの火を止めて、私たち同様、机の下に避難した。
地震は数分で収まった。しかし地震のために出発を早めた萌ちゃんが、いざあのトンネルの前に出て見るとトンネルが崩れ落ちているのである。先程の地震のせいであろうか。
私は彼女の母親に連絡をとるべく、彼女の家に電話した。未だに黒いダイアル式の電話を見て私は苦笑した。
「あっ、おばさんですか?」
「うん。そうだけど。翔ちゃん、何?」
「ちょっと、地震がありましてですね。閉じ込められてしまったんです」
「復旧にはどれくらいかかりそうなの?」
「ちょっと待って下さい」
と言って剣崎に復旧にかかる時間を訊いた。
「そうさねぇ」
強い東北訛りで
「一週間はかかるべっちゃな」
私は受話器を取り、この事を告げた。
「ほんと、すみません」
私は謝った。そして別れの言葉を述べ合うと受話器を置いた。“おばさん”、つまり彼女の母親は怒っているに違いなかった。私の立てたこの無計画な旅行。予期しなかったとはいえ、地震が起こってこの山奥の何にもないこの辺鄙な村に閉じ込められてしまった事・・・。
いくら脳天気、ポジティブ、そして楽観的な私でも流石にこれには罪悪感を感じずにはいられない。しかし、起きてしまった事をいくら悩んでも仕方ない。これが楽観的と言われる由縁だろうが。
「剣崎さん。」
急に私が言ったので少し驚いた様子で、
「はい」
「本当にあのトンネル以外ここからの脱出方法はないんでしょうか?」
「さあ・・・。」
「例えば・・・」
私は事件を解く時の要領で思考力を働かせた。
「そう、例えば警察に連絡をしてヘリで迎えに来てもらうとか・・・」
「誰がこんな村のために」
私の意見を嘲けるかのように言った。
「愛知県警に知り合いの刑事がいます」
と私は言った。
「彼に連絡して岩手県警にヘリの要請をしてもらいましょう」
正直言って望み薄しだった。なぜなら、警察組織はとかく縄張り意識が強いものである。こんな高校生のためにヘリを飛ばしてくれるとは思えなかった。かと言って私にはかのビル・ゲイツのような裕福な友人もいない。
ともかく私は藁にもすがる思いで西口警部に連絡した。
「この電話は電波の届かない区間におられるか電源が入っていないため繋がりません。この電話は・・・」
女性の機械的なアナウンスが私の耳に虚しく谺する。
「だから言ったべ」
「ええ・・・。」
どうしようという動揺の声が自分自身、見てとれた。私は窓に目を向けた。雨がちらついている。これでは仮に警部と連絡が取れたとしても雪のためにヘリの要請は断られてしまうだろう。
「トンネルの復旧まで待つしかねえべ」
「ええ、そうします」
私は仕方ないので苦笑して言った。
つまり、村全体が大きな密室と化した訳だった。
「さて」
剣崎は気合いを入れ直すように言った。
「どうかしたのですか?」
私はその声に少し驚いて言った。これから、何かパーティーでも始まる様子である。
「パーティーを開くんです」
素っ気なく家政婦は言った。出来るだけ共通語にしようと努めているようだが、それでも東北訛りが残る。
「あれ、でも結婚はあと五日後なんじゃないですか?」
私は疑問に思って訊き返した。普通は結婚当日か結婚前夜に行うのが普通である。
「違いますよ」
「えっ?でも、後輩、つまり南川さんから、結婚式は日曜日に行うって聞きましたけど?」
私は混乱して言った。
「違います。別のパーティーです」
家政婦はクスクスと笑った。
「何のです?」
私は混乱が解けて、ほっと安堵の溜め息を漏らした。
「旦那様の五十三回目のご誕生日パーティーです。旦那様に内緒で」
「へー」
「私もお手伝いします」
そう言ったのは萌ちゃんだった。
「本当によかんべ?」
「よかんべ、よかんべ」
どっと私と剣崎愛とが哄笑した。
「なにやら楽しそうだな」
今日、五十三才になったばかりの南章三が下りてきた。
「あっ、お誕生日おめでとうございます」
ダイニングにいた三人の声が重唱した。
「そう言えば、私の今日は誕生日だったな」
今まで忘れていたかのように言う。
「まあ、この年になると誕生日なんかどうでもよくなるが」
私の方を向いて微笑とも苦笑ともつかない笑みを浮かべる。
「そう言えば、お嬢ちゃん。今日名古屋へ戻るんじゃなかったのかい?」
「ええ、そのはずだったんですが・・・」
彼女は簡単に地震が起きた事と、そのせいでトンネルが崩れた事を説明した。
「地震?そんなもの全く感じなかったが」
南章三は苦笑した。私は正直言って鈍感だと思った。こう言っては、失礼極まりないが。その時、階段を素早く駆け降りてきたのは、あと五日後に“川”の字が抜け、南となる南川さくらだ。
「何ですか?さっきの揺れは」
「地震だそうだ、私は全く感じなかったがな」
「えっ、あんなにひどい揺れだったのにですか?」
「そのようだな。何せトンネルが崩れたのだから」
私と萌ちゃんは苦笑を漏らした。
「何せ熟睡してたからな。いや、今は爆睡というのか?」
続いて下りてきたのは秘書の原彬と長女、雪子だった。
「すごい揺れでしたね」
「そうだったのか?」
熟睡してて、何が起きたのか解らない南章三は、まるで流行のテレビを見ていないかのように驚きの目で見られた。
「そう言えば高明の姿が見えないが」
「ああ、ドライヴに行きましたよ」
「地震、大丈夫かな」
南川さくらは心配そうに呟くのが聞こえた。素晴らしい愛である。
「おっとロミオが帰ってきたようだよ」
私は茶化して言った。ドアの重々しい開閉音とともに入ってきたのは、ずぶ濡れの高明だった。南川さくらは駆け寄ると、手拭いを手渡した。
「ありがとう。」
彼女から手拭いを受け取ると、
「地震でドライヴどころじゃなくなったよ」
と言って、着替えるためだろう、二階の自室に上がって行った。南川さくらも、まるでヒヨコが親鶏を追うように彼の後を追う。何とも微笑ましい光景である。
「ぞっこんだな」
南川さくらを見て南章三は微笑む。雪子も羨ましそうな眼差しで見送る。その眼差しを見た南章三は、
「原君に探してもらってはどうかな?」
と笑いながら言った。
「い、いえ。結構です」
答えを聞いた南章三はただ微笑するだけだった。
「もう心に決めた人でも?」
私は思い切って訊いた。萌ちゃん、いや浅香萌が私をさっと一瞥する。雪子ははにかみながら、
「は、はあ。実は」
「まさか推理小説とでも言うんじゃないだろうな」
南章三が嘲笑気味に訊く。彼女は笑いながら、
「そんなんじゃありませんってば」
原は、
「まあまあ、推理小説と結婚するのも言いじゃありませんか。かのエリザベス一世はイギリスと結婚したと言ってますしね」
その通りである。もう一つ、つけ加えるならばアメリカのヴァージニア州と言うのは彼女、つまりエリザベス一世が一生処女を貫いたために処女と言う英単語のヴァージンに由来すると言われている。このような例は他にも見られ、ルイジアナは「朕は国家なり」で有名な太陽王、ルイ十四世から来ていると言われている。この際、どうでもいい話なのだが。
「まさか、考古学者とか?」
私の答えに、全然見当外れとでもいうように笑いながら手を振る。
「私が女流推理作家だからですか?」
「どういう?」
南章三が、私たちのかなりディープな話についていけない、というように訊く。
「つまりですね、アガサ・クリスティの夫は考古学者なんですよ。作品の舞台にエジプト、バグダッドなどが見られるのはそのためです」
彼女が説明すると納得したような表情をした。
「『ナイルに死す』は最高でしたね」
昼食のお盆を運んできた萌ちゃんが言う。
「さて、と」
昼食を取り終ると南章三は重たそうに腰を上げ、二階へと上がっていった。原はまるで領主を護衛する騎士のようについていく。
「ぼくも部屋に戻るよ」
そう言うと、私も二階へと上がっていった。部屋に戻った私はまず、『マクベス』の続きを読んだ。それでも何か忘れているようでならなかった。
数分後、後輩、南川さくらが扉もノックせずに入ってきた。ひどく動揺して、今にも泣き出しそうだった。私は駆け寄る。そして落ち着けようとする。
「落ち着いて。何があったんだい?」
それはさながら、いやどんな言葉を用いても的確に彼女の怯えて、泣き出しそうな様子を喩えることはできないだろう。
彼女の手を見ると小さめの茶封筒が握られている。これだな、私はそう思った。
「ちょっと、いい?」
彼女の答えも聞かず、その封筒を取った。私は封筒を太陽に透かして、剃刀が入っていない事を確認した。この手の脅迫状は剃刀がつきものである。
封筒にはただ一枚、B5の紙が入っていた。そして毎度の事ながら、卑猥な言葉がワープロの書体で書かれていたのである。
私はここで疑問に思った。なぜ彼女は封も切っていないのに脅迫状だと解ったのだろう?毎度の事で神経が過敏になってしまっているせいであろうか。私は冷静になるよう自分で努めた。
それで私ははっと思い出す。そうだ、私は脅迫状の送り主を見つけだすために来たのだ、と。
FILE10、脅迫状
「ひどい」
相方はさっと見ると、そう言ってその脅迫状を私によこした。今、相方が私の部屋に来ている。
彼女からやっと聞き出すことが出来た経緯は次の通りだ。私はこれを聞き出すのに一時間は祐にかかった。
彼女が朝起きた段階ではこの封筒はなかった。これは彼女が確認している。間違いないそうだ。それで、次は歯を磨くなどして、下に降りて来た。朝食は朝七時位に家政婦、剣崎が運んでくれるそうである。むろん、私はこの頃はぐっすり、高鼾をかいて寝ていたのだが、そんな事はどうでもいい。
剣崎が行ってからも封筒はなかった。よって家政婦はシロ。
ここからは前章に述べた通り私たちと一緒に昼食を取った。ここまでは私の目で確認している。次に婚約者の南高明がドライヴからびしょ濡れで戻って来た時に、彼女は二階に婚約者の着替えを手伝いに行った。
十分位して戻ってくるとあったと言う事だ。
「簡単に言うとこう言う事だね」
「ええ。」
「でも、ぼく見てたけど二階を上がって行く人なんか見なかったけどなあ。萌ちゃんは?」
相方は首を横に振った。
「見なかったわ」
「原さんと章三さん位なものだよ」
「訊いてみる?」
お願いしますと言ったので誕生パーティーの際にさりげなく訊こう。
そして夕方になってパーティーは始まった。南章三はこの秘密にしていたパーティーに驚き、嬉しく、そして感激した様子である。
私は南章三を捕まえて、さりげなく訊いた。もちろん、脅迫状の事は秘密だ。
「ああ。原君に訊いて下さい」
今度は原を捕まえて、同じ質問をした。
「ああ、旦那様と一緒にいましたよ」
「ずっとですか?」
「はい」
南章三が後ろから、
「なあ、有沢さん。もし、南川さんにまた脅迫状が届いたのなら、私たちを疑うのは筋違いもいいところですよ。」
そしてしばらく間を置き、
「私は犯人を知っていますからな」
私は驚いた。そして、
「だ、だ、誰ですか?」
「長男の清明ですよ。あいつは高明を憎んでいましたからな」
私は多少、うんざりしながら、
「しかし、それだと、高明さんに脅迫状を送る方が効率的では?」
「ふん!南川さんをノイローゼにして、婚約を解消させようという腹でしょう」
決めつけるように、南章三は言った。とにかくこれで疑わしく思われた南章三もシロだということが解った。
ここでパーティーの参加者を簡単に紹介しておく。これから起きる血腥い殺人事件に大いに貢献する事になるだろうから。
あの私を捕まえた東老人。
それに、北家当主、北友紀、北勇作。かなりの若夫婦で結婚したばかりである。北とめという老女を抱えていた。北友紀の実母である。“抱えていた”と過去形にした理由は四年前に亡くなったそうだからである。
次に、西家当主、西賢二、西賢一、西蛍子である。西蛍子と西賢二が結婚している。子供はいない。
最後は中央の教会の神父、茶木茂である。ちなみに皆、南川さくらと南高明の説明である。
そして説明する必要はないと思うがパーティーの参加者はもう一組。この南家の住人、南高明と南川さくら、家政婦の剣崎愛、私、有沢翔治、そして浅香萌である。
「皆さん、お酒が入っているようですので泊まっていかれては。父さんもそれでいいですよね」
南高明の提案に泊まる東西南北の人々が事になった。前も言ったと思うがここは元は炭坑労働者の宿舎のため、部屋は山ほどあるのだ。全員泊っても、余るほどだ。
「結構、結構」
と南章三が許可したため、
「そういうことですので皆さん、泊まっていって下さい」
そう言う訳で急に泊まる人数が増える事となった。
FILE11、殺人事件
前作「Hの悲劇」も殺人に至るまで間を置きすぎている。どうも私には殺人事件まで間を置きすぎる悪癖があるようだ。
さて、私は翌朝、決してよい目覚めとは言えなかった。なぜなら、隣の部屋でドンドンと物凄い音で目を覚ましたからである。
「どうかしたんですか?」
私はあくびをしながら訊いた。
「ああ、有沢さん。ちょうどいい所に」
「何ですか?」
私は苛立ちながら訊いた。せっかく気持ちよく寝ていたのに、起こしやがって。
「章三が起きて来ないんです」
そう言ったのは西賢二である。
「何ですって?」
と言ったが私は昨日の地震の事を思い出し、
「まだ寝てるんじゃないですか?ナルコプレシー並によく寝る人ですからね」
「ナルコ・・・何だ。そりゃ?」
東が訊く。
「突然、寝てしまう病気です。しかもちょっとやそっとの事では起きないんです」
「でも、こんなにどんどんやっても起きないなんて変じゃありませんか?」
南高明が神経質そうに言った。
「それもそうね」
雪子が同意する。扉には鍵がかかっているようである。結局、皆で扉を打ち破る事にした。西賢一が斧で破って、開いた穴から手を突っ込んで鍵を回す。
廊下状になっておりその途中にはカーテン付きの窓がある。そして、その光景を見た私は一気に目が覚めた。死んでいるのである。皆が釘付けになるような異様な光景だった。そして、後から原彬が、
「どうしたのですか?皆さん」
とやってきたのだった。
h2>FILE12、密室
『三つの棺』や『火刑法廷』などで名高い密室の巨匠、ジョン・ディクソン・カーに代表され、日本人作家では横溝正史の『本陣殺人事件』、乱歩の『三角館の恐怖』などなど、密室殺人を扱った推理小説は数多く存在する。そして私が語ろうとしているこの南家の殺人事件もその例外ではない。
さて、私たちの通報で巡査部長と数名の巡査が駆け付けた。その巡査部長は西原昭雄と名乗り「古狸」のあだ名が相応しく、五十過ぎの中年刑事である。
「おや、警察の人たちが到着したみたいだよ」
私が窓の下を見下ろして言う。私の部屋は玄関の真下に位置しているので誰が来たのか、ベランダに出ればすぐに解る。
「何してるのかしら?」
曙のようにでっぷり太った西原は戸惑っている様子である。
「さあ?」
やがてネクタイを締めて、まるで今から結婚式か高級レストランに入る様子だ。意を決した様子で扉を叩く。
「はい」
高明の声が響く。
「こ、こ、これは高明様!わざわざご苦労であります」
まるで戦前の天皇陛下に対してするように敬礼する。私はここはいつの時代だと思って苦笑した。
パトカーが十台ほど続き、まるで何か人質事件でもあったかのようだ。私はこれにも高々殺人、一件位にこれほどまでになぜ大人数でやらなければいけないのかと疑問に思った。
私は事情聴取を受けるために、階段を下りた。木の階段が古めかしい音を立て、軋む。私は殺された不幸な男の名を言うと西原は飛び上がらんばかりに驚いた。しかも下に揃っている面々を見ると巡査部長は顔面は緊張で真っ赤になり、汗がにじみ出た。
「ふむ」
現場検証を終え、ダイニングに私たちを集めた西原はそう呟くと、
「窓には鍵がかかっていて、扉にも鍵がかかっていた。そこで西様が斧でドアを壊された。これで間違いないでしょうか?」
例によってきつい東北訛りである。しかも丁寧すぎるほどの敬語である。
「はい、章三がいつまで経っても起きてこないから不審に思って」
「つまり、事件現場の部屋は完全な密室だったわけでございますね」
「ええ、おそらく」
西賢二が震える声で言う。まだ南章三が殺された事が信じられない様子だ。
「ええと、死亡推定時刻は」
手帳をぱらぱらと捲りながら探す西原巡査部長ののろのろとした動作に絶えかねて、
「死後硬直や、死班から少なくとも夜十時から明け方五時の間と見て、まず間違いないでしょうね」
ついでに言うなら、私が呆れたのはのろのろとした動作だけではなく、ばか丁寧な敬語にも呆れたのだが。
「何だべ、あんたは」
不機嫌そうに訊く。
「有沢翔治。探偵ですよ」
私はさらに続け、
「しかも死因は絞殺ですね。索状痕がありましたから」
と私の簡単な検死の見解を述べた。南高明のフォローが入る。
「ぼくの婚約者の先輩で有沢シュウジさん」
「翔治です」
私は軽く会釈をしながらさりげなく訂正する。すると、私に対する態度がガラリと百八十度変わった。
「こ、こ、これは失礼致しました。」
浅見光彦や水戸黄門もこんな感じなのだろうと思った。浅見光彦とは、警視総監の弟という探偵でそのことを知ると急に警察は協力的になる。
私の頭を悩ませている要因はただ一つ。いかにして密室を作りあげたのか、という事である。次の図は私の描いた簡単な見取り図である。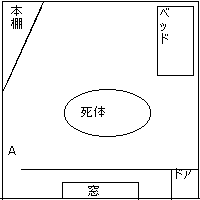
これから数行に渡る記述は見取り図を見ながら読む事をお勧めする。A地点は私たちが氏の死体を発見した現場だ。見て解るように短い通路の途中には簡単な窓がある。この窓はカーテン付きで死体を発見した時には、しっかり施錠されていた。それは私が確認している。しかも、扉は南京錠が二つもついており、斧で破ってやっと中に入ったのである。
「合鍵はないのですか?」
私は南高明に訊いた。
「合鍵なんかあったら斧で打ち壊す必要なんかないじゃないですか」
「それもそうですね」
次に私は、隠し通路といった気の利いたものはないかどうかを刑事の説明を一通り聞き終えてから、南高明に訊いてみた。彼は笑いながら、
「そんなものありませんよ、何なら家政婦の愛さんに訊いてみるといい」
私はその後、剣崎愛に確認を取ったのだが隠し通路はないとの事である。ベッドの下には、埃が溜っており、その事から人が隠れていなかったと解る。
本棚にはシェイクスピア、ダンテ、そしてゲーテなどの偉大な欧米の作家たちが並んでいる。本棚にはミルンの生涯で唯一書いたと言われている推理小説のように特別な仕掛けがないか、と探して見ても見つけられなかったのである。
南高明にこの事を話したら、
「ハハハ、無駄足でしたね」
と笑われた。
「この屋敷にはそんな面白い仕掛けなんてありませんよ」
窓、扉、本棚、ベッドについての記述が終了した。あと見取り図で残る情報は死体に関する情報である。私の推理小説はエラリィ・クイーンのように手掛かりを全て提示し、論理的な思考の元で犯人を割り出せる、言わば数学の問題のような小説である。従って死体に関する記述を書かなければ私のオンライン読者は納得しないであろう。
さて、死体はうつぶせに倒れており、死因は私の述べた通り絞殺である。鍵は彼の上着ポケットに入れられていた。現場には凶器となる紐状のものは落ちていなかった。
「鍵はいつも、章三さんの上着ポケットに?」
私は手近にいた原に訊いた。
「ええ」
以上の記述から解るように完全な密室でこの館の主人、南章三は何者かによって殺害され、犯人は煙のごとく消えたのである。
FILE13、整理する
「ねえ、何か解りそう?」
私の部屋で萌ちゃんが訊いた。
「うーん・・・。現場の状況を整理してみよう」
「ぼくが起きた時、あの部屋には鍵が掛かっていた」
「うん。窓も開かなくて、賢二さんが斧でやっと開けたのよ。」
彼女は私に、
「隠し扉とかないの?」
「うん。その点は高明さんに確認をした」
「ないって?」
「うん」
私は短く答える。
「ベッドの下には?」
「入った形跡はないよ。埃がそれを証明している。それにあの時は全員集合してたでしょ?」
「うん」
「本棚に仕掛けは?『赤屋敷の秘密』みたいに」
『赤屋敷の秘密』とは私の言った‘ミルンの生涯で唯一書いたと言われている推理小説’である。
「ないよ」
私はきっぱりと答えた。
「しかも鍵はただ一つ。その鍵は上着のポケットに入っていたよ」
「合鍵はあるの?」
私は首を横に振った。
「そんなものがあったら斧で破る必要はなかったんじゃない?」
私はからかうように言うと、
「とにかく、完全な密室だったことは違いないよ」
と断言したのだった。
FILE14、遺産相続争い
刑事たちによる事件の確認が終わった。私は、
「やれやれ」
と大きな溜め息をついて腰を下ろした。
さて、親が死ぬと当然、息子たちは遺産を分配しなければならないのだが、大富豪の家ではそれが醜い争いとなる。この家もその例外ではなく、私はうんざりしながら廊下での言い争いを聞いていた。いや、「聞いていた」という表現よりは「聞こえてくる」という方が正しいかもしれない。
扉の向こうでは故人の息子たちは始めはぼそぼそと小声で話し込んでいる。次第にそれが熱を帯びてくきて、扉越しにも聞こえるようになる。
「長男の俺が親父の全遺産を相続するべきだ」
と明治時代の大日本帝國の考え方を盾に、目茶目茶な理論をまくし立てているのは、長男、清明。高明が嘲笑するように、返事する。
「兄さん、何十年前の考え方ですか?東のお爺ちゃんなら通用するかもしれませんがね」
と、言った。更に続けて、
「次期、後継者はぼくなんだから遺産は全額、ぼくが相続するのが相応しいと思う」
これには雪子が反論する。
「あら、遺言状でもおあり?」
「遺言状はないけど、でも皆の前で発表したじゃないか」
「そんなんじゃ、遺言状として通用しないよな?」
と言うのは明治時代の頭の長男、清明。
「そうよ。遺言状は手書きの文字で実印が必要なのよ」
「だそうだ。残念だったな。高明」
と嫌味ったらしく言うのは清明。しかし、高明は一歩も譲らない。
「でも、皆の前で言った訳だから」
あくまで皆の前で言った事を強調する高明。私はうんざりしていたが、滝のように絶え間なく聞こえてくる言い争い。その描写を引き続き記す事にしよう。何が事件の鍵となるか解らないのだから。
「あら、そこにこだわるのね」
嘲笑する雪子。私は溜め息を漏らす。
「高明の理論でいくと、私だって遺産を全額相続する権利が発生するわよ」
「何で?」
多少ヒステリック気味に言う高明。
「あら、忘れてしまったの?」
「姉貴、だから何を」
苛立ちながら訊く清明。
「あっ、清明に言っても解らないかもね。だってあの時、あの場に飲みに行ってたかでいなかったもの」
「私、あの皆の前で私に全遺産をくれると言ってくれたのよ」
自慢げに言う雪子。
「ああ、でもあの時は父さんはお酒を飲んでただろう?」
「私の話している事はもし、高明の言ってる事が通るならよ」
「ほう・・・。じゃ、姉貴は遺産はいらないのか」
毒々しい嘲笑の声で言う清明。
「ちょっと、待ちなさいよ。清明、誰がそんな事!」
高いソプラノの雪子が言うと、よりヒステリックに聞こえる。
「姉さんの言ってる事だとそうなりますよ」
高明が清明の肩を持つ。
「だよな?」
「ええ」
「ちょっと、ちょっと!」
ヒステリックに叫ぶ雪子。
「第一、清明、あなたが殺したんじゃないの?」
「何で俺が!」
不当な疑いをかけられた高明は叫んだ。
「次期、社長の件で恨んでたじゃない!清明に椅子を取られたからって」
「そう言えば・・・」
高明が思い出したように言う。
「兄さん、一週間に一回は父さんと口論してませんでした?」
「俺じゃない、そんなこと言ったら姉貴にも動機があるぜ」
「何よ!動機って」
「姉貴の下らない推理小説を自費出版するって親父ともめてたじゃないか」
「私の小説が下らないですって?それに自費出版は粘り強い交渉で納得させたわ。取りあえず一万冊で様子を見ようってね。」
「じゃあ、高明。お前はどうなんだ!」
雪子がかなわないと解った清明は、今度は弟である清明に食ってかかった。私は清明があの状況だと最も疑われそうな感じがするのだが。
「ぼくが?兄さん、ぼくを疑うのは筋違いもいい所ですよ。次期、社長を約束されてるのですからね」
「だからこそ、殺したんだろう?」
「何ですって?」
「そうそう、社長の椅子が早く欲しくてね」
雪子が皮肉っぽく言う。ここまで来るとうんざりすると言う表現よりは、それを通り越してむしろ呆れる。
故人の腹心の秘書、原が、
「まあまあ、ここは均等に三等分したらどうです?」
彼の意見に同意する者がいれば言いのだが、一つのパンを三つに分けると言う考えがない三人は矛先を無防備な彼に向けた。
「すっこんでろ!お前には関係ないだろ!」
と異口同音に三人が原に向かって言った。私は法律的に見ても、倫理的に見てもそれが妥当であろうと考えた。ついでに言うならば民法の遺産配分に関する記載では、配偶者が半分を相続し、半分で均等に分配して息子と娘が相続する。
私は呆れ返ってしまい、この英仏海峡のように暗くよどんだ三巴の闘争の傍観を決め込むのだった。
FILE14、南高明の話
私は取りあえず、話をしやすいという理由から南高明から話を聞こうとした。
「わざわざ、ご足労をおかけしてすみません」
私の部屋に来てもらったのである。南川さくらは怯えきって、震えている。顔は死人のようにに蒼白である。
「大丈夫。大丈夫」
私と南高明が落ち着かせようと試みるが一向に、良くならない。私は彼女を萌ちゃんに押し付けるように任せて南高明の話の聞いた。
「まず、死亡推定時刻何をしていました?」
私は訊いた。これは愚問だったと私は言い終えたから思った。なぜなら死亡推定時刻は真夜中で全員、眠りについているはずのだから。
「ぼく?ぼくは寝てましたよ」
笑いながら彼は答えた。
「死亡推定時刻は真夜中でしょう?」
「ええ」
私は答えた。
「でも、もしかしたら、南川さんと・・・」
私は言葉に詰り、しどろもどろした。萌ちゃんはもちろん、どんな女性の前でも性的な言葉を使わないと心に決めているからである。
「なかったですよ」
南高明は私の言いたい事を察知したらしい。きっぱりと、しかし多少不機嫌そうな口調で答えた。相手が気を悪くするのももっともだ。
「すみません」
と私は軽く謝り、
「では、次にぼくの到着する前までの話を訊かせて下さい」
「いいですよ。えーと、どこから話しましょう?
昨日、父とダイニングで別れたところからでいいですよね?昨日、ぼくは夜十時位に少し酔いが回ったので、寝る事にしました。ぼくはお酒には弱いんでワインだったらグラスで三、四杯くらいでダウンしちゃうんです。兄は結構、強い方なんですけど。そんなぼくですので十時頃に寝ました。あっ、そうそう。自室へ行く前にトイレに寄りましたけど、三分以内ですよ。どう考えても父を殺して、密室にするなんていう時間はありませんよ。
翌日の朝早く、誰かが内線で
『お前の父親が部屋で殺されている』
と言う電話があって、始めは何かの冗談だろうと思いました。そんな物、まず真剣に受け止める人はいないでしょう。さくらの脅迫状の件もありますしね。そんな訳で、また一寝したわけですよ。
次、起きた時は壁を叩く音で目が覚めました。
『大変だ!親父が部屋で死んでるぞ!』
と兄が言うではありませんか。ああ見えても、意外と小心者なんですよ。兄に詳しく事情を訊いて見ると、兄の所にも同じような内線電話が来たと言うではありませんか。
『ははは、そんなのはデタラメに決まってますって』
ぼくは笑いながら言いましたよ。しかし、兄は本当に父が部屋で殺されてると信じているらしく、
『そこまでいうなら、親父の部屋に行ってみようじゃないか』
それで、扉を叩く大きな音で、皆さん目が覚めてしまい。父の寝室の扉を西賢二さん、・・・賢一さんかもしれません・・・が開けて中に入ったらあの通りだったと言う訳です。」
以外にも冷静だと私は驚いた。普通、父親が殺されて冷静を保てる人は犯人か、鉄の神経の持主と限定される。しかし、この場合、彼が犯人だとは思えない。なぜなら、次の後継者としての椅子が約束されているからである。
「その電話は聞き覚えのある声でしたか」
こう言う時の犯人は大方、ボイス・チェンジャーかタオルを受話器にあてがって自分の声を解らなくするのが普通である。そしてこの場合もその例外ではなかった。氏の話によると低く、くぐもった声だったそうである。
タオルを当てたのか、私はそう思った。
「と、すると男か女かも解らない訳ですね」
「ええ」
と、申し訳なさそうに答えた。
「次に章三さん誰かに恨まれているとかそう言ったことはなかったですか?」
「さあ?」
と、この質問には首を傾げるばかりである。
「兄は恨んでいましたがね、でも殺人となると・・・」
「ありがとうございました」
私はそう言うと次に最初に殺人予告の電話を受け取ったという彼の兄に話を訊く事にした。
FILE15、南清明の話
「俺は何を話せばいいのかな?探偵さんよ」
挑発的な口調である。私は訊きたい事が沢山あるので彼の子供じみた口調には構っていられなかった。私は冷静な口調で、
「ええと、まず形式的な質問から」
「何だ?」
「昨夜十時から翌日の早朝四時まであなたはどこで何をしていらっしゃいましたか?パーティーには参加していらっしゃらなかったみたいですが」
「アリバイか。パーティーって言うのは親父の下らん誕生日パーティーだろう?俺はちょうどその頃、コンビニでバイトを終えた。それでバイトの飲み仲間と一杯引っかけってから帰ろうと思ったんだ。でもよ、そのいつもの飲み仲間が急用が出来ちまって、仕方なく一人で飲んでたんだ。」
「それは何時まででしたか?」
「そんなもん、覚えてるかよ。ただ、家に着いた時には十二時を少し回ってたけどよ」
二時間か。私の事件談を見てると有沢翔治なる男は、さもワインやシェリーなどの洋酒をよく飲んでる印象を与えがちである。しかし、実際の事を言うと、私はお酒など読者諸君が思ってるよりは飲まないので二時間も飲むなど想像できないのである。もちろん、その間、おでんや焼き鳥などを食べているだろうが。
そのため、
「二時間ですか。ちょっと長すぎやしませんか?」
と率直に意見を述べた。
「そうか?俺はこの位が普通だぜ。最高で五時間半、居座った事があるからな」
「五時間半・・・ですか・・・」
私は唖然としてしまった。図書館になら何時間でも居座れるが、居酒屋となると長くて一時間なのである。そのため五時間半などという長時間は想像にも及ばないのであるる。
こう言う関係ない記述を差し挟むと、事件の最中も他事を考えていたと思われる。しかし、私は南高明から事情を訊いた時は事件の事で頭がいっぱいだった。
「十二時からの清明さんの行動は?」
「そのまま、爆睡したよ。酒もかなり入ってたしな」
ぶっきらぼうに彼が言う。
「ええと、一回変な電話かかってきたでしょう?その時の行動は?」
「ああ、親父が死んでるって奴な。俺はあれですっかり目が覚めちまったんだよ」
思い出したのか、さも不愉快そうに彼は言った。
「そして?」
私は後を促した。
「そして、ってそれだけだぜ。ムカついたから高明をからかいに言ったんだ。高明も最初は信じなかったけどよ。じゃあ、一緒に見てみようっていうことになって、ドアを破ったら、親父が死んでいたっていう訳だ。」
と言って、
「俺の知っている事は話したぜ、じゃあな」
そして、私の部屋を出て行った。
FILE16、南蛍子の話
次は南蛍子の番だった。彼女は一時間ほど前、遺産相続で揉めていた三姉弟の中では一番、動揺していた。彼女のソプラノの声が震えている。
父親が死んだ事の重大さに気付き、遺産相続など関係のない愛で結ばれた父娘の関係に戻ったのか、それとも探偵としてやってきた私に「父親を失った娘」という“悲劇のヒロイン”を演じているのかどちらだろう、と私は考えた。彼女はしきりにハンカチを目に当てている。
「落ち着いて下さい」
私は一まず、そう言った。抑揚がなく興奮している甲高い返事が帰ってくる。それはまるで黒板を爪で引っ掻いたような声である。
これでは尋問にならない。そう判断した私は萌ちゃんに、
「これじゃ、話を訊こうにも訊けない。」
とバツの悪そうな苦笑を浮かべ、
「階下に行って剣崎さんからブランデーをもらってくるよ」
一分もしないうちに私は、ブランデーの入ったグラスを南蛍子に飲ませていた。ブランデーを飲んだ彼女の顔は血色が良くなったので、彼女が落ち着きを取り戻し、ようやくこれで尋問を開始できそうだと私は一安心した。
「それで、まず形式的な質問から」
と私。
「はい」
幾分、まだ興奮しているものの、ブランデーのおかげで、ずいぶん落ち着きを取り戻している様子だ。死人のような蒼い顔だったのがだいぶん血色も好くなってきている。
「寝ていました」
今まで訊いた三人の中で一番短い返事である。
「そうですよね」
私は相槌を打つ。
「はい」
抑揚のない、少し震える声で彼女は言った。
「では、あの晩のあなたの行動を」
と言った後で私は彼女を気遣い、
「思い出せる範囲で結構です」
「えーと・・・、昨日は誕生日パーティーでしたので私もアルコールが入って、すぐに布団に入ったんです。私はアルコールはダメなんです。それで早朝、時刻は解りませんが内線で電話が掛かって来たんですね。
『お前の父親が死んでいる』
と。私も何かの冗談だと思いましたよ。でも、その後、弟たちが来て、それで見に行こうと言う事になったんですよ」
「そしたら、お義父様はお亡くなりになってたと言う事ですね?」
「はい」
抑揚のない声で答える。
「それでは、誰かに恨まれていたとか、そう言う事は・・・」
「さあ、私の知る限りではありませんでしたけど・・・」
「ありがとうございました」
私はそう礼を言うと、彼女を部屋から出したのだった。
FILE17、原の話
次に話を訊いたのは秘書、原彬だった。私は氏に期待していた。なぜなら、隣であり、しかも最後まで一緒にいた可能性が極めて高い人物なのだから。
「私は酔った社長に部屋までつき添った後、家政婦さんと分担で皆様のお部屋の案内をしていました」
私はノートのその事を書き取ると、
「では何時頃に布団に入られたのですか?」
「さあ?二時頃だったかと。仕事もありましたので」
「章三さんはいつも鍵を掛けて寝る人だったんですか?」
「はい」
と確信に満ちた口調で答え、泥棒に入られて金庫にあった財産を取られた経験があると教えてくれた。その頃の強盗事件と今回の殺人事件とは無関係なので省略するが、施錠を怠らないようになったのはその頃からだろう。
「死体発見時の状況を詳しく」
前の三人に釣られて聞いてしまった。彼は困ったような顔を見せ、
「何言っているんですか?ぼくは一番最後に到着したんですよ。ぼくより有沢さんの方がよく御存じのはずでは?」
私は苦笑して、
「そう言えばそうでした」
予告電話は来なかったのか。私はそう思った。
「早朝に章三さんが殺されているという予告電話は入りませんでしたか?」
秘書は犯人を嗤って、
「はははは、来ませんでしたよ。間抜けな犯人ですね。そうだと思いませんか?そんな電話かける暇があれば、逃げればいいのに。どこの部屋からかけたか解るんですよ。後でお持ち致しましょうか?」
「お願いします」
私は答えた。誰かに恨まれていないか尋ねても、収穫は得られなかった。
FILE18、剣崎の話
「原さんと分担でお客様を部屋に案内していたべよ。」
忙しそうに洗い物をしながら例のきつい東北訛で剣崎は答えた。というのも剣崎だけは忙しいだろうという理由から私が階下に下りて尋問を行ったのである。
「ふむ、ふむ」
私がノートに書きつける。
「昨夜寝られたのは何時頃ですか?」
「十一時位だべさ」
「どうして死体を発見されたんですか?」
この問いに剣崎は鼻でフフンと嘲笑う様に
「どうしてって・・・、あんな大声出せば誰だって気付くべ?」
予告電話は来なかったのか。私はそう思った。とするとあの三人だけ電話が来た事になる。
「電話は来なかったのですか?」
と私が聞いても、電話は鳴ってないと告げた。どうやら、あの息子たちだけに犯人は電話したようだ。
「原さんと別れたのは何時ぐらいですか?」
「十一時ちょっと前じゃないべか」
「その後、彼はどうしました?」
と相方が訊く。
「二階で仕事があると言って階段を上がってったべ」
私はその事をノートに書きつけるとパタンと手帳を閉じた。そして礼を言うと階段を軋ませながら萌ちゃんと上がっていったのだった。
FILE19、東西南北家の話
私は雨が少し小降りになったのを見計らい、東西南北の家をそれぞれ訪れたのだったが大した成果は得られなかった。訊き込みの描写をだらだらと描くと読者諸君は、ただでさえ詰らない私の小説をより一層詰らないものと感じるだろう。だからここは簡単に結果報告だけで済ませようと思う。
私は西宅を最初に訪れた。斧で密室の扉をぶち破った男が私を出迎えてくれた。私はまず、事件当夜のアリバイを訊いた。
「寝ていましたよ」
そう答えが返ってきた。
「奥さんも?」
「はい」
彼女もお茶を運びながら答える。やはり無理だったかと思い一人苦笑した。夜というのは草木さえも眠る時間帯である。その時間帯のアリバイを訊こうなんて無理なのだ。
「今朝は何時頃起きましたか?」
私は西蛍子の入れた日本茶をすすりながら訊いた。
「よく解らないけど四時頃だったと思います、隣の部屋の電話が鳴っていましたので。その後何やら、騒がしくなってドアをそっと開けると高明、清明が言い争っていたんです。」
ここは洟を垂らしていた頃からの近所付き合いで、名前の呼び捨ては別に普通であるそうだ。
「僕は二人に何事か訊きました。そうしたら・・・・・」
後の話は高明、清明と一緒だった。
ところで一種の警戒心というのだろうか。それとも私のようなよそ者が事件を嗅ぎ回っているのを不愉快だと思っているのだろうか。妙に他人行儀である。いきなり知己のように話し掛けられたら、私も対応に困らないではないが。
そんな事を考えながら向かった先は北邸だった。私は南から出発し、西、北、東の順に事情を訊こうとしたのである。夫婦二人で暮らしていると聞いて私は小じんまりとしたものを想像していたのだが、それとは裏腹に西洋の城のような屋敷だった。
私は奥に案内されたのだが応接間も見事である。窓は皆、ステンドグラスであり、数々の宗教画が掛かっている。
「それでですね」
私は北家の使用人の入れたダージリン・ティーをすすりながら言った。アリバイを訊こうとしたのだが、質問内容が変わった。その言葉で私は危うく飲みかけの紅茶を大理石の床に全て飲ませてしまう程驚いたのだった。
「あ、あの・・・。」
言おうかどうか決心しかねてる様子だったので、
「話を続けて下さい。些細な事程、何よりも重要なのです」
私は後を促した。数秒の奇妙な沈黙。時計の音のみが谺する。彼女は気分を落ち着けるためだろうか、紅茶を一口飲んだ。
「何なんだ、友紀?」
いらつきながら彼女の夫は言う。彼女は紅茶のカップを口に付ける。その豊満に満ちた香で気分を落ち着かせたらしい。やがて意を決した様に、
「私、犯人を知っています」
震えながら言った。私は、その口から出た余りにも意外な言葉に金田一耕助のようにどもった。
「そ、そ、それは、だ、だ、誰なのですか?」
「それは確かなのか?」
夫、勇作も信じられないといった口調で言う。
「はい」
確信に満ちた目をしている。私は高ぶった気分を落ち着けるために紅茶を口に含んだ。温かみ、苦み、紅茶独特の適度な甘味、そして、ダージリンの芳しい香り・・・。それらが興奮した私を落ち着ける。
「それで、犯人は誰なのです?」
「南さんの新しい奥さんです、厳密に言えば後六日後ですが」
南川さくらか。明らかにこの言い回しはどう考えても彼女を指している。
「何でそう思われたのですか?彼女が犯行を行っている現場を見たとでも?」
後半は私は少しムキになって質問した。
「天の声です」
余りにも真剣になって言ったので私は笑いだしてしまった。
「いやいや、失礼」
拍子抜けしてしまった私は言った。
「あのですねぇ、あなたは法の華の福山雅治ですか?」
「でも、天の声に従って成功した例もありますわ。例えばジャンヌ・ダルク、マホメット・・・。」
私は反論する気が失せた。私は訊きたい事を全部訊いたので暇を告げた。
「それでは、失礼します。紅茶まで出して頂いて」
と礼を言って、東邸へと向かった。東邸は西邸から徒歩三十分の所に位置する。
東老人は私が訪れた頃、精力的に庭の手入れをしていた。年齢は米寿を迎えているそうだが頭ははっきりしている。東老人は私を見つけると麦藁帽子を取って近付いた。私は前回、一時間近く話し相手にさせられた経験があるため、一瞬身構えた。彼は人なつっこい笑顔を作り、
「わしに何か用かの」
と言った。私は、
「ええ、事件のお話を伺っているんです」
「でもそれなら先刻、お巡りさんが見えたがの」
ほう。一応、関係者から話を訊いてるのか。この村の巡査だったら北友紀の話のように天声だとかタロット占いだとかで犯人を決めかねない。それほど四人の支配力は絶大なのである。まるで大日本帝國の天皇か、ムスリムにとっての唯一絶対神、アッラーであるかのように。
「そうですか。二度手間で申し訳ありませんが、もう一度訊かせて頂けますか?」
「ええ、ええ。何度でも訊かせたる」
まるで戦争の思い出を語るかのようにに話した。
「ここで立ち話もなんじゃから部屋に上がったらどうじゃ?ちょうど茶菓子もお茶もあるぞ」
大の甘党の私は茶菓子に釣られて部屋に上がらせてもらった。やがて、玉露のお茶と雪見大福が出てきた。
「さて、何から訊きたいんじゃ?わしがあの凶行について語れる事なら何でも語ったる」
私はまず、事件当夜のアリバイを訊いた。
「わしは寝てたよ。そう言えば、便所に一回行った位かの」
「お爺さん。それ何時くらいですか?」
「えーと、あれは夜中の一時くらいかの。年を取ると小便が近くなっていかんわ」
恥ずかしそうな微笑を浮かべて言った。
「その時、何か変わった事は?」
「変わった事というと?」
「例えば章三さんの悲鳴を聞いた、だとか逃げて行く人影を見ただとか」
「ははは、そんな事があったら今頃事件は解決しておる。」
私は緑茶を一口飲むと、
「ほんの些細な事でもいいんです」
「そう言えば・・・」
「そう言えば?」
私は後を促した。
「窓掛けが閉まっていたような気もするが・・・・」
「窓掛けって?」
「あっ、今の者はカーテンっていうのか。西洋の言葉が氾濫して年寄りには解らん」
苦笑しながら東老人は言った。私はこの事を手帳に書きつけておいた。
「あんまり老人の言う事じゃから信用しない方がいいかもしれんぞ。わしはこの頃、記憶が曖昧でな。」
「いえいえ。大変参考になりました」
「では、次に遺体を発見された時の状況を・・・」
西賢二、南高明らの話とそう大して変わらなかったので、私は手帳にはメモを取らなかった。私は雪見大福を頬張りながら、たっぷりと戦争体験談を余談として聞いた。
推理小説、数学や化学、物理学のみならず、クラシック音楽、犯罪心理学、天文学、ギリシア神など色々な事に興味を持っている私は、当然、歴史にも興味がある。最も興味があるのは十字軍からルネッサンスなのだが、二回の大戦、特に第二次大戦も結構興味を示している。そんな私に取って戦争体験を生で聞けるなんて滅多にないチャンスなのだ。例え、それが事件に関係ない事だとしても、である。
私はあぜ道を西洋風な家屋を目指して歩いていた。新鮮な空気が美味しい。しかし、そんな事も今の私にとって頭脳をフル回転させるための環境にすぎなかった。ここから南邸へは祐に徒歩で四十分はかかる。その間、私は手帳と睨めっこをしていたのである。
FILE20、逮捕
全て回るのに移動だけで二時間半もかかった。話を訊く時間もいれればもっとだろう。その割には私の挙げた成果はダージリン・ティー、玉露、雪見大福、戦争体験談と事件には結びつかないものばかりだった。
疲れた。久々にこんなに歩いた。私は疲れを取るため足を高く挙げ、ベッドに寝転がった。もちろん手帳と睨めっこである。しかし疲労困憊のために意識が遠のいていった・・・。
「ジージョ。起きて。起きてったら」
そう言う声ではっと私は目が覚めた。どうやら私は疲れのために微睡んで(まどろんで)いたらしい。手帳は私の顔を覆うように被さっている。
「ん?ああ。萌ちゃんか。何か用?」
頭はまだぼんやりとしている。私は時計を一瞥した。五時を少し回った所だった。どうやら私は三時間も居眠りをしていたらしい。
「ぼくを起こしたって事は何か用だったんじゃないの?」
私は眠気と疲労のために重い頭を抱えながら言った。
「大変なの」
「どうやら君は結果を先に述べる悪い癖あるみたいだね」
私は意地悪っぽい笑みを浮かべて言った。心地よい眠りを妨げられた私の、細やかな報復だ。
「そんな事言ってる場合じゃないよ!」
「だから、何が大変なんだい?ただ『大変』って言われただけじゃぼくは解らないよ。」
私は苦笑しながら言った。
「ごめんごめん。南川さんが刑事さんに連れていかれちゃったの」
意外に冷静である。これが親友や亡き彼女の兄だったらパニックに陥って、今頃泣いていた事だろう。
「それは大変だな。」
私は呟く。
「って本当!?」
半分寝ていた私は彼女の一言で、頭から氷水をぶっ掛けられたように目が覚めた。彼女の答えも聞かずに南邸を砲弾のように飛び出した。
私は走った。走ったと言うよりは突進したという表現の方が正しいだろうか。心臓がバクバク言っている。陽は赤く私を染めていた。
やっとの事で交番に着いた時にはもう薄暗くなり、家々には灯が灯っていた。私は心疾患患者のように胸を手で抑え、息を切らせ、そしてよろめきながら交番に入った。
「有沢様!わざわざご苦労であります!」
私は苦笑した。南家の客人というだけでこんなにも熱く持て成しを受けるとは。巡査の一人が私に椅子を譲ってくれた。私は軽く礼を述べると、その椅子に腰を下ろした。しばらく呼吸や脈拍を整えて、質問を開始した。その際、私はざっくばらんに話しても好いと言った。
「南川さくらが何で容疑者なんですか?」
私が一番尋ねたかった質問だ。
「もしかして、北夫人の天の声じゃないでしょうね?」
“狸”はその質問に親切に答えてくれた。彼は笑いながら言った。
「まさか。そんな物で犯人を決めつけるなんて、ここがいくら田舎でもそんな事で犯人扱いはしませんよ」
「では、どうして?」
私は巡査部長に苛つきながら訊いた。
「実はですね、事件当夜、アリバイがないのです」
「しかし、それでしたら皆容疑者ですよ」
私は刑事に嘲笑を少し交えて反論した。
「いや、ごもっとも」
と西原巡査部長は安物の紙タバコに火を点けて言った。
「しかしですね、彼女だけは夜中の十二時頃に起きて、ダイニングに行っているんです。夜中の十時から明方の三時と推測されたのはあなたでしょう?」
「ええ、死後硬直、死班などからみて間違いありません。その点はぼくが断言します」
私はきっぱり言った。
「でしたら夜中に起きている彼女を疑うのが当然でしょう?」
「彼女が夜中起きているのは自分で言ったのですか?それとも誰かの証言ですか?」
私は尋ねた。
「東様の証言です」
私は記憶を辿った。事件現場の見取り図、関係者の話を書いた手帳は慌てて飛び出して来たため屋敷に置いてきてしまったようである。東老人は事件当夜、カーテンが開いていた事を証言してくれた人物だと言う事を思い出した。
「それで、彼女はその事について何て言ってるんです?」
「喉が渇いたから下でお茶を飲みに言ったと」
「家政婦さん証言にも、原さんもそんな事は一言も・・・」
私は呟いた。一番遅くまで起きていた彼らの話によると出会った人物はいなかったと言う。
「そこなんです。そこなんですよ」
でっぷり太った巡査部長は我が意を得たりと得意げに、そして熱っぽく言った。
「どう思われます?」
私に意見を求めてきた。その答えに対して私は、
「さあ?」
とコメントするだけに止めておいたのだった。
FILE21、謎の電話再び
「今のままではまだ証拠がなさすぎます」
私は思った通りに言った。
「例えば、現場は完全な密室だったんです。しかも鍵は被害者、南章三さんの近くに落ちていた訳です」
「その通りです」
西原巡査部長は肯定する。
「南川さくらに密室はどうやって密室を作ったんでしょうか?また、なぜ密室に?それから早朝掛かってきた不審な電話は?」
「それは、今から私たちが捜査することです」
私は苦笑した。これでは、まるで本末転倒である。事件と言う物は充分な証拠を集めて、それを元に犯人を推理する物である。それを容疑者を捕まえて、証拠はそいつの口から吐かせようなんて、冤罪の元である。
「私たちはこれほど明確な犯人はいないとは思っているんですがね」
という巡査部長の口には多少、皮肉っぽい微笑を浮かべていた。
「アリバイ時に起き上がっていただけで犯人にされるんですか?」
「それと起き上がっていたという時刻に、誰も彼女の姿を見ていないんです。それも忘れてはいけませんね」
西原巡査部長が付け加えた。
「よく考えて見て下さいよ、西原刑事」
私はなだめるように言った。
「何ですか?」
と私に目をやる。彼は二本目のタバコを取り出し、火を点けた。かなりのヘヴィ・スモーカーらしい。私はタバコの煙が嫌いなので一、二歩退いた。
「もし、仮に彼女が犯人だとしますよ。そうしたら、何でわざわざ自分の不利になる証言をしたんでしょう?」
「それはこういう理由なんです」
ゆっくりと紫煙をくゆらせながら巡査部長は続ける。
「それまでは、南川さくらも部屋で寝ていたと言っていました。しかし、謎の電話が掛かってきまして、
『南川さくらは嘘をついている』
と言ってきたんです。それで、彼女を問い詰めたらあっさり自供したとのことです」
「その声の主は男でした?女でした?」
西原巡査部長は大柄で逞しい刑事を顎でしゃくった。
「はい。自分が電話を取りましたが年齢はおろか、性別も解りませんでした」
どうやら、この巡査が電話を取り次いだようである。横から巡査部長は机の上にあったガラスの灰皿を取り、タバコを押し当てた。
「それで、そのX・・・仮にそう名付けましょう・・・は何と言ったのですか?」
「西原部長がおっしゃったように『南川さくらは嘘をついている』と」
「それだけですか?」
私は訊いた。
「はい、それだけです」
私はいよいよこの事件にわくわくし出した。密室、謎の人物Xから二度に渡る電話、そして、脅迫状との関係・・・。それらの事件を解く重要な鍵が私の頭の中で交錯するのだ。
「どう、思われます?」
西原巡査部長は尋ねた。
「いや・・・、私はもっと証拠を集めたいですね。そして充分出揃った所で、もう一度考え直してみるのです」
「それは結構なんですが、時間の方も考えて下さいよ」
それに対して、私はあと一つ二つ調べたい事がある。それが解れば、犯人は判明するだろうと告げ、交番を後にしたのだった。
FILE22、南川の部屋
交番から帰った私は、夕飯も食べずに南高明に駆け寄った。今までの事情を簡単に説明すると、彼は卒倒しそうになった。仕方のない事だと思って私は自分のやり方を心の中で少し非難した。婚約者が疑われているのだから卒倒するか、ケルト人のように怒り狂って交番に殴りこむか、あるいは子供のように泣くかのいずれかだろう。
萌ちゃんが彼を支える。
「それでですね、ぼくはXなる人物は監視カメラで彼女の行動を観察してたんだと思います。他に行動を観察する手だてはありませんからね。彼女の部屋を調べてもかまいませんか?」
「ええ。もっともぼくの一存じゃ決められないですが」
後輩の婚約者は気恥ずかしそうに苦笑する。私は、
「ええ、解ってます。彼女にはぼくから事情を説明しておきます。それと一応彼女が帰ってきてからにします」
婚約者の許可だけでは倫理的にまずいので、私は彼女の帰宅を待つ事にした。
七時頃ようやく、可哀想な後輩が帰ってきた。
「あの、南川さんの部屋を調べたいんだけど、いいかな?どこかに隠しカメラがないか調べたいんだ」
流石にこれには少し迷った様子だったが、
「あの助手の子・・・名前、何でしたっけ?」
と記憶を辿るように言った。
「萌ちゃん?」
「そうそう、その子に調べさせるんだったらいいです」
やはり、男子禁制らしい。私は萌ちゃんを呼んで、事情を説明した。
その際に、私はよくカメラが仕掛けられそうな縫いぐるみや、ビデオのボタンなど数十ケ所を教えた。彼女は逐一、それらを手帳にメモする。電磁波計測器でもあると便利なのだが、そんな気の利いたものは持ってきていない。おそらくこの屋敷にもないだろう。
「頼んだよ」
私は相方にそう言うと、彼女は任せといてと言わんばかりに親指を立てた。
私は彼女が部屋から出てくるのを部屋の隣の壁に寄り掛かって待った。
「もらったものはないの?」
萌ちゃんのソプラノの声が私の耳に届く。緊張しているせいか、幾分声が大きくなっている。そのため、扉を隔てても聞き取る事ができるのである。彼女は私の指示通りに捜査してくれているので、非常に満足した。
数十分後、正確には七時四十分、相方が部屋から出てきた。
「ねえ、隠しカメラなんかなかったよ」
FILE23、推理作家との会話
私はダイニングに戻ると、西原巡査部長の部下らしい警官が、まさにミケランジェロが作った精巧な石像のように直立不動で立っていた。
私は家政婦にコーヒーではなく、紅茶を頼んだ。DARJEELING-TEA(ダージリン・ティー)と書かれたティーパッグが見えたからである。これなら信用に値しそうだ。前にも書いたと思うが、ここに来て最初、コーヒーを頼んで、インスタントを出された苦い経験がある。
「あっ、そうそう。雪子さん」
「はい」
彼女は答える。
「内線の記録って解るって聞いたんですが、簡単に解りますか?」
「はい、解りますわ」
彼女は私の向かい側に腰を下ろすと、ホットチョコを頼んだ。まるで喫茶店である。やがて、シャム猫が私の膝の上に乗った。
「エラリィ、こっちへいらっしゃい」
と彼女が呼ぶとエラリィは彼女の膝に乗り、丸くなった。なかなかセンスのあるネーミングであると思った。そして推理好きらしさが窺える。というのもエラリィ・クイーンの小説に『シャム双生児の秘密』という作品があるからである。
「ほう、エラリィって言うんですか?じゃあ、ペルシャ猫はアリスで、黒猫ならポオですか?」
私は冗談めかした。
「有栖川有栖の『ペルシャ猫の秘密』にポオは・・・、そのままですね。三毛猫ならホームズとか」
くすくすと笑いを浮かべながら言った。
「『三毛猫ホームズ』ですか」
「そうそう。四匹いたら、名探偵郡のできあがりですね」
「でも、有栖は探偵じゃなくて犯罪臨床学者の火村英生の活動を記録している探偵作家ですよ?」
「そうですが、まあいいじゃないですか」
これ以上、ディープになると読者諸君がついていけなくなる可能性があるのでこの辺で会話の描写は打ち切る事にしよう。
「それで本題に戻りましょう」
私がそう言ったのは話し初めて十分後の事だった。
「はい、電話ですね」
「はい、厳密に言えば内線記録です」
彼女は私に少し待つよう言うと、奥の部屋に入って行った。
「これです。昨日の分」
手にはファックスの用紙と同じ位の大きさの紙があった。そして、手触りもそれ似ており、ツルツルである。五時一分に南章三の部屋から内線が娘と息子二人に掛けたという記録が確かに残っている。内線は使用頻度が少ないため、探すのに苦はなかった。
「章三さんの部屋から、か」
私はそう呟く。
「ええ、私、清明、高明の三人に掛けていますわね」
「犯人は一体何のためにそんな事を」
「さあ?私には解りかねます」
南雪子も首を傾げる。
「どうですか?推理作家の見地から、何か思い付いた事はありませんか」
現役の“探偵”に推理作家と言われたのを嬉しく、あるいは恥ずかしく思ったのか、顔を朱に染めた。
「密室殺人・・・、一番初歩のトリックは糸に鍵を通すものですわね」
「そうですが、隙間より鍵の厚みが大きくて入らなかったんですよ。ぼくが実験済みです」
私は確信を持って言った。あの時、確かに厚みが大きくて、部屋の中には入らなかった。
「スペア・キーがあるとか」
私は率直に言った。推理作家は笑いながら、
「スペアなんてないですわ。唯一の鍵は父が持っていましたし、その鍵は父の死体の周囲に落ちていたんでしょう?」
「はい、問題はそこなんですよ」
私は頭を掻き毟りながら答える。
「完全な密室・・・」
私は呟いたのだった。
FILE24、隠し通路
話題は密室からカーター・ディクソンこと、ジョン・ディクソン・カーに移った。ふと目を上げると故人の秘書が警官に耳打ちしている。
「・・・なんて噂を耳にした事があるんですが」
それを聞いた警官は血相を変えて、二階へ上がった。面白そうなので私もついていく事にしよう。
着いたのは故人の部屋、つまり殺人現場だった。警官は床に耳をあてがって、タイル一枚一枚を叩き始めた。
「隠し通路を調べてるんですか?」
私は訊いた。
「はい」
警官は床を叩きながら言った。
「それは無駄ですよ。この部屋にはそんな気の利いた物なんて・・・」
「床板が外れるぞ」
警官はそう、呟いた。隠し通路はあったのである。
私は黙って、ポーカーフェイスでそのマンホール位の大きさの通路を見つめていた。
「あったのか」
私は呟いた。思ったのはその程度である。動揺も驚愕もしなかった。私は真事をただ推理の鎖の環として受け入れる。真事実が浮かび上がった時は、自分の今までの仮説が覆されても動揺はしない。私の推理が間違っていた。また一から考え直せばいい。
「入ってみましょう、有沢さん、刑事さん」
原はそう言うと、自らが先頭に立ち、進んで行った。その狭い通路は、見るからに人工的。足場もしっかりしており、一メーター半位おきに豆電球が配置しており、ペン・ライトの必要はなかった。しかし、人一人が腰を屈めてやっと通れる程度の本当に狭い通路だった。最近使われたらしく、蜘蛛の巣はなかった。いよいよ、私たちは、出口についた。
「早く、早く」
私は秘書に急かした。胸が踊る。原彬は少しタイルを押した。びくともしない。
「よいしょ」
と原の掛け声と共に重たそうな音を立てて大理石のタイルが開く。狭い通路を抜けて出たのはなんと、南川さくらの部屋だったのである。女性、特に婚礼前の女性の部屋を覗く事は道徳に反する。
私は慌てて、しかし音を立てないようにタイルを元に戻した。
「危なかった・・・」
私はそう呟いた。私たちは来た道をもう一回、引き返して故人の部屋に戻った。
私は海老のように屈めた腰を伸ばした。そしてその疲れを取るため、ダイニングに戻ろうと思ることにした。部屋から出る際、私はカーテンを何気なく見た。その瞬間、私の頭の中で縺れた糸が解けていく。
「だから、カーテンが閉まってたのか」
私は呟いた。私はポケットにしまってあった四つ折の見取り図を広げて確認する。
「なるほどね」
口元からは不敵な笑みが零れた。
幕間
さて、私の作品はエラリィ・クイーンのようにフェアな勝負であることは読者諸君も御存じであろう。
今回は完全なる密室殺人である。犯人Xはいかにして密室を作ったのか、また最終目標はXなる人物は誰なのか?第五部の見取り図を見てよく考えて頂きたい。
FILE25、秘密の相談
私は相方を差し招いた。
「何?」
と言って、彼女が私の元に駆け寄った。いつも通りの反応。
「密室の謎が解けたよ」
と私は自信に満ち、そして相方の言葉を借りるなら“何もかも見透かした笑み”を浮かべて言った。
「本当!?」
彼女は嬉しそうである。
「ああ、そして何で見なかったかもね。」
「じゃあ、南川さんは・・・」
その心配そうな浅香萌の問いに、
「無実だよ。もちろん」
と優しい笑顔を作って、言った。
おそらく二番目に彼女の事を心配した人だろう。一番目はもちろん恋人である。私などは事件の謎に駆られて、彼女の事を親友ではあるが、単なる事件関係者の一人としか受け止めなかったのである。もちろん彼女が犯人でない事を何とかして証明しようと言う気はあったが。
「それでお願いがあるんだけど・・・」
流石長年の付き合いである。相方は私の言いたい事をぴしゃりと当ててしまった。
「私に“殺されろ”と」
「う、うん」
と言うしかない。
「あっ。あともう一つ」
「何?」
怪訝そうな顔をして私を見つめる。
「実は、南川さんの部屋と被害者、つまり章三さんの部屋とを繋ぐ隠し通路が発見されたの」
「本当!?」
私の発言が信じられないように彼女は言う。
「うん」
私は短く肯定した。
「それでね、章三さんの部屋に行って持ちあげてみてくれない?」
「女の子の私に?」
私はからかって、
「あれ?萌ちゃん女の子だっけ?」
いつも通り、彼女は頬っぺたを風船のように膨らませた。その仕草が何とも愛らしい。
彼女に恥かしながら恋をしている私にとってどの仕草も愛らしく、そして可愛く見えてくるのは読者諸君にも容易に想像がつくだろう。英語の諺には「恋をしていると彼女の犬まで愛するようになる」という物があるのだが私の場合、正にそうなのだ。そして次の一言が浅香萌曰く“精密な思考機械”を狂わせた。
「いいよ、私、ジージョの事好きだしね」
その一言で私の事件一色だった頭が一気に掻き乱された。心臓の鼓動が、まるで運動をした後のように速く打つ。そしてその鼓動は、やがて私自身の耳にも聞き取れるようになる。しかし、私の鼓動とは別にもう一つの鼓動が聞こえたのは気のせいだろうか?
私がもしヘヴィ・スモーカーなら煙草を落としていて、足に火傷を負っていた事だろう。むろん、私は思考能力が落ちるので煙草は吸わないのだが。
「えっ・・・」
「な、何、か、勘違いしてるの?わ、私は、に、人間として好きだって言ったのよ」
まるで茹で蛸のように赤い私に気が付いて彼女は言った。私はがっかりすると供になぜか少し安堵した。しかし、彼女の顔も茹で蛸のように真赤だった。
「何してるの?さあ、行きましょう」
ぼおっとしていた私の腕を引っ張る。この時の私の目は白昼夢を見ているようだったと後々になって彼女から聞かされた。
「白昼夢か・・・」
私は故章三氏の部屋に行く途中で呟く。
「ん?何?どうかした?」
萌ちゃんが私の呟きに応えた。そして、事件以外の考え事をしていた俯き加減の私を怪訝そうに見る。
「い、いや、江戸川乱歩にそういう名前の小説があったなあって思っただけ」
私はとっさに思い浮かんだ嘘を言う。
それにしても、私という男はとことん推理オタクだと思う。とっさに思い浮かんだのが乱歩の、しかも『人間椅子』や『二銭銅貨』、そして子供向けの怪人二十面相シリーズではなく、あまりよく知られていない『白昼夢』を出すだなんて。
浅香萌はクスッと笑って、
「いかにもジージョらしいわね」
と言った。例の地下通路に着いた。
「ここなの?」
余りの狭さに驚いたのか、萌ちゃんは目を見張る。
「そうだよ」
前に入った事のある私は平然として言う。
「ちょっと狭いね」
中に入ってみた彼女の感想である。萌ちゃんがそう思うのも無理もない。一メーターそこそこしか天井の高さはないのだ。そのため私たちは腰を屈めるか、あるいは座りながら移動するしかしないのである。
「変な事しないでよ?」
という彼女の言葉に私は苦笑する。彼女のその台詞に警戒心というものは微塵も感じられないのである。私を男として見ていないせいなのか、それとも、私を全く信頼しきってるせいなのか・・・。どうも前者のように思えて仕方ないのだが、その辺の所を考えると少し憂鬱になるので考えないようにしている。
そう言えば一年少し前になるだろうか。私が『ミステリー愛好家殺人事件』と名付けた小説にも私を男として認識していないように思える場面があった。
「変な事ってどんな事?」
私はからかって言う。
「そ、それは・・・」
彼女はほんのり顔に朱を走らせながら言葉に詰まる。
「ははは、解ってるよ」
私は笑いながら言った。そして、
「さあ。行こうか」
と言って中に足を踏み入れた。狭い通路の中、私が先に行った。
彼女の吐息が私に吹きかかる。盲目の方は他の神経、例えば触覚などが鋭くなると言うが何となく解る気がした。見えるか見えないかの薄暗い通路の中で、やたらに私の恋しいその少女の気配だけが感じられるのである。むろん気配は誰でも感じるだろう。
しかし、彼女の胸の鼓動、石鹸の香り、そしてそれに混じって微かに漂う香水の香り・・・。そう言ったものも感じられるのである。
「ねえ」
萌ちゃんが後ろから私を呼んだ。
「こうして地下通路を抜けると『赤毛連盟』思わない?」
『赤毛連盟』とは私の最も尊敬する探偵の解決した事件である。質屋に掘られた地下通路は実は銀行まで続いていて、犯人は銀行強盗を企んでいたという筋書きだ。
「ああ、確かにね」
私が心ここにあらずという調子で返したので、
「もう。事件は解けたんじゃないの?」
とクスクス笑いながら言った。
「解けたよ」
「まだ何か引っ掛かるの?」
「いや」
「じゃあ、何でそんなに落ち着きがないの?」
「落ち着きがない?ぼくが?」
「そう。他に誰がいるの?」
私は彼女の台詞に苦笑した。
「落ち着きがないかなあ?ぼく」
私は誰に問うでもなく、あえて言うなら自分自身に質問した。
「ないって」
「そうかな?」
白状しよう。私は確かに彼女の言うように考え事をしていた。しかし、それは事件の事ではない。私が考えていたのは、浅香萌の事である。いつでも手が届きそうなのに、届かない。まるで月のような少女の事を・・・・。
「そう。だって考え事をするとその事に没頭するじゃない」
それは私も認める。私はこれ以上の詮索を逃れるため、
「もうすぐだよ」
本当にあと五メーターくらいの距離だったこともあったのだが。私たちが十数歩行くとようやく腰を屈めなくともよい場所へ出る。萌ちゃんが蓋を持ち上げる。
「ダメみたい」
力みすぎて顔を真赤にしている萌ちゃんが言った。
「ジージョやってみて」
私にやれと。高校時代に体育が大の苦手だった有沢翔治にこの蓋を持ち上げろと仰っしゃる。私に持ち上げられない事は、火を見るより明らかだ。
私が手を掛けたその時である。何かドーンという爆音に似た物凄い音がしたのは。
「入口の方からだ!」
「急ぎましょ」
「うん、解ってる」
とは言った物の狭い通路で腰を屈めていると、思うようには走れずスピードはかなり落ちる。もうそろそろ明かりが見えてくるはずだと思ったら、見えてこない。そう、私たちはこの薄暗い地下通路に閉じ込められてしまったのだ。
FILE26、危機
「ジージョ!どうするのよ!」
泣きじゃくりながら私を責め立てる。
「落ち着いて。きっと誰かが助けに来るよ」
私はそう言うしかなかった。しかし、助けに来る当てもない。携帯はもちろん圏外であるし、私と彼女で精一杯蓋を持ち上げたがびくともしない。何かタイルの上に乗っかっているようである。通路内の酸素は次第に薄くなり、何もしなくとも呼吸が荒くなる。
「誰かって誰!?」
涙を目に含ませて言う萌ちゃん。
「ジージョが・・・、ジージョが悪いんでしょ?」
それから十分間は彼女から一年分くらいの罵倒を浴びせかけられた。やがてそれに疲れて、土の壁に寄り掛かる。
「もう、こんな不毛な争いはやめよう」
と私が提案すると、彼女も同意して私に謝った。
「うん。そうだね。ごめんね。」
それから十数分間、私は土の壁を掘った。
「私たち、このまま死んじゃうのかな」
ぽつりと萌ちゃんが呟く。土の壁を掘った私の手は血と土まみれである。
「ねえ、ジージョ」
はあはあ苦しそうに浅香萌は言う。土の壁を掘りながら、彼女の方を向く。
「これで最期になっちゃいそうだから、言っとくね」
彼女は目を潤ませながら、しかし、精一杯の作り笑顔で言った。呼吸の乱れは一層激しくなっている。私には、もはやその言葉を叱りつける力すらなかった。
「私ね・・・・。私・・・。ジージョの事が・・・」
苦しそうに力を振り絞る浅香萌。その膝に私はとうとう力着きて倒れたのである。温かいものが私の身体を包み込む。浅香萌が私を抱き寄せているような感じがした。瞼を開ける体力も残ってない私は、彼女がそうしてくれているのだろうと信じた。
「私・・・私・・・」
酸素がかなり薄くなっているらしく、彼女の言葉もやっと精一杯の様子である。薄れ行く意識の中で、好きな人と最期が一緒でよかったと思った。最後に残った記憶は唇に何か柔らかく温かい物が触れた感触だけだった・・・。
それから何時間が経過しただろうか。私は、
「先輩!先輩!」
と激しく身体を揺さぶられているのに気付いた。
「その声は・・・南川さん?」
私はうっすらと目を開けた。私は足を摩った。確かにある。
「ある・・・、という事はぼく生きてるの?」
譫言のように私は呟く。
「萌ちゃんは・・・。ぼくと一緒にいた女の子は・・・」
私はバネ時掛けの人形のように跳ね起きた。見覚えのある顔が隣のベッドを親指で指差した。
「彼女ならベッドで寝てるよ。医師の診断だと命に別状はないそうだ」
隣の少女はスースーと寝息を立てている。私はほっと安堵した。
「西口警部?どうしてここに」
「ああ、事件を頼もうと思ったら、いないもんでな。国家権力を行使させてもらったよ」
と警察手帳を見せながら言った。警部は皆からの注目の的となっているのに気付き、ぎこちなく咳払いをした。
「冗談だよ。お前の部下を捕まえて訊いたら快く『高校時代の後輩の結婚式に行かれましたよ』と言ってくれたよ」
「ああ、そう」
と私は拍子抜けしてしまった。
「それで、原彬さんの姿が見えなませんけど?」
西口警部は、声を潜めて服毒自殺した事を告げた。私は驚きの色を隠せなかった。
「遺書だ。一応、お前宛になっていたからな」
私はびりびりと破った。
FILE27、遺書
私は主人である南章三さんを殺害し、雪子さん、高明さん、清明さんも殺すつもりでした。最初あった時に殺すつもりなどもちろん全くありませんでした。私はそこまで酷い男ではありません。まあ、一人を殺してしまった今の私に取って、そんな事は単なる言い訳に過ぎませんが。
まず殺害方法からお話ししましょう。皆さんは密室だ、密室だと騒いでいたようですが、実は私はカーテンの中に隠れていたのです。まさにシェイクスピアの『マクベス』に出てくるバーナムの森(反乱軍の指揮官、マクダフはバーナムの森に隠れて反乱の機会を窺った)のように殺人の機会を窺っていました。殺害方法を絞殺にしたのも、刺殺や惨殺だと私の体に付着した血痕がカーテンの内側に着いてしまい、この密室トリックがバレてしまう可能性があったからです。
次男、高明さんの婚約者、さくらさんをスケープ・ゴート(罪の着せられ役)として用意しました。私は章三さんが度々、実におぞましい事ですが、地下通路を作って覗きに行っていたのを知っていたからです。この事実を知ったのは章三さんの手の汚れを見た時です。変だと思ってブランディーを飲んで酔払っている時に訊きました。そうしたら、彼は下劣な笑みを浮かべてこう言いましたよ。
「君はいい女を連れてきてくれた。高明にやるのはもったいない」
とても、いつもの紳士的にふるまう彼とは似ても似付かない顔を持っていたのです。しかも彼は微塵も罪悪感を感じていなかったのです。彼は実に酷い男でした。しかし、それは私にとってさほど大きな問題ではありませんでした。私は道徳や正義のために人を殺すような“好い人”ではありません。
偶然出てきたので、私の殺害動機についてお話しします。私は、この会社を則るために、たまたま名古屋の栄辺りをぶらついていた十八、九の子に声を掛けました。それが南川さくらさんだったのです。彼女は可愛く、どことなく品のある正に私の信頼を得るためには最高の道具でした。
「えっ、私ですか?」
当然、始めは警戒心たっぷりでした。しかし、ナンパは見事成功。私は近くの喫茶店で一緒にお茶でも飲まないか、と誘いました。私はすぐさま用件を切り出さず、世間話をしたり恋人の話をしたりしました。彼女が私にすぐさま飛びついた理由もなんとなしに解りました。彼女は失恋間もなかったのです。私は計画とは関係なしに、彼女を振ったという男の名前を訊きました。好奇心に駆られたのです。有沢翔治という名がその男の名前でした。
私は失恋の傷を持つの彼女と出会え、計画の第一歩は滑りだし好調でした。
「君にとっておきの人がいる。また明日来れるかい?」
「え、ええ・・・。まあ・・・・」
彼女は一瞬、躊躇ったようでした。無理もありません。知らない人から声を掛けられ、挙句の果てには男を紹介すると言うんですから。
「キャッチセールスとかだったら結構ですので」
と言いました。大丈夫だと私は言いました。高明さんは顔だちも良く、誠実でしたので、きっと行けると思いました。次の日、私は彼女との待ち合わせ場所に彼を連れて行きました。彼女は手を振ってくれました。
半ば強引でしたが長男があの様子では仕方ありません。本当はああいう古い式たりの残る村では長男が家督の一切を継ぐという考え方が一般的でした。けど私は、実力者が家督を相続するべきだという考え方を熱心に説得しました。章三さんも私に折れました。
さてさくらさんと、高明さんの方は順調でした。結婚間違いなしと言う関係です。案の定、彼らは婚約し挙式は九月か十月に挙げることにしたそうです。これで私は事実上の南家の支配権を手に入れました。しかし、欲望という物はどんどん広がって行く物です。今度は事実上ではなくきちんとした支配権が欲しくなりました。そのためには、まず、章三を殺さなくてはいけません。
殺した時点では、人の人生って案外あっけないものだとしか感じませんでした。私は、まあ、有沢さん、あなたも知っての通りです。私は二人の彼の息子に電話を掛けました。そして、警察にもさくらさんをスケープ・ゴートにすべくパーティー用のボイス・チェンジャーを用いて電話をしたのです。
しかし、先日辺りから急に罪悪感という物が沸いてきました。私は罪をここに自白し、自殺する次第です。
FILE28、挙式
「さくらさん、幸せそうね」
まるで雪のように白い、ウェディング・ドレスを身に纏ったのを見て浅香萌は言った。そして、その次に彼女がしたのは溜め息である。
「私もあんな日が来るといいな・・・」
「萌ちゃんにはまだ早いよ」
私は意地悪っぽく言った。
「失礼ね、私十六才よ。法律的には婚約オーケーでしょ」
「じゃあ、一人でお嫁さんになるつもり?」
私はニヤニヤ意地悪く笑って言った。
「えー、突然ですがここで来客者の有沢翔治様よりスピーチをお願いしたいと」
正にゲリラ的だ。私は第一次大戦、ドイツ軍のユー・ボート無差別攻撃に巻き込まれたアメリカの民間船の心境になった。
「南川さん・・・・!!!」
私は心の中で後輩を恨んだ。東宅の一件もあるし、本当に恩知らずの奴だ。私は報復として軽い彼女の失敗談をスピーチした。
「あー、緊張した。スピーチってあんまり得意じゃないんだよね」
「えー、でも結構巧かったと思うけど。内容はともかく」
「妹」はオードブルを頬張りながら言った。
「おっ、いよいよブーケ・トスだよ」
「いいの。いいの。どうせ私はまだ十六才ですよーだ」
と言いながら目の前に出された豪勢な料理に箸をつける。
「色気より食気か」
「何?それ?ひっどーい」
笑いながら彼女は言う。私は後輩の投げたブーケを目で追った。奇麗な放物線を描き、浅香萌に入っていった・・・
FILE29、フィガロにて
「結局、脅迫犯は解らずじまいか」
フィガロのマスターがカウンターで印刷した私の小説を読み終わった後で言った。
「まあ。いいや。はい、これ」
彼は私にコーヒーの回数券を渡した。三十回分・・・と思ったら二十回分しかない。
「ん?いつもより少なくないですか?」
「脅迫状の犯人が解けなかっただろ?あれでマイナスだ」
「ああ。あれですか、彼女の狂言です」
私はさらりと言ってのけた。
「ぼくを結婚式へ招待するためのね」
カランカラン、という小気味よい鐘の音とともに姿を表したのは萌ちゃんだった。
「読ませてもらったよ、なかなか面白かったぜ」
マスターは私のクリップ止めの小説を彼女に見せて言った。『Mの悲劇』とゴシックで書かれた大きめの文字が目に止まる。
「特に生き埋めになる所」
「面白がらないでくださいよ。本当、死ぬかと思ったんですから」
萌ちゃんが座りながら言う。
「あっ、そうだ。萌ちゃん」
私が言うと、
「な、なに?」
「地下通路で生き埋めになった時だけど」
彼女は真赤になった。
「う、うん」
「ぼくがどうかした?ゴメン、最後の方聞き取れなくてさ」
「もう・・・。じゃあ一回だけしか言わないからね」
「うん」
彼女が言いかけたと同時にマスターが皿を落としたのである。彼女の声はガシャンと言う皿の割れる音に掻き消される。
「おっと、行けね」
マスターは満面のニヤニヤ笑いを浮かべて言う。・・・・ひょっとしてあんたらグルか?
「ごめん。もう一回」
私は人差し指を立てて言った。
「ダーメ!一回だけって言ったでしょ」
「今のは無しでしょう。マスターが皿割っちゃったんだから!」
「でも私は言ったもん!」
店を出てからも、そんな私たちのやり取りが雲一つない十月の空に掻き消されるのだった。
二〇〇二年三月十八日、名古屋の事務所にて執筆完了
この作品はいかがでしたか?
一言でも構いませんので、感想をお聞かせください。