声のしたほうへ顔を向けると、そこには刑事部の部長、吉川宗司がデスクに座って手招きしていた。なんだろうと思いながらも、獄盛は近づいていった。
「どうだった、事件捜査のほうは?」
獄盛が目の前に立ち止まるなり、そう吉川は訊いた。
「あまり思わしくありませんね。見てきましたが、殺じ……いや、殺物であることが明らかである事ぐらいしか分かりませんでした」
実際の所は、獄盛はこれが現実であるのかどうかという思案のために脳を働かせなければならなかったため、他の事、現場の分析などまでには頭が及ばなかったのだった。
「そうか……お前はもう捜査陣から降りて良いぞ」
「は?」
意外な言葉に暫し呆然とする獄盛。営業成績トップの営業マンが、絶好調の時期にいきなりリストラを宣告されたようなものだった。
その後、獄盛は執拗に問い質してみたが、部長の返事は、とにかく帰ってよく考えろ、の一点張りだった。
第三章――クリスマスプレゼントの代償
目が覚めると、そこはベッドの上だった。部長に捜査から外されて、それからすぐに家に帰って眠りについたはずだ。しかし、ここは家ではない。布団で寝ていた筈がベッドになっているのだ。意識が朦朧としている。ここはどこだ? 私は起き上がろうとした。しかし身体はいうことをきかない。私が唸っていると近くで人の声がした。
「おや、御目覚めですかね?」
依然朦朧とした意識の中、目を凝らして声にした方を凝視する。するとそこには、城嶋一孝が椅子に座ってこちらを見ていた。そこで獄盛は彼に訊いた。
「うぅん……何だ……ここは、どこだ……?」
「病院ですよ」
「病院、だと……何故だ?」
「…………」
そこで獄盛は上半身を起こし、真正面から城嶋の顔を見つめ、
「何故答えない?」
「え、いや……実は、獄盛警部は家に帰って眠っている間に盗みに入られたんですよ。そこで寝ている獄盛警部に、強盗は更にクロロホルムを使って眠りを完全にしようとしたんです。しかし、クロロホルムはドラマのように上手く作用せずに獄盛さんが死にかかることになったってわけです」
「何、俺は死にかけたのか?!」
「そうですよ」
城嶋は平然と答える。彼の顔に心配の様子は微塵も見受けられない。
「それにしては冷たいな、城嶋。俺が死に掛かったってのに」
「何ですか獄盛警部。僕に心配してほしいんですか? そりゃ、獄盛警部が病院に担ぎ込まれた時は心配しましたよ。手柄を分けてくれる先輩がいなくなっちゃ困るって」
「何ィ?」
「冗談ですって」
そう言ってハハハと城嶋は笑った。
「それとも今から泣きましょうか? え~ん、獄盛警部が死にそうだよぉって」
「はん。そんなものお断りだ。お前の下手くそな演技を見るぐらいだったら実際死んだ方がマシだ」
「だったら死んでください」
「何ィ?!」
獄盛は慌てて城嶋の顔を見つめる。すると城嶋はいつになく真剣な顔になっていた。獄盛にはこれが演技とは思えなかった。そうして沈黙していると、次第に恐怖が湧きあがって来て、獄盛は声が出せなくなってしまった。
「そうだ、死にたまえ」
突然病室の扉が押し開かれ、吉川宗司が現れた。彼の奇妙な第一声も、獄盛を圧倒するに充分だった。獄盛は呆然と彼ら二人の顔を見比べた。吉川は城嶋の隣にパイプ椅子を持ってきて座っている。するとまた、
「死んだ方がいい、獄盛」
と、前者二人と同じような台詞を言いながら部屋に入ってくる者があった。検死官の本山達哉だった。彼もまたパイプ椅子を部屋の隅から引っ張ってきて、吉川の隣に座した。三人とも一言同じような台詞を行ってからは無言である。獄盛には何が起こったのか理解できなかった。
三十分もそうしていただろうか。獄盛にはそれほどの時間に感じられたが、実際にはほんの五分ほどしか時間は過ぎていなかった。重く苦しい沈黙が、その五分を三十分も経過したように感じさせた。突然、その沈黙は破られた。破ったのは吉川宗司だった。
「何もわからないようだな、やはり頭がどうにかなってしまったようだ」
そんな事を言われたものだから、獄盛はついに口を開き声を発することが出来た。
「私は正常だ!」
「果たして本当にそうかな?」
「本当だとも。部長達こそどうかしている! 一体何故私が死ななければいけないんです?」
「本当にわからないようだな」
本山が言った。
「分かった。仕方がないから教えてやろう。そして改心するんだ。良いね」
吉川が言う。が、獄盛は一体何を改心すれば良いのか分からなかったため何も答えず、ただ怪訝な表情をするだけだった。
まず聞かされたのが今が西暦何年か。獄盛は二〇〇四年だろう、と答えたが吉川は首を横に振り、教えた答えは今は西暦二五〇四年だということだった。
「何? そんなわけないだろう。二五〇四年だと? 馬鹿な。そんな未来じゃロボットでも出来てるんじゃないか?」
獄盛は鼻で嘲笑う。
「だが事実なんだよ。世界は君が思っているほど進歩しなかったんだ。今も五百年前も、大差の無い暮らし振りさ。ただ一点を除いてはね」
「ただ一点?」
「そうだ。キリスト教の世界的伝播。今やキリスト教は世界教となっている」
「はぁ?」
獄盛は口をあんぐりと開け、吉川を凝視している。
キリスト教が世界教に? 一宗教がそこまで普及するものなのか? 自分もキリスト教徒ではあるが、なら俺は国の政策によって無理矢理キリスト教徒になったのか? 確かにあまり信仰心があるとは言えない態度ではあるが、そんな覚えは無い。自分は確かに、自ら望んでキリスト教徒になった。その記憶がちゃんとある。そしてその時、キリスト教が世界教になどなってはいなかった。そこで一つ、訊くべき点に思い当たったので獄盛は吉川に問うた。
「いつからだ。いつからそんなことになっている?」
「二〇〇四年からだ。新聞を見なかったのか?」
新聞、と聞いて思い出すこと。それはあの、自宅にあった二〇〇四年の新聞。あれには確か『殺物論』がどうしたとか書かれていた。そうか、あれは確かに全てに対し平等にというキリスト教の理念に適っている。だからキリスト教が世界教化したのか。獄盛は妙に納得する思いだった。
しかし、あれは五百年前の新聞。その新聞が家にあることが何故吉川に分かった?
「何故俺の家に五百年前の新聞があることを知っているんだ? まさかあれは部長がやったことなのか?」
「ふ、その通りだ。驚いたか?」
ふん、と鼻で息をして獄盛は黙り込んだ。そこで吉川は話の続きを始める。
「そうして、さっきも言ったように、今年はキリスト教世界教化五百周年の年だ。そこであるキャンペーンが行われる事になった。それが『全人類信仰心大幅増幅キャンペーン』だ」
面白く無さそうな名のキャンペーンだなと一瞬呑気に思った獄盛だったが、すぐにその意味を捉えて硬直した。うっすらと自分の立場が分かりかけたからだ。
「それで、だ。もう薄々気付いているだろうが、君もそのキャンペーンの対象の一人となった。君は何故か、十二月に入ってから様子がおかしくなってきていたので、我々が目をつけていたんだ。そうしたら突然君の信仰心が全くと言って良いほど無くなってしまった為にこういうことになった」
「こういうこととはどういうことだ。もっと詳しく説明してくれ」
獄盛が叫ぶようにして頼んだ。
「ああ、叫ばなくても元々そのつもりさ」
そう言ったのは本山だった。城嶋はずっと黙り込んだままだ。
「君は十二月に入って信仰心が落ち始めた。そのことは覚えているかい?」
また話し手が吉川に戻る。
「いいや。というかその前に、俺は元々信仰心が薄かった」
そう答えると吉川も本山も城嶋も、三人ともが怪訝な表情をして獄盛の顔をうかがった。何事かと思い、獄盛も三人の顔を交互に見返す。
「そうか、そこまで重症だとはな。まぁとにかく、君は信仰心が薄くなってきた、そして我々が目をつけた」
獄盛は頷き、吉川は続ける。
「そして今回の大掛かりな作戦が展開されたわけだ。君が物の大切さを理解できるように、君の部屋にあの新聞を置き――君の部屋に入るのには何の苦も無かったよ、大家さんも当然キリスト教徒だからね――、殺物課というものを急いでB県警察署に設けた。勿論仮にだが。そして実際に殺物事件を君に捜査させて物の大切さを理解させようとした。だが、君は私達の思惑など考えもせずに、信仰心の欠片も見せようとしなかった。そしてここに至る。
どうだい、案外簡単な経路だったろう?」
「……まぁ、そうだな。思ったより複雑ではなかったが……それで? 依然信仰心の高まらない俺はどうなるんだ?」
それを聞くと吉川達三人は、さっと顔の色を変え、何か怖ろしいことを企む狂人のような目になった。そして、彼らは懐から皆が皆同じ物を取り出した。それは銀色に輝く鋭利なナイフだった。
第四章――クリスマスプレゼント
「うわぁ、助けてくれぇ!!」とある病院の個室で男が叫んでいた。彼は三十分も前から叫んだり唸ったりとしきりにうなされている。しかし、どうしても目を覚まさない。
「俺が悪かった、悪かったから……これからは物を大切にするから……うわぁ!!」
「獄盛さん、獄盛さん、しっかりしてください」
男の名前を呼びながら男の肩を揺さぶり、起こそうと奮闘する女がいた。この個室には今、彼ら二人だけがいる。
「獄盛さん、獄盛さん」
女はそうして尚も男を起こそうとしていたが、結局途中で諦め、近くの椅子に腰掛けた。女がそうしてからも男はうなされ続けている。
女はここの病院の看護婦で、名を釜谷祐子という。彼女は大変仕事熱心で他の患者達からは勿論、看護婦仲間にも尊敬されているベテラン・ナースの看護部長である。
彼女が獄盛勲の看護を担当する事になったのには、ちょっとした神の悪戯的な事情がある。これは本当に、『神の悪戯』とでも形容しなければ他になんとも言い難い、奇劇的な事情だった。
午前十時、釜谷は遅刻して漸く病院の職員用入り口の扉をくぐった。出勤途中に彼女の運転する車の前方で事故があったらしく、随分な大回りをしなければならなかったのだ。釜谷は怪我人のことと時間を気にしつつも迂回してやってきた。そしてナース・ステーションに着いたら、部長なのに遅刻か、というように思われないだろうかと心配していたのだが。
通常なら七人ほどの看護婦がいるはずのナース・ステーションに、誰一人として看護婦らしい姿が見受けられない。事故か何か大勢の看護婦が必要となる急患でも入ったのだろうかと一瞬思ったが、ナース・ステーションに来るまでの廊下や入り口付近などはいたって静かで、急患が入ったような雰囲気ではなかった。
と、そこへ一人の男性研修医がナース・ステーションの前を通っていく。彼は確か第一外科の研修医、木津正治君だった、ということを思い出したので釜谷は彼に訊いてみることにした。
「ちょっと、木津君」
そう呼びかけると、ナース・ステーションを少し通り過ぎていた木津は、振り向き、はいと応えて釜谷のほうへ近づいてきた。その顔は妙にウキウキとしている。
「何でしょうか?」
「こんなことをあなたに訊くのも変な話なんだけれども……看護婦の皆、どうしちゃったのか知らない? ナース・ステーションにはこの通り、誰の姿も見えないのよ」
「あれ、本当ですね。一体どうしちゃったんでしょう。すみません、僕には分かりません。……あ、でも、何か御手伝いできる事があれば言ってください、何でも手伝いますから」
「ああ、いいのよ、大丈夫。……でも皆、どうしちゃったのかしらねぇ」
「皆さん、風邪とか」
「風邪? そんなに流行ってるのかしら」
「う~ん、どうなんでしょう。……そうだ、皆さん昨日はどうでしたか、風邪気味とかそんな様子はありませんでした?」
「ううん、そんな様子は無かったわ。皆いたって元気にしてた」
「そうですか」
木津がそう言うと暫く沈黙が出来た。
木津正治は背が高く痩せ型で、近寄ると釜谷は彼に見下ろされる格好になる。つまり釜谷は木津を見上げる格好になる。そうしていると釜谷は時折首が疲れるために首だけ正面を向けて上目遣いに木津を見るようになるのだが、今もまた釜谷はそうして何か次の言葉を発しようとしていた。しかし、その言葉を遮るようにして木津が口を開いた。
「釜谷さん」
その声は切羽詰ったようで、急に緊張味をおび始めた。
「な、何?」
木津の声に気圧されるようにどもりながら釜谷は問う。
「釜谷さん、僕はあなたが好きです」
「ええ?」
釜谷は我が耳を疑った。しかし、すぐに別のことを考えた。それは、木津は仕事仲間として自分の事が好きだと、そう言っているのだという解釈の仕方だった。木津は誰が見ても二枚目顔だと断言するほどのハンサムで、年齢もまだ二十代半ばあたりだった筈だ。それに比べ、私はもう四十五歳のおばさん。親と子ほども年が離れている。どう考えても今の木津の言葉が<愛している>という意味のこもった言葉とは思えない。
そうだ、そうに決まっているではないか、自分は何を焦っているのかと考え、釜谷は笑って言った。
「急にどうしたの? ええ、私もあなたは好きよ、真面目でちゃんと先生たちの指示通りに働いているようだし、私達ナースにも色々と気を遣ってくれているって、皆噂してるもの」
「そうじゃないんです、違うんです。……その、ですから、僕は……釜谷さんが好きなんです」
意外なことに木津は、消え入りそうな声ではあるが反論をしてきた。
「……あはは、本当に急にどうしちゃったのよ、いつもの木津君らしくないわよ」
「釜谷さん、信じられないという気持ちは分かります。でも僕は本気なんです。本気で釜谷さんのことが好きです。いえ、恥ずかしいからこれは言わないでおこうかと思っていたんですが、やっぱり言います。釜谷さん、僕は本気で、あなたのことを愛しています」
突然の告白に、釜谷は初め沈黙で答えるより他無かった。いくら本気で、と何度も言われても、やはり信じ難いことである。こんなハンサムで真面目な子がどうして、そんな思いばかりが彼女の頭を駆け巡った。
『ハンサムで真面目な<子>』そうだ、私は彼の事を年齢的に言って我が子のような感じで見ている。自分の子どもから愛の告白をされても困るばかりだ。しかし彼は我が子ではない。彼が本当に自分の子だったなら、私のこれからの対応がどんなに楽だったろうと釜谷は思った。
釜谷自身の気持ちはというと、実際まんざらでもなかった。研修医と、収入はまだ低いが、彼は優秀だからもうすぐ立派な外科医になるだろう。そうすれば釜谷もこの年になって玉の輿が叶うわけだ。そんな収入的な面とは関係無しに考えても、彼のことは釜谷は結婚しても良いぐらいに好きだったので、これが本当なら願っても無い話だった。しかし、どうも話が上手すぎる。信じがたい。
それでも、いつまでも黙っているわけにもいかないので、とにかく一番気になっている所を訊いてみる事にした。
「木津君。それ、本当に本気なの?」
「はい。本気も本気、マジですよ。釜谷さん、結婚はされてませんでしたよね?」
「ええ、結婚はしてないわよ」
「ひとまず安心しました。それで、返事の方は……?」
「返事?」
「ああ、そうでした。僕も緊張して焦ってしまいまして、この通り冷や汗びっしょりで」
それは本当で、木津は今や冷や汗で顔中汗だらけだった。前髪の黒髪にも額から汗が伝って、前髪は額に張り付いている。
「ええと、では、改めて言わせていただきます」
そこまで言って木津はわざとらしく空咳をひとつして、続けた。
「僕は釜谷さんのことを愛しています。ですから、釜谷さんさえよろしければ、僕と付き合ってください。いきなり結婚なんて無理は言いません。暫く付き合って、もしその間に僕の嫌な所を見つけて、それがどうしても我慢なら無いような事だったら、遠慮なくフッてください。僕も、釜谷さんの嫌な所なんてないでしょうけど、もしあってそれが我慢ならないようなら、僕から釜谷さんをフルこともあるかもしれません。そのことを了承していただいた上で、この返事をください。もう一度言いますが、これは本気です」
なんとちゃんとした告白だろう、真面目で誠実な木津君らしい告白だ。釜谷はそう思った。
どうやら彼の気持ちは本物らしい。未だに信じきれぬ気持ちはあるものの、彼の態度はかなり真剣なのは釜谷にも分かる。もう騙されたと思って返事をしてしまおう、彼女は遂にそう決心した。
「ありがとう。嬉しいわ。まさかこの年になって、あなたみたいな若くて二枚目な子に告白されるなんて夢にも思わなかったけれど。ええ、喜んでお受けするわ」
そう言い終るのを聴くと、木津の顔はみるみるほころんでいって、ついには満面に笑顔をたたえた。そして遂には感情を爆発させ、叫んだ。
「やったー!! ありがとうございます。嬉しいです。いや、信じてくださってどうもありがとうございます。もう少し疑われるんじゃないかって心配してたんですが、良かったぁ。それじゃ、付き合っていただけるんですね?」
「ええ、もちろん」
「何を叫んでいるんです?」
釜谷の返事を確かめ、もう一度、やった、と言おうとしていた木津に問いかけるものがいた。二人が揃って声のするほうを見ると、そこにはなんと婦長が立っていて、こちらに向かってきていた。ナース・ステーションの角の向こう側から木津の叫び声を聞きつけてやってきたらしい。
「どうしたんですか?」
二人の正面に立ち止まり、改めて婦長がもう一度訊く。釜谷も木津も、婦長に本当の事を話す気になどはなれないので、二人して懸命に取り繕った。それで漸く婦長に許してもらうと、
「じゃあ釜谷さん、ちょっとこっちへ」
そう言って婦長は、先ほど来た道へと戻っていく。一声掛けてからからは釜谷にも目もくれずに行ってしまったので、釜谷はさっき自分は呼ばれたんだったか、と考え込む事になった。すると、婦長が呼んでいる声がするので、急いで、はい、と応えて駆け出した。
ナース・ステーションの角を曲がると、暫く左右に病室のある広い廊下が続く。その廊下の真中を歩いている婦長に追い付いた釜谷は、まず訊いた。
「あの婦長、ちょっと……」
「何?」
「私以外のナースは一体、どうしたんでしょうか? ナース・ステーションには誰もいなかったんですが」
「ああ、彼女達は皆欠勤よ」
「欠勤、ですか。またどうしてですか?」
「風邪とか頭痛とか、ああ、水野さんは産休らしいわよ」
「皆そんな病気なんですか?」
「ええそうよ。それで今日は誰も来ないかと思っていたんだけれど、あなたが来てくれて助かったわ。今からあなたには個室を担当してもらう事にしたの」
なんともあっさりした回答だった。性格のキツイことで有名な婦長が、何の愚痴もこぼさずにただ皆病欠だという説明をした。婦長まで病気になったのかと訊きたい衝動に駆られたが、もちろんそんなことは実行できず、それに自分が今から担当することになる個室の患者様のほうへ興味がいった。
「個室ですか。どんな患者様ですか?」
「頭を強く打ったらしいの。今は意識不明で眠っているはずです」
そういう言い方をするということは事故か。誰かに殴られたりしたのなら、『打たれた』とかいう言い方をするだろう。
「ここですよ」
気付くと婦長は右手を上げてある個室のドアの脇に留めてあるネームプレートを指していて、今その手を下ろし、ドアをスライドさせて開け始めた。ネームプレートには『獄盛 勲』とマジックペン書かれていた。苗字は何と読むのか分からなかった。因みに下の名前は『イサオ』だろう。
「獄盛さん、気分はいかがですか?」
婦長がそういいながらベッドに近寄っていくので、患者の苗字は『タケモリ』と読むのだと知った。
患者様はベッドの上で瞼を閉じ、軽く唸っていた。
「まぁ、特に何もする事は無いのだけれど、ちゃんと見張っててくれる? あなたはこれからずっと、この患者様の傷が完治するまでそうしていてくれればそれ以外は部下のナース達にいつも通り指示を出していてくれればいいから。つまり、当分の間はこの仕事をあなたは最優先にして、他の仕事はしなくても良いってこと。簡単でしょ」
「え? あ、はい、分かりました」
「何か言いたそうな顔ね。まぁ、良いわ。あなたのそういう聞きたくても聞かないってところがあるから、あなたが今日来てくれていたのは本当に助かったわ。というのも、あなたは治療中は勿論のこと、患者様が退院した後もずっと一生涯、あなたは彼の担当を持った事、どんな患者だったかなど、今回の事実を絶対に口外してはいけません。これは命令です。分かりましたね?」
「は、はい。絶対口外しません」
「木津君にもよ?」
なんと、婦長は私達の会話を盗み聞きしていたのか。これだから彼女の肩を持つナースが現れない。
「はい、分かりました」
婦長の命令となれば守るしかない。木津君にも言えないことになったが、それも仕方ないだろう。もし言って、そのことがバレでもしたら恐らくクビにされるだろう。そうなっても玉の輿でなんとかなる、とも言い切れない。釜谷は確実性の欠いた『賭け』というものをやらない主義だったし、またそのことを婦長もよく心得ていたので、これは全く婦長の思惑通りに事が進んだと言ってよい。
こうして、釜谷祐子は暫くの間、獄盛勲専門のナースということになった。
幕間
ある大学の講堂で、一人の教授が、大勢の生徒に向かって熱弁を振るっていた。彼は本文を話し始める前に、その文の題名ともなる言葉を先に口にした。それは以下のようなものだった。『神は全てに平等である』
そして彼は語りだす。
「聖があれば邪がある。そしてその<間>となる存在もまたある。
分かりやすく言えば、コインにたとえることが出来る。
コインには表裏があり、そしてそのコインの表面と裏面の間の厚さという<間>がある。
<間>の厚さによって表面と裏面の距離が変わるのは言わずもがなだが、それは聖と邪の関係においても、いや他の全てのことにおいても言えることだと思う。
<間>の厚さが表と裏、聖と邪の距離を左右するということは、つまり、<間>こそが全ての支配者――神なのではないか。言い換えれば、神は<間>なのではないか。
その地点は、全てに平等で、絶対的な存在であるはずの神にふさわしい地点と言える。
<間>という地点は数直線でも考える事が出来る。そうすることによって分かってくることがあるので、以下で少し考えてみようと思う。
では、数直線でいう間とは何だろうか。それは、一般的に言えば0という基点だろう。基点ならどこでもいいから、別にマイナス一でも七でもなんでも良いが、ここでは分かりやすく0で考える。
数直線には0などの基点や、右へ延びる正の領域と左へ延びる負の領域がある。正と負は、聖と邪の関係に良く似ている。これはそのまま置き換えることが可能なものだと言えるだろう。
では、正の領域を聖と、負の領域を邪と置いてみると、これは間の神を境にした勢力図と見ることが出来る。
そして聖の領域も邪の領域も、0の方とは逆の方向の端の位置は、それぞれの勢力の大きさによって決まる。
しかし、聖も邪も、どちらがどれだけ多かれど、やはり神の支配からは逃れられない。基点が移動すれば勢力の大きさなど簡単に逆転することだって有り得るのだ。
例えば、聖が百まであり、邪がマイナス五百まであったとしよう。それらの勢力は絶対数によって比較が出来るから、勢力の大きさはそれぞれ百と五百となる。差は四百。邪が勝っている。しかし、基点がマイナス二百まで移動したら、それぞれの絶対数は三百と三百。等しくなった。
だが、基点――神が、いつもそうすんなりと均衡を保たせてくれるわけでもないようだ。それは私達の暮らす世界が表している。
歴史は戦争を繰り返してきた。その際、戦争する国同士の領土が広くなったり狭くなったり、あるいは滅ぼされたりもした。しかし、何事にも終わりは来る。戦争は何度も繰り返されたが、その分何度も終わってきた。いや、まだ続いているところもあるぞと思われるかもしれないが、それだっていつかは終わる。地球が滅べばそれで御終いだ。
そうして今の均衡の取れた形を形成してきた。この世界の何処か、あるいは何かとして、基点が、神が存在しているから均衡は保たれる。
だが、基点は動く。だから世界は戦争を繰り返してきた。基点は、神は気まぐれらしい。
それでも、いかに気まぐれであろうと神は平等である。聖であろうと邪であろうと関係ない。全てに対して平等なのだ。だから悪人がいる。善人がいる。地獄がある。天国がある。マイナスがある。プラスがある。
地獄と天国があると言ったが、本当にあるかどうかなどは関係ない。人がそう考えた以上、もうそれはこれらの例に当てはまると言って良い。
では、今日はちょうどクリスマスなので、以上の考えをクリスマスに当てはめて考えてみよう。
だがその前に、諸君らにはさっき配った、ホチキスで留めたプリントを見ていただきたい。まずは表紙を捲って目次を見てくれ」
彼の長い前置きが漸く終わったと知ると、生徒たちは各々プリントを一枚捲って、目次を見た。因みに表紙には何も書かれていない白紙だった。目次の内容は以下のようなものだった。
*目次*プロローグ第一章――強盗殺人事件第二章――殺物事件第三章――クリスマスプレゼントの代償第四章――クリスマスプレゼント |
「それは私が昨日までの三日間をかけて大急ぎで作った小説だ。推敲なんてろくにしていないし、小説など書いた事も無かったから怖ろしく読みにくいかもしれない。だが我慢してくれ。
その小説は、クリスマスに材を取った、先ほど私が説明したような神の全てへの平等について小説として作ったものだ。諸君らはそれを読み、結末部を予測し、更にその予測した結果についての感想と、そして、見ての通りその小説の表紙には、あるはずの題名が無い。というわけで、その小説に相応しい題名も考え、それらをまとめてレポートとして提出してもらいたい。つまり、その小説はそれで終わりではなく、最終章の部分が欠けているというわけだ。その最終章部分は、レポート提出後に渡す。提出日は、来週のこの授業の時に集める」
教授がそういい終わると、ちょうど昼休みのチャイムが鳴り響いた。鳴り終わったのを確認すると、教授は、
「よし、諸君らは、レポートの提出を忘れないように。来週だぞ。では、解散」
そして一週間後、生徒達はレポートを提出し、代わりに教授は小説の結部、最終章のプリントを渡した。
終章――神の悪戯
獄盛勲は病院のベッドの上で上体を起こしていた。彼は周囲を見回し、その後自分の身体を見た。窓の外では満月が青白く輝いていて、雪も降っていた。しんしんと降る、穏やかな雪だ。どうやら自分はどこかの病院に入院しているらしいということは分かったが、はたして何故こんなことになったのかが分からない。思い出そうとしてみる。すると思い出すことが出来た。坂下に刺されたのだ。そのことに気付いて、自分の腹を触ってみた。しかし、驚いたことに傷が無い。手当てをしたらしき痕跡も、包帯も何も無いのだ。これはどうしたことかと思い頭に手を当てると、なんとそこに包帯が巻いてあった。額の上にガーゼが間に挟まれているから、傷は額にあるらしい。しかし、腹に刺された傷はどうしたのか。
獄盛がそうして自分の身体をいじくっていると、個室の扉がゆっくりと開かれた。扉は全開には開かれず半分ほどだけ開かれただけで止まり、またゆっくりとしたスピードで、人が入ってきた。いや、人ではなかった! 入ってきたのはなんとミイラだった! 全身に包帯をぐるぐるまきにしたミイラが入ってきた。しかしおかしなことに、そのミイラは病院の入院患者が着る薄青い服を包帯の上から着ていた。ミイラの入院患者? 死んでいる者が入院するとはおかしな話だ。
獄盛が驚いて何も言えずにいると、ミイラはどんどん部屋の中へ入ってくる。そして獄盛の方へ近づいてくる。ミイラは、よく映画で見るように上手く歩けないようで、手を前に伸ばし前方に障害物がないかを確かめつつといった調子で、包帯で縛られているせいか棒の様に硬くなった足を一歩一歩ゆっくりと動かして進んでいる。
顔をよく見ると獄盛はギョッとした。ミイラにはまだちゃんと目がついていたのだ。両目ともパッチリと見開かれ、獄盛のことを凝視している。それに気付いて漸く獄盛は声をだした。
「うっ、うわぁ! な、なな、何なんだお前は!?」
年甲斐もなく大声を上げて大慌てに慌てる獄盛だったが、ミイラが何か呟いているということには気付いた。ミイラは獄盛のベッドのすぐ近くまで来て立ち止まり、何か言っていた。言葉は聞こえないが口が動いているのでそれと分かる。獄盛は耳を澄ました。
「獄盛さん……」
ミイラがそう言った気がしたので驚いた。
「た、けもり、さん……私……さかし……た」
獄盛さん、私探した。そう聞こえた。俺がミイラなんか探すものか、と思った。
それでも尚、ミイラは何か喋っている。と、突然咳き込むと、それで何かつっかえていたものでも取れたのか、急に饒舌になった。
「獄盛さん。私、坂下です」
そうはっきりと聞こえた。坂下……坂下紀子か!?
「坂下さん? 坂下紀子さんか?」
「はい、坂下です」
言われてみれば、目は坂下紀子の見覚えのある目だし、声も聞き覚えのある坂下紀子の声だった。この目の前にいるミイラのような格好をしたものは、坂下紀子であることに間違いは無さそうだった。
「こりゃ驚いた。これは一体どういうことだ。なんでまたそんなミイラみたいな格好して……一体どういうわけだ?」
彼女に刺された筈だというのに、不思議と恐怖は湧かなかった。彼女は味方だ、なんとなく獄盛は自分の中でそう決め付けていた。
「順を追ってご説明します。まさかこんなことになるなんて、正直私も驚いているんですが、少なくとも獄盛さんよりは事情に通じていると思います」
淡々と坂下は語りだす。今は女性らしい格好で足を斜めにして椅子に座っている。坂下紀子はいつもこのようにして座っていた。
「まずは、最初に起こった変化について。最初に起こった変化というのは、獄盛さんもお気づきのことと思いますが、クリスマスが二度繰り返された事です」
「ああ、そのことには気付いていた。だが俺以外の皆は別に知らないようだったから夢でも見たのかと思っていた。そうしたらその、なんだ、二回目のクリスマスとでも言おうか。その二回目のクリスマスの日に起きたらおかしなことになっていたから、こっちが夢で一回目のクリスマスのほうが現実なんだと思っていたが」
「違うんです。どちらも現実です。でも、一回目のクリスマスの日は無かった事になりましたが」
「ん?」
「一回目のクリスマスの日……私が、獄盛さんを刺しましたよね」
「ああ、あれは現実だったのか! しかし、傷がなくなっているんだ。何故だ?」
「それは、さっきも言いましたように、無かった事になったからです」
「無かった事? それがいまいち分からんのだが……全人類を皆タイムスリップさせてクリスマスがもう一回始まったっとでも言うのか?」
「まぁ、そんなところです」
「何? そんなこと出来るのか? そうか! 今は二五〇四年だからそういう技術もあるのか」
「え、二五〇四年? 今は二〇〇四年ですよ」
「何? しかしさっき部長たちは二五〇四年だと……ああ、あれは夢だったのかな」
「夢? どんな夢でした?」
「ん、ああ、吉川部長がそこに座って、左隣に城嶋、右隣に本山が座っていた。それで皆してこう言うんだ。今は二五〇四年で、キリスト教が世界教になっていて今はあるキャンペーン中だと」
「キャンペーン?」
「ああ、確か……『全人類信仰心大幅増幅キャンペーン』とか言ったかな。それで俺の信仰心が急に低くなったからと言って俺をそのキャンペーンの対象にと目をつけていたんだそうだ。それでいざキャンペーンになって、俺にある事件捜査をさせることになり、俺は捜査したが信仰心の増幅なんぞ出来るわけもなくキャンペーンは失敗。捜査陣から下ろされる事になり家に帰って寝たんだが、起きたらベッドの上で、今坂下さんのいる場所には城嶋が座っていた。それで吉川と本山も途中から入ってきて、そんなお前は死ねと言って部長達全員がいきなりナイフを取り出して俺に刺しかかってきたんだ。それから気がついたら、無事にベッドで寝ていたってわけだ。まったく意味が分からない」
「……ああ、きっと悪夢でしょう。それも意図的な」
「意図的な悪夢? 誰の意図だ?」
「神、です」
「…………」
坂下は体だけでなく頭までおかしくなってしまったのか、獄盛はそう考えて顔を歪めた。
「信じがたいでしょうが事実です。全ては神の意図したことなんです。神はサンタ・クロースという使者を使って子ども達にプレゼントを配る代わりに、こういった遊びを、いえ、悪戯と言った方が適切ですね。悪戯をプレゼントの代償としているんです。この悪戯は自然に、いえ神の意図によりもみ消されます。人々の記憶から消されるんです。
そして、サンタ・クロースについてなんですが……」
「ちょっと待ってくれ。神の意図したこと? 悪戯? それでその悪戯の記憶は都合よく皆の記憶から消えるってのか。まさに神だな」
「本当に神はいるんです」
「しかし、いきなりそんなこと言われても……」
「いきなりじゃないですよ。獄盛さんは体験したじゃないですか、クリスマスが二度あったでしょう?」
「そりゃあ……夢だったんじゃないかな」
「私だって体験してます」
「そうか、そうだなぁ……確かに、坂下さんもそうだと言うんだし、それにあれは夢にしてはかなりリアリティがあったからなぁ。神はいるのか……そうか、そんな気がしてきた。
分かった。そうと信じよう。では、続きを頼む」
「ありがとうございます。獄盛さんなら信じてくれると思ってました」
そう言って坂下は笑ったようだった。包帯の上から見たのでは、目が笑っていること以外、口元の包帯が少し吊りあがるぐらいしか変化が無いからよく分からないのだ。
彼女のこの笑いは、獄盛のロマンティストぶりを指してのことだろう。坂下と獄盛とは交友関係が長いので、坂下には彼の性格が分かっている。
やっぱりこいつは坂下さんだ。獄盛はあらためてそう思った。
「次に……そうですね、神の存在を信じてもらえたので大分話しやすくなりました。
今までの話をまとめますと、孤児院メリーフラワーで起こった強盗殺人事件に際して、私が獄盛さんを刺しました。そして神がそれを無かった事にするために、その日自体を無かった事にしてしまい、クリスマスがもう一度始まりました。しかし何故か、私と獄盛さんには記憶が残ったままの状態でした。そして二回目のクリスマスの日、獄盛さんがさっき自分で言ったようなこと――目が覚めたらベッドの上で、警察の仲間の方々に刺されたという悪夢を見たんでしたね。これは神の、ちょっとした悪戯でしょう。
そして、今にいたるわけですね」
「……うん、分かった。全ては神の悪戯だったわけか……しかし、どうして私達二人の記憶だけは残っているんだろう?」
「それも悪戯なんじゃないでしょうか」
「ふぅん。ところで、坂下さんは何故体中包帯でぐるぐる巻きなんだい? 入ってきた時はミイラかと思ったよ」
「はい、私にも実はよく分からないんですが、一回目のクリスマスの時、獄盛さんを刺し殺したと思ったんですが、そしたらいつの間にか意識を失っていたみたいで、起きたらこうなっていたんです。全身火傷だそうで……私が意識を回復したのを知ると、刑事さんたちがやってきて事情を訊きに着たんですが、逆に私の方が教えてもらう事になりました。何せ何がどうなって全身火傷なんてしたのか、さっぱりだったので……話によると、どうやら私は孤児院メリーフラワーで起こった強盗殺人事件の最有力容疑者らしいんです。それを聞いて考えたんですが、もしそれが事実だったなら……そんなことをした覚えはないですし、実際していないんですが、神によってそういう風にされたんだと思います。それで発覚を恐れた私は焼身自殺をはかった。しかし失敗し生き残る。そういうストーリーを警察も組み立ててくると思います」
「そうか……それも神の仕業……なんて酷い神なんだ」
「いえ、そんなことはありませんよ。神は平等ですから、こういう悪戯もすれば、逆にどこかに幸福をもたらしているでしょう。誰かの幸せを実現するためには、こうしてどこかに残酷な仕打ちをしなければならない……それがルールなんです。神が神在らしめるためには、こういうルールを守らなければいけないんです」
「……どうして、坂下さんはそんなに事情に詳しいんだ? 一体どうしてそんなことまで……?」
「……そんなことより、大事な話がまだ残っています。サンタ・クロースについてです」
「サンタ・クロース?」
意外なものの登場に、獄盛は目を丸くした。
「ええ、サンタ・クロースは神の使者だということはさっき言いましたよね。そのサンタ・クロースですが、何故彼は人類にプレゼントを無償で配っていると思いますか?」
「それは……良い人なんじゃない?」
「違います。全く逆と言わなければならないんです」
「全く逆?」
獄盛は一段と目を丸くした。
「はい。サンタ・クロースは、実は殺人狂だったんです。昔、まだクリスマスプレゼントをサンタが持ってくるという習慣が無かった時代。グリーン・ランドで、サンタ・クロースという名の男による子どもを狙った連続殺人事件が発生しました。サンタ・クロースは煙突を使って家の中に侵入し、子どもを殺し、そのついでに戦利品として物を盗んでいったのです。それも殺した子どもの部屋にある玩具などをです。
そんな事件が、何度も何度も行われました。数え切れないほどの数です。ゆうに百人は殺していたでしょう。しかし、一向犯人は捕まりません。サンタ・クロースという名前は、犯行現場に必ず落ちている――というよりわざと残していったんでしょうが――靴下に書いてあった名前からそう呼ばれるようになりました。
そしてとうとう、希代の連続殺人鬼サンタ・クロースは、逮捕されぬまま百年が過ぎました。いくら殺人鬼でも、百年も経てば死んでいます。ついに彼は史上二度と見ることが無いだろうと思われる猟奇連続殺人事件を完全犯罪として終了してしまったんです。
しかし、神がそれを許しませんでした。サンタ・クロースに殺された子ども達、またその家族らが許しませんでした。そして彼は償いをしなければならなくなったのです。いえ、彼自身はもう既に死んでしまいましたから、償いをすることになったのは彼の子孫です。しかし子孫に非は無いということで、神も考えました。どうすれば良いのか……そして考え付いたのが、償いは子孫達にやらせるが、その償いをやっている最中の記憶は消すことにしよう。そう決めたのです。それでは殺された者達が納得いかないのではないかと思いますが、確かに最初はそうでした。しかし、記憶は残らなくても身体的疲労は蓄積されます。それに、子孫達に特にそれ以外の罰は与えない代わりに、特に幸せな生活も送らせないということで殺された者達も治まりました。
そういうことで、今も尚、サンタ・クロースの子孫は各地でプレゼント配りを無意識下で行っています。勿論子孫の数は時代が進むに連れてだんだん増えてきましたから、世界各国にサンタ・クロースの子孫はたくさんいます。ここ日本にも何人か……」
それで話は終わったものと思い、獄盛が感想を言おうと口を開きかけたところ、どうやら話はまだ終わっていないらしいことに気付いた。坂下が獄盛を見つめ、口を開いて何か言おうとしている。
「その内の一人が、獄盛さん、あなたです」
少しの間、何の事を言っているのか分からなかった。しかしすぐに見当がついた。
「俺が、サンタ・クロースの子孫?」
信じがたいことの連発だ。
「はい、そうです。クリスマスの朝、起きてみると疲れていませんか?」
「ああ、確かにそうだ。そう言われてみるとクリスマスの朝だなぁ、疲れがでるのは。その数日前から嫌ぁな気分にもなっているんだが、体がそのことを覚えているのかな」
「きっとそうでしょうね。二十四日イヴの夜にクリスマスプレゼント配りを終えて、体が疲れているんです。その疲れは、さっきも言いましたように蓄積されていきますから」
「ふぅむ、そういうわけだったのか」
「そうなんです。それで……私は止めようと思ったんです。図々しいかもしれないけれど、獄盛さんを解放してあげようと思ったんです。それでどうしたら良いかって考えた結果、一つ思いついたんです。獄盛さんを殺せばいいと……」
「何!?」
「すみません。勝手にそんなこと決めて、勝手に刺してしまって……こんな時に言うのもあれなんですけど、私、獄盛さんのこと好きなんです。だから、解放してあげたくて……」
「そうか、そういう理由で刺したのか。分かったよ。その気持ち、ありがたく受け取って置こう」
「え、じゃあ、許してくれるんですか?」
「ああ、許すとも。俺だって君のことは好きだからね」
獄盛は微笑む。坂下もどうやら笑っているようだ。
「ところで……サンタ・クロースの話はそれで終わりかな?」
「……はい」
「じゃあ訊くが、どうして坂下さんはそんなに事情に詳しいんだ? それがさっきから不思議でならないんだよ。まさか、全部作り話っていうんじゃないだろう。今日はエイプリル・フールじゃないんだし」
「ええ、作り話なんかじゃありません。今までの話は事実です。……いえ、史実といった方が良いかもしれません」
「史実?」
「はい、ログという歴史上の事実です」
「ログという歴史?」
また信じがたい話か、獄盛はうんざりしていた。
「はい、ログは知っていますよね。コンピュータ操作の記録なんかのことを言います。 つまり、現実の歴史ではない、コンピュータ上の歴史での事実、とそういうことです」
「んん? わけが分からん。もう少し分かりやすく説明してくれ」
獄盛は唸った。
「分かりました、ご説明しましょう。どうして私はこんなにも詳しいのか……そんなことは簡単です。私が全てを操る、神なんですから!」
獄盛は声も出ない、口あんぐりの態だった。驚きの連続、連続、連続だ。
「驚きましたか。そうでしょうね、何せ目の前に人間の形をして神様が座っているなんて誰も思いませんものね。
これは私の仮の姿です。本当の坂下紀子は存在自体をデリートしました。生かしておく理由はありません。その代わりに、消えた坂下のキャラクターを神が使ってこうして姿形を得たわけです。これはライフ・シミュレーションゲームなんですよ。あなた達はみんなそのゲームの登場人物に過ぎません。しかしあなた方はそんなことは露知らず、立派な人間と思い込んで生活しているんです。私の作った地球というデータの星でね。
しかしあなたも、坂下も、容姿から人格、全てを私が作ったものなんですよ。それ以外の人間全ても同じです。これは二五〇四年最新のライフ・シミュレーションゲームなんです。そういうかなり細かい設定までが出来る究極のライフ・シミュレーションゲームなんですよ。地球という名も私が考えたんですが、ゲームの登場人物が考えたということにしておきました。日本やアメリカの国の形や名前も、海の広さも陸の広さも形も、何もかも私が作ったんです。
私以外他にもプレーヤーは多数いましてね、このゲームは宇宙というオンラインで繋がっているんです。私は太陽系と言う名前のサーバーでプレイしています。そこに地球を作りました。ここは太陽系の中でも最高のポジションでしてね、ラッキーでしたよ。太陽系の他の惑星では太陽からの位置関係上生命を育む事が難しいんです。それでも全然無理ってわけじゃありません。でないとプレイのしようがありませんからね。それで、我が地球から見て宇宙人という、UFOという奇抜なものが出来たんです。他のプレーヤーは、UFOを使って私の地球を覗きに来ているんですよ。ただ時々悪質なクラッカーがいましてね。UFOに見立てたウィルスで我が地球を侵略しようとしてくるんですよ。それが時々あるUFO飛来の噂の真相です」
獄盛は返す言葉が見つからない。ただただ、呆然と聞き入るばかりだ。
「それで、今回はクリスマス・イベントがあったんです。クリスマス・イベントというのは、まず地球のどこかで、神が作っていない善事、もしくは悪事が発生するんです。どちらかは分かりません。通常は神である私が、善事も悪事もイベントを考えてちゃんと平等に作っていきます。現実は二五〇四年だと言いましたよね? だから今はキリスト教が世界教になっているんです。これは現実で本当なんです。全てに平等に……その理念がこのゲームにも埋め込まれていまして、善事を行うには悪事をどこかで起こす必要があるんです。それを神――プレーヤーである私が交互に作って均衡を保ちつつイベントを作っているんですが、クリスマス・イベントは特別で、ポイントの高い善事か悪事が勝手に発生するんです。このイベントは、ゲーム会社の方が地球視察に来て、考え出したイベントなんです。これは他の惑星でも行われていて、キリスト教世界教化五百周年記念のキャンペーンなんです。『全てを平等にキャンペーン』です。ですから、私達プレーヤーは、その善事か悪事に対して、速やかに逆のイベントを作り、対処しなくてはなりません。しかし、対処してなお、更に善事と悪事を発生させることが出来たら、ゲーム会社から特別ポイントが貰えるんです。ポイントは、貯めるとゲーム内で色々なことが出来るようになります。例えば、今私はデリートした坂下紀子のキャラクターを使っていますが、これは一時的なもので時間制限があります。そうじゃなく、ポイントを貯めれば、神自身のキャラクターを作って降臨させることも出来るようになるんです。そんなことが出来たら、神は私なんですから、現実世界と同じような世界で、好きなことがし放題なんですよ。最高じゃないですか! ですから私もポイントを貯めるために更なる善事と悪事を作っておきました。少々無理があるかと思ったんですが、なんとか成功しました。それは、両方ともこの病院内で起こしました。まず善事のほうは、あなたの担当の看護婦さんと、第一外科のハンサム研修医に結婚の約束をさせました。もちろんこのまま結婚させます。対して悪事の方はというと、獄盛さん、あなたに向けて行ったんですよ。見たでしょう、リアリティな悪夢を? あれです。悪夢とは言え夢だったので、あまりポイント――これはイベント・ポイントと言って善事、悪事をするたびにプラスされたりマイナスされたりしますが、これは零に保っておかなければならないんです――も減らないかと思っていたんですが、案の定、足りませんでした。善事の方が質的に良いほうが特別ポイントも多くもらえるので賭けてみたんですがねぇ……失敗しましたね。 数をこなせばもっともらえるんですが、イベントを作って行うのも大変でしてね。何せ作る部分がかなり細かく出来ていますから、一日に二、三イベントが限度です。
……おっと、もうそろそろ時間のようです。それじゃあもう消えます。最後に悪事を一つしてからね。そうでないと、均衡が保たれませんので」
坂下は、いや、神はニヤリと歯を出して笑い、透明人間のように消えていった。
驚くべきことを聴いてしまった。獄盛は最後まで口をポカンと開けたまま、何も言えず終いだった。
「最後の悪事……」
そうだ、神の言っていた最後に悪事を一つというのはどんなことだろう?
クリスマス・イヴの夜。後一時間もすればクリスマスだ。空には青白い光を放つ月が佇み、しんしんと雪が降り積もる。
そんな夜の空に、真っ赤な服、真っ赤な帽子、白いもじゃもじゃした顎鬚と髪。がっしりとした体を持った男が一人、風に長い顎髭をなびかせながら飛んでいた。
彼の乗るソリは、二匹の真っ赤な鼻をしたトナカイによって引っ張られている。
トナカイは勿論、男のほうも何も言わず、無言のままに手綱を振るって走っている。ソリの積荷はまだまだたくさんある。
今年もこの男――獄盛勲は、子ども達の家へプレゼント配りをしているのだ。
「体が信じられないスピードで動いてくれるが、こりゃ大変だ。こんなこと知らなかったってだけでこんなにも疲れが違うものなのか」
独りぼやく彼には意識があった。神が残していった悪事とは、彼の記憶だった。
2.Twilight Cross ~黄昏の十字~
クリスマスパーティを、卒業した大学の研究室の仲間たちと開かれるという知らせが届いたのは、当日から二週間ほど前のことだった。出席者たちを確認すると、どれも卒業以来はめったに顔を合わせなくなった面々だった。その中には、教授の名前も記されていた。
「なんだ、それは?」
僕が招待状をしげしげと眺めているのに興味をそそられたのか、同じ音楽教室の友人の皐月がこちらの手元を覘いてきた。
「いや、招待状だよ。クリスマスパーティの」
「ふぅむ……どれ、見せろよ」皐月は僕の承諾を聞かずに招待状を取り上げると、無愛想にひん曲げた口元を吊り上げた。
「23日の夜……。これ、お前の大学のか?」
「ああ」
しかし飛び入り参加も可能だという。
「色気はあまり期待できそうにないようだな。それはいい! 行ってこいよ笠原。俺もついていってやる」
「は?」
「俺だってどうせ暇なんだからさ。ほれ、さっさと返事を書いちまえ」
「き、君は暇じゃないだろ……。彼女がいるじゃないか」
僕がそう言うと、皐月は心外そうに肩を竦めた。
「誰がいるって?」
「恋人だよ。ほら、フルートの。イヴの前日とはいえ君にそんな野暮なことをさせるわけにはいかない。僕一人で行くよ」
「彼女は違う。それに、クリスマスだからって無条件に恋人と一緒に過ごすなんていう風潮自体、俺には理解しがたい。みんな、無意識のうちに長いものに巻かれているよ」
「そうか?」
「そうさ!」
皐月が珍しく強調して否定するものだから、僕はそれ以上追求をせず、しかたなく頷いた。
「そうか……。なら誘わないわけにはいかないよな」
そんなわけで当日、僕らは車で主催者である高梨の家に向かった。助手席には皐月が居座っている。彼はいつもだらしなく黒のスーツを着崩しているので、几帳面な僕は特に気になってしまう。
長い道程なので、ラジオにもCDにも飽きてきた。皐月も僕と同じ思いを抱いていたらしく、眉間に皺を寄せて、オーディオのスイッチ自体を切ってしまった。
「少し休憩するかい?」
僕が聞くと、
「もう少し時間的余裕があったらな。お前こそ運転、疲れないか?」
と懐中時計を確認しながら言った。確かに、少し時間が押し迫っている。
「僕は平気だ。……ところでクリスマスって、キリストの誕生日ってことだろ?」
「うん……まあね……」皐月はシートを倒し、懐中時計を眼上で弄びながら言った。「細かいことを言えば、色々と複雑なんだが。たくさんの説があってどれが本当とか、断定できないと俺は思うけど」
「どういうこと?」
「いや、例えばキリスト誕生の際の描写さ。その晩に、羊飼いが野宿をしていたと、書物にはある。おかしいだろ? 12月25日は立派な冬だ。冬に野宿するやつがあるか?」
「まあ……そうだね」
「他にも1月2日とか6日とか、4月18日とか19日とか、ひどく曖昧なんだ。だから断定できない。最も一般的とされたのが12月25日というだけのことさ」
「ふうん……」
「ところで、北欧神話って、知ってるか?」
「神様の名前くらいは知ってるよ。オーディンとかロキとか、ラグナロクとかでしょ」
「ラグナロクは神様じゃないんだが……」
皐月は苦笑した。
「神々の黄昏、という、分かりやすく言えば神様同士が演じる最後の大戦争のことさ」
「あ、そういえばそんなだったな。ラストには世界樹が燃えてなくなる」
「スルトーという炎の巨人が、炎の剣を世界樹に投げつけるんだ」
「うぅん……それは知らないな」
僕は運転に集中しながらも、皐月の込み入った話に耳を傾ける。初心者にはできない高等テクニック……だと僕は勝手に思っている。
「クリスマスのルーツは、その北欧神話にあると言われている」
「え? 一神教のキリスト教にとったら、当時ならそれは淘汰すべき異文化ということにはならないか?」
「そうなるな。でも、いいか……クリスマスの由来が北欧神話にあるといわれる所以は、こうなんだ……」
そう言って、皐月は僕にその理由とやらを、僕に分かりやすく説明し始めた。
―――北欧神話の主神オーディンは、八本足の妖馬スレイプニルに乗って、冬至の祭の日に贈り物を届けにやってくるのだという言い伝えがあったという。そして興味深いことに、彼は贈り物を届ける時、煙突から家の中に侵入したのだそうだ。これはサンタクロースそっくりだ。
このことからも、北欧神話がクリスマスの由来として考えられるのはごく自然なことだろう。そうなると、派生して考えられるのは、ツリーだ。それは僕も知っている世界樹ユグドラシルを指しているのではないだろうか、と皐月は言うのである。
ツリーの起源としては、他にもいくつか考えられるものがあるらしい。
聖ニコラウスの後継者がお菓子を分けて家々をまわり、その家の子供たちが靴下を下げて待っていたからだという話。
宗教改革者で有名なルターが、家の木にキャンドルを灯してクリスマスを祝ったことが始まりという話。
宣教師ボニファティウスが、ドイツでオーディンに生贄として捧げられている人を発見した際に、カシの木にくくりつけて今にも殺されようとしている人を説いて改宗させた日が12月25日で、そのカシの木がツリーの元になったという話。
しかしどうも、オーディン=サンタ・クロースというイメージが強く残り、やはり同じ北欧神話として密接に関わっているユグドラシルがツリーの由来なのではないかと思う、と皐月は言った。僕もその皐月の話を聞いたのだから、そう思う以外にどう解釈していいのかという術もない。
「まあ、興味が向いたら色々調べてみるといい。俺も神話系は、ほとんど独学だから」
皐月はそう言って笑った。
「そうか……」
「もっとも、サンタクロースがオーディンだけをモチーフとして創りあげられたものだとは、俺は思っていないけどな」
「……え?」
「それは……、おっと。もうそろそろ着くんじゃないか?」
カーナビを見ると、確かに高梨の実家のすぐ傍だ。ナビは既に案内を中止してしまっている。どうやら話が面白くて、そちらに気が回らなかったようである。
出迎えに現れたのは、研究室の仲間だった高梨心と、その旦那さんのエドだった。高梨は、僕たちとヨーロッパに卒業旅行中、エドと知り合って一目惚れをされてしまったのだそうだ。末っ子だったエドは、そのまま日本に渡り、二年前、強引に押し切って高梨を物にしてしまったというわけだ。
家の中に導かれ、僕たちは高梨の手料理というもてなしを受けた。他のメンバーはまだ来ていないので大したものじゃないわよと高梨は言ったが、一人暮らしの僕らには十分だった。本格的な料理は、みんながやってきてから改めて出されることだろう。
人付き合いが比較的苦手に思われた皐月を心配し、僕は彼のほうを気にしていたが、意外なことに彼はエドと意気投合して話に興じていた。それも僕にはまったく着いていけないレベルでの会話である。
「いや、あれはあくまでも『スルトーの炎剣』であって、それがイコール『レーヴァティン』であるという神話的根拠は全くないんだよ。そもそもレーヴァティンが剣であるという描写すら疑わしいのだから」
エドが皐月と、何やら北欧神話に関して話している。付け焼刃の僕の知識ではまったく追いつけそうに無い、マニアックな世界。
「最近ではファンタジー小説とか、ゲームとかで多くはそれら二つを混同しているみたいだから、北欧出身者としてはちょっといただけないな、とは思っているんだけど」
そう言ってエドは笑った。
「でも、『レーヴァティン』はロキがスルトーの妻に贈った『恐ろしい力を持った武具』だから……それが巨人族随一の戦士スルトーの手に渡るとは容易に想像が付くんじゃ……?」
皐月は反論を試みるが、やや押され気味である。
「いやそれはあくまでも想像だよ、皐月くん。神話的な推理としては成り立つかもしれない。実際に、先述した小説などでも、そういう連想をして二つを同じものとして扱っているみたいだからね。しかし再三言うけど、スルトーの炎の剣が神話内でレーヴァティンとして描写されたことなどないよ。ほら、そこの本棚に、僕の故郷に伝わる神話の本があるから、読んでみるといい」
「あ、どうも……。お借りします」
皐月は、普段は全く見せないような愛想の良い表情を作ってエドに対している。どうやら僕の心配はいらなそうである。
「しかし地元出身者はさすがに詳しい。参ったよ。出身は?」
「……ノルウェーの外れにあるレーラズ村だ。しかし、君も良く知っているほうだと思うよ。まあ神話内で混同されているものもいくつかあるからね。そういった齟齬は仕方がないのかもしれない」
そんな二人の会話をぼんやりと聞いていた僕を見て、つまらなそう、と判断したのだろうか、高梨が飲み物を持ってきて言った。
「どうしたの?」
「いや、エドはそういえばヨーロッパの出身だったな、と思ってね。日本語が達者だから、つい忘れがちになるよ」
「そうね。でも良かったわ、エドが日本に住むと言ってくれて。私、まだ仕事は当分辞められなかったから」
高梨はまだ仕事を続けているのだそうだ。エドもこちらで働くようになったが、まだ落ち着いてはいないらしい。
そういうやりとりがしばし続き、いつのまにか外には白い雪が舞いはじめ、積もっていった。
外から車のドアが閉じられる音が聞こえてきたので僕たちは外に出た。
一時間遅れてのご到着。しかし車から現れたのは教授を除く、学生全員だった。
「やあ、遅くなってすまん」
ゼミ長だった黒川信二が、運転席を降りるなり言った。
「途中で原野が車酔いしてよ」
「そういえば原野君、酔いやすい体質、まだ治っていなかったんだ」
原野光男は、ゼミ生の中で一番の軟弱体質だった。車はもとより、酒を飲んでは一杯で二日酔いになるわ、ちょっと運動をすれば翌日体調を崩して休むわ、極めつけはヨーロッパ旅行で、彼はホテルに着いたとたん高熱にうなされ、結局そのまま一人何もせずに過ごした。ちなみに彼は、クリスチャンである。彼のために、当日ではなく23日にしたのだ。
「大丈夫か、原野」
助手席からは、ムードメーカーの村越義治。彼はメンバーの中で一番身体が大きい。
「平気だよ。落ち着いたしね」
原野はそう言ったが、顔色が悪いので、こちらとしては心配である。
「あ、みんな一緒に来たんだね」
高梨が車からみんなが降りてきたのを確認して、そう言った。
「待ち合わせしていたの?」
「そうだ」
黒川が太い眉を触りながら言った。
「どうせ三人とも隣町から来るんだから、それなら一緒にってな。ガソリン代も三人なら安くなるし」
……現実的な彼らしい意見だ。
「そちらさんは?」
村越が皐月のほうを覗き込みながら、僕にきいた。僕が何か言おうとするより先に、高梨が説明した。
「彼はね、笠原君と同じ音楽教室の友人さんだって」
「よろしく」
皐月はエドと接していた時の愛想をそのままに、片手を挙げて挨拶した。
「……って、部外者俺だけかよ」
後半、ボソッと呟いた彼の言葉を無視して、僕は高梨と共に皆を家の中に迎え入れた。
さらに程なくしてタクシーで菊地教授がやってきて、いよいよパーティが開かれることとなった。クリスマスパーティといっても、七面鳥が出てくるわけではない。チキンで代用。シャンパンで乾杯し、アルコールが飲める者はワインに手を出した。
黒川は車の持主なので、運転のためにアルコールを飲めないと言って悔しがっていた。僕はといえば、もともと下戸なのでアルコールは遠慮している。
「ここらでだな、俺がひとつ手品ってやつを披露してやろう」
村越が顔を赤くしてトランプを取り出した。
「いいね」
原野も先ほどまでの不調が嘘のようで、楽しそうである。
「どんな手品かな」
「私は騙せないよ」
教授もそちらに注意を向けた。村越はそれでも余裕の表情を浮かべながら、ジョーカーを抜いた52枚のトランプを無造作に切った。
「ほれ高梨よ、お前の好きな数字を、4枚選ぶんだ。絶対忘れるんじゃないぜ」
「私? 選ぶって……同じ数字でも良いの? 別々のマークで」
「何でも良い」
僕と皐月もそちらを向く。高梨が選んだのは、エースを4枚だった。村越は満足そうに頷き、
「じゃあ、その4枚はテーブルの端に置いといてくれ。さてこの残り48枚は」
カードを全て高梨に手渡す。
「左から順に、四つの山に配って欲しい。一度右端まで行ったらまた左からだ……そう。最後は右端で配り終わるだろ?」
「……うん
「そうしたら、さっき選んだお前の好きな数字のトランプ4枚のうち、一枚を裏向きに取り上げ、左から一番目の山の上に置くんだ」
「裏向きで?」
「そうだ。そうしたら隣の、二番目の山より、上から数枚を取り上げ、一番目の山の上に重ねて。……よし。じゃあまたさっき選んだトランプを、裏向きで左から二番目の山の上に置いて。……三番目の山から適当な枚数のトランプを取って、二番目の山の上に重ねて」
高梨は村越に言われるままに、機械的な作業を繰り返す。
「さっき選んだ数字の3枚目を取って、三番目の山の上に、裏向きに置いて」
「はい」
「四番目の山から適当に数枚取って、三番目の山に重ねて」
「……やったわ」
「じゃ最後に残った4枚目の選んだカードを、これは表向きで四番目の山の上に置いてくれ。4枚目だけが表向きだぞ」
「見ればわかるでしょ。クラブのエースよ」
「まあそうだな。じゃあ今度は、四番目の山、全てを取り上げ、三番目の山の上に置いて。次は三番目の山全てを二番目の山の上に。そして二番目の山全てを、一番目の山の上に重ねて」
「一番上にクラブのエースが見えてるけど?」
「うんわかる。じゃあここでいったん山をカットする。山の真ん中から半分に分けて。そして上と下を入れ替えてくれ。それを何度か、繰り返してくれ」
「そんなに切っちゃって、良いの?」
高梨が不安げに村越を見る。
「大丈夫だ。俺は魔法使いだからな」
「良く言うよ」黒川が鼻で笑った。
「……満足したか、高梨。じゃあその一つになった山全部を、今度は13の山に配ってくれ。配り方はさっきやった4つの山の時と一緒で最後まで行ったらまた最初に戻る」
「ややこしいわ」文句を言いながらも、高梨は素直に従う。「……これで最後……ね」
「さて13の山に4枚づつ配られている訳だが……」村越は得意げに身体を揺する。「一枚だけ、クラブのエースが見える山があるな?」
「まあ、一枚だけ表にしていたからね」
「そこの四枚を取ってみな。……おっと、ちゃんと自分が選んだ数字を念じるんだぜ。じゃないと、俺の遠隔魔術は失敗してしまう恐れがある」
「まさかー。あんなに切ったのよ」
「良いから良いから」
皐月は黙って僕の隣でその様子を見ていた。
高梨が『クラブのエース』がある山に手を伸ばす。ゆっくりと。
「取るわよ」
果たして、そこから現れたのはエース4枚だった。
「え、何!? 村越、お前何か細工した?」
驚いたのは高梨よりも黒川だった。原野は素直に感心している。エドは微笑みながら見守っていた。
「何かって、俺は遠隔魔術を施しただけさ」
村越は得意になって「フハハハハ」と高笑いをした。
「面白い手品だな」皐月が僕だけに聞こえるように呟いた。「しかし彼はマジシャンには向かないよ。せっかくいい手品なのに、あれじゃ誘導がバレバレだ」
「……どういうこと?」
「いや、今のは誰がやっても、ああいう結果になるということさ。算数だよ。それさえあれば原理はすぐに理解できる」
皐月は今の手品の結果に感心しているのではなく、過程に感心しているのだった。
しかし僕には、どういう原理なのかさっぱりわからなかった。
「笠原はクラシックギターができるんだよな? お前、今日のために楽器ぐらい持ってきているんだろ?」
黒川が僕に話題を振ってきた。何か弾かせるつもりらしいが、あいにく僕は楽器を持ってきていない。
「それを言うなら、ほら皐月さんも音楽教室に通ってるって?」
エドが皐月のほうを向いて言う。
「ああ」皐月もきょとんとした顔で反応した。「ヴァイオリンだけど」
「何か弾けるのかい?」
「う~ん……ブランクあるしなぁ」皐月は苦笑したまま、それでもいくつかのレパートリーを挙げる。「『アニー・ローリー』とか『トロイメライ』とか……『メヌエット』あたりかな」
「えっ、いいなぁ。私もヴァイオリン習いたかったんだけど、もうムリかな」
高梨がエドのほうを向いてもの欲しそうな目つきになったがエドは軽やかに笑って流した。おそらく楽器の購入を、何度かせがんでいるのだろうと思う。
結局音楽の話題はそれ以上には発展せず、酒がまわってきた一同は、それぞれ思い思いの行動にでた。
エドは神話の話がしたいと言って、皐月を誘って隣の書斎に行ってしまった。僕と高梨、黒川はキッチンで後片付けをし始め、菊地教授と村越はなんと、場所を外に移しワインを傾けている。原野は案の定腹をこわし、トイレである。
「原野、相変らずだね」
僕が黒川に同意を求める。
「全くだ。あれで胃腸薬を携帯していないってんだから驚きだ」
僕たちが笑っていると、書斎の扉が開き、皐月とエドが顔を出した。
「笠原、お前も書斎に来るか? ほら、お前が欲しがっていた例の曲のスコアがあったんだ」
「エドが? 行く行く。見せてよ」
僕は軽く目をみはって書斎の方に向かった。
僕がエドの書斎に入ると二人はまた、そんな僕を放って話を再開し始めた。僕は目当ての楽譜をめくりながらも、そちらの話に引き込まれていく。その内容は、僕と皐月が車の中で話していた話題の延長のようなものだった。
「なるほどねぇ、皐月さんはクリスマスの起源に関しては、そういう意見を持っていたのか」
「意見ってほどでもないんだけど」皐月は薄く笑う。「まあ、北欧神話が元ネタだっていうことはほぼ間違いないと思う」
「いや実はね、その意見は私と一緒なんだ。もともと故郷では12月25日に冬至祭を行っているし、そういう言い伝えが、私の村にはある」
「……しかし、どうも俺には腑に落ちない点があるんだ」
「それは?」
「キリスト教は、中世の話だが、遠征などで良く他国侵略を繰り返し、そのたびに異国の文化まで取り入れてしまっている。そう、北欧神話のような、一神教にとってはおそらく忌むべき存在すらも」
「…………それが、おかしいと思うのかい?」
「まあ……。これにも色々な説があるみたいだけど……調べてみる価値はあるかな」
二人の言葉が、数瞬の間途切れ、そしてやがて、エドが口を開いた。
「クリスマス・キラーって、知っているかい?」
「……ああ、2年前から、クリスマス当日より3日ぐらい前から、一日一殺。敬虔なクリスチャンばかり無差別に一人ずつ殺していく殺人者のこと? 犯行現場には、ミニチュアのツリーが燃えた状態で残され、いくつかの目撃証言ではサンタの格好をした人影がその辺りをうろついていたとか」皐月はエドの真意をはかりかねたように訝しがる。「それが何か……? 確かまだ正体は割れていないとかいう話だったが」
「三文雑誌では、『死のサンタ』とか色々と言われているらしいよ。今年もやってくるかな?」
「さあ、俺にはわからないが」
皐月は肩を竦めた。
「話が変な方向に向いてしまったね」自分で方向を変えたくせに、エドはそんなことを言う。「どうしてクリスチャンばかりを狙うんだろうと思ってね」
「警察の見解では、クリスチャンに恨みがある者の犯行だとか」
「この辺なんだよね。私はクリスチャンではないが、少し心配だ」
エドの言葉で、原野のことが気になった。彼はクリスチャンだ。
「エド、まさか……ツリーが燃やされている……って」
「そうだよ。『ラグナロク』だ。炎の巨人スルトーが投げつけた剣によってユグドラシルは燃え、世界を炎に包みこむ。『クリスマス・キラー』の目的はそこに隠されている。彼は真実を伝えようとしているんだ」エドは真剣な表情で皐月を見すえながらそう言った。「どうして一神教のはずのキリスト教が、侵略地の文化を『淘汰』ではなく『吸収』してしまったのか。地元民がこっそりと過去の風習を受け継いでいったということも言われているが、それならばここまで大きくなった文化に反映されるということはないだろう。弾圧の対象になってしまうからね。ツリーの意味、サンタの意味、……真実に、屈辱に耐えかねて『クリスマス・キラー』はその衝動を抑えきれない」
「大した分析をするね」
皐月はエドの表情に気圧されつつ、彼から目を逸らした。僕は身動きが取れなくなっていた。
ていたようだが、僕の報告を聞くと目をかっと見開き飛び起きた。
「……まさかな……」
皐月はそれだけを呟いて新聞を僕に返す。
「どうしたんだ、皐月」
「昨日、色々と調べてみたんだが……、エドの出身について」
「エドの出身?」
「ああ。しかし資料自体が圧倒的に少なかったから、事務所の仲間にまで手伝ってもらったよ。全て俺の自腹で。……だが結局、レーラズ村についてわかったことは、外界に漏れる情報などほとんど無いほどの、かなり閉塞された村らしいということだけだった。しかしレーラズというのは象徴的だな」
「え?」
「ユグドラシルの別名さ」
そう言って皐月は、手帳の切れ端を数枚、僕に向かって放った。そこにはいくつかレーラズ村についての殴り書きがされていた。
「これが……?」
「昨日エドが言っていたことを覚えているか? 何故、キリスト教は文化を吸収する真似をしたのか、と。キリスト教には良くあることだが、しかしそれならば北欧神話の件はあまりにも矛盾した行動だ。他の神をある意味で認めているということになるのだから」
「ああ……歴史の謎というのかな」
「だがもし仮に、仮にだぞ。キリスト教は、侵略した地の文化を、『戦利品』として捉えていたとしたら、こういった矛盾は辻褄が合うんじゃないか?」
「戦利品?」
「つまりこうだ……、異教の文化をアレンジして、貶めてしまうことによって、自分たちの宗教の優位性を確立するんだ」
「キリスト教がか……? そんな!」
皐月は眠そうに欠伸をしてから、
「だから仮にだと、最初から言っているだろう。……これをクリスマスに当てはめて考えてみると……、クリスマスのルーツが北欧神話だということは昨日言ったことだから端折るが、サンタクロースについてだ。サンタは何故赤い? ツリーはユグドラシルがモチーフなのに何故過剰な装飾を施す? 答えはこうだ―――サンタのモチーフは『オーディン』だけではない。それでは異教の神であるオーディンを、ありがたがるということで肯定してしまうことになる。だからサンタには別の意味も込められている。それは、異教の神界を炎によって滅ぼした、キリスト教にとっては実に都合のいい存在―――『スルトー』だ。炎の巨人たるスルトーの全身は真っ赤な炎に包まれている。キリスト教にとってはそのスルトーこそ、ありがたい存在だったと言えるんじゃないか? それとオーディンが微妙に融合しサンタの元となったんだ。スルトーはもともと『ナグルファル』という船を所有していてラグナロクの後にはそれに乗って何処かへ姿を消している。ナグルファルこそサンタの乗る『ソリ』の由来と考える。そしてツリーの装飾は、世界樹ユグドラシルが燃えるさまを、再現したものだ。これは異教に対する痛烈な皮肉という意味でだ。クリスマスに何も知らない皆は、燃えるユグドラシル―――装飾されたツリー―――を眺めて楽しむのさ。北欧神話に対する、これが痛烈な皮肉」
「そんな……」
「すべては想像の産物だ。だが……」
皐月が言葉を続けようとした時。
「その通りだよ」
玄関から声がした。エドの声だった。
「あの名刺は、わざとだったんだね?」
エドが尋ねる。名刺?
「ああ、ギョッとしただろ? 『クリスマス・キラー』の名は……と、名刺の裏に思わせぶりに書いておき、あんたの部屋にわざと忘れていった。それを発見したあんたが本物なら、きっとこの住所に尋ねてくる。本当は自分でも、やめにしたかったんだろう? だから昨日あんなことを俺に話したんだ」
「神話について、久し振りに実りある話ができる人物とめぐり合えたと思ったよ。早く誰かに気付いて欲しかった。……悔いはない」
「どうしてだ? あんたの出身の村が、そうさせるのか?」
「私の村は、かなり閉塞された空間でね」
「それはわかる。徹夜で調べたからな」
「村の言い伝えでは、君が言った通りのことを教えられてきた。『北欧の神々は、キリスト教によって貶められてきたんだ。お前はそれを絶対に忘れちゃいけない』とね。だが村から外界に足を踏み入れることは厳禁だった。それは、その村の『血』がそうさせるからだ。だが私はその禁を犯した。家出同然で村を飛び出し、そして、心に出会った」
「村の『血』……?」
「そうだ。はじめは私も意味が分からなかった。しかしクリスマスになってみてやっとそれを実感した。そして実感した時にはもう手遅れだった。クリスマス間近に外界に出ると、クリスチャンに対する憎悪が増大するんだ。それはもう抑える抑えられないのレベルじゃない。衝動と言っても良い。……それが『クリスマス・キラー』の誕生というわけさ」
「あんたが高梨さんと結婚してこっちに住むようになったのは二年前だ。キラー誕生と同時……」
「プロバビリティーの犯人当て、かい?」
「今回はな」皐月は悲しそうに笑った。「俺の知る人間の中で、犯人に一番近い位置にいたのが、あんただったというだけのこと。……ミニチュアのツリーを燃やしたのは、世間に対するユグドラシルの痛みを知ってもらうためか?」
「みんな知らなさ過ぎるんだ。クリスマスという表面的な華やかさにばかりに目が行って、その裏で、歴史の影で私たちのように苦しんでいる人々がいるということを。それを少しだけ、伝えたかったんだよ。だから私は待っていた。神話に対して理解を持ち、その裏にある真実に気付く可能性のある人を。――それが君だ、皐月君」
「ずいぶん買い被られたもんだ」
「……私はこれから自首をする。最後に君と話がしたかっただけだ。悔いはない」
そう言って、エドはくるりと背を向けた。その背中に、皐月は声を投げかけた。
「教えてくれ、どうしてレーラズ村の人間だけがそうなる?」
「他の村の連中は、合理化してしまったんだ。『クリスマスには自分たちの文化も取り入れられている。これはキリスト教に対する小さな抵抗だ』とね。でもレーラズ村の人間は、もっと高潔だった。そんな理屈で自らを納得させることは、我々の神に対する侮辱として、決してしなかった」
エドは振り向きながら言い、また後ろを向く。そして足を踏み出す。
「心さんはいいのか?」再びその背に声をかける皐月。
「………お別れは、済ませてきたよ。今までは彼女の優しさに甘えてきたが、最後のけじめくらいは、自分で付ける」
エドは、今度は振り返らずに答えた。
高梨は知っていたのだ。エドが『キラー』だということを。知っていた上でエドを受け入れていたのだろう。
【おわり】
この作品に関して、何ら宗教的な意図はありません。
4.クリスマスツリーは高すぎる (Kei)
――都筑道夫に捧げる――*prologue*
大学に行く途中だった彼女は思わず顔を見上げた。
商店街の真ん中に目の前には大きなクリスマスツリーが立っていた。あわや、アーケードに届こうかという高さだ。きちんと、上には星がのっけてあるし、箱や靴下なんかも吊るしてある。
ふと、すぐそこに靴下を吊るしてあるのが見えた。届くかな――と思って手を伸ばしても届かなかった。ジャンプすると、ようやく靴底の部分に触れた。
女子としては大柄な1メートル65センチの身長が珍しく役に立った日だった。
*quiz*
♪Silent Night Holy Night「マスター、何で日本人はクリスマスは十二月二十四日にやりたがるんですかね?」
彼がカウンター越しに急に、声を掛けてきた。彼は、この近くの大学の学生で、ミステリ研に――正確には名前が違った気がするが ――所属してるらしい。私もミステリファンなだけあって、時々ミステリ談義に花が咲く。名前は、たしか早坂聖と言ったはずだ。
「どうしたんだい、急に?」
こちらは、コーヒーを作ってる最中。最も、ここはさほど本格コーヒーに拘っているわけではないのだが。
「だって、日本人はイブに盛り上がって、二十五日なったらみんなクリスマスなんてこと綺麗さっぱりに忘れてません?」
「まあ、日本は正月準備があるから仕方ないから仕方ないんじゃない?年賀状だって、さっさ出さないと元日に届かないしさ」
私は、コーヒーを彼の前に置きながら言った。
「あっ、やばい。年賀状書かなくちゃ。実家帰るの二十七日なんすよね…。俺、パソコンあるけど、プリンタ持ってないんですよ」
「学校にないのかい?」
彼は一応、コンピュータ系の学科ではないが理系である。
「学校?学校の一回試したんですけどね。学校のぼろくてケーブルのジャックがないんですよね。とか言って、俺のノーパ、 しか付いてなんですよ。そもそも、あのぼろさじゃ解像度は怪しいですけどね」
パソコンでやっと表計算ソフトを使えるようになった私程度では、コンピュータ用語は暗号としか思えない。
それを素早く察したらしい彼は、話題を振ってきた。
「そういえば、マスター、クリスマスの謎解きやってみません?」
いたずらっ子がやるような表情を見せて、彼は言った。
「謎解きかい?」
彼は今まで幾度となくヘンテコな謎を持ち込んできては解かせようといた前科があるのだ。
「『このクリスマスツリーは高すぎる。他のところにしよう』って、言葉からどのように推理が立つと思います?」
*approach*
「まるで『九マイルは遠すぎる』みたいじゃないか」
私は本腰を入れて聞こうと、彼の正面に体をもっていった。どうせ、他の客は閑古鳥がしかいない。
「そうなんですけどね。ええ。うちの部員の平山がですね…、平山って知ってます?」
「早坂君が一度連れてきた、あの落ち着きのない子かい?」
身も蓋もない言い方に彼は少し笑ったようだったが、続けた。
「そう。あの平山が商店街の中で聞いたそうなんですよ。そういう声を。慌てて、そちらの方向を振り向くとデブとノッポな二人組みがいた」
「『デブとノッポの国』の入り口の門番みたいだね」
この間、子供にその本を読んであげたばかりなのだ。一応解説しておくと、デブの国とノッポの国が真ん中の浮かんでいる島の名前を巡って戦争するという物語。いつも思う事だが、児童文学というのは世界を風刺している。
「なんですか?それは」
「いや、なんでもない」
知らなかったのも、無理はないだろう。
「で、そのデブとノッポの二人組みのうちノッポの方が言ったそうです」
そこで、彼は一旦切り続けた。
「場所は、商店街のクリスマスツリーの前だそうです。ほら、あそこに馬鹿でかいクリスマスツリーが立ってるじゃないですか」
「ああ、そうだね」
「そう言えば、今年はどうかしたんですか?例年は、あんな馬鹿でかいクリスマスツリーなんて立ってないじゃないですか」
私のこの喫茶店も、商店街連合に所属している。確かに、去年まで馬鹿でかいクリスマスツリーはおろかクリスマスソングすら掛かってなかった。
「まあ、あれは金づるが出来たからね」
どうでもいいが、市が実行している駅前の再開発計画に組み込まれて、助成金が出ただけなのだが、説明するのが面倒なので適当に流す。
「ふーん。それは、ともかく服装が二人とも随分とおかしかったそうです。デブの方は風邪をひいているのか普通のマスクをしていたそうです。それに、咳きもしていたって話ですし。でも、そのくせ黒いコートをきらずに手にもっていたそうです。ね、この時点でおかしいと思うでしょ?それに対して、ノッポは12月の日差しも強くない日に、サングラスは掛けていたそうです。しかし、こちらは同じような黒いコートは着ていたそうですが、手袋までしていた」
そこで、彼はコーヒーに口をつけた。
「そこで、平山の問題編は終わり。これだけで、どう推理しろっていうんだよ」
ようやく、彼の訪問の意図が読み取れた。問題を出されて、自分ではどうしようもないから他人に聞きに来たわけだ。いつも通りとは言え、なんともいいがたい。
「一つ、聞いていいかい?」
私は、ふと浮かんだ疑問を口に出した。
「別に、構いませんよ」
「それ、いつの話だい?」
「えーと、昨日の昼頃って言ってましたっけ」
昨日ということは、今日が天皇誕生日だから二十二日となる。
「ノッポの方はマスクはしてなかったんだよね?」
「そうみたいですね」
「それと、反対にデブはサングラスはしてなかったんだよね?」
「ええ」
「つまり、アベコベコンビってとこだな」
私は、思わず考え込んだ。
ふと気付くと、彼は喫茶店に置いてある紙に、何か書き付けていた。
「こんな、感じですかね?」
| デブ | 持ち物 | ノッポ |
| × | >サングラス | ○ |
| ○ | マスク | ×|
| × | 手袋 | ○ |
| 手にもっていた | コート | ○ |
| 風邪気味 | 備考 | 例の言葉を喋る |
彼の提示してきた紙には、彼のダラダラと話していたことが簡単にまとめられていた。
*TRICK & MISTAKE*
「で、早坂君はどういう推理をたてたんだい?」私は駄目もとで聞いてみた。
「僕ですか!?」
まさか、自分に来るとは思っていなかったらしい。が、しばらく考え込むとやけに自信なさげに答え出した。
「今、マスターの話を聞いて思いついたんですけど…、これは言葉のトリックじゃないかなーと」
「トリック?Kが逆さまになってる奴じゃなくてかい?」
完全に、『九マイル』の連想から頭がロジックの方向に言っていた私自身言っていたのでかなり意外だった。
「ええ、Kが逆さまになってるのじゃなくて、言葉のトリックだと思ったんですよ。あんなに高いクリスマスツリーの前でクリスマスツリーは『高すぎる』と言ったら、誰だって値段が高いの方じゃなくて、高さが高いの方を連想するでしょう?」
「そうだろうね」
私も瞬時にそう訳した。
「そこにミソがあったと思うんですよ。あれだけ高さが高いクリスマスツリーなら値段も高い」
「だろうね」
といっても、商店街連合の会議に滅多にでない私は、あれがいくらかは知らない。
「ならこう考えたわけです。余計な財政負担を強いられれたこの商店街の商店主の二人が雑談していた、何てどうですか?」
「『他の所にしよう』という言葉はどうやって、解釈するんだい?」
「だから、この商店街は駄目だ。ほかの商店街に移ろう、という意味だと…」
と、いいつつ本人が自信なさそうだ。いつもは、大抵自信満々なのだが。
「あの奇妙な服装は?」
「職業柄という、所じゃないですかね…。デブのほうは、食品関係の仕事をやっているんじゃないですかね。多分、この商店街食品作っているのはパン屋とラーメン屋ぐらいですよね?だから、マスクを掛けていたし、デブになってしまった。まあ、かなりこじつけですけど。ノッポのほうは、写真屋でもやってるんじゃないですかね。ストロボ撮影の時に、眩しいからってサングラスを掛けていたとか…」
即興で思いついた割には、なかなか凄い。が、この推理を破ってあげなければならない。
「何で、風邪気味だったのに、デブはコートを着てないんだい?」
「えっ!?それは…。工場の中にいたからですかね。工場の中って機械とかが動いていて結構暖かいじゃないですか」
彼は、さらに自信なさげになった。
「まずさあ、この商店街。食品工場って、パン屋とラーメン屋しかないって言っただろう?パンっていつ作るかしってるかい?」
「…朝方でしょうね」
NHKの朝の連ドラを見ていれば自ずとわかることなのだろう。最も、学生がそんな早い時間に起きているかは不可思議であるが。
「そんな彼が、今の今まで暖かい工場の中にいたとは思えない。ラーメン屋は論外だろうね。昼頃は、一番の書き入れ時だ。そんな時に、のんびりと外を散歩しているとは思えない。さらに言えば、食品を作っているような所のマスクはまた特別なものだしね。それに、早坂君の推理には根本的に大きな間違いがある」
「なんですか、それは」
「あれは、商店街の金で作られたものじゃないんだ。だから、商店主は一銭も寄付してない」
「えっ!?」
「しかも、市から再開発計画の一巻として特別に助成金が降りたもので、しかも、駅前再開発委員会とやらから、特別のイベントに使えって、言われてるんだから。商店主の出る幕ではないんだ」
商店街連合の会合に滅多にでない私だが、会合の事後報告だけは全件に配られる為、知っていた。
「だいたい、何で写真屋がサングラスを掛けるんだい?ストロボ撮影で被写体になるなら眩しいだろうけど、取る方が眩しい分けないじゃないか。だいたい、サングラス掛けてたらファインダーが見えずらいだろう?」
彼はとうとう完全に黙ってしまった。
「そもそも、やっぱり寒い屋外に出たら風邪気味なら普通、今まで暖かい所にいたらなおさら急に寒くなるからコートをきると思うけどね」
彼は、コーヒーが苦かったのか、それとも苦笑いしたのか顔をしかめた。
*coffee break*
チリンチリン――この閑古鳥が大盛況の喫茶店にお客さんが珍しく来店したようだ。
二人は、同時に入り口の方を向いた。そこには、見事に頭が禿げ上がった商店街連合の会長が何やら紙を持って突っ立っていた。
「どうも、いつもいつもすいません」
頭を下げながらマスターはカウンターから出て、会長の所まで出向いた。
「いやー、いつにもまして繁盛してますな」
「お陰さまで」
明らかに、厭味かお世辞だがマスターはさらっと流した。さほどコーヒーが美味しいわけでもないこの喫茶店に集まる数少ない学生たちは、やはりこのマスターの人柄に惹かれたのかもしれない。最も、惹かれる人間自体少ないから、いつもガラガラなんだろうが。
「マスター、これよろしく。警察から、これをすべての商店に配れって言われてね、面倒であらしない。せっかく、防犯カメラまで付けたっていうのに。ともかく、これを読んどけって話だから。ええ、最近物騒な事件が起きたばっかだしさ。じゃあ、そういうことで」
かなり乱暴な日本語を言いながら、そそくさと会長は出て行った。
聖が、マスターの手許を除くと、そこには『商店主の防犯マニュアル』と書かれた紙があった。金庫の管理は云々だの、レジは云々だのが延々と書いてあって、とても見る気は失せそうだ。
「今更、何を配ってるんだろうな」
と、呟きマスターは店の隅のゴミ箱に捨てた。その瞬間、マスターの目に光が灯った気がした。
*logic& answer*
「うーん、まずキーポイントになるのは、この奇妙な服装だと思うね」
元ダイエー(南海だったっけ?)の藤本博史似(マイナーかつローカルかな?)のマスターは唐突に語りだした。
「随分、夢がないですね。『九マイル』みたいに言葉から推理していかないと」
聖が冗談交じりに言ってみたが、マスターは真面目に受け答えた。
「それでもいいよ。重要なキーポイントもココにあると思うね。重要なのはノッポがデブに言っているという点だと思う。まず、言葉の意味から確認していこう。この「高い」はexpensive意味じゃなくて、highの意味である。ここが推理できると思う。何故なら…」
マスターは随分と意気揚揚に言ってのけた。が、訂正してやらなければならない。
「マスター、値段が高いってexpensiveじゃなくて、high priceを使うんですよ」
「へー、そうなんだ。覚えとくよ。で、ノッポがわざわざデブに言ってるということは、デブには絶対出来ないことなんだ。でも、ノッポには出来るかもしれない、とそのデブは思ったわけだ。つまり、デブがneverで、ノッポがperhapsなわけだ」
「マスター、その間違えだらけの英語言わなくていいよ。デブが0%、ノッポが40%ぐらい出来るってことでしょ?」
いつの間にか、二人ともデブとノッポが固有名詞と化している。
「まあね。デブからそういわれたノッポは高すぎるせいで『出来ない』と判断した。だから、『このクリスマスツリーは高すぎる。他のところにしよう』といったわけだ」
「随分説得力ないですね」
聖は呑気に二杯目のコーヒーをすすりながら言った。
「だろうね。重要なのはココからなんだ。ノッポがわざわざ高すぎて出来ないというんだから、ノッポの背より高いところに用があるんだろう。さあて、ノッポの背より高いところに一体何があったのだろうか?」
「クリスマスツリーですか?」
確かに、二人はクリスマスツリーの近くに立っていた。
「そうだね。さあ、ここから別方面から推理してみたいと思う」
「別方面?」
もう少しで、謎が解けるというところで推理小説を取られるのと等しいようなことをやってくれる。
「そう。本当は、ここから始めたかったんだけどね。二人のいでたちのなかので一番奇妙なのはどこだと思う?」
「サングラス?」
「この時期、サングラスと言えば奇妙ではあるね。まるで、銀行強盗だね」
そこで、何故か知らないがマスターはニヤリとした。
「でも、銀行強盗ならマスクも付けとかないとねいけませんよ。それに、デブがサングラスも手袋していなかったってのも絶対おかしいですよ」
絶対に、銀行強盗は最低でも手袋とサングラスぐらいはしているだろう。
「いいとこに気付いたね。だけど、肝心なのはそれでない。そっちの方の推理に行っていいかい?」
マスター自薦のアップルパイが熱くて、言葉が出せなかった聖は無言で頷いた。
「二人の服装で、一番妙なのは『風邪をひいていたのに、コートを着ていない』だと思うよ。明らかに、相反しているから。ならば、ここが最大のキーになるんじゃないか?と思ったわけなんだ。さあ、コートを脱ぐ理由として考えられるような場合はどういう場合だと思うかい?」
この髭面マスターも、結構のってきているらしい。
「ええと、暑いってことですか?」
熱いアップルパイに苦戦していた聖は答えた。
「それが、一番多い理由だろうね。でも、寒くて着ておきたいのに着れない、というのはどういうパターンだろうか?」
「ええーと、服が汚れたとか破れたとか…」
「そうだね。よく、書道の時間なんかに服を汚してしまったなんてことがよくあったね」
それは、マスターが下手だっただけではないか、という大いなる疑問を抱いたが心の中にとめておく。
「で、服が汚れたんですか破れたんですか?」
「多分、汚れたんだと思う。破れても、そんなに黒なら目立たないだろうし、目立つほど破れたならば手に持っていてもわかるだろうしね。だから、服が汚れてしまったんだと思う。で汚れてしまって、脱いだんだ。でも、黒いコートが汚れるってどんな場合だろうか?」
「少なくとも、墨じゃないですね。あとは…、ペンキぐらいですか?ペンキ塗りたてに座ってしまったとか…」
「いい感じになってきたね。さあ、ココらへんでまた別の検証に写ろうか。重要な事がある。二人ともてんでバラバラに見えるけど、重要な共通点がある」
「なんか、ありますか?二人とも、コートを持っているとか?」
こうも、推理展開を変えるような探偵が他にいただろうか?普通、探偵は一つの答えから結論にたどり着いて、他の手がかりは証拠固めとして使われるのではないかという疑問もあるが、仕方なくマスターに応じる。
「この時期には珍しくないだろうね。二人の共通点は、人間だったとか、日本人だったとかと同じぐらいナンセンスだね。ならば、何か。一般人とは違って、彼ら二人だけの共通点だ。それは、二人とも“顔を隠している”という所だと思う」
「つまり、顔を隠さなければいけない理由があった」
「ひとえに言えば?」
「犯罪者?」
「そうだね。二人は、犯罪者だろう。監視カメラを設置してある商店街では素顔を見せるわけにはいかない。しかし、ここでデブの方に重要な要素が欠けている気がしないかい?」
「サングラスも手袋も付けていない、ということですか?」
「そうさ。相棒はサングラスと手袋をしているんだ。片方だけ、しないというのはやはりおかしい」
「ノッポは逆にマスクを付けてないですよね?」
「そう。ペンキ塗りたてか何かの為に汚れのせいで、デブのコート、手袋、サングラス、マスクは全て駄目になってしまったんだ」
ここにきて初めて、マスターは断定口調になった。
「えっ?でも、デブはマスクかけてますよ」
「仕方がないからと言って、素顔をさらすわけにはいかない。警察なんかに、追跡されてなくてもあとから、監視カメラを追跡すればわかるからね。だから、ノッポは応急策としてデブに自分のマスクをやったんだ。これで、一応は二人とも顔は隠れた」
ここで、マスターは息を深くついた。
「さあ、犯罪者が呑気にペンキ塗りたてに座るとは思えない。ならば、デブのマスク、コート、手袋、サングラスは何故汚れたのだろうか?」
「ひょっとして、血?」
「だとすると、相棒のノッポが汚れてないのはおかしいだろね。ノッポが単なる共犯者だったとしても、殺人犯がマスク、サングラスいるか?」
「世間一般のイメージはそうですけど…」
「それは、世間一般のイメージだろ?実際、相手を殺すなら顔見られてもいいわけだし。大体、血ぐらい固まる前ならサングラスに付いた程度は取れるだろう」
人を殺した事はないので、わからないがきっとそうなのだろう。
「なら、なんですか?」
「サングラスに付着しても取れないものさ。わからないかい?」
「ボンド?」
「犯罪者が使うとは思えないね…。わからないかな…。答えは、カラーボールだよ」
「カラーボールって、あれですか?銀行強盗とかに投げる…」
「そうそう。多分、職員が投げたカラーボールがデブの肩にでも当たったんだろうね。まあ、デブのほうが足遅そうだし、当てやすかったんだろう。それが、破裂してマスクやサングラスに飛び火した。まあ、コートは一発でアウトだろうね。手袋は、飛んだのが当たったのかもしれないし、何かの拍子に付いたのかもね。早坂君は、まるで銀行強盗だって僕が言ったとき、君は否定しただろう。でも、その否定材料は全部覆したでしょ?」
マスターはニコニコ笑顔だ。まるで、子供みたいだ。この店の数少ない常連客に、女性が多いのはそのせいかも知れない。
「ええ、まあ」
確かに、聖はその時「ノッポがマスクをつけていないのはおかしいし、デブがサングラスと手袋をつけていないのはおかしい」と言ったが、その材料は全て覆されている。
「じゃあ、例の言葉の検証に行こうか。その銀行強盗の二人は、一体クリスマスツリーの何に届かなかったのだろうか?ここで、重要なのは強盗の気持ちになってみることだ」
「なりたくないですね」
アップルパイを片付けた聖は一言で片付けた。
「まあ、そうだけ…」
とマスターは笑った。
「強盗は今一番何を欲しているだろうか?」
「さあ。強盗はやったことないからわかりませんね」
「本当かい?子供の頃、隣の子供からおもちゃ取り上げたりしてなかった?」
マスターは急に面白がるように言った。
「してません」
聖は、やや語気を荒くしていった。
「まあ、それは信じるとして。強盗は一番何を欲しているか。お金の隠し場所だろう。ガキ大将が、子供から取り上げたおもちゃを取り上げた際一番困るのが、どうやって母親に見つからずに隠すか、と同じ論理さ。強盗とガキ大将は大して変わらないってわけだ」
マスターは妙な締めくくり方をして続けた。
「おそらく、いち早く非常線をひいたである警察の網もくぐるのは大変だ。ココらへんに一旦隠しておきたい。そこに、お誂え向きのものがクリスマスツリーに釣り下がっていた。それは、一体何か?」
「箱ですか?」
「ああいうところにぶら下がっている箱は、開かないだろうからね。ならば、何か。多分、靴下だろうね。靴下は中空洞の上に、上がポッカリ空いている。アーケードの中に立っているから雨の心配もいらない。金の隠し場所としては最適じゃないかい?多分、ノッポが丁度背が届くか届かないかあたりに靴下が飾ってあった。そこの中に入れたらいいんじゃないか、とデブは考えて、ノッポに言った。でも、ノッポはギリギリ背が届かないから駄目だ、と言った、というところが真相じゃないかな」
「時系列順に並べると、まずノッポとデブはマスク、サングラス、手袋、コートを完全にきた状態で銀行に押し入った。
そこで、金を巻き上げたデブとノッポは、逃走した。それで、急いで追いかけた職員はデブの肩にカラーボールをぶつけた。それが破裂して、デブのコートやサングラス、手袋、マスクなどに付いてしまった。それで、デブは全部脱いでしまった。しかし、それでは素顔が丸見えになってしまう。仕方がないので、ノッポは応急策としてマスクを貸す事にした。それで、商店街方面に逃げてきた二人は、警察の非常線を警戒して、一旦お金を置く事にした。そこで、デブが、靴下の中に隠してみたらどうかと言ってみたら、ノッポが駄目と言って、他の所に隠した…、ってとこですか?」
「多分ね」
マスターはニッコリ笑って言った。
*epilogue*
その喫茶店からの帰り道、ふと交番の前を通るとある壁紙を見かけた。「二十二日、○○銀行××支店で発生した銀行強盗事件で、警察は情報を求めています。
犯人の様相は、身長180 センチぐらいと160センチぐらいの2人組で、二人とも痩せ方。黒っぽいジャンパーのようなものを…云々」
本当に銀行強盗はあったらしい…、って本当にマスターは最初から銀行強盗があった事を知ってて言ってるのではないだろうか?」
などと、余計な事を考えていると、ある文句に気付いた。って、二人とも“痩せ方”!?まさか、同じ日に二件の強盗事件が発生したのではないだろうか、と思い翌日訪れた例の喫茶店のマスターにそのことを告げた。
「ああ、なら簡単じゃないか。つまりさあ、160センチの痩せ型の奴がデブに見えたのは服の中に、アタッシュケースでも入れてたからだろうね。勿論、銀行から盗んだのをね」
これまた、あっけなく片付けてしまった。
「ところで、早坂君。一ついいことを教えてあげようか?あの、クリスマスツリーは二十四日、つまり今日までなんだ」
「何で、今日までなんですか?今日はイブですよ。本当は、明日がクリスマスですよ」
昨日からずっと主張していることを聖は言ってみた。
「さあね。それは、市のお偉がたの考えることだからね。ところで、クリスマスツリーの前で張り込みでもしてみたらどうだい?どうせ、クリスマスツリー付近に隠してるだろうしね。昨日見に行ってみたら、たかさが2メートルぐらいのところに靴下があったけど、それの反対側にもっと低いところに下げてあったよ。まあ、ネコババしちゃうってのも、面白いけど。その時は、この店にも寄付してくれよ」
呑気にコーヒーを注ぎながら、随分と物騒な事を言う。腰を浮かせた聖に、マスターが聞いた。
「張り込みするかい?」
「ええ、犯人を捕まえる為に」
「相変わらずの正義感だね。でも、夜中遅くに取りに来ると思うけど」
「ええ、構いませんよ」
「一つ聞いていいかい」
マスターは本当に子供のような笑顔を浮かべて聞いた。
「何ですか?」
「去年、付き合ってた彼女とはいつ別れたんだい?」
「何で、そんなこと知ってるんですか!?」
たしかに、彼女とは3ヶ月ぐらい前に別れた。
「推理だよ」
マスターはにっこり笑って言った。
4.クリスマスと少年と未来予知と(ガッチョン)
1
雪が見える…。
今頃の俺の心はまさにあの雪景色を象徴しているように思える。
真っ白のノートのような、銀世界。
まだ白紙の中身に新たなる物語が書き込まれるまで…
あれと一緒だ。
出来れば、そのままにしておいておきたいのだ。
道を踏み外したくはない。
人間として、今から行おうとしている行動は明らかに法の道に外れたものなのだから。
しかし、それはあくまで分かっているのだ。
それよりも、自分は悩んでいた。苦しんだ。
その計画は既に決定されている事なのだから、後は意思だ。精神力…。
ギィィィィッ
扉を開けた。暗い部屋の中で一人、目を見開きながら驚いている人物がいた。
そして…事の顛末…。
吹っ切らなければならなかったからだ。だからした。理由など、意味など無い。
しかし、これで何もかもが終わる。
我ながら完璧な計画だった。
天才的としか言いようが無い位に自分が怖い。
あの殺害状況から、凶器を特定するのは実に困難なのだから。
しかし、もし気づいた奴がいるとすれば…。
いいや、決して分かるはずが無いのだ。
クリスマスと言う時期を逆手にとって考えることが無い限り…。
暗闇の中で、彼はクスクスと笑いながら両手を踊らせていた。
闇に呼応するかのごとく『見ろ! ここが私の空間だ!』とでも主張したいように、その表情の不気味さは一層凄みを増している。増すことによって彼は彼自身の内側を垣間見る事になるのだから。
普段はもちろん人には見せることの無いであろう滑稽な姿であるために、彼の表面的な姿しか見ていない人物にとってはその認識を改める必要に襲われるかもしれない位のギャップがある。それはほとんどの人間が持っている可能性で、彼はそれが『ホンの少し』過剰なだけなのだが…。
と、その時だ。起動中のワードパットで小説を執筆している最中のディスプレイが影に覆われた。何事かと思い、視線を上に傾けるとそこには見慣れた女性の顔があった。
「うわぁ、何書いてんのよ? もしかして、もしかしなくともそれって小説かしら? 文才の塊すら微塵も無い岩崎が何を真剣に作業していると思えば…」
「わあぁっ! な、ななな…」
岩崎と呼ばれた人物は振り向いて驚いている様子を見せる。
「芳野! 何でここに…勝手に上がりこんできてたのか? ここは僕の部屋だぞ」
「知ってるわよその位。チャイムを何回も押したけど、返事がしないから上がりこんで来たの。居留守かと思ったけど、ちゃんといたから後ろから忍び寄って、ゆっくり近づいてみるまで全然気づかないんだから。貴方、多分耳がおかしいでしょう?」
耳を疑われて正直少しだけムカッと来たが、事実はその通りで全く気づかなかったのだから仕方が無いかと彼は一息をつく。右腕をずらすと、しわくちゃになった紙、文房具、後は何やら買ったことも忘れたようなプラスティックの玩具等を巻き込んで降下した。
「あーあ、何やってんのよ」
机の上はまさに氾濫状態で、ゴミが不確定に領地を占有していて周りにも足の踏み場はなかった。それは多数の国が醜くも陣地をせめぎあっている光景にも見える。周りが散らかっているのは彼の悪癖だ。どうあっても直らないかもしれないな、と如月芳野は頭を抱えた。
「それにしても…よくもこんな環境で住めるものだとつくづく思うわね。クリスマスが近づいているのに部屋を真っ当な景観にしようとは思わないのかしら?」
「クリスマスがどうって? 関係ないね。むしろそんな風に一日一日を特別に認識している人間の感覚こそ真っ当でないと思うし、他の日に失礼じゃないか。今日は12月23日だぞ! 常に見向きもされない12 月23 日に謝れ!」
「何訳のわかんない事言ってんのよ。偉そうに」
岩崎幹は前を向くと、またデスクに向かってカタカタと小説を書き始めた。芳野とは中学時代に一緒だった時からの腐れ縁で、今も近所に住んでいる。彼はよく部屋に閉じこもっているので、それにかまけていたずら好きな彼女は暇があれば度々押しかけて来る調子なのだ。芳野は、今はフリーでいる岩崎が自分の部屋で怪しげな時間の空白が何に置き換えられているのかは、気になっていたことだったがこれで納得できた。しかし、昔は漫画ばかり読んでいた岩崎が小説に置き換えた推移には驚いているのだろうか。文才は全く持って無し、数学が得意な典型的理系人間である彼は、現在は甲斐性無しの胡散臭いトリックばかり書いているオンライン作家なのである。
「所でちょっと見せて、何々、凶器を特定するのは実に困難、クリスマスと言う時期を逆手にとって…。まさか、まさかだけどアレでしょう? 推理小説?」
彼はその言葉でびくっとした。冷や汗がたらたら出ている。それは彼女が推理小説に相当詳しいのだから、謎が好きで身の回りにそれがあふれていると誰もがわからない問題でもスラスラ解けてしまうというつわものである。それだけに自分の作品を見られたくなかったという負い目もあったのだ。
「何? 文句があるわけ? 自慢じゃないが、ちゃんと推理もするし、人間ドラマっぽいのをでっち上げてみるつもりだよ。別におかしくは無いだろう?」
「プッ。今頃の俺の心はまさにあの雪景色を象徴しているように思えるだって…」
と、クスクスと笑い始めた。彼女にはこういう人を茶化す性格があるのが腑に落ちない所だが、ここは岩崎自身も陳腐な表現だなとうすうす思っていたので…
「ああ、わかったよ。下手だよ。文章は下手。雪を描写するほどの高度な技が使えるわけないから背景描写もおざなりさ、そっちでいつも色々言われてるから自分の弱点はわかってるよ。でもトリックとかにはそこそこ自信がある、何度不条理と呼ばれようが読者を騙せば勝ちなんだから」
話をすり替えてみた。強引なすり替えであるが、確かに自分としては騙しに長けたタイプの話をかくのが得意なのであながち嘘ではないと思えるが…
「でも、まさかだとは思うけどクリスマスという時期を逆手にとった凶器って、何か硬いものでもぎっしり詰めたくつ下とかじゃないでしょうね?」
ギクッ
そのものずばりでさっきの言葉が台無しになってしまい、さらにのけぞった態度を感づかれた様で、しまったと感じた。さすがに推理小説マニアなだけあってかなり勘がいいなと岩崎は思う。が、その実彼女の勘がいいのではなく、その謎自体が安易過ぎる事は自明の理であった。しかし、当の岩崎はそんな事に気づきもせず、むしろそのネタを軽々しく用いてミステリを書こうとしているのだから、間抜け意外の言葉が見当たるはずも無かった。すると呆れ顔の彼女は、それとは別にふと何かを思い出したように話を始めた。
「まぁいいか。それはそうと、今日は何か話があるんじゃなかったのかしら?」
忘れていた。兎に角忘れやすい性格なのだ、いつだって一つの事に集中できない悪癖を持つ彼はこの時間に彼女を呼んでいたことを忘れていたのだ、それに全く気づかないという浅はかさ。おそらくこんな滅茶苦茶な部屋の中で暮らしているから徐々に脳ミソが腐食されているのだろう、ととりあえずは生活環境のせいにして、岩崎幹は急いで思い出そうとする。
「え~~~と、たしか、そうそう。『未来予知をした少年』について話し合うところだったんだ。去年のことだったか、クリスマス近くの時期にアルバイトをしていたことがあったんだ…」
経緯は忘れたが、いつものように何気ない話をしていた時にうっかり出しかかったその奇妙な事実を今日彼女に話すことにしていたのだ。『未来予知』という独特の響きが彼女の好奇心をくすぐったのだろう、何かといえば話し、わめきたてていたことがあった。確か、そうだったなと思い出しながら…岩崎は回想した。巡らしていくうちに、もう一度あの問題に関して自分でもまとめてみようと意識してみた…。
「そこは聞いたわよ、戸井君に薦められた妙なバイトでしょう?確か…」
「引きこもりの少年と遊んであげるバイト?」
「ああ、知り合いに頼まれてさ、うまい具合に時間の空いている奴がいないかと探していた時にお前もバイトを探しているのを思い出してな。」
戸井英輔はこちらの顔を眺めながらそう言った。彼は古くからの親友で飽きるほど顔を合わしているので、部屋に寝転がりながら典型的な怠け者と呼ばれる生態活動を行っている岩崎の部屋に唐突にやってくるのは自然な成り行きだ。しかし、いきなりの彼の提案にその時は驚いたものだった。
「おいおい、確かにバイトは探しているが…なんだそりゃぁ? 遊んであげることがバイトなのか? そんなことで金をもらってたら真面目に働いて、稼ぐのに一生懸命になっている人に申し訳ないと思わんのか?」
と、とりあえず文句をいう事にする。その実内面ではおいしいバイトだと思いながらもその奥に潜む胡散臭い香りも感じ取ってはいたのだが…。
「俺はお前にバイトを薦めているだけだよ。俺も前にそのアルバイトを受け持ったことがあるので、別に怪しい仕事じゃあないといえる。その息子は引きこもりをしているが、そうひねくれた性格の持ち主じゃあないんだ。むしろ世間知らずで純粋無垢と言う感じがするね。引きこもりの原因は病気だったからだしね…。体が弱いからそれを気にして『取り残されている』という雰囲気を感じ取るようになっているんだ。純粋に甘えてくれる大人が必要なだけ、お前はそういう子供の扱いは得意だったろう? 俺はどうも合わないみたいだし、所属している演劇のサークルでの活動があるから行けない。まぁ、話をするだけだから幾らお前でも十分にやりこなせる仕事だし、時給はさほど悪くないだろうと思える、さてどうするね?」
友人のいつもながらに調子のいい言葉に溜息をつきつつも、子供の扱いは…確かに得意だと言えるなと思った。しかし、厄介な事に戸井の紹介してくるバイトに過去ろくなものがなかったのは確かなのである、彼は昔から人を落とし入れることを楽しむタイプなのだ。いたずら好きで、何かを企むのが好きだ。それだけにバイトの紹介と聞いたときから疑っていたのだが、興味があったために不安と期待が錯綜し、混雑するうちになるようになれ、と感じていた。
「じゃあそれでいいんだな。こっちの紙に時間とその家の住所が書いてあるからものは試しに行ってみなよ。スケジュールは固定化されていて、何をするかは決まっている。最初の三日間は話しをするだけ、それで少年と話が合うならOKだ。散歩のコースも固定されている、この近所の麻野川の土手からスーパー、オークスまでの道のりまで。体が弱いから、あまり遠くには行けないしね」
しかし、いつものパターンならこれで終わるはずも無いだろう…。彼はいつも妙な付録を残していく、最近の雑誌によく付いてくるガラクタと一緒だ。いらないのについてくる、邪魔になるだけなのに…。
「ああ、そうそう。その少年に関する妙な噂を伝えるのを忘れていたよ。彼は予知能力者なんだ、何が起こるかわからない未来をいとも簡単に当ててしまうんだよ、凄いだろう?」
ほら…こんな風に…。
「で、クリスマスの夜に起こった惨劇は、どうしても凶器が見つからなかったんだ。警察の苦難の捜査に関わらず、それは難航した。凶器が無ければ犯行が立証できない、すなわち犯人を捕らえる決め手にならない。目星はついていたんだけど、まさに犯人にしてはしてやったりと言うわけだった」
「うん、わかんないや。どうやったんだろ…」
少年は悩み始めた。目はぱちりと大きくして、じっとこちらを見ている。その様子は演技ではなく、純粋に悩んでいる様相が感じ取れるだけに岩崎にはその反応が予想外のものであった。話を続ける。
「そう、そんな風に刑事達も悩んでいたんだ。『わからん、一体凶器は何処に行ったんだ! くそっ! 犯人め!』と言う感じにね、でも、偶然にその時パーティの招待を受けていた名探偵はそんな彼らの前に現れ、『お困りですか? ならばこの私にお任せあれ』と言って見事に事件の謎、即ち、凶器が何処にあるかという答えを解き明かして見せたんだ。クリスマスにて身近に感じられる発想、それが単純すぎて誰 もその事実に辿り着きはしなかったのに…」
「ふうん、凄いんだ。名探偵って。それにかっこいいし、ゼブーラマンみたいだ」
ゼブーラマンというのはテレビアニメで最近放映している賞金稼ぎのヒーローが悪の組織と戦うストーリーで、低年齢層に絶大な人気を誇っているらしい。岩崎も何度か見た事がある。賞金首の張り紙に×をつけて、「これで悪はいなくなった」というお決まりの言葉を残して去るのだが、子供には印象に残るらしい。彼もそのアニメのファンである。それはそうと、まだ悩んでいるようだ。
「う~ん、駄目だ、全然わからないや。どういうことなの? 一体…」
その言葉は本当に純粋そのものと言ってよかった。今風の子供とは違う、しゃべり方、仕草、何もかもが岩崎の耳に覚えが無い少年像をかもしだし たのは確かだった。答えを明かすと、また一段とその 仕草に引き込まれていくようで…。
「えぇぇ~、靴下にビー玉を詰めて犯人はそれを凶器にしたの~? 凄いなぁ…」
以前、近所の子供に同じ事を話したときはさめた表情で「それで?」と返されたのだったが、矢張り思いっきり驚かれてしまったのだ。こういう驚きを感じてしまい、ついつい岩崎は調子に乗って…。
「実は僕はこういう小説を以前から書こうと思っていてね。そう、推理小説だ。そこで思いついたこのトリックを使った話にしてみようと思っているんだよ。書くのが遅いからどのくらいかかるかはわからないけど、これは完成したら真っ先に君に見せてあげるよ」
少々自慢気に語ってしまった。話すのは自分の事ではない、この少年の心の居場所になる仕事なのだから横道にそれてしまったかと岩崎は危惧するが、目を輝かせる彼を見ればそんな事はどうでもいいかと思えてしまう。
「へえ~、すごいなぁ…。そういう小説も書くんだ、それ、僕に見せる事は約束だよ。絶対だね」
そう言いながら、少年は先に走り始めた。突然どうしたのかと驚いたが、雪が降っているのではしゃいでいるだけだったのだ。岩崎はほっとして上を向いた。
菊沢都樹、8才、小学校3 生、体が弱くて病院のベッドの上が多く、退院したばかりなのだが、時間が彼と友達の間の距離を遠ざけてしまった。そうして離れてゆくうちに内気な性格に育ったと聞いていた。学校には行っていない。確かにそういう雰囲気はある、始めてあった時は下を向いて中々しゃべらなかった上にうちとけるまで苦労したが、今は全くそうでもない。無邪気で、純粋そのもので、驚くほどに…。
(それで、君にやってもらう仕事は『息子と遊ぶこと、話し相手になること』だ。どんなやり方でも構わん。息子にとって最良と思える方法で接してくれ。どれが最良かは君が判断してくれればいい、ゲームセンターに行くなら使用した分の費用を報告してくれればこちらがもつ、何か買いたいものがあれば遠慮なしに与えてくれ。くれぐれも、息子のためにならないようなことを教えるのは決してならん事だから、万一そうなればこの話は無かったことにしよう。息子はデリケートだからな、細心の注意を払ってくれたまえ…)
金持ちの息子はこうは育たないものだ。自分勝手に一人歩きする性格の人種をよく見てきただけにさらに違和感がある。それはまだ若いからだろうか? それとも病気が原因なのだろうか? 親が良いから(見ただけで判断の仕様は無かったのだが、印象はよかった)なのだろうか? 人の心は不可解なものだ、まして純粋な子供の心は…。その問題に答えなど、無いのだろう…。
「ねぇ? どうして雪はこんこん、なのかな? 雪はこんこんって鳴らないよ、狐がいて、後ろで鳴いてるからこんこん、なの?」
考えにふけっているうちにひょっこりと彼は顔を覗き込んできた。少しだけびっくりしたが…。
「さぁ…、どうしてだろうな。もしかしたら狐がいるかも知れない。うん、それは考えなかったよ。君はすごく頭がいいよ。確かにクリスマスの歌には変なところがある。ジングルベルとも鈴はならないしね、日本語はおかしな事ばかりだと思う」
長い散歩道を抜けて行き、クリスマス風に改装した建物、スーパー『オークス』の看板が見えてきた。大きくX'masと書いて、すぐ横にはサンタの顔が描かれているダイナミックな看板だ。店の規模は大きいが、地方にしか出回っていないスーパーで、全国的にはそれ程有名ではないが、品揃えなどが豊富、価格が安い、質が高い等の理由から地方での需要は高く、それなりの客数をキープしている。モットーは『ビッグサイズ』である事らしい、宣伝ポスター、看板やら何やらはとにかく大きいのが目立つ、商品までビッグサイズのものが多いのだ。値段以外は兎に角『ビッグ』にする方針が果たしてその経営状態にプラスなのかマイナスなのかどうかに関しては、当然のごとく岩崎に興味など無く、分析したことなど皆無だった…。少年は3階の駐車場から、その方向に向かっていく…。クリスマスセールの前なので、客はそれほどいない、がらんとしている。安くは無いが、押しくら饅頭よりはマシかと岩崎は思い…。
(何か買いたいものがあれば遠慮なしに与えてくれ…)
手持ちは多少あったな…と岩崎は思い出し、少年の後を追った、上階のゲームセンターのほうに向かうのだろうか…。頭で少し落ち着くと彼は何かを思い出し始めた。
(確か、戸井がこの子供が未来予知をするとか何とか言っていたがどうやらヨタ話だったようだな、あの時はちょっと真剣な顔で言われたから少しだけ信じ込んでしまったが、幾らなんでもそれは…)
「サンタさんが、襲われる!」
3
近くで、声がした。いきなりだった。何のことか理解するのに時間がかかったが、とりあえずは都樹がしゃべったことには間違いが無さそうだなと判断する。それにしても…何でまたいきなり…
バァン!
何かが、破裂したような音が聞こえた。聞き覚えのありそうで、実際には無い音。岩崎はそれを耳ではっきりと聞いていた。
(銃声…?)
上を向くと、サンタがよろめいて倒れそうだった。
(撃たれて倒れた…?)
渦巻く突然の激流は、当然彼の自制心を揺さぶったのだ…。
(サンタが…?)
普段見かけない光景、自分が創り上げている虚構の世界を現実に具現化したようでいた…突然の圧迫感。
(襲われる?)
少年も驚いていた。何が起こったのか、分からない様子なのか、それが判断できない岩崎よりは正常かもしれなかったのだが…。
(未来予知…?)
気づいたら、走り出していた。都樹もついてくる。転びそうになったのでうまく抱えて、彼のペースにあわせることにする。落ち着かなければならない…。エレベータに乗る。
(屋上で倒れたあのサンタは、こちらからもよく見える位置で金網に寄りかかっていた。それにしても…なんでまたこんな事に)
屋上に着いたところで、子供に死体を見せるのはまずいのではないのか? と意識が走ったが、少年は一目散に飛び出した。が、続いて係員らしき男に抑えられたので岩崎はほっとする。
「危ないから、離れて離れて…」
「何があったんですか?」
岩崎は質問する。現場にはギャラリーがそれ程いないので意外に思う(学生らしき人たちがせいぜい5,6人居るくらいだ)が、奥には赤い服の男、サンタが倒れていた。胸をぎゅっと押さえている。指の隙間から、幾つかの赤い筋をたらりたらりと流しつつ…。
「大丈夫だ。死んでいるわけじゃない、致命傷を外れたようだから医者を呼べば何とか済む傷だ。しかし銃とは…」
「彼は屋上で何をしていたんですか?」
「何って…ただのビラ配りさ…。どうして狙撃されたかどうかなんて皆目よく分からんのだ。可能性としては十分に可能だろう、この周辺には高い住宅ビルがいくつかあるから、そこから狙撃されたとすると…」
(いや、それよりも少年がどうしてあの言葉を言えたかどうかが何よりも不可解だ。一体どうして…?)
(くれぐれも、息子のためにならないようなことを教えるのは決してならん…)
「あっ」
狙撃事件に居合わせたなんて事がばれればすぐさま首にされてもおかしくは無い。年末はただでさえ金欠なのに、それにこの子のことを案じると、事件に首を突っ込むべきではないだろう。推理小説を書くからと言って、推理能力が長けている訳でもないのだし。探偵ごっこをやっている場合ではない…。やはり…。
…
暗転。
「それでおめおめと逃げ帰っちゃったわけ? 馬鹿ね、本当に。」
如月芳野は溜息をつきながら感想らしからぬ言葉を述べた。とりあえず、その態度は馬鹿にすることを忘れていない。彼女に馬鹿にされる人間は多いが、何故か岩崎幹はほとんどの場合、その対象になるらしい。彼自身も、そのぎこちない性格は直そうとしているが、性格は直そうとしても中々直らないものだ。
「それで、そのサンタさんは?」
「さあ、知らない。死者が出ていないんだからそれ程噂にはならなかったらしい。新聞には出なかったし、後でそのデパートの屋上に行ったら『事件? 何のことだいそれは?』と、とぼけられた」
「何で?」
「知らない」
「銃は?」
「何処にあったのかな?」
「興味を持とうとしないの?」
「疲れた」
「アンタねぇ…」
苛苛しているようだ。これだけの情報からじゃ、事件のおおよその展開など分かりはしないだろう。小説にある登場人物はこの辺りから颯爽と乗り出して、サンタに恨みを持っている人物を探し出して闇の組織に戦いを挑んだりするのだが、一年も経っているのだし、例え今がその時だったとしても岩崎という物書きにできることなど無かっただろう。闇の世界に興味や好奇心なんて、小説のネタになることくらいしか浮かばない。
「それで、そのバイトはどうなったの?」
「首になった。都樹君が事件を見たいというのを無理やり引っぺがしてつれて帰ったから、嫌われたらしい」
「いい気味ね。まぁ、それはいいとしてもね…」
芳野は考え始めた。謎を解くことが好きな彼女はこの事件を暴こうとするも、悩んでいるように見える。岩崎が事件の情報をうまく仕入れていないせいだと思われるが…。
「彼は、『サンタさんが襲われる』と言ったのね?」
「それは確かだ。突然屋上の辺りを見て、叫び始めた。未だにそれは謎だよ、銃でも構えている人影を見たんだろうか…? しかし犯人が屋上にいるとすれば、あの辺りはもっと大騒ぎになっていたはずなのに…。ビルは周りにあったが、都樹は『真っ直ぐ屋上を見ていた』んだし、実際に犯人を見たとは考えられない…」
「その子が勝手に言った…事なのね。う~ん、どうだろう。彼もはっきり意識してそういったのか、無意識で言ったのかは分からないのね…?」
「うん、前もってそう喋れと誰かに指図された様でもなかった。その後で彼に聞いてみてもよく分からないの一点張りだったから…」
ふうん、と一息をついて彼女は部屋の中に落ちているビラを拾い上げた。彼の部屋にはとにかく何かが落ちている。
「これは、オークスのチラシね。今年もセールがあるようだし、繁盛しているようね。私は行かないけどね、何でもでかくするというよく分からない経営理念が好きじゃないわ」
と呟くとその紙を凝視しはじめた。食い入るように、やがて目を上げて…。
「ふうん…」
と一息を入れつつも…。
「チラシには、せいぜい値段と商品くらいしか書いていないよ。あと店の外観が見えるところ位か…。ふふん、流石の推理マニアも現実に起こった不可解な出来事は解き明かせないんだな、いわば小説の謎は親切すぎるんだ。クイズ性を出すために荒唐無稽な推理ドラマをでっち上げているから単純な構成力、伏線などにより『名探偵でも普通に解けるように』出来ている。それは話が成立しないからしかたなくそうしてるだけで…」
勝ち誇ったような顔をして話す岩崎に向かって、割り込んだ声…。
「岩崎幹という馬鹿はこんな問題にさじを投げてしまう男なんだ。よく考えれば簡単じゃない、純粋な子供の心があるものを見てどう思ったか、そして倒れるサンタ。忘れ去られる事件。全てはパズルのようにつながるもの…」
「はぁ…」
「所で、未来予知という言葉を聞かされたのは戸井君で間違いないのよね? 他にその言葉を言った者はいない?」
頷くと、何か一人で納得したようで、こっちは気になって仕方がなかったのだ。
(そういえば、戸井は何処からそんな情報を仕入れてきたんだろうか…。以前に同様のアルバイトをしていて似たようなことが起こったとか、いや、非現実的な解釈だ。あんな事が二度も続けて起これば、それは予知能力が証明されたことになる。アレだけの事実でこれだけ悩んでいるのだから、これ以上荷物が増えるのは御免だ)
「そういう事なの…。君は知らないほうがいいかもしれないわね、この事件の謎に対するその無神経ぶりはある意味最も望ましい形だわ」
(……)
彼女の言っていることがよく分からなかった…。この事件に関しては岩崎自身、色々考えてみても答えは出なかったのだから絶対に無理だろうと思っていたのだ。彼女は話を聞いたばかりなのだから…、一年間もそれで悩んでいるだけにたかだか聞いて数分の相手に負けるわけがないだろうと、同時にそれ が分かった事により自分の面子も立たなくなると恐れたのも理由である。
しかし、自信を持ってそういった彼女の宣言が外れたこともことさら無いので不安も錯綜した。何はともあれ、『とりあえず』話を聞いておこうと思ったのである。
「ふむ、仕方がないから聞いてやるか。とりあえずの時間は少しだけ空いているから事短く頼むよ。簡潔で、丁重に言ってくれたまえよ。ホームズ君」
「帰る」
「お願いです。話してください、芳野様」
読者への挑戦状さて、もう言うまでもないが、作中の岩崎幹はガッチョン自身であるのか? 何てバレバレの問題をふっかけるつもりなどは毛頭無い。問題の構成がいつもと違うので、どこから推理していいものか、多少混乱されている人がいるかもしれない。その為にちょっぴりヒントをここで公開します。 今回の推理のポイントは少年が何を見たか…それはクリスマス風に装飾された看板。そこでどうして『襲われる』という言葉を連想できたのか? そしてサンタは本当に狙撃されたのか? そこにも微妙な伏線を作っておいたので、気づいていただければ幸いです。 |
3
懇願するのかしないのか、いい加減な態度の岩崎にやれやれ、しかたないなと溜息をついて彼女は話す事にしたようである。
「このチラシにはオークスの外観が書かれているの。そこで、クリスマス風に飾り付けされた看板が印刷されているのでその答えが分かったわけ、多分、私がわかったのはこの看板を初めて見たからだと思うのよ。あんたは普段からオークスの安売りセールに飛んでいくから、それで見慣れて、わからなくなってしまった。気づいた要因はそこにあると思うの」
「要因? 初めて見たものじゃないとわからないって事か?」
「それは違う。少年がこの看板をどう捉えたかが鍵になるのよ。アンタのお堅い頭脳じゃとてもその考えに結びつかなかっただけ…。これよ、よく見なさい」
と言ってチラシをかざして見せるとX'masという大きな白抜きの文字とサンタの顔がダイナミックに描かれた看板が目に入った。流石にダイナミックさをアピールする程のデパートなだけあって中々に迫力がある。しかし…やはりどこからどうみても…
「普通の看板だろう? ただ派手なだけで…。とても彼が何を印象付けたか等という疑問の答えになりそうもないよ」
「まだ分からないのかしら? このチラシの文字、X'masと書かれているでしょう? 特にそれを印象付けるためにXの部分が大きくはみ出る位に描かれているの」
「……」
「その少年はそれを英語のXでは無く、○×の×の記号だと思ってしまった。と純粋に捉えればどうかしら? 君と少年が会話している内容で、少年は純粋で、頭がよくて、それが時に突飛な言葉を紡ぎ上げた要因になったのかもしれなかった。原因は別かもしれないけど。そのXの印象が大きく、彼にはmasの部分が見えていなかった。もしくは、クリスマスをX'masと省略する事を知らなかったのかもしれない。まだ子供だから、それは仕方がないことだけどね。
そこで、その看板に並行してあったサンタの顔から、彼は位置がずれてるにせよサンタが×印をつけられているのかと感じたの。都樹君は確かゼブーラマンのファンだったわね。あのアニメは賞金稼ぎの主人公が悪者の張り紙に×をつけて、「これで悪はいなくなった」というお決まりのセリフを残す内容があったわね。まして彼はそのファンなのだから、人の顔とその×が接近しているのを見て、現実にそのアニメの世界を投影していたとしてもおかしくはないと思うの。だから、いきなりにせよ、『サンタさんが襲われる』という言葉が出てしまった。デパートの看板がダイナミックだったために、子供の心理に与える影響があまりにも大きかった。そういう事なのだと思う」
「うっ…。と、突飛だな…。しかし、事実そうだとしても、銃弾事件の方はどう説明するんだ? そのときに全くの偶然で事件が起こったとでも言うつもりなのか? そんな奇跡的なことが…」
そう、それにより、彼が「サンタさんが襲われる!」と言った理由は説明できるが、それとサンタが狙撃されたことは全くの別である。むしろ、余計に不可解なのだ。しかし、彼女は『まだ説明が必要なのかしら』と言う風に岩崎に視線を向けた。
「だから、まだわからないの? 『あんたは戸井君に騙された』という事に…。いまの話で少年の言葉は未来予知でもなんでもないことが分かったから、彼の「少年は予知能力者だったんだ」という言葉の意図は、少年のその性格により、「サンタさんが襲われる」という言葉がオークスの看板を見た事により叫ぶことをあらかじめ予測しておき、彼自身が屋上に待機してその未来予知を演出するためだったの。都合よくその言葉が出るかどうかは確率だけど、彼は以前、あなたの言うそのバイトをやっていたからあらかじめ都樹君の性格を知って、看板を見せたらそうなるだろうかという期待と、岩崎を騙せることを企み、『未来予知』という言葉を出して、その計画を遂行することにした。
あくまで、都樹君がそれを話した場合にだけ成立すると言う賭けだけれど、それは的中した。彼が所属している大学のサークルは演劇部だったわね? 何人かメンバーを集めて、事件があったように演出したの、全員がグルでね…。サンタの衣装も、中々手が込んでるけど、あらかじめ用意されていたのね。あの建物は、屋上の下にゲームセンターがあったし、壁が厚いから銃声があったとしても下に届く心配はなかった。だから、テープレコーダーか何かで偽装された偽りの銃声をながしたとしても外にしかそれは聞こえなかった。セール前なので客は少なかったのだし、的を絞って外にいる者にのみ聞こえる銃声で、岩崎に事件があったのだろうと言うように錯覚させた…」
「何てこった、あのサンタの中身は戸井だったのか…。確かにそうかもしれん、あいつは人を騙すためなら何でもやりかねん、そういう性格をしているのだから…。しかし、よくそんな事がわかるな。僕が一年かかってもさっぱり分からなかった謎をちょっと聞いただけで…というのもね」
「あんたの説明は、屋上の人たちの描写で幾つか矛盾があったのよ。それでおかしいと思った。まず一つ目、被害者は胸をギュッと押さえてると言うのに係員は『致命傷は外れている』と言っていたの。胸って致命傷でしょう? 二つ目は、ギャラリーが少ない屋上でビラ配りなんかしても渡す人がいないでしょう? 三つ目、銃弾事件が噂にならなかったなんて事があるかしら? 死人がなかったとしても普通あり えないわ。本当の事件なら、次にそのデパートに行ったときには捜査員が押し競饅頭よね。幾ら何でも 「銃弾事件? なんだいそれは?」と聞き返されることなんてありえないと思うのよ」
岩崎はヒタスラ唖然としながら彼女の言葉を聞いているだけだった。戸井は今まで何度も会っていた が、それを隠しながら、騙しながら一年の間放っていたのだろうか? 正直腹が立ってきた。あまり気が短いほうではないが、この行動は友人とは言え幾らなんでもやりすぎに思えてきたのだった。
と、その刹那玄関のドアが開き、また見慣れた顔を見ることになった。今までの話を立ち聞きしていたのだろうか? 戸井英輔である。今まで騙していたという事での負い目はなさそうで、逆にニヤニヤしながら言った。
「やあ、遂にばれてしまったかね。銃声を鳴らしたときは正直危ないかと思ったけど、今思えばうまく言ったと思うよ。ああ、そんなにおこるなよ、君の大好きな愛媛みかんをたっぷり持ってきてやったんだから…」
と言いつつ、ナイロンからみかんを取り出してきた。岩崎はみかんには目がない、正直大好きなのだ。 あの微妙な渋み、袋から流れ出す果実の新鮮さ、美味の宝玉。果物の王様。みかんがあれば誰だろうと許せてしまう、至高の存在であった。だから…。
「ああ、戸井君。いやいや、全然気にしてないよ。久々にミステリとしての謎あふれる快感を味あわせてもらったのだから礼を言いたいくらいなのだよ。所で、それを、一つでいいから是非ともそれを…」
戸井が放ってきたそれを受け止めた岩崎はむしゃぶりつくようにそれを食べ始めた。あまり食わないと、禁断症状に襲われたりするのだから必死なのである。
「あまり急いで食うと喉に詰まるぞ。所で話は変わるが、今日はバイトの話を一つ持ってきたんだ。菊沢都樹のね、時期的にもクリスマスなのだし、去年の会話を思い出してもう一度お前に会いたくなってきたらしいんだ。都樹本人の希望らしいよ」
「あっ」
しばらく経っていたから忘れていた…。そういえば、彼に作品を見せてあげる約束をしたのですっかり忘れていた所だったのだ。執筆が遅くなるとはいったが、一年もたっている。しかし、完成したのだから一応は…といいつつ岩崎はやはり悩むのだった。一応、作品はここにあるのだが、ハリボテで、尚且つだらしのないトリックであるからして…
「何してんのよ。ぼけっと突っ立ってないで早くその作品を見せてあげるっていったんなら約束は守りなさい、それが礼儀というものなのよ」
(へぇ~、すごいなぁ…)
(うわぁ~)
そう言えば、自分の何でもない話にあれだけ驚いた表情を見たのは初めてのことだった。小説を書いている理由も、誰かが自分の作品を読んで驚いてくれる瞬間を楽しみにしているから書いているのだ。ただそれだけのこと、他に理由は無いのだから。むしろ、理由なんて曖昧なものだ。
だから、もう一度彼に会ってゆっくり話がしたいなと思い、二人に部屋を任せて岩崎は外へ飛び出し、雪が降っている路面の中を頭を上げて走っていった。
そういえば、明日はクリスマスだっけ……………
5.「クリスマスの雪密室」 有沢翔治
FILE1.講演会の依頼(十二月十七日、午後六時三十分)
あと一週間経てば十二月二十四日。名古屋の街では街路樹に色取り取りの豆電球がチカチカと光っている。軽快なクリスマスソングも流れ、夕闇にロマンチックな雰囲気を醸し出していた。若いアベックが腕を組んで楽しげに喋っている。
そんな幻想的な街中を私はくっついてきた萌ちゃんと連れ添って歩いていた。彼女は卵形の顔、ショートヘアの髪型の可愛らしい少女で、私とは向かいの家に住んでいる。そんな彼女に私は恋心を抱いているのだ。
「その髪なんとかしたら?」
と苦笑しながら萌ちゃんが言った。
「ああ、これ?」
私は頭を掻きながら言った。確かに萌ちゃんの言う通り、キャベツや雀の巣を乗せたようだ。おまけに普段から櫛を入れてないので、そのだらしなさにより拍車が掛かっている。そろそろ床屋に行った方がいいかな。私はそう思った。おまけに着ている白いジャンバーは薄汚れ、鼠色になっている。
これじゃまるで浮浪者だな、と私は心の中で苦笑した。とは言え、色白の肌が幸いしてか、私は一度も浮浪者と間違われたことはない。顔の輪郭がシャープなのや、私が掛けている青緑色の眼鏡のせいもあるかもしれない。
「そのうち行くよ」
「そのうちっていつ?一緒に歩いている私が恥ずかしいんだからね」
「解ったよ」
じゃあ、何でついてくるんだよ。私はその台詞が喉もとまで出てきたが、黙って苦笑いを浮かべた。どうせ行かないんでしょう。そう思っているのか冷ややかな目で私を見ている。
「ところで大学はどうするの?」
「・・・ねえ、話を逸らそうとしてない?」
心を見透かされて、私はハハハと乾いた笑いを浮かべる。
「まあ、いいわ。答えてあげる。法学部だよ」
「受験勉強は?」
「内部推薦だから大丈夫」
「じゃあ、もう決まったの?」
「うん。十月の半ばに」
「おめでとう」
「あれ?言わなかった?」
そうだったかと私は記憶をまさぐったものの、一向に思い出せない。うーんと唸っていると、ポケットの中で携帯電話が鳴り出した。いつものように、西口警部が事件を持ち込んできたんだろう。
「はい、もしもし?」
「もしもし、私」
私の予想とは違い、チャット友達の<有栖>からだった。彼女とは長野のギリシャ館で宝探しをしたり、彼女の通う大学で起きたちょっとした事件を解決したりとオンラインとは思えない付き合いをしている。
「ああ有栖か。どうしたの?」
聞き慣れない名前を聞いて萌ちゃんが妙な顔をした。アリスと言う名前から外国人だろうか、と訝っているのかもしれない。
「ちょっと頼みたいことがあるんだけど・・・」
「何?」
「私の入ってる部活で講演会頼めない?」
「講演会?」
私は驚いて訊きかえした。まさか私に講演会を頼むとは相当な物好きもいるものだ。あまりの驚きにしばし硬直していると、有栖は不安そうに
「ダメかな?」
「いや、それでその講演会はいつ?」
「十二月二十四日・・・、クリスマスイブよ」
「それで何について話せばいいの?」
「<推理小説研究会>だからその辺の事を」
私は古今東西のミステリを読破していて、自分のサイト上にも推理小説に関する論評などを載せているのだ。二年ほど前からは本物の犯罪捜査に加わっている。
「ああ、そういう事か。ミステリ関係の話じゃないなら、僕に講演を頼むはずがないもんね」
「そんな事ないわよ。ホームズは理系から文系まで詳しくて六カ国語話せて、それに普通<の人なら知らない知識もあるし」
<ホームズ>とは私がインターネットで使っているハンドルネームである。オフラインで逢う時もこの名前で呼び合っているのだ。
「買いかぶりだよ」
「ふうん。それで講演はしてくれるのね?」
「うん。何分間くらい話せばいいの?」
「十分間くらいよ」
「解った。十二月二十四日に、何時くらいに?」
「十二時の講演だから・・・、八時五十分にJR中央改札の前で待ち合わせましょう」
「うん、了解」
「ありがとね。あ、クリスマスパーティも一緒にやるつもりだから昼はいらないわ」
「解った」
と言って私は電話を切り、ポケットにしまった。ふう、と私は溜息を吐く。私の深刻そうな顔を見て、萌ちゃんは
「どうしたの?」
「いやね、友達からスピーチ頼まれちゃって」
「ああ、ミステリ関係がどうだか言ってたよね」
「うん。できればクリスマス関係のネタがいいかなと思って」
安請け合いしたものの、何を話せばいんだろう?クリスマスに見合った話がしたいし、きっと有栖もそう望んでいるだろう。私がどうしたものかと困って、頭を掻きむしりながらうんうん唸っていると、不意に萌ちゃんが、
「いっその事、全部アドリブでやるってのも手かもよ」
なんて言い出したのである。
「おいおい」
冗談じゃない!と私は少しムッとした。後援会で何を話そうか、としばらく考えていると、彼女はまたとんでもない事を言い出したのだ。
「ねえ、私も連れてって。妹としてついていくから。ねえ、いいでしょう?」
FILE2.講演会(十二月二十四日、正午)
翌朝、私と萌ちゃんは待ち合わせ場所のJR中央改札の前に着いた。真後ろにある丸型で白い文字盤の縁に金細工を施した大時計の針は十時四十分を指している。朝から蛍光灯が煌々と灯っているのを見て、私はいつもながら無駄遣いだと感じた。クリスマスリースがあちこちに飾られていて、クリスマスムードを盛り上げている。
行き交う人はほとんどが若い男女だ。寒いと言うのにミニスカートを履いていて、私は目のやり場に困り、萌ちゃんに目を移す。ウォークマンから流れる流行歌に合わせて、身体を小刻みに動かしている。
「僕も何か暇が潰せるものを持ってこればよかった」
私が萌ちゃんを見つめているのに気付いてか、ウォークマンのイヤホンを外して
「どうしたの?」
「いやいや、退屈しちゃって」
「ふうん、眠いんじゃないんだ。さっきから欠伸してるけど」
意地悪っぽくそう言った。気付いてたのか、と私は恥ずかしい気持ちになった。
「それもあるね」
「やっぱり。だっていつも九時に遊びに行っても寝てるジージョが七時起きなんてありえないもん」
私はハハハと乾いた笑いを漏らす。
「奇跡に近いね」
「そこまで言うか?」
私は笑いながら言った。萌ちゃんもフフフと笑って、
「冗談。車の中でぐっすり寝たら?」
「そうするよ」
私は大きな欠伸を一つして言った。私は有栖の車が駅前の車寄せに来たのを見て、
「あ、来たみたいだよ」
と言って、車から降りて私たちを探している有栖に手を振ると、向こうもそれに気付いた。軽いウェーブがかかった髪と細身の体格が特徴の女性である。
「お待たせ。さぁ、行きましょう」
有栖はそう言って、さっさと歩き出してしまう。私たちも遅れないように後に続く。
車寄せから車が静かにスタートした。
「見えてきたわ」
有栖は、車のハンドルを握ったまま助手席で眠りこけていた私を揺さぶって起こした。まだ完全には起きていない頭で私が彼女の言う方を見た。しんしんと降り注ぐ雪の向こうに、古風なレンガ造り建物が見えてきた。雪はまだ降り始めのようで、積もってはいない。
「何で萌までついてくるの?」
私は萌ちゃんを睨みつけた。妹と言うことになっているので「ちゃんづけ」はできない。妹といっても、全然似てはいないのだが。
「まあまあ」
「とにかく、頼むから邪魔だけはするなよ」
そうこうしているうちに有栖は車をその家の前に止めた。駐車場に目を向けると、既に何台かの車が停まっている。
「もう皆来てるみたいだね」
リースとクリスマスツリーが飾られている玄関の扉を開けた。木の靴箱の上には馬の置物や人形などが飾られていて、賑やかな雰囲気を与えてくれる。土間には六、七足の靴が乱雑に脱いであって、ワイワイと喋る声と軽快なクリスマスソングが中からかすかに聞こえてくる。
「準備はいい?」
そう言うと彼女は扉を勢いよく開けた途端、パンパンとクラッカーがはじけ、中にいる学生たちが拍手で出迎えてくれる。まるで人気作家だな、と私は苦笑した。学生たちの中に、髭を生やした壮年の男性、それに付き添う上品な物腰の夫人がいた。
「彼が有沢さんよ」
「初めまして。有沢です」
私は顔を赤らめながら、頭を下げた。こんな待遇は今までされたことがない。
「土木技術学科の明智です」
と明智龍太郎も頭を下げる。歓迎の挨拶を適当に聞き流しながら、昼飯は何だろう?と、私はテーブルを見た。テーブルクロスの敷かれた食卓には、まだ空のワイングラスや紙皿が並んでいる。まだか、と心の中でちっと舌打ちをした。すみには長靴やサンタクロースのモールのついた小さなクリスマスツリーと、それにならんでCDラジカセも置いてある。
「彼が二階堂部長よ」
有栖が紹介を始めると、二階堂清春の横に推理小説研究会のメンバーが並ぶ。
「あぁどうも、初めまして」
「彼が横溝耕輔君」
「ど、どうも・・・」
がっちりした体格で、無精ひげを生やしているが、目はどこかおどおどしていて、怯えた視線を私に向けている。
「山村みゆきさん」
能面のような細面の顔で、体格もすらりとしている。紹介されてもただ頭を下げるばかりなのだが、存在感はこのメンバーの中でも際立っている。
「島田君」
「初めまして」
スポーツ刈りの男、島田清がぼそぼそと聞き取りにくい声で言った。清という名前とは裏腹でどことなく影がある。
「はい、マイク。ホワイトボード使ってもいいわよ」
有栖からマイクを受け取ると、BGMの音量を男が下げた。
「初めまして」
「あぁどうも、初めまして。今日はどうもありがとうございます」
清春は眼鏡の奥から鋭い目線で私を見た。髪を脱色して、長く伸ばしている男だ。私は少し前に出て、
「皆さん、初めまして。有沢翔治です。本日はクリスマスと推理小説の関係を御話しようと思います・・・」
居間が拍手に包まれる。拍手が終わると、私はカンペを見ながらスピーチを始めたのだった。
FILE3.昼食(十二月二十四日、正午)
「素晴らしい講演だったわよ」
有栖はサラダの皿を運びながら私に言った。せっせと女性達が料理を運んでいる間、私たちは最近読んだ推理小説の話題や、誰それの作家がよかったとかぺちゃくちゃと喋っていた。
「いやいや。あんなのでよかったらいつでもするよ」
と私が言うと、清が、
「どのくらい考えたんですか?」
「一、二時間くらいですね」
「そんな時間であんないいものができるなんて、凄いですね」
耕輔の言葉に私は照れ笑いを浮かべた。
「いやあ、ホームページでエッセイとかを乗っけてるんで、慣れてるんですよ」
「もう、男どもは食べるばっかでちっとも働かないんだから」
みゆきが笑いながら言った。
「まあまあ、そう言うなって。山村。この舞台、セッティングしたの俺らだろ?」
「そんなこと言ったって、ちょっとは手伝ってくれてもいいじゃない?」
そう言いながら有栖はシャンパンの瓶を抱えてテーブルに置いた。
「あとこの一皿よ」
文代がそう言いながら有栖に皿を渡した。何が入っているんだろう、と私はその皿を覗きこんだ。
「今日のメインディッシュ、ローストチキンでございます」
有栖はレストランのシェフよろしく、グイッと胸を反らした。
「上原、それが最後か?」
清春が有栖に確認する。
「へぇ。有栖の本名、上原って言うのか」
「言わなかった?うん、上原」
「うん」
「そう、なら改めて。上原英子って言うの」
お互い顔も知っていて、何度も話した(といってもチャットだが)事があるのに、一番大事な名前を知らないなんて、なんだか奇妙な感じである。私がボンヤリとそんな事を考えていると、
「早く食おうぜ。さっきから腹が減ってしょうがない」
と清春が言うその言い方があまりに悲痛で、教授は笑いながら、
「そうだな」
その台詞に教授はポケットから茶色い小瓶を取り出しながら言った。
「あなた、お水」
「ありがとう」
水をグラスに汲んでテーブルの上に置く。
「何ですか?」
と私が尋ねると、隣に座っていた萌ちゃんが脇腹をつついて
「失礼だよ。そんな事訊いちゃ」、
と私を窘めた。教授は微笑んで、
「いや、いいんですよ。肝臓を悪くしましてね。だから食前と午後三時頃に薬を飲まなきゃいけないんです。だから私だけオレンジジュースなんですよ」
「酒の飲みすぎよ。毎晩日本酒飲んでるんだもの」
文代が付け足すと、教授は面白くなさそうな顔で、オレンジジュースをグッと煽った。
「この歳になると酒だけが生甲斐だよ」
サラダに箸を付けながら言う。
「煙草はお吸いにならないんですか?」
と萌ちゃんがオレンジジュースを飲みながら訊いた。
「先生は喘息持ちで煙草はダメさ」
清がスープを啜りながら言った。私も頷いて、
「あんな毒ガスはやらない方がいいですよ。僕の知合いの刑事が煙草を吸ってるんですけど煙くて、煙くて」
「毒ガスとは厳しいな」
笑いながら耕輔が言う。彼は煙草を喫うのかな?どことなく笑いが引きつっている。ふと目を窓に向けると、さっきよりも雪が勢いを増して降っていた。
「吹雪いてきましたね」
帰れないんじゃないかと思うあまり、私が料理に箸をつけずにいると、みゆきが、
「ラジオを聞いてみますか」
と心配そうな声で言って立ち上がり、CDコンポのラジオをつけた。
「・・・長野県に、大雪警報が発令されました。午後十一時頃を回る頃には三十センチほど積もるでしょう。お車で移動される際は、スタッドレスタイヤ・・・」
予想通りの結果に、私は頭を掻きながら
「参ったな、こりゃ」
「帰れないのか・・・」
清春も呟く。すると教授が、
「どうだ?ここに泊まっていっては。皆もこの大雪で車を運転するのは危ないだろうから」
「でも先生は・・・」
耕輔は心配そうに言った。
「なあに、部屋は五つくらいはある。それに今夜、私は資料を作らなきゃいけないから書斎で寝るよ。皆を招いておいて悪いんだが急な仕事が入ってしまってな」
「書斎?」
「ほら。あそこに見えるのが書斎」
英子は窓の外を指差して言った。小さなロッジのような建物が見える。
「有沢さんと萌さんは兄妹だから相部屋でもいいだろう?」
と、教授が恐ろしい事を言い出した。ここで否定したら明らかに変だ。私は引きつった笑顔で、
「え、ええ、それで構いませんよ」
私はそう言って、思わず萌ちゃんと顔を見合わせたのだった・・・。
FILE4.部屋(十二月二十四日、十三時十分)
「変な気起こしたら殺すからね」「はいはい」
私たちは泊まる事になった部屋の前に立っていた。ドアを開けて中に入ると、そこは六畳ほどの小さな部屋だった。隅には書き物机とタンスが置いてあり、その隣には本棚がある。そして・・・、
「ベッドは一つ、か・・・」
つい萌ちゃんと一緒のベッドで寝るところを想像してしまい、私は顔を真っ赤にした。
「そう・・・みたいね」
萌ちゃんも顔を赤に染めて、こっくりと頷く。
「仕方ないわね」
一緒の布団で寝ましょ。そんな答えをさっきの想像(と言うよりは妄想に近いが)の影響で考えてしまった。
口に出したら間違いなく殺される。
「私が下で寝るわ。ジージョはベッド使っていいよ」
「いや、萌ちゃんがベッド使いなよ」
「うん」
「ありがとう」
彼女は屈託のない笑みを浮かべていった。私も笑顔で、
「どういたしまして」
と答えて、私は窓の方に歩いていった。雪の様子はどうかな?私が窓の外を見つめていると後ろから萌ちゃんも覗き込む。空はどんよりと鉛色で、雪はさっきよりも酷くなっていた。空はどんよりと鉛色で、雪はさっきよりも酷くなっている。あと六時間もすれば車で走れなくなるくらい積もってしまうだろう。
「こりゃあ、二、三日はここから出られそうにないな」
私は苦笑した。
「雪が止めば出られるんじゃないの?」
「そうだといいんだけどね。生憎そうじゃないんだよ。ここは山道でただでさえ事故が起きやすい。雪解け水で濡れた地面ならなおさらだよ」
「つまり雪が止むのに一日、雪解け水が完全になくなるのが一日という訳ね」
「ご名答」
私はため息を一つ吐いた。陰気な空を見上げていると、何だか気が滅入ってくる。振り返ると萌ちゃんが不思議そうな目で私を見つめている。私が微笑むと、萌ちゃんも微笑む。その笑顔を見ているうちに私の気持ちも徐々に明るくなってきた。
とその時、不意に誰かがドアをノックした。
「有栖よ」
扉を開けて上原を招き入れると、萌ちゃんは少し不機嫌そうな顔で、
「どうしたんですか?」
「邪魔しちゃったかな」
上原は萌ちゃんの表情を見て苦笑を浮かべた。
「いやいや。ところで何の用?」
「退屈してるかなあ、と思って。何もないしね。皆で居間に集まってるんだけど、一緒に来ない?」
「どうする?」
私は萌ちゃんに尋ねる。
「うん。私は行きたいけど」
私と萌ちゃんと英子の三人は揃って居間に行くと、屋敷にいる全員が揃っていた。テーブルの上にはコーヒーカップが置かれていて、文代の前には裁縫道具が並び、縫い物をしている。テーブルの真ん中にはクッキーを載せた皿があり、談笑しながらそれを摘んでいる。
「文代、有沢さんにもコーヒーを」
教授が言うと、文代は縫い物の手を休めて腰を上げた。
「はい、どうぞ」
と言ってコーヒーカップを私たちの前に出した。
「どうもありがとうございます」
「ミルクと砂糖はそこですから」
「あ、結構」
萌ちゃんは牛乳パックを取ると、コーヒーに注いだ。しばらく推理小説の話をしていると、清が思い出したように言った。
「トランプ持ってきたんですよ。よかったらやりません?」
「お、用意いいな」
と清春が身を乗り出す。
「先生もどうですか?」
「いや、結構。資料を作らなきゃいけないんでな」
「でもさっきの話だと夜にやるんじゃ・・・」
耕輔が言った。
「そのつもりだったんだが、雪が本降りにならないうちに行く事にするよ」
教授は窓の外で一向に止む気配のない雪を見ながら言う。もし私が彼の立場でも同じことをしていただろう。
「じゃあ、私も布団を持っていくわ。書斎で寝るんでしょ?」
「頼む。あと夜はここで食べることにするよ」
文代は立ち上がって私たちに会釈をすると、居間を出ていった。しばらくして階段を上がる音が聞こえてくる。
私たちはワイワイ騒ぎながら、トランプに興じ始めた。
FILE5.夕食前(十二月二十四日、午後六時)
「もうそろそろ先生を呼んだ方がいいんじゃない?」
みゆきが時計を見ながら言った。紺色の四角い壁掛け時計は六時を指していた。台所からはコトコトという鍋の音やトントンという包丁の音が聞こえてくる。
「私が呼びに行きますから大丈夫ですよ。どうぞゆっくりと休んでて下さい」
そう言いながら、文代が鍋を運びながら台所から出てきた。
「どうもすみません」
文代が鍋を運びながら台所から出てきた。私は頭を掻きながら、 「いえいえ、あと一、二個運ぶだけですから」
「じゃあ、お願いします私、主人を起こして参りますから」
「あ、それなら僕たち起こしてきますよ」
清春がそう言って椅子から立ち上がると、ドアに向かった。部屋から出る前に足を止めて振り返り、耕輔と清が立ち上がらないのを見て、
「ほら、お前らも行くぞ」
「嫌だ。二階堂一人で行けよ」
耕輔が言うと、清春はニヤリと笑みを浮かべた。何か悪戯でもするのかな、と私は彼の笑みを見て思った。
「二階堂さんが行かなくとも私が起こしてきますのに」
申し訳なさそうに文代が言うと、耕輔が、
「いやいや、いいんですよ。何なら奥さんも一緒に行きますか?」
文代の前では流石に清春も悪戯は出来ないと思ったのだろう。
「そうですわね」
と答える文代を見て、耕輔はニヤリと笑って清春を見た。私は、
「僕も行っても構いませんか?」 と言った。皆が手伝っているのに私だけボケッと座っているのは気が引ける。 「ええ、それじゃ一緒に行きましょう」 清春がそう言うと、私は立ち上がって、彼らの後をついていった。
外に出ると開けた野原は一面雪に覆われ、その奥には鬱蒼としたモミの林が広がっている。モミにはまるでクリスマスツリーみたいに雪が覆いかぶさっていた。百メートルくらい先にはロッジのような離れが見える。 「うわぁ、真っ白だ」
「僕、足跡のない雪道って歩くの初めてなんですよ」
雪がこんなに積もるなんて、名古屋ではお目に掛かれない。白い息を吐きながら書斎へ向かった。だが私は十歩も歩かないうちにうんざりしてきたのである。
くそ、居間でみんなを待ってればよかったな・・・。私は心の中で毒づいた。歩くたびに靴の中に雪が入ってきて、足の感覚を奪っていく。だが、やはり文代は慣れた様子で、ドンドン先へと歩いて行ってしまう。
「寒いですね」
私がガタガタ震えながら歩いているのを見て、清春が頷いた。何かボソボソと喋ったみたいだが、唇がかじかんでいるせいか、何を言っているのか分からない。
「大丈夫ですか?」
耕輔が心配そうに言った。私は作り笑いを浮かべて、
「え、ええ、大丈夫です」
と答えたものの、耕輔が苦笑いを浮かべている。どこからどう見たって大丈夫じゃない。それは私が一番よく知っているのだ。
そんな話をしているうちに、私たちは書斎についた。清春は相当お腹が減っているのか、
「早く起こして飯にしようぜ」
と言いながらドアに駆け寄ってノックをすると、
「先生、夕飯ですよ。先生!」 返事が返ってこない。寒さに耐えきれなくなったのか、耕輔が、
「なあ、入ったらどうだ?」
「そうだな」
と言って清春はドアノブを回した。ガチャガチャと何度回しても引っ張ってもドアが開かない。私が横から、
「どうしたんですか?」
と聞くと、
「いや・・・、鍵がかかってるみたいなんです」
「どけよ」
耕輔が清春と交代して、またドアをガチャガチャとやり出した。
「ほんとだ・・・」
と、妙な顔をしている。
「合い鍵を使いましょう」
文代はポケットから鍵を出してドアを開けた。
「あなた、ご飯ですよ」
と言いながら中に入る。書斎は八畳ほどの部屋だった。机の上にはCDコンポや原稿用紙が散らばっている。部屋から漏れてくる音楽を耳にして、ベートーベンか、と私は呟いた。
「まあ、うたた寝なんてしちゃって」
「早く起こして飯にしましょう」
清春が言って教授を起こそうと駆け寄るが、文代はそれを遮るように、
「二階堂さんにそんなことしてもらっちゃ悪いですわ。お客さんですもの」
文代は笑いながら、教授の肩を揺さぶった。
「あなた、ご飯ですよ」
教授はすっかり寝入っているらしく、なかなか起きない。
「あなた」
文代が強く揺さぶると、眠っていたはずの教授がドサッと床に倒れた。次の瞬間、耳をつんざくような悲鳴を上げて、文代がその場にペタンと座り込んだ。
「どいて下さい!」
私は倒れている教授に駆け寄って、手首に手を当てる。三人は緊張した顔で私を見ていた。
「ど、どうですか」
耕輔の顔は真っ青である。私は立ち上がりながらゆっくりと首を振った。
「ダメだ・・・死んでるよ」
FILE6.閉じ込められた九人(十二月二十四日、午後七時)
居間にはまるで葬式のような重苦しい沈黙が流れていた。私は居間で皆の様子を観察した。
清春は何も言わず、ただ震えていたし、耕輔はどうして、どうしてと壊れたテープレコーダーのようにひたすら呟いていた。また清は目を泳がせていたし、文代はまだ信じられないと言いたげな虚ろな目付きをしている。みゆきはきゅっと唇を結びんでおり、一見気丈に見えるが目に涙を浮かべている。英子はうずくまって泣いていた。
「大変だよ」
重苦しい空気をはね飛ばす勢いで、萌ちゃんが居間に駆け込んできた。
「どうだった?」
「今ね、西口警部に連絡を取ったら、大雪でこっちには来られないって・・・」
「そうか・・・仕方ない」
私は収まることを知らない雪を見ながら溜息を吐く。
「どうする?」
萌ちゃんが私の顔を覗き込みながら心配そうに訊いた。
「どうするって・・・、僕たちで何とかするしかないだろ」
それを聞いたみゆきは机をドンと叩いて立ち上がった。皆はその音に驚いた様子で電気にでも撃たれたかのように身体を震わせ、一斉に彼女の方を向いた。
「私反対です!それは警察の仕事でしょう」
私を睨み付ける。すると清春が、
「おい、今、萌さんが言ったろ?警察は来られないって」
「でもいつかは来るんでしょう!?」
「そりゃいつかはな。でも俺たちは雪が止むまでここに閉じ込められてるんだぞ。お前も知ってると思うが日が経つほど捜査は難しくなる」
清春とみゆきの口論に清が口を挟む。耕輔は臆病な性格らしく、じっと物言いたげな目付きで口論の様子を見ていた。
「なあ、それよりさ。俺らの中に犯人がいることにならないか?」
その台詞を聞いて皆の顔に緊張が走った。みゆきはヒステリックに、
「人殺しと一緒にいるなんて冗談じゃないわよ!」 そう言うと、今の扉を乱暴に開けて部屋を出ていってしまった。すると今度は耕輔も立ち上がり、
「俺も山村と同じ意見だ。自分の身は自分で守るよ」
そうは言うが、声は震えているし、おまけに足も震えている。
「お、おい、待てよ!」
清春の声を無視して、耕輔が居間から出ていった
「まったく・・・、皆でいたほうが安全なのに」
英子は呆れ顔で耕輔が部屋まで歩く様子を見送っていた。
「ほっとけ」
清は彼らの様子にはまるで関心がないようである。しばらく気持ちの悪い沈黙が流れる。
「あの・・・文代さん」
手付かずの料理を放心状態で眺めていた文代は私の言葉ではっと我に返る。
「何でしょう?」
「できれば、書斎を見せていただきたいんですが」
「私も行く」
萌ちゃんが目を輝かせながら言った。あまりいい趣味とは言えないが、私自身、こういう事件に出くわすと魚を前にした猫みたいに、目を輝かせてしまう。
注意なんか出来るわけがない。それに萌ちゃんと一緒にいる方が、私も考えをまとめやすい。
「すみませんが軍手を二つ貸していただけますか?」
と言って、私は軍手を二組借りると書斎へまた足を向けた。
FILE7.現場検証(十二月二十四日、午後七時三十分)
「死後まだ一時間と経ってないね」
しばらく教授の死体の上にかがみ込み、触ったりしながら私はそう言った。死体が転がっている部屋には似つかわしくないベートーベンが、まだ流れ続けている。
教授の首筋に目を向けた時、私は赤い斑点を見つけた。
「おや、何だ?」
萌ちゃんも腰を落とし、
「ホクロ・・・かしら」
「さあね」
私は肩を竦めると立ち上がった。腰を軽くトントンと叩いたり、伸びをしたりしながら辺りを見回す。部屋の隅にはオンとオフしかない簡単な作りの電気ストーブがあった。埃が雪みたいにうず高く積もっている。検死が一段落したのを見て、萌ちゃんが、
「死因は何?」
「毒物中毒だね。目立った外傷は見られないことからすると」
「まさかあの肝臓の薬に毒が?」
「いや、薬を飲むのは三時ごろだよ」
「カプセルとかじゃない?」
「いや、それは違う。僕があの薬を見たとき、錠剤だった。いくら何でもカプセルに変わってたら気付くだろう?」
私は机の上に置いてある小瓶を見つめながら言った。小さいラベルが貼ってあり「食前、食後、食間」と書いてある。何か事件を解く鍵になるものは入ってないかな。私はそう思いながら机の引き出しを開けた。
「鍵・・・?」
私は銀色の小さな鍵を見つけた。先には鉄腕アトムのキーホルダーがぶら下がっていて、振ったらチャリンと可愛らしい音がした。どうやらこの中には鈴が入っているようだ。
「この部屋の鍵かしら?」
「さあ?文代さんに訊くことにするよ」
「でも変じゃない?」
「ああ、この部屋には完全に鍵が掛かってたことになる。しかも僕たちがここに来るとき足跡一つ付いていなかった」
「つまりこれは・・・」
「ああ、二重の密室だよ」
「ジージョの検死が間違ってるとかは?」
「いや、それはない」
私は少しむっとして言った。
「あれは死後一時間と経っていない死体だった。暖房を使えばちょっとはずれるけどね」
と言って私は電気ヒーターを指差した。
「でも埃が積もっていたって事は、最近まで使われていなかったわけね」
私は黙って頷いた。そして机の上に置いてあるコンポを開け、中に入っているCDを慎重に取り出す。
コンポはヒーターと違って最新式のものだった。
「なんでこれだけ新しいのかしら」
萌ちゃんが辺りを見回しながら言った。確かにヒーターを始めとするテレビ、ビデオデッキ、冷蔵庫等は皆、旧式である。相当のメカ音痴だったんだな、と私は思った。大体、二十一世紀の世の中に未だ原稿用紙と万年筆で執筆をしている人がこの世にいるなんて。
「大方、古いラジカセが壊れたから新しいの買ったんだろ」
しかしそれは間違いだと解った。机の引き出しから小さなバースディカードが出てきたのである。文代さんから教授へのプレゼントだと書いてある。
「これは文代さんからのプレゼントだったんだ」
私はそう呟いて、慎重にポケットに入れた。
「そんなものが役に立つの?」
「何が役に立つか解らないよ」
私は机の引き出しを一通り開けた。ハサミ、糊、万年筆ケース、インクなどが入っていて、特に珍しいものは見当たらなかった。私はさてと、と呟くとぐるりと辺りを見回した。
そして床にまるで獲物の臭いを嗅ぐ犬のように這いつくばった。しかし埃以外のものは見当たらい。十分くらい床を探した後、
「もう目ぼしいものはないようだね。行こうか」
と言うと、私と萌ちゃんは書斎を後にした。
FILE8.完全なるアリバイ(十二月二十四日、午後八時)
部屋を開けると文代が整えてくれたのか、丁寧にベッドメイキングされていた。私はいつもソファに薄いタオルケットを掛けて寝ているので少し感動する。私はベッドの縁に座り、椅子に座った萌ちゃんに質問した。
「ちょっと紙とペン取ってくれる?」
私なら机の引き出しを開け、ごそごそと探すのだが、他人の引き出しを開けるのは非常識だと思ったらしい。彼女はピンクのハンドバッグから手帳とボールペンを取り出すと、白紙のページを探し、ビリビリと破って私に手渡した。
「ありがとう」
と私は萌ちゃんにペンを構えた。
「仮に犯人が何らかの方法で死亡推定時刻をずらしたとして、明智さんが離れに行くのは何時ぐらいだっけ?」
「二時くらいじゃない?」
私はペンをさらさらと動かした。読者諸君の推理の参考となるかもしれないので、私の書いた図を載せておこう。章末に載せた図をご覧頂きたい。
「その時、皆居間にいたよね?」
「うん、二階堂さんたちはトランプをしてたし、文代さんは縫い物をしてたでしょ?」
「と言うことは全員にアリバイがあるわけだ」
「そういうことになるね」
「ここまではOK?」
「うん」
「じゃあ、今度は何らかのトリックを使って、足跡を付けずに離れまで行ったとしよう。その場合死亡推定時刻は僕の言った六時から七時ごろになるね」
「ええ」
「その時、皆何してた?ほら僕たちが離れへ明智さんを起こしに行った時だよ」
「ちゃんと皆夕ご飯の準備してたよ」
「居間から出た人は?」
萌ちゃんは人差し指を顎にちょんと乗せて考える仕草をした。しばらく考えていたが、やがて、
「トイレに行くぐらいならあったけど・・・十秒かそこらだよ。明智さんを殺せないと思う」
「十秒じゃ萌ちゃんの言う通り、確かに不可能だな」
「って言うか、明智さんが離れに言った時から私たち皆一緒だったじゃない。殺すことは私たちには不可能なんじゃない?」
「じゃ、外部犯だとでも?」
「その可能性のが現実的じゃないかしら?だって全員にアリバイがあるんだから」
「じゃあ、何で密室にしたり足跡を残さず立ち去ったりしたんだい?」
「それは・・・」
萌ちゃんが口籠った。何か言おうと彼女が口を開きかけたとき、ノックの音が聞こえた。上原かな、と私は思った。
「どなたですか?」
萌ちゃんが訊いた。
「文代です」
何だろう、と私は首を傾げながらも私は立ち上がると扉を開けた。英子なら「どうぞ」と言うだけなのだが。
「何ですか?」
私はカフェイン中毒なのでコーヒーが入りました、という文句を期待していた。しかしそれは違い、文代の第一声は、
「私考えましたの」
「何をですか?」
萌ちゃんは尋ねた。
「犯人はもしかしたら外部犯かもしれませんよ」
私はハハハと笑って、
「萌と同じことを言いますね」
「そうなんですか?」
文代が驚いた様子で萌ちゃんを見ると、彼女は恥ずかしそうに笑いを浮かべた。
「今、こいつにも言ったことですが何で密室にしたり足跡を残さないように立ち去ったりしたんですか?」
「でも・・・」
「あなたの言おうとしていることは解ります。全員にアリバイがあるからこの家に集まった人には犯行は無理だ、と言う事でしょう?」
「そうです」
「確かに外部犯なら全員にアリバイがあるという疑問点は解消されます。しかしこの大雪です。生身の人間なら耐え切れないでしょう?」
「でも・・・」
文代は何か言いたそうに私を見たが、やがて
「解りました。失礼します」
気分を害したのだろうか、険しい顔付きで出て行こうとした。私は文代に訊こうと思っていたことがあったのを思い出し、
「あぁそうそう、お尋ねしたいことがあるんですけど」
「何でしょう?」
文代が振り返るのを見て私はポケットから鍵を取り出した。そして私も立ち上がると文代の側に寄り、鍵を彼女に見せた。
「これはどこの鍵ですか?」
「離れですわ。どこで見つけたんですの?」
「いや、どうもありがとうございました」
私は文代の問いに答えず微笑を湛え、そう言うだけにしておいた。そんな私を彼女はきょとんとした顔で見つめていた。
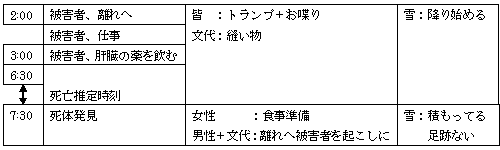 (表1)
(表1)
FILE9.二重密室の謎(十二月二十四日、午後八時三十分)
文代が出て行って、私はベッドの縁に座った。窓の外を見ると相変わらず雪は止まず、しばらくは出られないなと思った。
「でもどうやったのかしら」
私はロダンの考える人のポーズでうーん、と唸った。
「考えられる可能性は二つ」
私は二本の指を出して言った。
「何らかの工作をして死亡推定時刻をずらした場合」
「あの部屋にあったのは・・・」
萌ちゃんが顎に指を当てて言った。
「電気ストーブ、ラジカセ、散らばった書類、本棚、机と椅子・・・それくらいね」
「よく覚えてるね。机の引き出しには鋏、糊、ペンケース、あと重要なのは鍵、カードだね」
「アリバイ工作と密室の問題ね」
「うん、まずアリバイから考えてみようか」
「ええ」
「じゃあ、アリバイ工作に使えそうなものは?」
「ストーブ・・・ぐらいよね?」
私は黙って頷き、
「でもあのストーブは使われてなかった」
「埃が積もってたからね」
「うん」
「じゃ、ストーブを使わないで部屋を暖める方法は?」
数分間、萌ちゃんは考えていたがやがて
「絨毯が敷いてあったらホットカーペットって事も考えれるけど・・・」
「あの床はフローリングだった。ちなみに床暖房説も否定される」
「床が冷たかったからね。でもタイマー式の床暖房って事は?」
「いや、ストーブを点けないで厚着をする倹約家が床暖房にすることはないと思う」
「うん。じゃあ、ジージョの推理通り離れは床暖房じゃなかったとして他にどんなアリバイトリックがあるかしら」
私はしばらく考えていたが一向にいい推理は思い浮かばない。萌ちゃんはいい考えが思い浮かんだかな、と思って私は彼女をちらっと見ると、うーんと唸っている。
「案外、自殺とか」
萌ちゃんは力なく笑って言った。彼女も自分の言った自殺だと言う話を信じていないらしい。
「確かにそれなら全ての謎は解決されるよ。でもコップと毒薬はなかった。」
「コップも毒薬もなしに自殺できないね」
「だから自殺じゃないね」
「ねえ、砒素だとか効くのに時間が掛かる毒だとしたらどう?カプセルはさっき否定したけど」
「うん、それは僕も考えてみた。もし仮に遅効性の毒だとして、何で体の異変を母屋の僕たちに訴えなかったの?砒素なら吐き気や目眩がするし、下痢とかの症状があるんだよ」
「それじゃあジージョはどう見てるの?この事件」
「さあ、解らないけど」
「ふうん」
萌ちゃんの不満そうな声に対し私は言った。
「単純すぎるトリックだから僕たちも気付かないだけかもよ。手品のタネがすごく簡単なのと同じようにね」
FILE10.居間での会話(十二月二十四日、午後九時)
私は萌ちゃんを誘ってコーヒーを飲みに居間に向かった。と言っても喉が乾いた訳ではない。いい考えが浮かばないのでカフェインの刺激が欲しくなったのである。
居間に着いた私は驚いた。部屋に籠ったはずの耕輔が居間にいるのである。清春、清、耕輔、英子が椅子に座っている。清春はぽかんとしている私を見つけると、
「あ、有沢さん」
と言って立ち上がって私に近付いた。
「二階堂さん。何で横溝さんがいるんですか?部屋に閉じこもったはずじゃ・・・」
「さあ、中に」
「は、はあ」
私は何が何だか解らず、清春に言われるままに中に入った。そして私たちも椅子に腰を下ろすと、
「何があったの?」
と英子に囁いたが、含み笑いをするだけで何も答えない。それを見て私はますます訳が解らなくなってしまった。
私は様子を少しでも探ろうと四人の顔を見回した。耕輔はバツの悪そうな笑いを浮かべているし、清は仏頂面で耕輔と目を合わせようとはしない。清春が、
「いや、横溝を説得しに部屋に行ったんですよ」
「ほっときゃいいのに」
面倒臭がりなのだろうか、清がぶつぶつと文句を言っている。皆が気を悪くしていないのかと心配していたのだが、それは私の杞憂らしい。彼らは慣れているらしく、けろりとした表情である。私は興味をそそられ、
「それで?」
「いや、それが傑作なんですよ、なあ」
と言いながら清春は英子にアイコンタクトを送る。彼女は
「ええ」
と含み笑いをしながら言った。
「私が二階堂部長と横溝君の部屋の前でノックしたのね。始めは出ないって片意地張ってたんだけど二階堂部長がね・・・」
「ええ、僕がこいつの部屋からゴキブリのおもちゃを投げ込んだんですよ・・・。これです」
と言いながら清春は悪戯っぽい笑みを浮かべて、ポケットからそれを取り出した。よくできたおもちゃだが蛍光灯の下だったせいもあってか、一目で本物ではないなと解る。ははん、大体話が読めてきたぞ、と心の中で呟いた。
「つまり大騒ぎして出てきたわけですね」
「ええ、こいつの慌てようときたら」
「だって・・・本当に驚いたんだぜ。暗くしてあったし」
不貞腐れたように耕輔は言う。
「お前が悪いんだろ?」
清春が耕輔を睨み付けるように言った。清春は二人の険悪なムードを払おうとしてか、彼は話題を変えた。
「それで有沢さん」
「はい」
「事件の調査はどこまで進んでますか?」
「警察に任せておけよ、二階堂」
面倒そうに言ったのは清だ。
「まあまあ、島田も。それで有沢さん」
「かなり難航してまして・・・」
私は頭を描きながら言った。そしてポケットからメモを取り出し、机の上に置いた。表1をご覧頂きたい。
「この通り全員にアリバイがありましてね」
「成程・・・、しかも足跡一つ付いていなかった。おまけに完全な密室だった」
「そうなんですよ」
「ところで有沢さん。何か用があったんじゃ・・・」
「ああ、そうそう。すっかり忘れていました」
「それで用って何?」
英子が私の顔を覗き込みながら訊いた。アリバイでも何でも訊いて、と言いたそうな目付きだったのでコーヒーをくれ、なんて言いづらい。そこで私はいい考えを思い付いた。
「明智さん、誰からも恨まれてなかった?・・・ああ、それとコーヒーを一杯くれない?」
「そうですね・・・僕は特に思い当たることはありませんけど」
清春は考え込みながら言うと、英子に何かあるかと言いたそうな視線を投げかける。それを受けた彼女は力なく首を振った。
「私もないわ。気さくな先生でとってもいい先生だった」
「俺も見当たりませんよ。まぁ、事務との衝突はあったみたいですけど・・・、それはこの際、無視しても構わないと思います」
耕輔が何に怯えているのか、びくびくして言う。特に収穫はなさそうだ、と思いながら私は一口、コーヒーを飲んだ。
「ふん、よく言うぜ」
清は聞いていて呆れると言いたそうに清春を睨む。
「二階堂、お前は先生に単位落とされたろ?選択ならいいんだけど、あれは必修だったよな」
客である私たちの前からか、平然とした顔つきで座っている。しかし、私は彼の顔が一瞬、曇ったのを見逃さなかった。
「講義といえば横溝にも動機があるよな」
「俺にも?」
「ああ、こないだの講義でお前、赤っ恥かかされてたじゃないか」
「それから上原」
「私?」
清春に指摘され、英子は目を丸くした。本当に思い当たる節などないのだろう。
「忘れたんならいいけど、確かセクハラの疑いの被害者はお前だよな?
それを聞いた文代は、信じていた夫に裏切られたと思ったのか顔を曇らせた。あるいは彼がゴシップを暴く様子に見かねたのかもしれない。
「あれは山ちゃんが勝手に誤解しただけよ。ほら、あの子気が強いし」
山ちゃんとはみゆきのあだ名だろう。
「本当に山村の勘違いならいいんだけどな」
「どう言う意味?」
「深い意味はねえよ」
そう言うと清は意地悪っぽくニタニタと笑った。
「さっきから人の事ばかり言ってますが、そういう島田さんはどうなんですか?」
私はさっきから我慢していた怒りを爆発寸前にしながらも、感情を抑えて尋ねた。
「そうよ、島田君はないの?」
「島田が一番ありそうな気がするけどな、俺は。その捻じ曲がった根性から」
そう言うと清春は島田を鋭く睨みつけた。よく言った、と私は彼に心の底からエールを送った。
「俺は・・・」
清春に睨みつけられた清は、まさに蛇に睨まれた蛙のように竦み上がってしまった。さらに清春は詰め寄る。
「全くない、と言いきれるか?」
その言葉に清は肩を竦める。この性格からして何かあるはずだ。
「どうなの?」
「明智先生、お前の指導共感だったよな?卒論の」
今までの復讐と言わんばかりに清春が意地悪くニタッと笑う。
「そ、それがどうした」
「そん時、何かトラブルでもあったんじゃないのか?」
「な、何もねえよ」
清の目が泳いでいる様子を見て私は何かあったな、と思った。しかし清春たちは清の事を思ってか、深入りする事を避けた。
「文代さん、プライベート面で思い当たるトラブルはなかったですか?」
急に自分に白羽の矢が立ったので驚いてか、一瞬身体を震わせる。
「そうですわねぇ・・・、私は夫が独身時代のことは知りませんけど、特に恨まれてるようなことはなかったかと思います」
「夫婦間のトラブルはなかったんですか?」
私の質問に気分を害したのか、一瞬顔を曇らせた。
「ありません。私にも、一人娘にも愛情を注いでくれました」
「もしあったとしても自分が疑われるようなことは言わないと思いますよ」
清が言うと、文代は興奮のためかさっと顔色を変える。またこいつか・・・
「そんな、誤解ですわ。私、本当に夫と何もありませんでした」
「僕は何も奥さんが先生を殺ったなんて言ってませんよ」
突然のガタンという音に驚いた皆は音のする方を見た。怒りのためだろう、顔を火山のように赤くした清春が立ち上がって肩で息をしている。
「いい加減にしろ!」
流石にこれには清も堪えたらしく、黙りこくってしまった。
「すみません、お恥ずかしいところをお見せしてしまって」
清春は糸の切れた操り人形のようにストンと椅子に座ると、呟くように彼は言った。清は不貞腐れたように床を見つめている。
コーヒーを飲みに来ただけなのに、何でこんな不快な気分にさせられなきゃいけないんだ。これ以上、清の話を聞いていたら腹が立つだけで何のいいこともありゃしない、と判断した私は部屋に引き上げることにした。
「ご協力ありがとうございました。おやすみなさい」
清は廊下の途中まで差し掛かると駆け寄ってきた。何だろう?
「あの・・・有沢さん・・・」
肩で息を切らせながら言った。私は振り向き、皮肉を込めて、
「またゴシップですか?」
「とんでもない!」
「なら何でしょう?」
「僕・・・二階堂たちの前ではああ言ったけど教授を恨んでいました」
やっぱり、と私は心の中で呟いた。萌ちゃんが、
「どうしたんですか?」
「あいつのせいで俺の人生はメチャメチャですよ」
清が吐き捨てるように言うのを聞き、私は静かに、
「どういうことですか?」
「俺の親父は去年、マイホームを買ったんですよ。あいつが監修したってパンフレットに書いてあったから信用したんですが・・・」
彼は涙を堪えているらしく、肩を震わせている。私は、
「欠陥住宅だったと」
「ええ、九月に台風が直撃したでしょう?その時でしたよ。家が吹っ飛びましたよ・・・」
重苦しい沈黙がしばらく流れた。しばらくして、
「原因は壁に使う柱が圧倒的に少なかったみたいです・・・」
清の押し殺したように泣く声が続いた。私は何が解ったか解らなかったが、
「解りました。それで島田さん、あなたが・・・」
彼は勢いよく首を振って、
「違います!俺はやってません」
私は微笑んで、
「解りました。さ、行くぞ」
私はそう言うと奥の自室に歩を進めた。心の中につっかえていたものを吐き出したためか、清はほっと安堵の息を吐いた。
FILE11.夜(十二月二十四日、午後十時)
私はベッドの縁に腰を下ろして、溜息を吐いた。萌ちゃんの洗いたての髪の香りがぷんと漂ってくる。彼女は文代から貸してもらったガウンを身に纏っていた。雪に閉ざされるのは全く予想しなかったことで、着替えなど用意しなかったのも当然である。
私はというと、上から下まで全く昼間とは変わらない服装だった。風呂には入ったが、昼間と同じ服を身に着けているのである。これは何も今日限りではなく、普段の生活でもやっていることだ。
「ええ」
萌ちゃんは欠伸をしながら言った。彼女のとろんとした目やしきりに欠伸をしている様子を見て、
「眠そうだね。早く寝たら?」
「ううん、大丈夫だよ」
彼女はそう言っているが、また欠伸をしたのを見て私は無理しているな、と思った。色々なことがありすぎて疲れたのだろう。
「ごめん、もう眠いから寝るね」
そう言うとベッドに潜り込んだ。なんだ、眠かっただけか。私は少しホッとして立ち上がるとスイッチの前に行った。電気を消すと月明かりだけになる。私はちょっと道化けて、
「トイレに行くとき僕を踏まないようにね」
「うん、解った」
萌ちゃんは眠たそうな声をして言う。
「ねえ・・・ジージョ」
ベッドに入ってしばらく経って萌ちゃんが私を呼んだ。まだ寝ていないのか。
「早く寝たら?眠いんでしょ?」
「うん・・・寝られなくて・・・何か怖くて・・・」
「大丈夫だよ。僕が寝るまで話してあげるから、ね?」
「うん・・・」
怯えているのか、相変わらず萌ちゃんの声は沈んでいる。暗闇だから怖いのかな。私はそう思って、
「電気点けようか?」
「ううん、電気点けたら寝られないでしょ?」
「そう、か」
「ごめんね、心配かけて」
「いや。そんなことはないよ。僕にできることがあったら何でも言って」
「じゃあ・・・」
「じゃあ?」
数秒の間、沈黙が流れた。寝ちゃったのかな、と思っているところへ萌ちゃんのぼそぼそと言う声がした。
「そっちに行って・・・いいかな?」
私は恥ずかしさで顔が真っ赤になるのが解った。私は小さく、
「うん」
と頷くと萌ちゃんが私を踏まないように慎重に降りてくる気配を感じた。部屋は真っ暗闇なので気配でしか彼女の動きを感じ取ることができないのである。
やがて暖かい布団が急に冷えた。萌ちゃんが私の布団に潜り込んできたのである。萌ちゃんと一緒の布団で寝ている。そんな信じられない、夢のような出来事に私の心臓はまるで運動した後のように速く動いていた。
彼女の清潔感溢れる髪の匂いが私の鼻をくすぐる。彼女のもちのような肌の温もりが私に伝わってきた。
「このまま告白しちゃおうかな」
私は呟いたが、萌ちゃんには幸いにも聞こえなかったらしい。眠たそうに、
「え?何?」
「い、いや。何でもない」
そう言いながら、恥ずかしさの余り私は顔を茹蛸よりも真赤にしているのを感じた。
「あ、あのさ」
愛の告白をするぞ、私は自分に言い聞かせた。いつも恥ずかしさの余り話を逸らしてしまうのである。
「実は・・・僕・・・萌ちゃんのことが・・・」
なぜかぼそぼそと呟くようにしか私の声は出ない。
「その・・・す、好きなんだ」
言ったぞ、と心の中で自分自身に拍手喝采をしたい気持ちになった。さて彼女の様子はどうかな、と思って彼女の様子を見る。
「寝ちゃったのか・・・」
私は安らかな顔でスースーと寝息を立てている萌ちゃんを見て、少し肩透かしを食らった気分になった。しかしなぜかほっとした気持ちになった。無防備だな、と私は彼女の幸せそうな寝顔を見てクスッと笑って思った。
「僕も寝よう」
怯えていた彼女が幸せそうな顔をして寝ているのを見て、急に安心した私は一つ欠伸をして呟いた。しかし隣に女の子が、しかも想いを寄せている女の子が寝ているというのに平然と寝られるほど私は無頓着ではない。
「寝れないからしばらく下でコーヒーでも飲もう」
FILE12.ほぐれる糸(十二月二十四日、午後十一時)
皆を起こさないように足音を殺しながら、私は居間に行った。二階堂たちはもう引き上げてしまった後で電気は消え、閑散としている。私は電気のスイッチを手探りで探すと、蛍光灯を点けた。さっきまでは机の上にあったインスタントコーヒーの瓶は紅茶のティーバッグが並んで電子レンジの近くに置いてある。
「誰かが片付けたんだろう」
私はそう呟くとガスコンロの上に無造作に置いてあるヤカンを手に取ると軽くすすぎ、水を入れ、湯を沸かす。
「ええと・・・紅茶がいいな。インスタントは不味くて飲めたもんじゃない。やっぱり豆からじゃないと」
私はコーヒーに関しては少しうるさく、自分で飲むときはいつも電動コーヒーミルで豆から挽いているのだ。紅茶も好きだがコーヒーほどではない。
「お湯が沸くまで事件について考えるか」
私はそう思って椅子に深く腰を下ろした。私はロダンの「考える人」のようなポーズをして考えに耽った。
「犯人はどうやって密室を作り上げたんだ?鍵は間違いなく机の引き出しにあった。もしかしてあの部屋は最初から密室だった?」
ああでもないこうでもないと考えてあぐねているうちにコポコポと沸く音が聞こえた。立ち上がると私は火を止め、手近にあったカップを取った。
「砂糖、砂糖は・・・と」
机の上に置いてあるポットのような金色の砂糖壷を開けてみると空っぽだった。私は砂糖を探し、台所の戸棚を色々と開けてみた。砂糖と書かれた赤い蓋のプラスチック容器を見つけて私はそれを机の上に置いた。紅茶のティーバッグを垂らし、カップにお湯を注ぐ。
「さあ、できたぞ」
私は砂糖を入れ、紅茶に口を付けた。その瞬間、
「何だ、これ!?塩じゃないか」
どうやら誰かが間違って、砂糖壷と塩壷の蓋を間違えてしまったらしい。クリスマスパーティの料理で混乱していたので無理もない。私はもったいないと思いながらも
「こんな紅茶、飲めるか」
と吐き捨てる気持ちで流し台に捨てた。
「そうか・・・これだったんだ・・・」
流れる紅茶を見つめて思わず私は呟く。
「成程ね。解ったよ、全ての謎が」
幕間~読者への挑戦状~
さて私はここで一旦、話を中断しよう。これまでの話で全ての手掛かりを読者諸君はてにしている。つまり私と同じ考え方をすれば、間違いなく犯人を導き出せるのである。謎は再三に渡って触れられているが、
①どうやって密室にしたか
②どうやって足跡を付けず、離れまで行ったか?
③私が割り出した死亡推定時刻に全員のアリバイがあったのはなぜか?
の三つである。さあ賢明なる読者諸君よ。この謎を解けるだろうか?
FILE13.一夜明けて(十二月二十五日、午前七時)
「おはようございます」
朝飯を食べに居間に集まった私は清春たちを見つけて挨拶した。居間では既に文代と英子が朝ごはんを並べている最中だった。
「あ、おはよう。あれ、萌ちゃんは?」
英子が挨拶する。
「おはよう、あいつは二階で着替えてますよ」
と私はみゆきがいないことに気付いて、辺りを見回す。それに気付いた清春は
「山村はまだですよ」
困ったように清春は言うと、清は、
「ほっといたらいいんですよ、あんな奴。腹減ったら降りてくるでしょ」
清春は私が気を悪くしていないかと心配そうに私を見つめる。それに気付いて、
「心配いりません、ありがとうございます」
と彼に微笑を送った。萌ちゃんが伸欠をしながら今にやってくる。
「雪、止んだわね」
清春と同じように思ったのか、英子が話題を変えようとする。
「うん、今日中には帰れそうだね」
私も窓の外を見て言った。昨日の吹雪が嘘のように晴れ渡っている。
「警察がくれば先生を殺した犯人も解るしな」
清春が意地悪そうに言う。これくらいの時間で犯人が解らないなんて有沢という男も大したことないな、とでも思っているのだろう、多少彼は嘲るように私を見る。
「そのことですけど、犯人は解ってますよ」
私は微笑みながら皆に言った。
「本当?」
萌ちゃんが驚いたように私を見た。清は、
「ほう」
と呟くと挑戦的な目で私を見た。
「じゃあ、その犯人は誰なんですか?」
清春が訊く。
「まずそのことを考える前に事件の謎を整理してみましょう。事件の謎は三つ」
「どうやって犯人は離れを密室にしたのか、犯人はどうやって足跡を付けないで離れまで行ったか、そしてなぜ全員にアリバイがあったのかよね」
英子が言ったのを聞き、私は黙って頷いた。
「それではこう考えてはどうでしょう?密室と足跡は偶然であって犯人にとって幸運なことだとしたら」
「どういうことですの?」
台所に立っていた文代が訊いた。
「つまり最初からアリバイを確保することが犯人の目的だったんですよ」
「どういうことですか?」
清が苛立ちをあらわにして言った。
「つまり僕たちが見てる前で犯人は堂々と殺したんですよ」
「そんなこと、できるわけないでしょう」
清が私を馬鹿にしたように言う。私は不敵に微笑して、
「それができるんですよ。針を使えばね」
清春と英子は納得したように頷いたが、清は小馬鹿にするように鼻を鳴らした。
「面白い推理ですが二つ問題がありますね。針を刺すときに先生が暴れたらどうするんですか?それと上手くさせてとしても先生が呻き声を上げたらどうするんですか?」
「そう、そのために犯人は明智さんの肝臓の薬と睡眠薬を入れ替えたんですよ」
「何?」
清春がしかめ面で私を見つめる。
「そして呻き声の問題はベートーベンの強い曲で掻き消される」
「一回きりじゃありませんか。一トラック、精々十二分ですよ」
清が不平そうに言うと、私は微笑して、
「リピート機能ですよ。あのコンポにはリピート機能が付いてます」
「有沢さんの推理を聞いているとどうも私が犯人みたいな言い方ですわね」
文代が微笑みながら口を挟んだが、私は彼女のそれが引き攣っているように見えた。
「ええ」
私は微笑みながら言った。
「犯人は文代さん、あなたですよ」
FILE14.物証(十二月二十五日、午前八時)
「そ、そんな私、や、やってません」
文代は顔色を蒼白にし、唇をわなわなと震わせて言った。身体までガクガクと震えている。そんな様子を見た上原が、
「大丈夫ですか」
と椅子をさっと差し出すと礼を言うのも忘れ倒れこんだ。
「有沢さんのおっしゃる状況証拠であって物証は何もないような気がしますけど」
清は反発するようにきつい口調で言った。清春も控え目だが
「有沢さん、島田に賛成するつもりはありませんが僕も確実な証拠がほしいですね」
「あの死体の首筋には赤い斑点が付いていました。僕は最初ホクロかな、とも思ったんですけど血でした」
「そ、それがどうしたと言うんですの?」
文代はなおも譲ろうとはしない。
「あなたの裁縫道具の針を調べれば血液が付着しているはずです」
「そりゃ付いてるでしょうね。私が針で指を刺したかもしれないですから」
彼女が口を挟んだのを聞いて私は微笑した。
「確かに血液は付いているでしょうね。しかしそれが誰の血液であるかぐらいは鑑識で調べれば解りますよ」
「テレビの刑事ドラマを見てると血液型が精一杯じゃないんですか?」
文代の言葉に私は微笑みを浮かべながら、
「いや、最近の技術は進んでましてね。DNA鑑定をすれば一発で解ってしまいますよ」
顔面はますます蒼白になって死人のように血の気がなくなってしまった。痙攣でも起こしたかのように手足は震え焦点が定まっていない目を私に向ける。
「上原、ブランディーを」
清春が文代の様子を心配して上原にブランディーを持ってこさせた。英子は電子レンジの脇に置いてあったブランディーをコップに注いで出す。しかし文代は飲もうとはしない。
「ちょっと貸して」
英子を押し退けるようにどかすと私はブランディーの入ったコップを無理矢理、文代の口に注ぎ込んだ。それが功を奏してか、文代の顔からは血色が戻った。それを見た私たちはほっと安心する。しばらくして気が付くと、
「有沢さんのおっしゃる通りですわ」
と長い息を吐きながら言った。
「で、でも信じられない。何で?」
耕輔は喘ぐように言ったのを聞き私は微笑を湛えながら言った。
「恐らく突発的な殺意ではないでしょうね」
「何でまた?」
清春が言った。
「これを見てください」
と言って私はバースディカードを渡すと、皆が一斉に見るので清春は困ったような表情を浮かべ次々と手渡した。皆が見終わるのを目で確認してから、
「そのカードは離れの机の引き出しで見つけたものです」
「こんなもんがどうしたって言うんだよ。単なる誕生日カードじゃないか。事件とは何の関係もないじゃん」
島田は言った。
「そうですか?あの部屋にあるものは皆ボタン類の少ない、機械音痴向きの電化製品ばかりだった。僕が文代さんならリピート機能なんかない、できるだけボタンの少ないものを買いますけどね」
「ええ。おっしゃる通りですわ。針で皆さんの見ている前で殺す方法は呻き声が聞こえてはいけません。しかし計画ではあの男が薬を飲んでから私が殺しに行くのに三時間以上の時間が掛かってしまう。そこでどうしたか?リピート機能の付いたコンポをプレゼントしました」
「それからクリスマスと言う日を選んだのも訳がありますね」
「どういうこと?」
英子が言う。
「つまりね、学生に見せて自分のアリバイを確保するということさ。二人きりの状況で殺害したんじゃ疑われるからね」
「ええ、まさか雪が降ってくれた上にあの男が鍵を掛けるなんて幸運でしたわ」
そう言うと文代はぽつりぽつりと語り始めた。
FILE15.動機(十二月二十五日、午前八時)
「有沢さん、あなたにお貸しした部屋は娘のものでしたわ」
文代は言おうかどうか迷っているらしく、一瞬口を閉ざした。やがて意を決したように
「・・・娘は・・・自殺しました」
「自殺ですって?」
私は驚いて思わず訊き返した。文代は娘の死を思い出し、悲しんでいるのか黙って頷く。
「でも先生は何も・・・」
上原も唖然として言う。
「何も言わないでしょうね」
文代は怒りからか、わなわなと肩を震わせている。聞いていいのだろうかとその様子を見た私は思った。
「だって娘はあの男に殺されたようなものですから」
「先生が・・・殺した?」
二階堂は呟くように訊いた。
「ええ。私、前の夫はずいぶんだらしない男でした。十五歳の一人娘を残して失踪してしまったんですから」
別れた夫には未練がないのか何の感情も表さず、さらりと言った。私には別れてよかったと言う気持ちさえ見受けられた。
「あの男に比べれば別れた夫は可愛いもんですわ」
「先生が何か・・・したんですか?」
清春が尋ねた。
「てっきり私を愛してくれてると思ってましたけど、あの男は娘を愛してたんですわ」
「娘さんを愛してるのは普通だと思いますけど・・・」
「萌さん、愛と言っても父親が娘に注ぐ愛じゃありませんわ」
何かまがまがしいものを吐き出すように言った。
「あの男は私にじゃなく、娘に性愛を抱いてましたの」
「それじゃ・・・」
「二階堂さんのご想像してる通りです。私が同窓会で遅くなって帰った時、娘が泣きながら出泣く声が聞こえてきました。私は悪戯でもして起こられてるんだろう、と思いましたわ。でも扉を開けてみて愕然としたと同時に、全てを理解しましたわ」
ここで言葉を区切らせて本当に悲しそうな顔をした。
「だって・・・服が破れて胸がはだけているんですもの。その翌日・・・」
皆が文代と彼女の娘のことを思い沈黙している中、彼女の絞り出すような嗚咽が聞こえていた・・・。