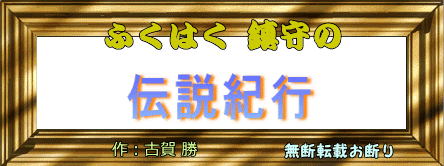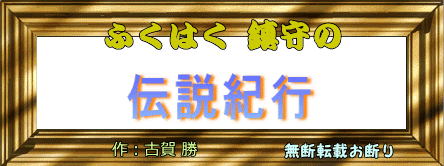|
崇福寺別院由来
福岡県太宰府市
1.gif)
崇福寺別院の遠景
我が儘なお坊さん
太宰府市を流れる白川(御笠川)の上流に由緒正しい崇福寺別院が建っている。周囲を奥深い原始林に囲まれた山寺だ。この寺は、仁治元年(1240年)に、随乗坊堪慧(ずいじょうぼうたんね)なるお坊さんが創建されたのだという。堪慧さんとは誰あろうこの物語の主人公なのである。
時は鎌倉時代の中期ということになる。朝早いお勤めを終えた住職の堪慧(たんね)さん、仏院独特の簡単な朝飯台を前にすると、早速孟宗竹を輪切りにしたコップに水ならぬ酒を満たして一気飲み。お師匠さんの身体のことを心配する一番弟子の珍念が、そっと徳利を自分の後ろに隠した。
「珍念、出かけるぞ」、言うなり立ち上がった堪慧和尚を、「その格好で?」と呼び止める珍念。見ればお師匠さん、寝間着のままで褌(ふんどし)の前垂れを見苦しくぶら下げたままだ。
「いいではないか、こんな山ん中でこんな爺さんの身なりなぞ気にする奴がおるもんか」と、そのまま出て行こうとする。「駄目です、せめて衣なりと身につけないと。正月の里は寒いです。風邪でも引いたらどうします」
1.gif)
天満宮の西側を流れる白川(遠方が豊満山)
弟子に叱られ、仕方なく一応身なりを整えて外に出た。東方の宝満山の尾根から太陽が顔を出したばかりである。眼下に見える白川の向こうには、菅原道真公が眠る天神さまの甍が光っていてまぶしい。天神さまから伸びた陽光は、眼前の朝日山を直射して、冬枯れの落葉樹の下草に暖かさを振る舞っている。
「気持ちがよいのう、珍念」、声を掛けて振り向いたが、ついてきているはずの弟子がいない。一回転して前方を眺めると、道ばたに座り込んでいて、堪慧師匠の追いつくのを待っていた。
「心配をかけるでない」と叱った。そのあと、朝日山の外れを右折しようとする師匠の裾を珍念が慌てて引っ張った。
「駄目です、こちらは」
「どうして?」
「あちらに観世音さんのお堂が見えませんか?」
.gif)
観世音寺の境内
「師匠を馬鹿にするな。こう見えても、耳と目は、若者にだって負けはせん。観世音さんがどうしたと言うのだ」
「本日は、観世音さんの鬼すべの日ですよ。夜の本番に向けて準備の真最中です」
観世音寺の鬼すべ

鬼すべ(イメージ)
太宰府の観世音寺といえば、歴史事はさておいても、九州で一番スケールの大きな寺院である。当時、270㍍四方の寺院を持ち、講堂・金堂・五重塔を中心に七つの伽藍が立ち並ぶ大寺院であったのだから。
「鬼すべ」とは、毎年正月七日に、旧年の厄を追い払い新しい年をすがすがしいものにしようとする行事である。藁や枯れ葉を燃やす炎と煙で、鬼を隠れ家から追い出す燻手(すべて)と、隠れた鬼を守る側の「鬼警護」が、攻防を繰り広げる勇壮な火祭りである。最近ではこの催し、太宰府天満宮には残っているが、観世音寺からはなくなっている。
「鬼すべだからこそ、わしは観世音さんに行きたいのよ」とごねる堪慧和尚。「駄目です」と止める珍念。珍念が止めるには訳がある。鬼すべの準備にかかる世話人の仕事の第一は、「燻手(すべて)」と称する鬼を退治する役が、観世音寺に近づく人間を片っ端から捕らえて鬼に仕立てる。赤鬼・青鬼に化粧して荒縄で作った褌を締めさせ鬼に仕立てるのだ。
一方、お堂に隠れた鬼を守るのが「鬼警護」。藁や松葉を焼いた煙で追い出された鬼を守って燻手と戦う。鬼は、見物人を含めた大勢の善男善女に袋叩きにされる運命に。
そんなことは承知の堪慧和尚なのだ。かまわず観世音寺のお堂に近づいていった。飛んで火に入る夏の虫とはよく言ったもの。待ち構えた燻手に捕らえられ、本堂裏の小屋に連れ込まれた。
「わしは・・・」と、身分を明かして縛り縄を解かせようとするが、燻手に聞く耳などなかった。大勢が堪慧を真っ裸にして青汁を塗りたくり、下半身には荒縄で作った褌を巻き付けられた。「まだ祭りの火入れには間がある故、そこでゆっくりされるがよい」と燻手の一人が言い残すと、全員外へ出て行った。傍では高く積まれた薪が、うるさいほどの音を立てて燃え盛っている。
悟れないままで仏さまに
燃え盛るたき火の脇に佇む堪慧を気にする様子もなく、初老の男が近づいてきた。
「おお、観世音さんじゃありませんか」
声をかけられても、青鬼姿の男など知るわけがない。
「いったいどなたで?」と応じられたら、堪慧が身分を明かす。男が驚いたのなんの。
「新しい年を迎えて、ご住職にご挨拶に上がろうと参りましたらこの始末。丸裸にされておしろいならぬ青粉を塗りたくられ、恥ずかしいやら悔しいやら。まさか、僧侶にまで鬼にされるとは・・・」
堪慧は、観世音寺周辺の寺院の頭領の会の一員だったのである。
.gif)
観世音寺正面
早速世話役が呼ばれて、堪慧の縛りが解かれ、無事釈放となった。
「待っていましたよ、お師匠さま~」。堪慧和尚の姿を見るなり大声で泣き出した珍念。一方迎えられる堪慧はといえば、不機嫌顔がこれ以上はない様子で、珍念に命じた。
「許せぬ、臨済宗大徳寺派を背負って立つこの堪慧を、鬼に仕立てるとは」
少々のことでは、堪慧僧の怒りは収まりそうになかった。
「わしを縛り上げた上に、青鬼に仕立てた奴らを懲らしめるために、これから念仏を唱える。庫裏に戻って穴を掘る道具と、飲み水を入れる桶を持参せよ。急いでだ」
「・・・して、念仏を唱えられる場所は?」
「この朝日山の土手っ腹に穴を開けるのだ」
すさまじい形相に、慌てふためいて庫裏に駆け込む珍念。朝日山に人がようやく入れる横穴を明け、そこに経本と飲み水だけを持ち込んだ堪慧の読経が始まったのは、夜も更ける時刻。丁度その時刻は、すぐ近くの観世音寺で鬼すべの松明に火がつけられた時刻であった。「鬼じゃ、鬼じゃ、あぶり出せ」のかけ声が、鉦や太鼓の音とともに聞こえてくる。穴の外で、和尚の無事を祈る珍念の耳に、読経の声と重なって不思議な音階が両耳たぶをくすぐる。
堪慧の即身成仏

旭地蔵堂
堪慧和尚は、息の続く限り経を唱えて、座ったままの姿勢で息絶えた。世に言う「即身成仏」である。それにしても、悟りの境地にあるはずの僧侶が、どうしてここまで身に降りかかった恥を気にするのか、これもまた凡人には計り知れないことなのかもしれない。
堪慧のご遺体は、崇福寺と観世音寺の丁度中間にあたる白川ほとりの朝日山に葬られた。地蔵菩薩像を添えて。現在旭菩薩像が祀られているその場所が、堪慧和尚がお隠れになった場所なのである。
また、本院になった博多の崇福寺には、これまた立派な地蔵堂が建てられ、やはり地蔵菩薩さまが、気持ちよさそうに立っておられる。(完)
.gif)  - コピー1.gif)
上が太宰府、下が博多の旭地蔵さん
疑問に残るのは、崇福寺が太宰府から博多の千代の松原に移転された理由です。
「物語」の後、天正14年(1586)島津と大友の戦いで崇福寺の伽藍が全焼した。その跡に、大宰府別院として再興された。
慶長5年(1600)に、黒田長政が筑前の国主になり、大徳寺からの要請により復興を計画する。黒田長政、復興する崇福寺が大宰府では福岡城から遠すぎるために、博多に移して最高に着手した。それが今日の横岳山崇福寺の大伽藍である。長政は本院を黒田家の菩提寺として、歴代の藩主が眠ることになったのである。
1.gif)
崇福寺山門
|