|
1.gif)
藍染川の石標
天満宮参道脇の案内所を右折して、浮見堂を過ぎると、間もなく古刹光明寺に。道路脇には小川が流れている。道端に「藍染川」の石標が建てられているからすぐわかる。この小川、伊勢物語や後撰和歌集・謡曲などに取り上げられる物語の舞台にもなったんだそうな。一見何の変哲もない川だが、平安時代から続く古典文学の発祥地だったんだ。
伊勢物語:平安時代の実在した人物在原業平を彷彿させる男を主人公とした短編歌物語集で一代記的物語。
父を慕って
母梅壺は、8歳に成長した息子梅千代に告げた。「遥か九州の筑紫国(つくしのくに)におわすそなたの父に逢いに行こう」と。母子が住む京の都から筑紫まで、170里の山坂を越えなければならない。息子の成長を待っての誘いであった。
梅壺は、侍従の位を持つ女官である。8年前、筑紫から上京してきた中務頼澄(なかつかさよりずみ)に言い寄られて、二人は結ばれた。頼澄は菅原道真を祀る太宰府天満宮の神職だった。退路を断って都を後にした梅壺・梅千代の母子。険しい旅路も愛しい人に会える嬉しさと比べればそれほど難儀なことではなかった。
1.gif)
大宰府光明寺通り
妨害されて
山を越え海を渡っての旅を終えて、母子が筑紫国に着いたのは出発から3か月後であった。天満宮近くの宿で荷解きをした梅壺は、宿の主人に頼澄宛ての文を託した。「貴方のお子とともにやって参りました。宿までお迎えを願います」と。その時、愛する頼澄に妻と子がいようとは夢にも思わぬことであった。
主人に依頼した梅壺の文は、あろうことか頼澄の妻浪江の手に渡ってしまった。浪江は、文のことを夫には内緒にして、母子を京に戻すことを考えた。「貴女がお尋ねの中務頼澄殿は、先年流行り病で他界なさいました。お気の毒ですが、気をつけてお帰り下さいませ」との返事を認めて、宿の主人に手渡した。
「あんまりです。梅千代が可哀そうでたまりません。お上よりいただいた侍従の職まで投げ出してまいりましたのに…」
泣き崩れること数日間。梅壺は、宿の前を流れる藍染川の濁流に身を投げた。
1.gif)
太宰府天満宮
蘇生の祈り
梅千代は、主人の知らせで、母が身を投げた川の畔に駆け付けた。その時梅壺は、天上を向いたままで息絶えていた。「ははさま、ははさま…」、取りすがって泣く息子を、近所の衆が遠巻きにして見つめている。
その時、通りすがりの烏帽子姿の男が声をかけた。
「あっ、頼澄さま…」。宿の主人の大声に、梅千代がはじけるようにして立ち上がった。まさか、目の前の大人が自分の父親であろうとは。顔も姿も知らぬ人でも、名前だけは母から聞いていて、しっかり憶えていたのである。
「知らなんだ、そなたらが筑紫まで来ているなんぞは…」。頼澄は、梅壺の遺体を荷車に乗せると、全力で天満宮の社を目指した。梅千代も、宿の主人に手を引かれて天満神の楠森の中へ。
神職が総動員で、ご祭神の道真公にすがった。「何とか生き返らせてほしい。我が身に替えてでも、どうか梅壺の命だけは助けてくだされ」
飲まず食わずの祈祷が続いた。息子梅千代も、父に従って祈り続けた。知らぬ間に、祈祷には頼澄の妻浪江も、泣き崩れながら加わっていた。三日三晩のお祈りが続いた夜明け方、梅壺の目が開いた。確かに息遣いが聞き取れる。助かった、梅壺が生き返ったのだ」。「道真公のお情けじゃ」。頼澄の喜びの叫びは、天満杜中に響き渡ったのである。
史実においても能舞台や伊勢物語・和歌集でも、梅壺が蘇生した後のことは語られていない。ただ、成長した梅千代が、藍染川の畔に寺を構えたという話はかすかに残っている。
時代が進めば、太宰府周辺の地形まで変わるものなのか。目の前を流れる藍染川は、どう考えても、人が身投げして命をなくすような怖い川ではない。ボクでも飛び越えられるほどの小さな川幅なのだから。
1.gif)
現在の藍染川
|
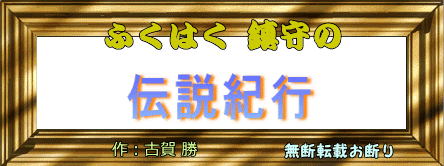
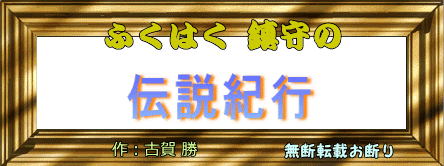
.gif)