| 弾圧の足音

六角の獄跡
馬場文英と比喜多源二が連行されたとの一報は、遠く離れた望東尼の耳にも届いた。2人は、六角の獄舎に入れられているという。
六角獄舎:平安時代に造られた京都の牢獄。1708年に再建されてからは、中京区の神泉苑近くに移転して、六角獄舎又は六角牢などと呼ばれる酔うになった。平野国臣など、本編にも登場する多くの志士たちが投獄され、処刑されている。
「筑前も、無事ではいられませんよ」、と孫の助作が耳打ちした。望東尼自身が尊皇攘夷の志士らを庇い、世話をしてきたことが藩主の耳に届いているはずである。それでも、今日まで何事もなく時間は過ぎてきた。特に、最近家老職に就いた加藤司書の存在が、尊攘派の志士たちを勇気づけている。
これまで、藩庁から睨まれているだろう志士たちは、どの者も国を憂い、正しい道を導き出すために運動してきたと信じている。もし、藩庁から尋問を受けることがあれば、正々堂々と自分らの考えを述べれば済むこと。例え尊攘派に理解を示さない役人も分かってくれるはず。望東尼は、そう信じ、必要以上に怖れることはないと、助作に言って聞かせた。
時代は維新直前の慶応年間(1865年)に入る。福岡藩の尊攘派弾圧の動きは、知らぬ間に、楽観的予測を遙かに超えていた。乙丑の獄を指揮した黒田長溥(くろだながひろ)と言えば、歴代黒田藩主の中でも名君として語られることが多い大名であった。
黒田長溥(くろだながひろ):筑前国福岡藩11代藩主。蘭癖大名と称され、藩校修猷館を再考させた。名君と呼ばれた。

福岡藩11代藩主 黒田長溥
濡れ衣
巷では、尊攘派志士への風あたりがますます強くなっていた。望東尼は、噂を聞く度に、気持ちが落ち込むばかりであった。気晴らしに、曾孫と戯れるために野村本家に出かけた。やがて夏を迎える時期である。
近くの神社でひとしきり曾孫と遊んだ。その時、野村家の手伝さんが玉垣の向こうから駆け込んできた。何事かと問うても、口もとを震わせるばかりで、はっきりしたことを言わない。とりあえず、幼子を手伝いさんに預けて家に戻った。
帰るなり、本家の嫁から一通の書状を見せられた。それは本家を継いでいる助作に対する藩庁からの召し文(呼出状)であった。内容は「戒めがある故出頭せよ」とある。座敷に入ると、助作が既に身支度を済ませて望東尼を待っていた。召し文に書かれている「戒め」の意味が分からないと、助作はぼやいている。助作は、実家の浦野吉之助と連れだって出かけていった。
山荘での句集の編纂が気になるが、ここは当主の祖母として野村家を護らなければならない。親類の者が続々集まってくる中、落ち着かない気持ちを悟られまいと気遣いながら、望東尼は助作の帰りを待つことにした。
この日の出来事が、所謂乙丑の獄(いっちゅうのごく)と呼ばれる、福岡藩における大弾圧の始まりであった。
野村家に集まった者らが待っていると、夜中になって吉之助一人が戻ってきた。右手に藩庁から渡された仰せ文を握っている。誰に対する文なのか、見てびっくり。対象は、助作ではなく望東尼だった。
「疑いの義あり。次なる沙汰があるまで、親族の家で謹慎するように」とのこと。その間、身内の者がしっかり見張るようにとのお達しであった。仰天する望東尼は、このときの心境を日記「夢かぞえ」に書き記している。

頭を丸め、仏の世界に入った我が身に、思いもよらぬ濡れ衣をかけられようとは。それも、我が頼りにする福岡藩からである。とても、畏まって承服できることではない。怒りは心頭に達した。それから助作を待つ時間の長かったこと。たったの半日が、1年にも感じられたものである。
東の空が白みかける時刻、助作が戻ってきた。助作は、祖母への謹慎言い渡しを知らされていないらしく、まずは自らの今後について語った。自身にも謹慎を言い渡されたというのである。助作は現役の藩士であるため、見張りも公の守人がつくと言う。
「謹慎を受けるのは、そなたと私だけではなかろう」
祖母の問いには答えず、助作はそのまま寝間に入っていった。
喜多岡勇平暗殺さる
野村家の一族郎党が集って、藩庁から下された件を話し合っている最中、表でただならぬ物音がした。何事かと訝っていると、隣屋敷に住む喜多岡勇平の妻が駆け込んできた。顔から血の気が失せている。入ってくるなり、「旦那さまが何者かに殺されました」と告げた。
ただならぬ出来事に、集まった一同も息をのみ、身体を寄せ合って震えている。家人に出された井戸水を一気に飲み干すと、喜多岡の妻は話し始めた。
「押し入ってきたのは、武士らしい男が3人で、顔を布で覆っていました。土足で上がり込むなり、現れた娘に斬りつけたのでございます。何事かと顔を出した夫に、鞘を払う間もなく一刀両断でした」と言う。
妻は、恐ろしさで涙も出ない有様であった。集まった野村家の誰一人、場を離れようとする者はいなかった。
自宅謹慎
夜が明けて、藩庁からの申し渡し通りに、望東尼は嫁入り前の浦野家に移動させられた。維新まで3年に迫った慶応元年(1865)年8月15日である。
1.gif)
望東尼実家の赤坂3丁目付近
久しぶりの実家なのだが、懐かしさや両親への思い出など感傷も湧いてこない。実家の浦野吉之助が、望東尼の見張り役となり、複雑な面持ちで向き合った。吉之助は、姉タネの息子である。
「嫌疑がかかる者を、甥っこに見晴らせるとは、情けないことだね。だって、私に何かあったら、身内の者のせいにするって言うことでしょう」
望東尼は、藩庁への恨み節を吐き出した。
福岡藩から厳しい「戒め」を受けるのは、名前を挙げるだけでも、半端な人数ではない。
月形洗蔵、筑紫衛、鷹取養巴、森安平、万代安之丞、江上栄之進、伊能茂次郎、海津亦八、伊丹真一郎、今中作兵衛、真藤善八、尾崎逸蔵ら
みんな我が子のように庇ったり、助けてきた若者たちばかりである。 望東尼と助作を加えて総勢14名に上った。その他にも、側筒・足軽を含めると39名が「戒め」を受けることになった。
悲しいことに、望東尼を頼って和歌の弟子入りをし、平尾山荘の管理を引き受けている瀬口三兵衛まで連れて行かれたという。三兵衛は、今朝も、山荘に咲く草花を切って届けてくれたばかりである。
「どうして?なぜなの?」
自分の周囲にいた人たちが、ことごとくしょっ引かれていくことで、望東尼の頭は真っ白になり、ただ座敷に額を付けて呻くばかりだった。(つづく)
|
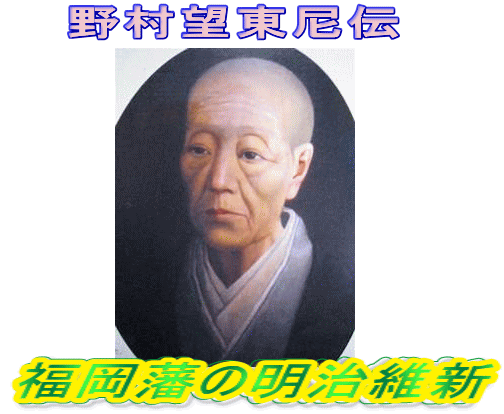
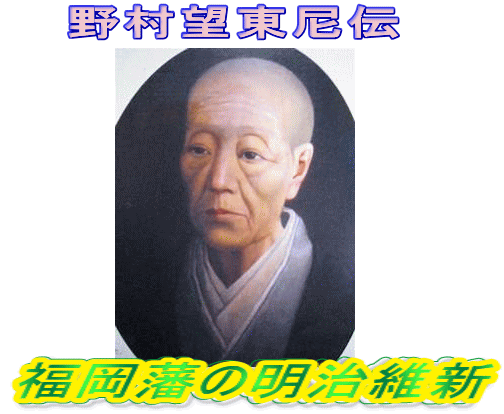
![]()


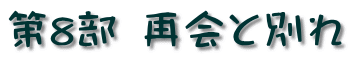
 桜坂の近影
桜坂の近影![]()