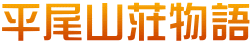

2024/03/17
11.gif) 
復元された平尾山荘&野村望東尼像
福岡市内に定住して40年。恥ずかしながら、すぐ近くに保存されている貴重な「文化遺産」を見過ごしてきました。福岡市中央区平尾5丁目に建つ平尾山荘のことです。倒幕派と佐幕派が激突した江戸末期、ここ平尾山荘も重要な舞台となっていたのでした。
山荘の住人だった野村望東尼(のむらぼうとうに・旧姓野村モト)は、大田垣蓮月・中山三屋と並ぶ江戸時代を代表する女流歌人です。特に、野村望東尼と中山三屋は、勤王女流歌人として討幕運動にも貢献した人物として有名でした。
改めて平尾山荘とその周辺を歩きました。復元された山荘は、西鉄平尾駅と動・植物園で賑わう南公園の丁度中間地点にあたります。山荘の周辺でまず気がつくことは、坂道だらけの高級住宅街であること。一カ所たりとも、平らな道が見当たりません。
主人公・望東尼が過ごした頃の平尾村は、古木に覆われた丘陵地帯であり、山を伐り拓いた典型的な農村地帯だったようです。手元の資料で調べると、当時の村の戸数は150戸、人口643人、田53町歩、畠17町余とあります。
明治維新から遡ること十数年前、そんなのんびりした丘陵地帯に、藁葺き屋根の一軒家が建ちました。家の広さは、6畳・3畳・2畳の3間で、厨房と土間を合わせても10坪に満たないほどです。家の周りには雑木が密集していて、外からではそこに誰が住んでいるか伺うことは出来ません。そこが、野村望東尼が住処とした平尾山荘なのです。
ボクはこれまで、身近に隠れている歴史的人物や伝説・民話を掘り起こすことに頑張ってきました。この度は、望東尼の勤王女流歌人としての生き方を、彼女が歩いた足跡を辿ることによって深掘りして参ろうと思います。
最初からお読みいただくには、 第1部 仏門に入る へお進みください。ご意見・ご感想をお待ちします。


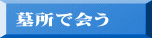
.gif)
高杉晋作墓所
高杉の死後、望東尼の心は虚ろのままで、ただぼんやりの日が過ぎていった。楫取素彦が手配してくれた手伝いの娘・トキとの世間話が、唯一の安らぎの時間にもなっていた。
「谷梅(高杉)さんが逝って、もう10日経ったね。待っていなさるだろうね、わたしの来るのを。早く行かなきゃ」
虚ろな目で庭を眺めながら呟いた。そばにいるトキが反応した。
「出かけましょうよ、お供しますから」
高杉が眠る吉田村(現下関市大字吉田)まで北へ6里、男の足でも5時間はかかる。若いトキの体力を頼りに、朝早く出立して長府の茶店で昼ご飯をいただいた。宿泊先は、吉田村の庄屋宅。これも、楫取の手回しである。庄屋の家に着いたのは、陽も完全に沈んだ時刻であった。
翌朝、庄屋に案内されて、高杉の墓前に額づいた。
「やっとお会いできましたよ。貴方がいなくなって、本当に寂しゅうございます」
そばにいる庄屋にもトキにも悟られないように、俯いたままで10日ぶりの再会を告げた。事前の心配とは逆に、不思議と涙は出てこなかった。
墓標と敷地は、山県有朋が高杉の愛妾・うのに贈ったものである。「東行」の墓名は、高杉晋作の号名。
※山県有朋:明治・大正時代の軍人・政治家。長州藩士出身。吉田松陰に学び、奇兵隊幹部として活躍。
高杉晋作亡き後、途方に暮れる望東尼を支えたのは楫取(かとり)素彦・ヒサ夫妻であった。楫取とは、太宰府での初対面以来、姫島脱出後も何かにつけて世話になった。病床にあった高杉が、難を逃れて長州に来た望東尼の面倒を楫取に託していたのであった。
高杉の四十九日法要も過ぎた頃、望東尼のもとにその楫取がやってきた。楫取は、居を山口に移すよう促した。「ここなら、妻のヒサも十分にお世話ができる」からとも言ってくれた。山口における滞在先は、湯田温泉郷にある吉田屋であった。吉田屋は、この地にあって由緒ある家柄である。身に余る厚遇であると、改めて高杉に感謝するのであった。 吉田屋に落ち着いて間もなく、今度は藩主敬親(たかちか)の遣いが現れた。正装である。遣いは、十三代藩主からだと、一服の反物を差し出した。姫島の牢獄から一転して、藩主からの下賜を授かるとは、想像すらしなかった栄誉であると望東尼は感謝した。

鼓の滝
湯田の郷を出て、西へ1里も歩くと鼓の滝に行き着く。名前の通り、飛沫を跳ね上げながら落ちるさまは、鼓に合わせて踊る龍のごときである。心行くまで自然の美を楽しみながら、歌人としてこの上ない贅沢な時を過ごした。
わすられぬ心づくしのなかりせば湯田のたゆたに物を思はじ
この歌は、身に余る藩主からの恵みを受けて、湯田の里に落ち着いた気持ちを詠んだものである。

心に落ち着きを取り戻すと、すぐに平尾山荘と若き同士たちのことを思い出す。特に孫の助作のことが心配でならなかった。だが願いも空しく、助作は城下に造られた枡木屋の獄中で帰らぬ人になったと知らされた。助作の獄中生活は2年近くに及んだと言う。
浮雲はまだ晴れやらぬ身なれども露の心は世には残さず
助作の辞世の句である。嫌疑が晴れないままの身ではあるが、少しも心をこの世には残すまいと詠んでいる。助作に続いて実姉のタカも没したと知らせが届いた。続けさまの故郷での不幸を聞いても、駆けつけられないこの身が恨めしい。
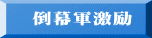
その間にも、世の中は激動の最中であった。倒幕派雄藩と幕府存続を唱える藩が、日本列島を二分したまま、睨み合いが収束しそうにない。270年もの間続いた德川の世である、これも当然の成り行きなのかも知れない。
慶応3(1867)年9月19日、大政奉還の大号令まで残り3ヶ月。江戸時代最後の時節であった。野村望東尼は62歳になっている。
坂本龍馬らの仲介もあって、薩摩と長州藩が手を結び、倒幕のための密議が熱を帯びていた。討議に加わったのは薩摩側が大久保利通や西郷隆盛であり、高杉亡き後の長州からは桂小五郎らであった。その密議では、倒幕のための出兵に関する合意がなされた。薩摩藩兵は、9月25日までに三田尻の港に到着し、長州軍と合流する。その後は東上して、幕府の主要人物が集まる大坂城に攻め入る算段であった。長州藩はお隣の安芸藩にも働きかけ、薩長芸の三藩連合軍の出兵という予定もできあがりつつあった。
※薩長同盟:1866年に薩摩と長州両藩が結んだ同盟。両藩は1863年8月18日の政変以来反目していたが、第2次長州征伐の頃から、大久保利通・西郷隆盛ら討幕派が藩論を動かした。土佐藩の坂本龍馬らの仲介により、長州藩の木戸孝充らと折衝して同盟が成立した。
9月23日。望東尼は、三田尻港に向かう長州兵を見送るべく、湯田郷から山口に出た。山口は、倒幕を目指す若者が進む道である。彼らに接していると、かつて平尾山荘に出入りしていた福岡の若者の姿と重なる。もう少し自身が若ければ…、自分が病弱でなければ…、それより何より、この身が男であったなら。「間違いなく、このような部隊に身を置いていたであろうに。そして幕府を、この手で打ち負かす一翼を担っていたろうに」と、声を震わせながら彼らを励ました。

湯田郷に戻った望東尼を、内儀風女性が待っていた。楫取素彦夫人のヒサである。初対面である。彼女は高杉晋作や桂小五郎などが学んだ吉田松陰の実妹であった。
「早くお訪ねするようにと、主人から言われていたのですが…」

楫取素彦夫人ヒサ
遠慮深そうに挨拶する姿は、いかにも楫取素彦の夫人に似つかわしいと感じる。
「私も、三田尻におられる荒瀬百合子先生に習って、少しばかりですが…」 和歌を勉強中であると、ヒサは自己紹介した。
「荒瀬先生も、望東尼先生にお会いしたいとおっしゃっていました」
三田尻は、長州軍が薩摩軍と合流する予定の港町である。長州軍の参謀には、ヒサの夫である楫取素彦が任じられているとも聞かされていた。
望東尼は、出来ることなら自分も三田尻まで出かけて、若い兵士らを激励したいと思っている。三田尻に着いたら、防府の天満宮に額づいて、若者らの戦勝を祈願するつもりであった。心を込めて詠んだ和歌を、信仰する天神さま(菅原道真)に捧げて祈願したかったのである。
「きっと、荒瀬先生も喜ばれますわ。早速使いを出して、その旨伝えておきます」
近々再会することを約束して、ヒサは吉田屋を後にした。
9月25日早朝。望東尼は、藤 四郎にも告げず萩往還に向かった。藤四郎に言えば、「ご自身の歳をいくつだとお思いか」、「病み上がりだということをお忘れか」ときつく叱られるに違いない。自身、年齢や病弱のことを気にしていないわけではない。それよりも、杖一本を頼りの一人旅では、心細くないわけがない。それでも、湯田郷で倒幕の吉報を待つだけでは、その方が耐えがたかった。「もしも私が若かったら…、男だったら…」の気持ちがそうさせるのである。
往還に出て鰐石橋を渡る頃には陽も昇り、川底から吹き上げてくる風が冷たかった。萩往還は、日本海側の萩城を起点として、瀬戸内海の三田尻まで、ほぼ直線的に結ばれている。この道は、大名行列だけではなく、一般庶民にとっても、「陰陽連絡道」として重要な役割を果たしてきた。

往還を行き交う人々も、商人風であったり武士であったり、百姓や遊び人風まで様々である。一里塚や茶店などもそれなりに整備されていて、老女の一人歩きでもさほど心配ではなかった。吉田屋を出て3里ほど歩いて、景勝地の鳴滝に着いた。そこで疲れをとっている間も、日暮れが気になる。途中いくつかの峠道を越えるときなど、足が重くて道ばたに座り込むこともしばしば。夕刻が迫っての、勝坂峠の上りはさすがに堪えた。座り込んでいるところを、通りがかりの百姓の荷車に乗せてもらった。
百姓と別れた後は、また一人旅になる。ここで座り込んでいては、天満宮まで行き着くことなどおぼつかない。気持ちを高めて、また歩き出した。茶をすすりたいが、次の茶店がなかなか近づかない。そんな時は道端を流れる小川の水がありがたかった。老体を心配してくれて、道中の話し相手をしてくれる娘に手を取ってもらうこともあった。
11.gif)
車中から勝坂峠付近
次の峠道にさしかかったとき、追い越してくる屈強な男に「大丈夫かい」と声をかけられた。
「松崎の天神さま(防府天満宮)まであとどのくらい?」。力ない声で尋ねると、「3里ほどかな」。男は、「もとは侍だったが、今は浪人」だと断りながら、手を引いてくれた。
「あんたはお坊さんらしいが、その言葉だと地のもんじゃないね」と、男が問うた。
「筑前の博多の出ですよ。生業は和歌を詠む歌人ですがね。見ての通り仏に仕える身ながら、なかなか俗世とも縁が切れなくて…」
そんな会話も長くは続かず、分かれ道が来たら男は別の方に走り去った。再び一人旅に戻ると、両の足が絡まって先に進まなくなった。泣きたくなって座り込むと、なぜか福岡城下の平尾山荘が瞼の裏に浮かぶ。助作亡き後、野村本家は取り潰しになったのだろうか。早く帰って、私がなんとかしなければ」と、気持ちが空回りする。考えることは、兄弟喧嘩や塾の師に叱られたことなど、遠い昔の出来事ばかり。目の前がぼやけて、膝から崩れかかったところまでは覚えている。
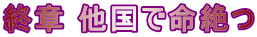

「気がつかれましたか?」
優しい女の声で目が覚めた。だが、声をかけた人が誰だか見当がつかない。
「荒瀬百合子です。楫取(かとり)さまからお知らせを受けて、お迎えに上がりました」
「ここは…」
「松崎の天神(防府天満宮)さまですよ」
3日前だったか、楫取素彦夫人のヒサが湯田の吉田屋を訪ねてきた際、防府天満宮にお参りする旨を伝えておいた。その後、荒瀬百合子女史の自宅を訪ねるとも。楫取夫人が早速、連絡してくれたのだろう。
起き上がった望東尼は、挨拶を済ますとすぐ拝殿に向かった。吉田屋を出る際、心に決めていた「七日詣で」の初日分を実行するためである。
本日9月25日より7日間、欠かさず天神さまに「戦勝祈願」を行い、和歌を一首ずつ奉納することを決めていた。神前に深々と頭を垂れた後、道中詠んで書き留めておいた句を神官に差し出した。
もののふのあだにかつ坂かけつつもいのるねぎごと受させたまえ
朱に染められた本殿は、太宰府や京都の北野天満宮とはひと味趣を異にしている。拝殿に上がると、今にも目前に天神さま(菅原道真)が現れそう。本殿から見下ろす向こうには、町のシンボルである桑山(くわのやま)が居座っていた。更にその向こうに広がる海が、三田尻の港であろう。
1.gif)
防府天満宮
望東尼は、荒瀬百合子が手配した駕籠に乗り、半里先の荒瀬宅に向かった。百合子の夫は商人だったが、先に亡くなっている。残された夫人は現在58歳。現在歌人として活躍中であった。
百合子は、望東尼に不自由なく過ごしてもらえるよう、離れの間を提供した。望東尼は、疲れをとる間もなく、翌朝から天満宮通いを始めた。境内の手水鉢で身を清めた後、拝殿に上がり精神を統一して二日目の和歌を詠んだ。
薩摩船を待つ 薩長盟約によれば、薩摩兵を乗せた船は、9月25日か26日までに三田尻の港に到着する予定である。だが、いくら港を望んでも、それらしき船影は現れなかった。荒瀬家の離れで知らせを待つ気持ちも落ち着かなかった。
山口の湯田温泉から遙々三田尻までやってきたのに、激励すべき長州兵が、いつ戦場に赴くのか見当もつかない。望東尼は、案内役として若くて力持ちの使用人友三を付けてもらった。桑山(標高107㍍)登りを手伝ってもらうためである。

桑野山山頂
「あちらに見えるのが三田尻の港で、その向こう側が中之関です」
「それで、佐賀関は?九州と四国の間の…」
友三の指先を頼りに、視界を巡らせていく。港の向こうが向島。いくつかの小島を飛ばして、その向こうにかすかに四国の佐多岬が見える。目を細めて眺めたが、薩摩兵を乗せた軍船らしいものは見当たらなかった。
「やっぱり駄目だね」 深いため息をつくが、薩長盟約のことなど知らされていない友三には、彼女の気持ちを察することは出来ない。
ちぎりおきて帆かげも見えぬ薩摩舟またうき波や立ちかえるらむ
9月28日、楫取素彦が荒瀬宅にやってきた。彼は、三田尻に居を移して、薩摩兵の到着を待っているのだと言う。
「遅いですね、薩摩のお方たち」
出迎えた望東尼が呟くと、楫取は「そんなこともあるさ」と、焦っている風にも見えない。「八月十八日の変」以来、長州藩内に漂う「薩摩不審」が、頭をもたげたのかも知れない。訪問者は、和歌の詠みあいなどした後帰って行った。
それから6日経った午後、友三が駆け込んできた。
「薩摩の船が中之関に入ったらしいです」と。
慌てて身支度を済ますと、再び荷車に乗せられて桑山山頂へ。 「あれが、待ちに待った薩摩船ですか」
桑山の頂上から眼下に見える船を見て、足下が不安定になるほどに気が抜けた。見下ろした向こうに見える船には、薩摩兵が400人乗っていた。それから三日後には、更に859人の藩兵が到着したと知らされた。

望東尼は、桑山山頂より薩摩軍船の姿を見届けたあと荒瀬宅に戻ってきた。いかに友三の助けがあっても、62という年齢からくる体力には限界がある。床につくと、間もなく始まる新しい世への期待も薄れてしまい眠りこけた。
「どうしましたか、嬉しいはずなのに」
百合子とヒサが部屋に入ってきて声をかけた。眠っているわけでもないのに、すぐには返事ができない。
みよひらくたよりや菊の花ならんあきつむしさへゆたにやどれり
天皇の御代が始まるという知らせを聞くのは、菊の花であろうか、あきつむし(とんぼ)さえゆったりと止っている。
客人の異常を感じ取った百合子は、受け取った歌の清書をヒサに頼んだ。 「頑張ってくださいよ、貴女が命をかけて戦い取ろうとする新しい世が、すぐそこまで来ているのですから」
百合子は、叱るような口調で望東尼を抱き起こした。
間もなく長州藩主から、反物と菓子の見舞い品が届いた。追いかけるように、藩主が指名した開業医師3人が、交代で枕元に付き添うようになった。 「まだまだ、そんなに早くは逝きませんから…」
この期に及んで、望東尼は強がりを忘れていなかった。

望東尼が体調を崩して寝込んでいるその瞬間も、世界はすさまじい勢いで動いた。まさしく地殻変動である。
時は慶応3(1867)年10月の半ば。王政復古の大号令まで、残すところ3ヶ月。長州藩主父子に下されていた官位剥奪が、天皇の名のもとに取り消された。
※官位剥奪:「八月十八日の変」以後、朝廷から長州藩主に下された処罰のこと。
藩主父子の官位が復活した10月13日、将軍德川慶喜は京都の二条城にあって、上洛中の諸大名らに大政奉還についての意見を訊いた。そして翌日には、朝廷に対して大政奉還の上表を提出した。
世の動きは、年でもなければ月でもない。日・時刻単位で急変していくのである。薩摩と土佐藩が盟約を結んだ後、土佐藩主の山内豊信(容堂)が、大政奉還の建白書を幕府に提出した。間を置かずして10月15日には、朝廷は幕府からの大政奉還上表を受理する。ここに、権力機構としての江戸幕府の使命は、実質的に終了する。
望東尼が、死に際まで気をもんでいた「倒幕」と「天皇による治世」の実現は、黄泉の世界に旅立つわずか10日前に実現したのでああった。
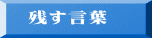
望東尼は、息を引き取る寸前まで、和歌を詠むことにこだわった。次が、人生最期の歌である。
冬籠り怺えこらえてひとときに花咲きみてる春は来るらし
冬籠もりをして、こらえにこらえていた花が一斉に咲き満ちる春の到来です。=防府野村望東尼会=解釈 望東尼辞世の句碑(防府市桑山)
息せき切って駆けつけた藤 四郎の手を握り締めて、望東尼は声を絞り出すようにして訴えた。
「死ぬ間際に、四郎に言い残したいことがあります」
そこまで言って、喉が詰まり咳き込んでしまった。それでも藤 四郎は、辛抱強く次なる言葉を待った。
「私が死んだら、三田尻の桑山の麓に埋めておくれ。これは、お世話になった長州への、せめてもの私の気持ちです」
望東尼は、生前博多の妙光寺に自分の墓を建てている。妙光寺は、野村家の菩提寺であり、夫貞貫が死んだ折、そばに置いてくれるよう住職に頼んで建てた生前墓であった。
「私は、お世話になった高杉さまや長州の皆さま方に、そのご恩を忘れませんから」と言いたかったのだろう。
「それから…もう一つ。叶うものなら、死ぬ前に一度、海の向こう(九州)のお国に戻りたかった。あの平尾山荘の畳の上で死にたかった。喧しいほどの小鳥たちの鳴き声を聞きながら…。これだけは、かつて福岡の地で過ごした四郎にだけ言い残しておきたかったことです」
そこでまた、望東尼の声が止った。 「ハハウエには、もうしばらく生きていて欲しいです。貴女の願った夜明けは、すぐそこまで来ているのですから」
小刻みに震える望東尼の手を握り締めながら、藤 四郎が呟いた。そこにヒサが入ってきて、話は途切れた。二人だけの会話は、福岡藩で育った者にしか通じない情感であったろう。地獄のような筑前姫島から救い出され、長州に来てからは、一挙に天国に昇ったような待遇をいただいた。こちらの皆さまに、これ以上の贅沢を言える立場などあろうはずもない。それでも本音は、死ぬときくらい、生まれ故郷で、身内の者たちに囲まれていたかった。それが偽りのない気持ちでもあった。
「必ず、必ず、私が馬関海峡(関門海峡)の向こうまでお連れしますから。その間、あまり遠くへ行かないで、待っていてください」
藤 四郎は、向かい側に座っている荒瀬百合子と楫取ヒサに気づかれないよう、俯いたままで望東尼に話しかけた。
荒瀬百合子と楫取ヒサの献身的看護もあって、望東尼の容態は奇跡的に快復するかに見えた。が、すぐに危篤に陥る。その繰り返しが幾度も続いた。そして、周囲の者の問いかけにも反応しなくなる。慶応3(1867)年11月6日夜の五つ半(午後9時頃)。つきっきりの医者が首を横に2度振った。望東尼は永遠の眠りについたのである。享年62歳。
王政復古の大号令まで、一ヶ月を残すばかりであった。
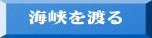
望東尼の死後7日経って(11月13日)、薩摩藩主・島津忠義は、西郷隆盛以下3000人の藩兵を従えてお国を出立した。4日後の17日には、三田尻港に着岸して、先着の軍兵と合流する。11月23日に、錦の御旗をおっ立てて京都に入ったのである。
薩長同盟成立を仲立ちした坂本龍馬と中岡慎太郎が、京都河原町の料理屋で暗殺されたのは、その少し以前であった(慶応3年11月15日)。
一方長州藩の軍兵は、1200人を乗せて三田尻港を出港した。その後、西宮に留まって陣を構えた。その他の軍兵は、次の司令を待つべく尾道で待機した。続いて安芸藩も、11月28日には300人の軍兵が京都に入っている。
運命の12月9日。十五代将軍德川慶喜が、朝廷に対して政権を返上する歴史的な日になった。御前会議を開いて王政復古の大号令を発布したのである。ここに、江戸幕府の消滅と明治維新新政の第一段階が始まった。それは、望東尼が死去した1ヶ月後のことであった。
幕府による政権返上のその内容とは…
幕府・将軍職の辞職 京都守護職の廃止 摂生・関白の廃止 新たに、総裁・議定・参与の設置 というものであった。
望東尼は、浄土への道すがら、どのあたりでこの「大号令」を聞かされたのであろうか。そしてもう一つ。心から気にしていた、三条実美以下七卿は。慶応3(1868)年12月27日に、すべての罪が許されて、太宰府を発って京都に帰還したのであった。
1.gif)
野村望東尼の墓
天下国家が大きく変動する中、望東尼の葬儀は、桑山麓の正福寺(禅寺)で執り行われた。故人に付けられた法号は、「始本院向陵望東大姉」。棺は多くの長州藩士や関係者に見守られて、桑山々麓へと向かった。遺言通り火葬にはせず、桑山の麓に埋められた。すべて行事は長州藩の仕切りで進み、費用も長州藩主の毛利家が負担したとのこと。
その後、桑山大楽寺境内に、「正五位野村望東尼之墓」と刻した華々しい墓碑が建てられた。死去した後も、高杉の危機を救ってくれた恩を忘れない、長州人の心意気であった。
時は更に進んで、明治20年代の中頃。歳の頃なら五十代の男が、徳山からの連絡船に乗り込んだ。船は穏やかな関門海峡を門司港に向かっている。心地よい風を受けているのは、望東尼の最期を看取った藤
四郎であった。
息を引き取る間際に交わした、「必ず、馬関海峡(関門海峡)の向こうまでお連れしますから」の約束を果たすべく、ふるさと筑前への旅である。既に故人となった高杉晋作や、維新後群馬県知事となって大活躍中の楫取素彦などに、少しなりとも恩返しをと務めてきた年月であった。
顔を上げると、前方に門司の港が見えてきた。 「さあ、ハハウエが待ち望んだ九州の港に着きますよ」と、手元の小箱に話しかけながら立ち上がった。白布に包まれた箱の中には、桑山々麓の土と辞世の句が納められている。

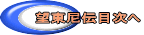

|
11.gif)


.gif)


11.gif)
1.gif)

1.gif)
