|

福岡市内に定住して40年。お粗末ながら、すぐ近くに保存されている貴重な「文化遺産」を見過ごしてきました。福岡市中央区平尾5丁目に建つ平尾山荘のことです。倒幕派と佐幕派が激突した江戸末期、ここ平尾山荘も重要な舞台となっていたのです。
平尾山荘の住人野村望東尼(のむらぼうとうに)(旧姓野村モト)は、大田垣蓮月・中山三屋と並ぶ江戸時代を代表する女流歌人でした。特に、野村望東尼と中山三屋は、勤王女流歌人として討幕運動に貢献した人物です。
執筆にあたり、改めて平尾山荘とその周辺を探索しました。復元された山荘は、西鉄電車の平尾駅と動・植物園で賑わう南公園の丁度中間地点にあたります。山荘の周辺でまず気がつくのは、坂道だらけの住宅街であることです。江戸時代まで城下に隣接した里山からなる農村でしたから、当然のことではあります。
望東尼が過ごした頃の平尾村を、手元の郷土史で紐解いてみます。当時の戸数は150戸、人口643人、田53町歩、畠17町余とあります。
そんなのんびりした丘陵地帯に、江戸末期藁葺きの一軒家が建ちました。家の広さは、6畳・3畳・2畳の3間で、厨房と土間を合わせても10坪に満たないほどです。家の周りには雑木が生い茂っていて、外から中を伺うことは出来ません。それが、野村望東尼の平尾山荘だったのです。
身近に隠れている歴史や民話を探し求めてきた筆者として、彼女の女流歌人としての生き様を深掘りしたくなりました。
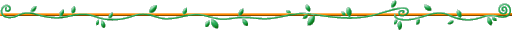


望東尼の前半生を、少しだけ振り返っておきたい。結婚する前の名前は浦野モト。文化3年(1806年)、300石とりの福岡藩士浦野重右衛門勝幸の三女として生を受けた。
産声を上げた場所は、福岡城の南門にあたる追廻橋(おいまわしばし)を出てすぐ近くの、南谷赤坂御厨後(おうまやのうしろ)である。今日の住所に置き換えれば、中央区赤坂3丁目で護国神社の東側一帯を指す。
近所には、御馬方や鷹匠など200石から500石取りの中級武士が多く住んでいた。モトの父親も御馬方に組み入れられていたようである。
.gif)
望東尼生誕の地(福岡市赤坂)
モトは生まれるとすぐから、父親が決めた道を進むことになった。幼くして習いごとや行儀見習いに追われ、17歳で20歳上の藩士と結婚させられることになる。だが、年齢の離れ過ぎた夫婦生活はうまくいかず、半年後には嫁入り先を出て実家に戻ってきた。
その後のモトは、幼い頃から習っていた和歌詠みに没頭することに。近所の仲良しと通う二川塾(ふたがわじゅく)は、その後の歌人としての人生を形成する大きな踏み台になった。
モトの2度目の結婚は、24歳を過ぎてからだった。双方とも再婚である。相手はやはり福岡藩士で、413石とりの野村新三郎貞貫(のむらしんざぶろうさだつら)。歳の差は11で、石高は実父や前夫よりかなり格上である。
モトが再婚を決意したきっかけは、野村貞貫が同じ和歌を教える二川相近(ふたかわすけちか)塾の熟生であったことだった。
モトの姓が、浦野から野村へと変わった。嫁いだ先は、城下の林毛橋袂にあった。現在の国体道路沿いである。後妻として嫁いだ先には、先妻の男の子が3人いた。長男は貞則、次男は貞一、三男は雄之助である。モトは、後妻として生きていくために、義理の子らに心遣いを惜しまなかった。時を経て、世の習いとして次男と三男は他家へ養子に出され、長男の貞則だけが野村家に残って嫁をもらうことになる。
夫貞貫は生来身体が弱く、その上藩内での出世争いを得意としない優しい性格の持ち主であった。結婚後15年が経過して、貞貫は成長した長男の貞則に早々と家督を譲り、隠棲することにした。藩士仲間から紹介された城下平尾村の土地を手に入れ、そこを晩年の住処と決めたのである。新しく建てる家は、野村家から半里(2㌔)ほど南方の丘陵地帯であった。
「ここなら、何かと気を使う武家屋敷からも離れられるゆえ、気持ちも落ち着くだろう。それに、子供や孫に会いたければ、気軽に行き来できる近さだし」
モトにも言い返したいことはあったが、黙って従うことになった。
「わしも、モトに負けないように、大隈先生のもとで和歌づくりに励みたい」
平尾山荘に家移りしてしばらく経って、貞貫が言い出した。「大隈先生」とは、望東尼の和歌の師匠である大隈言道(おおくまことみち)のこと。引っ越しが済むと、早速夫婦揃って今泉(現警固神社近く)に居を構える大隈言道の塾に通うようになった。その頃に望東尼が詠んだ句が残っている。
音もなき寛の水のしたたりもたりあまりたる谷の一つ家
師の大隈言道は、彼女の才能を見込んで歌集をつくるよう誘った。その後は、夫婦して大隈言道(おおくまことみち)の指導を受けながらの、「歌集向陵集」の編集に励んだ。「向陵」とは、彼女が住む丘陵地帯の風景から名付けたもの。

平尾村に転居してから10年が経つと、夫の身体が痩せ細っていった。医者に診てもらったが、はっきりしたことを言ってくれない。いよいよ、最悪の時がきた。夫は、山荘に駆けつけた長男の貞則や孫の助作などが、傍についていることさえわからなくなっていた。
貞貫が息を引き取ったのは、安政6(1859)年7月28日の早朝であった。夫が残していった子供や孫たちの行く末を、すべて後妻の自分が見なければならないことを考えると心配でならなかった。僧侶の読経の間、微笑んでいるようにさえ見える夫が恨めしくもあった。そのとき浮かんだ感情を詠んだ句である。
うち群れて庵(いお)はいづれど君ひとり帰らぬ旅となるぞ悲しき
貞貫、享年65歳であった。遺体は長男貞則が住む林毛町の本宅に運ばれた。山荘に一人取り残されたモトは、ありったけの声をあげて泣いた。山荘が雑木と畑で囲まれているため、誰一人彼女の叫びを気にかけるものはいなかった。
12.gif)
野村家墓所、左:望東尼生前墓
貞貫の初七日が過ぎて、モトは野村家の菩提寺である呉服町の明光寺(現在は吉塚に移転している)を訪ねた。住職に得度(出家すること)を願い出た。住職は、仏門に入る心得を承知することを条件に承知した。
「そなたの名はモトであったな」
住職は、一枚の和紙にモトに与える法名を書いた。「招月望東禅尼(しょうげつぼうとうぜんに)が、これからの名前である」
この世に生を受けて以来、慣れ親しんできた「モト」の名と決別するときであった。
「ご住職さま、もう一つお願いがございます」
モトは頂いた自分の名前にたじろぎながら、次なる願いを申し出た。
「野村家の墓の隣りにもう一つ、私の墓を建てることをお許しくださいませ」
聞いて驚いたのは、住職である。
「この墓は、亡くなられたお方が眠る場所ぞ。現にそなたはそこに生きておるではないか。ご遺体と同居できるわけはなかろう」
「わかっております」
生きている自分の墓を、夫のそばに建てると言う。「生前墓」のことである。「生前墓」なら、長生きを果たすためのおまじないとして、仏も許されるであろう。間もなくして、望東尼は夫が眠る墓の脇に小さな墓を建て、墓石には「望東尼墓」の碑銘を彫った。墓室には、住職に剃り落として貰った自らの頭髪を納めた。夫の遺骨さえ思うようにならない後妻の辛さである。新しい自分の墓の建立は、家族や一族に対するせめてもの意地であったのかもしれない。
庭の池で泳ぐ鯉にうつろな目を向けて、モトの目頭は濡れたままであった。これから残された人生を、女一人でどのようにして過ごせばよいのか。

師匠大隈言道に勧められて始めた歌集「向陵集」の編纂も、なかなか先に進まない。こんな折には、なによりも師匠からの叱咤激励が必要なのだが、その人は大坂に去っていて福岡にはいない。今でも師匠に会いたいと、胸が締め付けられる。
そんな折、林毛町の自宅から孫の助作が訪ねてきた。助作は長男貞則の継嗣(長男)で21歳。元服もとおに済ませていて、月代(さかやき)の青さがなんとも初々しい。
「おばば上、何をしているのですか」と近づいてくる。わざと知らぬふりをしていると、「ぼんやりしていると、池に落ちて鯉にかじられますよ」と孫が大きな声で注意した。縁側に座り直すと、助作もぬくもりが伝わる隣に座り込んだ。
「おばば上は、元気で歌を詠んでいるかと、みんな心配しております」
助作は、林毛町の実家との連絡役を担っているようだ。そこに瀬口三兵衛がやって来て会話に加わった。三兵衛は助作より7歳年上で、よき遊び相手であった。勤めの傍ら、山荘にきては望東尼に和歌づくりを習っている。お城の内情や城下のことなど、事細かに情報を伝えてくれるのも三兵衛であった。
望東尼は、丸めたばかりの自分の頭を撫でながら、助作と三兵衛の会話を嬉しそうに聞き入った。山荘にやって来る若き藩士は、三兵衛に限らず望東尼のことを「ハハウエ」と呼ぶ。
「おハハウエ、江戸では大変な騒ぎが続いておるそうですよ。長州の吉田松陰先生が、江戸伝馬町の獄舎で打ち首になられたとか。最近では、幕府の大老さま(井伊直弼)が、江戸城の桜田門を出られたところで襲われたそうです」(桜田門外の変)。
「それは大変だ。天皇さまや公卿さまたちが、無事であればよいが」
近い将来幕府による取り締まりが我が身に迫ることになろうとは、このとき考えも及ばないことであった。
夫貞貫が亡くなって2年が経過した。毎日やってくる瀬口三兵衛から、藩の事情や藩主の仕事ぶりなどを聞くのが唯一の山荘外との繋がりにもなっていた。
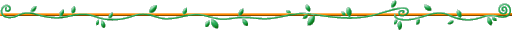



夫貞貫がこの世を去って2年が経過した。文久元年(1861年)の秋も深まった時期である。山荘での一人暮らしも、なかなか慣れないでいる。人恋しさが増すばかりであった。
諦めきれない望東尼は、師の大隈言道に会えないのなら、こちらから出向いていこうと決意した。頭を丸めて初めての遠出である。野村家の当主となった貞則は猛反対した。義母の年齢は既に57歳に達している。60歳といえば、完全に老人の域に入る時代である。上方までの遠出を、義理とはいえ息子として見ぬふりなどできるわけがない。それでも、望東尼は上方への道行きを譲らなかった。
この決断が、後の彼女の人生を決定づけることになる。
.gif)
現在の関門海峡
望東尼にとって、生まれて初めての上方までの旅であった。それでも、一人旅の心細さは少なかった。長旅が独りぼっちではないし、大坂には、野村家の縁者が多く住んでいると聞いている。厳封されたとはいえ、家禄は300石の武家である。縁故も少なからず手繰ることが出来るはず。野村望東尼が上方に向かって出立した文久元(1861)年11月は、やがて来る江戸幕府の終焉まで6年を残す時代であった。親類や知人に見送られて野村家を発つとき、望東尼は、後ろを振り向かなかった。
旅をともにしてくれるのは、大隈言道の高弟子・野坂常興と、所用で上方に向かう親類筋の藩士高谷弥太夫であった。出立する時期、「安政の大獄」と呼ばれる幕府による苛烈な弾圧が始まった時とも重なっている。薄々聞こえてくる江戸での騒動も、望東尼の足を止める枷(かせ)にはならなかった。
.gif)
金比羅宮参道
望東尼の旅が始まった。一緒する野坂と高谷は結構気が合うらしく、終始賑やかな旅となった。福岡からは唐津街道を徒歩で行く。門司で渡し船に乗り、馬関(ばかん)(関門)海峡を渡って下関へ。下関を出航したのが12月1日朝であった。
途中、3人は気ままに船を降りながら名所旧跡に足を踏み入れた。これも望東尼の当初からの目当てであった。多度津港を降りて金比羅宮に詣でる。その日は参道沿いの大きな旅館に泊まり、船上での不安定な寝床からしばし解放されることに。
兵庫に着く頃、船上から赤穂城を望みながら、かつての赤穂浪士を偲んだ。6日目も上陸して、楠木正成の墓地を訪ねた。この墓には志士らが多数参拝していると聞いたことがある。後に望東尼に関係する人物だけあげても、三条実美・西郷隆盛・高杉晋作・平野国臣らである。
大坂港に入ると、安治川を遡り中之島で下船した。7日間の船旅はここで終わった。

中之島で船を降りた望東尼らは、福岡藩の御用商人を努める津嶋屋藤蔵邸で草鞋を脱いだ。翌日は、高谷と二人で今橋に住む大隈言道の住まいを尋ねた。二人とも、師との再会は4年ぶりである。
「よう来たな、高谷君もモト君も。ご主人が亡くなられて、モト君もさぞ辛かったろう」

大阪中之島玉江橋の賑わい
大隈は、夫婦ともに和歌の弟子であった望東尼に、貞貫の悔みを伝えた。改めて再会を喜ぶ間もなく、大隈は望東尼を連れだした。途中船場あたりを通る際、忙しそうにすれ違う人の多さに酔ってしまいそうになる。
連れて行かれたところは、大坂で四大呉服商の一人と言われる商人の屋敷であった。主人も大隈言道に和歌を習う弟子だと知らされた。屋敷内の庭や造りは贅を尽くしたものばかり。これまでに見たこともない置物が誇らしげに飾ってある。食事が出たあとには、雅な舞踊が囃子の調べが座敷を華やかにする。時の経つのを忘れる思いであった。
次の日に大隈が連れ出したのは、鼈甲屋の邸宅であった。剪定された黒松を配した庭園を散策したあとには、今宵も宴会が待っていた。接待する豪商の妻は大名の奥方気取りであり、調子を合わせるのに苦労した。それにしても、大隈言道の顔の広さには、舌を巻くばかりである。
大隈言道に紹介される中には、福岡藩の大坂蔵屋敷に勤める者も多かった。全国から大坂に集う各藩は、堂島川・土佐堀川・江戸堀川の岸辺に大坂蔵屋敷を有している。蔵屋敷とは、各藩内で得た収穫物を、売り捌くまでの間所蔵する施設のことである。これらを中之島の取引所で売りに出し、藩の財にする。現在、その福岡藩蔵屋敷の建物が、四天王寺の美術館敷地内に保存されている。
望東尼は、宿泊所を津嶋屋から本町の旅籠に移した。望東尼は、大隈とともに大文字屋の大坂支店を訪ねた。店には主人の比喜多五三郎が待っていた。
「ようおいでなさったな。わては京都の商売人だすが、たまたま大坂に来てましてな。あんさんにお会いでけて、ほんまに嬉しいわ」
遠い九州から出て来た博多の女流歌人を迎える五三郎、上機嫌この上ない面持ちである。そろそろお暇しようと、大隈が目配せしたときだった。五三郎が膝を乗り出した。
「わて、あした京に帰るさかい、ご一緒しまへんか」と誘った。
「それはよかですな。モトさん。いや、望東尼さんでしたな。せっかく大坂まで来たんやから、ゆっくりみやこ見物でもしてきたらよろしい」
誘った五三郎より、大隈の方が熱心である。
「もっと、言道先生の傍にいたいから・・・」とも言えず、望東尼は京都行きを承知することにした。
「ほな、準備もありますやろから、ここらで・・・」
五三郎も、京都までの道中が楽しみだと言って送り出した。

望東尼は、大坂を離れるのが辛かった。大坂というより、4年ぶりに会った師匠の言道と別れるのが切なかったのである。
翌朝、比喜多五三郎一行は、淀川を遡る三十石船(さんじゅっこくせん)に乗りこんだ。夕刻には京都の伏見港に着く上り船である。発着場に言道の使いの少年が現れた。師からの手紙を手渡すとすぐに走り去った。どうして、ご本人が来てくれないの。言道のつれなさに、心に重いものを感じずにはいられなかった。このときの心境である。

※三十石船:江戸時代、淀川の京都―大坂間を往復する30石積みの川船。28人乗りの乗合船で、上りは岸からの曳き船、下りは流れを利用していた。
上流に向かって滑り出した三十石船上では、五三郎が左右を指さしながら得意げに名所旧跡を案内した。途中石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)を通過するときには、五三郎の声がますます大きくなった。淀川は、石清水八幡宮あたりで大きく三つに分岐する。奈良に向かう木津川と嵐山への桂川、そして彼女らが向かう伏見方面への宇治川である。
伏見の船着き場は、その宇治川の途中に設けられていた。(現在は京阪本線中書島駅付近の公園あたり)
比喜多五三郎の邸宅は、上立売(かみだちうり)(現上京区上立売町)の十文字屋本店と隣り合わせに建っていた。伏見から上立売まで、距離にして3里余りである。陽が落ちているせいもあって、どこをどう進んだのか見当もつかなかった。
「御所はすぐそこです。反対方向に歩くと間もなく金閣寺…」
主人一行を出迎えた番頭が、客人の望東尼に説明した。上京翌日、大文字屋からの知らせを受けて、福岡藩京屋敷(別名筑前黒田屋敷)に勤める吉松言正がやってきた。大文字屋は、福岡藩御用達にふさわしく、藩京屋敷の目と鼻の先に暖簾を張っていた。
※京屋敷:全国に散らばる藩が、藩主の参勤交代の際の宿泊所にしたり、江戸と国元の連絡の場合の中継所として、京都に設けていた施設。
望東尼が生来尊敬してきたのは、天皇と藩主である。そのせいもあって、京都名所を案内すると言う吉松に、淀みなく御所まで連れて行ってくれるよう頼んだ。大文字屋を出ると、すぐ今出川通である。番頭が言うように、京都御所は目と鼻の先にあった。

京都御所
この塀の向こうには、大君(天皇)や公卿さまなど、雲の上の方々が大勢お住まいになっておられる。そう考えるだけで、身震いするほどの感動を覚えた。遙か彼方まで続く玉砂利を踏みしめながら、手入れされた黒松の列を伝うようにして進んだ。
ふるさとを出立して1ヶ月経った大晦日である。夜中になると、八方から除夜の鐘がもの悲しく伝わってくる。望東尼にとって、運命的な文久2年(1862)の夜明けであった。彼女にとっても57歳の新春であった。
せっかくの京都滞在である。この機会に、一カ所でも多くの名所を巡り、和歌つくりの糧にしなければと思う。まさしく田舎者の物見遊山であった。
元日の早朝、今では散歩コースにもなっている御所の前に出た。この日案内するのは五三郎夫妻であった。途中往来する鳥帽子姿の従者の仕草を観察して、興奮を抑えきれないでいる。1月3日は下鴨神社に足を向けた。この日からの案内役は手代の馬場文英に替わった。4日は上賀茂神社へ。5日には福岡藩の手回しで、特別に御所の内部に入ることを許された。老舗呉服屋の持つ人脈が活きたのだと思った。
御所内では、新年を祝う千秋万歳(せんずまんざい)や猿楽(さるがく)などが華やかに催されていた。子供の頃からの願望であったみやこの貴人との触れ合いが現実となったのである。
※千秋万歳:中世期に存在した民俗芸能。大道芸の一種である。
※猿楽:古くは「さるごう」とも呼ばれた、能と狂言で構成される能楽の一種。

京都に到着以来、寸暇を惜しんでみやこ見物をしているうち、体力との相談を怠っていた。もともと強い方ではなかったから、一度上がった熱はなかなか元に戻らない。
そんな折、気を遣ってくれるのが京屋敷(福岡藩邸)の藪幸三郎夫妻であった。出入りの激しい商家では身体も休まるまいと、自分の屋敷に移るよう誘った。言葉に甘えて藪家に転居したのは、御所の梅が咲き始めた頃であった。
ようやく体調も回復した4月15日。望東尼は十文字屋五三郎に誘われて伏見に出かけた。福岡藩主の黒田(くろだ)長溥(ながひろ)が、参勤交代の途中京都に立ち寄ると聞きつけたからである。五三郎が望東尼を連れ出したのは、この際藩主に対して、福岡藩士野村貞一(長男)の義母である女流歌人を藩主に引き合わせる魂胆であった。
「大坂から上ってきたときは、陽が落ちていて暗かったさかい。周囲がよう見えんじゃったから」
言われて眺めれば、宇治川から引き込まれた人工河川の周囲が華やかである。遊郭群であった。
「ここは酒造りの本場じゃ。酒のあるところには男の遊び場が寄ってくるというからね」
現在の京阪電鉄・中書島(ちゅうしょじま)駅近くの川港である。
「あの看板は?」
望東尼が目を向けた先の建物には「船宿」の提灯が下がっている。
「寺田屋という宿屋どす。聞くところによると、薩摩とか長州のお侍さんたちが、毎晩のようにお泊まりだそうな」
京都に着いてはまだまだ世間知らずの望東尼である。それだけの説明では、この時代の政争の奥深さなどわかりようがない。世に知られる「寺田屋事件」は、望東尼が訪れたその日から8日後に起こっている。
※寺田屋事件:幕末、京都伏見の船宿寺田屋で、尊攘派志士の薩摩藩士らを薩摩藩主が殺傷した事件。
福岡藩主・黒田長溥の行列は、いくら待っても姿を見せなかった。
周囲にいた役人に様子を聞いた。返事は、一行が播州大蔵谷で不穏な動きを察知したため、行列を西へ引き返えさせたとのこと。この事件を、歴史家は「大蔵谷回駕(おおくらだにかいが)」と呼んでいる。
やむなく上立売の屋敷に引き返した五三郎は、藪幸三郎にことの成り行きを調べてもらった。わかったことは、「不穏な動き」の中心人物が、福岡藩士の平野国臣(ひらのくにおみ)だということ。当然望東尼は、平野という人物を知らない。だが、大蔵谷回駕事件は、比較的平穏に過ごしてきた福岡藩を、「明治維新の隠れた主役」に押し上げることになるのである。
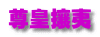
望東尼の京都見物は、滞在期間が半年になってもなお続いた。4月には上賀茂・下鴨神社で執り行われる葵祭へ。大人気(おとなげ)もなく、見物客の先頭に出てしまうほどに興奮した。馬場は望東尼を嵐山や奈良・吉野方面など、遠方へも進んで案内した。
※葵祭:京都の三大祭り(葵祭・時代祭・祇園祭)の一つで、上賀茂・下鴨神社の例祭。日本最古の祭りと言われる。
まもなく4月も終わろうとする頃、望東尼は公家の千種有文を訪ねた。千種には、編纂中の歌集に序文を書いてもらうつもりであった。千種有文といえば、孝明天皇の妹和宮を徳川家茂に嫁がせる、所謂公武合体論に熱心な公家である。望東尼が尋ねた4ヶ月後には、千種有文は閉居の身となっていた。公武合体論を敵視する一派に、退けられたのである。結局、依頼した序文は、望東尼の許に届くことはなかった。
望東尼は、嵐山見物の帰り道、頭から離れないことを馬場文英にぶっつけた。
「どうして、薩摩のお殿さまは身内のご家来衆までお斬りになったのでしょう?(寺田屋事件)」「千種有文さまが、糾弾されたわけは?」
みやこ見物で心が浮つきがちだった望東尼が、目の前で見せつけられた「事件」の意味を理解したかったからである。馬場文英は、望東尼からの問いに、しばし目を閉じて考え込んだ。次に見開いた目は、みやこ案内時のにこやかさが一変していた。人を刺すようにギラギラ光る眼が、彼女の表情をも固まらせたのである。
「貴女が考えているほど、今の世の中は平穏ではありませんよ」
「どういうことなの?平穏じゃないって」
望東尼もつい大きな声で聞き直した。
「いつ京都で戦いが始まるかわからないということです。これ即ち、幕府の力が日に日に落ちてきて、公武合体論が力を増してきたからです」
※公武合体論:幕末、公家(朝廷)と武家(幕府)が提携して、政局を安定させようとする主張。
馬場は、昨今の都の政情をこと細かに話し始めた。
「もう一つ、お尋ねしてもよろしいか?」
「どうぞ」
「先日大文字屋のご主人と伏見までご一緒した際、黒田のお殿さまを乗せた駕籠が上洛できなかった本当の理由(わけ)を教えてください。回駕の原因となったとされる平野国臣という御仁はいったい…」
「どういう人物か知りたいのですね。皆さんの先頭に立って尊皇攘夷論を世の中に広げている福岡藩のお方です。黒田のお殿さまも、行列を妨害した者が誰か、薄々はわかってらっしゃったはずです。しかし藩内には、尊皇攘夷派のお方もたくさんおられるし…」
馬場が彼女に伝えた大蔵谷回駕の顛末は、おおよそ次のようなものであった。
望東尼らが伏見で待った4月15日の2日前、福岡藩主の黒田長溥を乗せた行列が、播州大蔵谷宿に到着した。そのとき本陣に2人の男が現れて藩主への面会を申し出た。応対した者が面会を断ると、男は「京都滞在中の島津久光公からの書状でござる」と言って懐から取り出した紙包みを手渡すと、すぐに立ち去った。
あとで書状を確かめた藩主が驚いた。薩摩の島津久光からとは真っ赤な偽りであり、黒田長溥当ての「平野国臣」名義の建白書であった。
内容は、「我ら尊皇攘夷派の同士とともに、倒幕の戦いにご賛同いただきたい」というものであった。
黒田長溥は、平野国臣からの書状を見て驚き、急ぎ参勤の方向を福岡に逆転させた。これが、後の世まで伝わる「大蔵谷回駕」と呼ばれる事件のあらすじである。
「それで、平野さまはどうなされたのですか、その後」
「帰国途中、福岡藩の役人に捕まったそうです。それ以上は私にもわかりません」
公武合体論を振りかざす一部の公家や武士と、270年の間武家社会を死守してきた佐幕派との対立は、抜き差しならぬ所まで進んでいると馬場文英は言う。
「それでも、この国には天朝さま(天皇)がおいでです。かけがえのない崇拝すべき…」
「わたしの考えも、貴女と同じです。武士の世がどう変わろうと、天朝さまの立場は変わってはいけないのです」
それならば、公武合体を持論とする千種有文さまの立場はどうなるのか。望東尼の考えは、それ以上先に進めなくなった。馬場の話を聞いて望東尼は、京都で物見遊山に呆けている自分が情けなく思えてきた。

京都滞在も半年が過ぎた頃、心境を詠んでいる。
ふるさとも菖蒲葺(あやめふ)くかと競馬見るうちさえも思いやられし
間もなく京都を後にしようとする5月、すっかり馴染みとなった上賀茂神社で、競馬(くらべうま)を観ての感想である。
※競馬(くらべうま):天下太平と五穀豊穣を祈って行われてきた神事。
半年の間福岡の地を離れて、すっかり都の風に酔いしれていた。もの珍しさと、400石取りの我が身の立場の有利さに甘えた旅でもあった。京都を離れる際には、馬場に大坂まで送ってもらった。馬場文英とは、福岡に戻った後も連絡を保ちたかったからである。滞在期間中動き回ったせいで、疲れもかなり積もっている。

と馬場に対する惜別の念を詠めば、馬場文英も

と返して、将来の再会と今後の交流を誓った。
大坂に立寄った望東尼は、名残り惜しさも手伝って、再び大隈言道の家を訪ねた。だが、大隈は遠方に出かけていて留守だった。わざわざ九州から出かけてきたのは、大隈言道に叱咤激励を受けるためだったのではなかったか。悔しさと切なさを重ね合わせながら、望東尼は船に乗り込んだ。帰りは、所用で大坂に滞在していた福岡藩士の岡部某と、同じく藩士の腰元下枝(しずえ)が同行することになった。
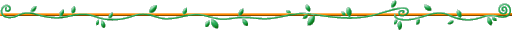
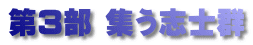

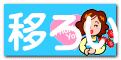
文久2(1862)年6月。望東尼は九州小倉に上陸した。半年ぶりの帰郷である。久方ぶりの九州は、別世界に降り立った気分であった。
この間に実家の野村家は、貞一から孫の助作に代が移っていた。住居も林毛町から下警固村の立益町(りゅうえきのちょう)に替わっている。立益町は、現在の地下鉄桜坂駅付近である。
平尾山荘に着くと、早速野村家の家族が集まってきた。彼らには、大切に持ち帰った土産話を披露した。話を聞こうと、藩の若者も集まってきた。
皆が帰ったあと、一人山荘の庭石に座り込んであたりを見渡した。どうしてここだけがこんなに静かなのだろうと、不思議な感覚にとらわれる。
彼女の帰郷を追いかけるように、京都の馬場文英から便りが届いた。激しい政情の移り変わりが、こと細かに記されていた。馬場は、福岡に住む志士たちの動向も気にしているようだ。
そんな折、野村家の家督を継いだ孫の助作が、中村恒次郎なる青年藩士を連れてやってきた。青年に年齢を聞くと、23歳だと答える。助作より1歳上である。
「おハハウエ、私にも京都の話を訊かせてください」と、子供がねだるような言葉付きで挨拶した。平尾山荘にやってくる若者は、望東尼のことを「ハハウエ」と呼ぶようになっている。中村は、京都での尊皇攘夷派の活動ぶりを知りたいようだ。最近起こった大蔵谷回駕の一件や寺田屋騒動のことなどには、特に興味がありそう。
望東尼は、蘇る記憶をなるべく正確に伝えようと心がけた。日を置かずして、望東尼の山荘には幾人もの若者が寄って来るようになった。助作から事情を聞きつけたのだろう。いずれも、自分とは母子ほどに年齢差のある青年ばかりである。彼らは、望東尼の話を聞きながら、誰憚ることなく尊皇攘夷論を戦わせる。口から泡を飛ばす青年らに、望東尼も危うさを感じることはなかった。立派な志士の卵たちである。
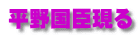
望東尼が上方から帰国して、一年が経過した文久3年のこと。山荘に平野国臣が尋ねてきた。望東尼にとって、大蔵谷回駕の事件もあって、彼のことは忘れられない人物の一人になっていた。風貌は想像していた以上に武士らしくない体裁である。月代(さかやき)は剃っていないし、長刀だって刃を下に向けて腰に吊り下げているだけ。望東尼も、平野国臣が大蔵谷回駕事件後福岡藩に身柄を拘束され、枡木屋(ますこや)の獄に閉じ込められているところまでは聞かされていた。
枡小屋の牢獄:幕末期に福岡藩が橋口町(現天神4丁目日銀付近)に造った牢屋のこと。
「枡小屋に閉じ込められているはずの貴方が、どうして私の目の前にいるのです?大蔵谷の一件は、私もそれなりにわかっているつもりです。貴方は、薩摩の島津久光さまの名前を語って、黒田のお殿さまに建白書を渡したのでしょう。黒田のお殿さまだって、貴方を易々とお許しになるとも思えませんよ。いったい、その間に何があったのでしょう」
1.gif)
平野国臣像(福岡西公園)
「ありがたいことに、朝廷からのお力添えがありましたようで。3ヶ月前に無罪赦免になったのです。拙者ごときに、朝廷がどうして働きかけをしてくださったのか、そこのところはようわからんのです」
ひと通りこれまでの経過を聞かされたあと、望東尼が問うた。
「貴方が本日拙僧の前に現れたわけは?」
「福岡藩からの命により、これから京に上ります。京都では、馬場文英殿に会いしたいと思っています。そこで、御尼に紹介状を書いて欲しいのです」
平野国臣の上京の目的の一端が尊皇攘夷のためだとわかり、望東尼は早速、馬場文英宛てに紹介状を書いた。
大蔵谷回駕の後、福岡藩による尊皇攘夷派に対する監視はますます厳しくなっている。志士たちの中心にいる月形洗蔵もその一人である。月形は、望東尼が生まれた御馬屋後(おうまやのうしろ)の数軒東側に住んでいて、幼い頃からよく知った仲である。3年前に、藩主に対して参勤の中止などを求める建白書を提出したこともある人物。その時藩主の黒田長溥は、藩政批判の罪で、月形をはじめ30名余に島流しの処分を科した。だが間もなく、全員の処分が撤回された。これまた朝廷からの働きがあったためであった。このときの処分を歴史家は、「辛酉(しんゆう)の獄(ごく)」と呼んだ。
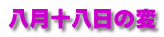

平野国臣や月形洗蔵らは、藩の取締りにより捕まった後も早期に釈放された。すべて、朝廷からの指示でなされたことであった。ところが、それまで優位に働いていた朝廷における尊皇攘夷派の公卿らは、一日にしてその力関係を逆転させられることになる。八月十八日を境に、尊皇攘夷派の中でも急進派だった三条実美ら七卿が、朝廷を追われることになったからだ。朝廷を追われた公卿らは、雨の中を草履と簔だけの姿で、長州藩の兵士ら2000人とともに西に向かったのであった。
※八月十八日の変:1863年。幕末、公武合体派が尊攘派の公卿らを朝廷から追放した事件。長州藩を中心に尊攘急進派が朝廷を動かして統幕計画を進めたので、公武合体派にあった薩摩藩が京都守護職らと画策して、八月十八日に朝議を一変、長州藩の御所警護を取り上げて三条実美ら急進派公卿を追放した。実美らは長州藩内に逃げ込み(七卿落ち)、尊攘討幕運動は一時頓挫することになる。
望東尼にも馬場文英から、八月十八日の変とその後の平野国臣や志士らの動きについて動静が伝えられた。平野は、新撰組の追っ手を逃れて但馬へ向かった。更に平野国臣は周防国三田尻を目指すことに。みやこを追われた実美ら七卿に会うためである。更に播磨へと移動する。三田尻を発つにあたり、平野は望東尼に宛てて自らの歌を添えて訣別の書状を送っている。
「幾度か捨てし命の今日までも残るは神の助けなるらむ」
平野はその後豊岡の藩士に捕まり、京都の六角の獄に移された。後に新撰組の手で処刑されたのであった。
※六角の獄:平安時代に建設された京都の牢獄。正式には「三条新地牢屋敷。宝永大火のあとは、六角獄舎、または六角牢といった。
中村円太も同時期に、脱藩の罪で捕縛されて、枡木屋の獄(福岡)に繋がれてしまった。平野国臣が処刑され中村円太まで獄に繋がれていると聞き、望東尼は居たたまれなくなった。自分が女でなかったら、もっと若かったらの思いが、なおさらのごとく気持ちを暗くさせるのである。


年号は元治(1864年)に移り、元年の春まだ浅い3月24日のことである。福岡藩内で二つの大事件が起きた。
一つは、藩の老臣・牧市内が地行ヶ浜(現PayPayドームあたりの海岸)で暗殺されたこと。牧を斬ったのは勤王志士であった。
もう一つの事件は、深夜、枡木屋に繋がれている中村円太が脱獄したこと。脱獄を手引きしたのは、二人の福岡藩勤王志士であった。
二つの事件は、それまでどちらかと言えば優柔不断に見えた福岡藩主の態度を、決定的に幕府寄りの立場にしてしまうことになる。
中村円太が脱獄したその夜。10名の藩士が平尾山荘に集まっていた。談合の途中で、中村恒次郎と小藤平蔵が席を立った。二人の行き先は枡木屋である。牢獄に押し入り、予め示し合わせていた獄吏に扉を開けさせ、繋がれている中村円太を解放した。小藤は、脱藩するまで枡木屋の牢で獄吏として働いていた経験があり、獄を開いた人物とは同僚の仲だった。
同じ日に、重臣の暗殺と勤王派人物の脱獄という大事件が重なったのだ。福岡藩の上層部はもちろん、対立する勤王派と公武合体派を並立させようと考えていた藩主黒田長溥は、冷や水を浴びせられる格好になった。
望東尼の気がかりは、山荘での談合中、車座から抜け出した中村恒次郎と小藤平蔵のその後の行方であった。中村円太と二人の足取りについては、山荘に現れた若者の一人が教えてくれた。脱獄に成功した中村円太と、円太を救い出した弟の恒次郎・小藤平蔵は、事前の打ち合わせ通り同士の家に匿われて難を逃れていた。
その後3人は、対馬藩の飛び地である肥前国田代宿(現鳥栖市)まで逃げた。そこで長州藩士の小田村文助と名乗る長州藩士に出会う。小田村は、3人に長崎まで同行することを勧めた。長崎に着いた3人は、商船に乗せられて長州の三田尻港まで送り届けられたという。
ここで登場する小田村文助こそ、望東尼にとって後の人生を決定づける存在となるのである。

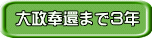
月形洗蔵が山荘にやって来て、長州の志士を匿って欲しいと願い出た。元治元年(1864年)11月11日のこと。明治維新の4年前である。匿って欲しい人物は高杉晋作だと言う。高杉といえば、先頃、四国(英・仏・米・欄)連合艦隊による下関攻めの後、和解交渉の長州藩正使となった人物ではないか。
翌日山荘に現れた高杉晋作は、想像した豪傑風とは似ても似つかぬ優男であった。たわし風の髭面もない。
望東尼は、初対面の男の顔と仕種を見て強烈な衝撃を受けた。5年前にこの世を去った夫新三郎貞貫と似ている。そんなはずはないと自身に言い聞かせながら、改めて高杉晋作と向き合った後、投宿を承知した。
「このような破れ小屋でよかったら」

高杉晋作
高杉晋作が平尾山荘にたどり着くまでのいきさつを、少しばかり補足したい。
文久3(1863)年3月。高杉は、藩主から下関防御の役を任されたことがある。高杉はその機を逃さず、下関界隈に建つ功山寺で騎兵隊を結成した。その後、藩の許可を得ずに藩を飛び出して京に上ったため、脱藩の罪で野山獄に閉じ込められた。イギリス・フランス・アメリカ・オランダの四カ国連合艦隊が長州を攻めにかかったそのときであった。
1.gif)
功山寺
※奇兵隊:長州藩の非正規軍隊。門閥に関係なく、農商人を編入して実力主義をとったことで知られる。
※下関砲撃事件:1863年~64年。幕末、長州藩の攘夷実行に報復する英・米・仏・蘭4国連合艦隊が下関を砲撃した事件。長州藩は、降伏後の交渉で四国艦隊と講和を結ぶべく、高杉を牢からだして、長州藩正使に抜擢した。
※野山獄(のやまごく):江戸時代、長州藩萩に造られた獄屋敷のこと。
「勝手なものですね、お上のなさることは。気に食わなければ牢に入れ、場面が変われば、外国との交渉大役を担わせるのですから」
望東尼が、深くため息をついた。四国連合との交渉が一段落すると、長州藩内ではまたまた正義派と俗論派の論戦が始まった。幕府に対して抗戦を主張するのが「正義派」。幕府に恭順であるべきと主張するのが「俗論派」に分かれた。正義派をリードしたのが高杉晋作である。
長引く論争に嫌気がさした高杉は、地元の萩に引き下がった。それでも俗論派の攻撃は高杉を攻め立てた。たまらず萩を抜け出して下関の豪商・白石正一郎の屋敷に身を潜めた。そのとき白石邸にとどまっていた福岡藩の中村円太から、筑前行きを勧められたのであった。
高杉は、馬関(関門)海峡を渡って門司の港に着いた後、月形らの助けを借りて肥前国の田代宿に到着した。田代は対馬藩の飛び地であり、攘夷派の勢いが強い土地柄である。田代代官所に滞在中、佐嘉の鍋島など九州諸藩の大名に尊皇攘夷論を説いて、倒幕の戦いに加わるよう説得を試みた。だがそれもうまくいかず、逆に高杉の身が危険にさらされることになる。
「それで、当平尾山荘に隠れようと…」
話はそこで途切れて、しばし沈黙の時間が過ぎていった。その間望東尼は、目の前の男の表情を見つめたままであった。
「貴方には奥さまは?」
考えた末の質問ではなかった。
「萩に置いたままです」
この話も、次には進まなかった。狭い山荘で他藩の男と同居することは、望東尼自身辛いことであった。そこで、自分は立益町の野村家に寝泊まりしながら、山荘に通うことにした。野村家から山荘までの距離は半里に満たない。女の足で通うにも、それほどきついことではなかった。山荘での高杉の世話は、瀬口三兵衛に任せた。
その頃長州藩内では、俗論派の勢いがますます増幅していた。正義派3人の家老が、禁門の変を引き起こした責任で切腹するに及んだ。それだけでは済まない。俗論派は、更に4人の参謀に打ち首の刑を処した。このままでは、藩内の正義派は決定的に追い込まれることになる。
※禁門の変:幕末(1864年)。長州藩兵による兵乱。蛤御門の変・元治の変ともいう。前年の八月十八日の変で失墜した勢力を回復するため、尊皇攘夷派志士が長州藩を動かして京都に出兵。御所を護る薩摩と会津・桑名諸藩兵と、蛤御門周辺で戦って敗走。京都は大火となり、長州藩は朝敵とされて、長州征伐が起こるきっかけとなった。

蛤御門
平尾山荘に隠れている高杉は、藩の同士からの連絡を受けて衝撃を受けた。一時も早く長州に戻らなければならないと、気ばかりが急く。
「今帰藩したら、待ち伏せしている俗論派の餌食になるだけですぞ」
止める月形洗蔵の声も高杉の耳には届かなかった。
「悲しいね、せっかく世の中のことを学ばせていただいていたところだったのに・・・」
望東尼は、高杉の滞在が10日足らずでは、もの足りないと悔しがった。高杉が去った後まで自分のことを記憶に止めてくれる証を差し出したいと考えた末に、夜通しで旅衣を縫った。両袖の裏地には、自身が身につける襦袢の袖を切り取って縫い付けた。翌朝、旅立つ高杉に手渡すときのときめきの感情である。

ここでいう「谷」とは、高杉晋作の別称である。高杉もまた、山荘を去る際に漢詩を書き残した。その中の一首である。
突然舞い込んできた危険人物を、嫌がりもせず受け入れてくれた恩は終生忘れまいと誓った高杉晋作の句である。そして平尾山荘を去って行った。このときの高杉晋作との切ない別れは、望東尼の記憶から遠ざかることはなかった。
山荘を後にする高杉晋作は、月形洗蔵らの身を挺しての援護で、無事長州藩に戻っていったのであった。
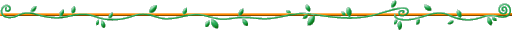



11.gif)
延寿王院跡(太宰府天満宮内)
福岡藩内の尊攘派は、三条実美(さんじょうさねとみ)ら五卿(三条実美・三条西季知・東久世通禧・壬生基修・四条隆謌)の筑前下向を支持して、各方面に働きかけた。まずは、実質長州藩内に囚われの身である五卿とその後ろ盾である長州藩主に賛意を求めることである。月形洗蔵ら尊攘派は、長州の萩や湯田まで出向いて関係先の説得にあたった。彼らの行動は功を奏して、5人の公卿は五つの藩(福岡・薩摩・肥後・佐賀・久留米)が分担して預かることに決まった。そして五卿の落ち着き先は、太宰府の延寿王院(えんじゅおういん)ということになった。延寿王院とは、安楽寺天満宮(現太宰府天満宮)の宿坊のことである。
五卿が長州を発って太宰府に到着したのが、慶応元年(1865年)1月であった。五つの藩が分担して警備する中、五卿は王政復古の日までこの地で暮らすことになったのである。
尊攘派の動きを嫌う幕府は、福岡藩主黒田長溥ら5藩の藩主に対して、直ちに五卿を江戸に送れと命じてきた。命令を受けた五つの藩は、たまたま筑前入りしていた薩摩の西郷吉之助(隆盛)を交えて協議した。結果、幕府の命令をきっぱり拒否することになった。
望東尼は、念願であった公卿への面会を実現すべく、延寿王院に出かけた。五卿が太宰府に入った2ヶ月後の3月25日である。
延寿王院は、天満宮の大鳥居を潜ってすぐのところ。恐る恐る門番に来意を告げると、間もなく館内に案内された。奥の間で待つことしばし、現れたのは三条実美であった。世が世なら、福岡藩士の後家ごときが面会できる立場ではない。
正面に座った三条公は、お眉墨もお歯黒もない簡素な袴姿であった。聞き及んでいた公家の身繕いとはほど遠いものである。
「よう来はりましたな」との挨拶だけで、多くを語らない。望東尼にとって、直接三条公に声をかけてもらっただけで十分である。天にも昇る感動を覚えたまま門外に出た。後日三条実美からは、扇子と手紙が贈られてきた。尊皇派を自認する望東尼にとって、これ以上の名誉はない。早速差し出した礼状には、
空蝉(現世の人間)の世の障りがちにて心に得まかせ侍らず
の句を添えた。
「もし…」
三条公と別れて延寿王院の門外に出たとき、後から見知らぬ武士に声をかけられた。
「どちらさまで?」と伺うと、男は丁寧に頭を下げた。
「小田村文助と申す長州藩士でござる。先頃は、我が藩の高杉晋作が大変お世話になり申した。もしかしてと、失礼ながら声をかけた次第」
小田村文助とは、後に望東尼が深く関わることになる、後の楫取素彦(かじとりもとひこ)のことである。小田村は、先頃枡木屋の牢獄を脱走した中村円太らを、対馬藩の飛び地である田代藩邸(現鳥栖市田代)に匿った人物であった。
「この度は、天神さまにお詣りでしょうか?」
「いえ、公卿さまにご挨拶を」と言うなり、小田村は延寿王院の門の中に消えていった。
1.gif)
旧陶山一貫宅三条実美手植えの松
望東尼はその足で、通古賀(とおのこが)に住む陶山一貫を訪ねた。陶山は、当地で開業する医者である。一方陶山は、尊皇攘夷運動の熱心な活動家でもあった。陶山は、延寿王院に謫居中の五卿を訪ねては、みやこのことや同士の活動など近況を報告している。五卿を政治の世界と結びつかせる貴重な尊皇派の連絡係であった。陶山一貫の屋敷跡には、現在も三条実美手植えの松(途中植え替えがなされている)が保存されている。


十一代福岡藩主黒田長溥
高杉晋作の平尾山荘逗留を境にして、尊皇攘夷派志士らの山荘への出入りがますます頻繁になった。出入りするのは福岡藩士ばかりとは限らない。領内での正義派と俗論派の対立から逃れてきた対馬藩の重役なども。中には、脱藩した他藩の浪士や英彦山の僧まで混じっていた。
いかに周辺に人家が少ないとはいえ、出入りする人の多さは住民の話題にならないわけがない。いつしか、山荘が浮浪の輩の巣になっているとの噂まで広まった。尊攘派の動きに、それまで見て見ぬふりをしてきた藩主・黒田(くろだ)長溥(ながひろ)の気持ちも、尋常ではいられなくなった。
黒田藩主は、もともと五卿の太宰府受け入れに積極的ではなかった。そのため、藩主と尊攘派贔屓の家老たちとの間にできた溝は、抜き差しならぬところまで深まっていたのである。
※黒田長溥(くろだながひろ):筑前国福岡藩十一代藩主。蘭癖大名と称され、藩校修猷館を復興させるなど名君と呼ばれた。
この度の長州征伐結果に不満を持つ幕府が、いよいよ第二次征伐に動いた。そのことが、福岡藩の立場をますます窮地に追い詰める結果となる。尊攘派による老重臣の暗殺、中村円太の牢破り、五卿の受け入れなど、尊攘派による意に反する出来事が続き、その上、平尾山荘への不逞の輩の出入りの噂まで広まったのである。藩主の堪忍袋も限界に達したのだった。
そんな折、望東尼にとって、怖れていたことが現実となってしまった。京都にいる馬場文英が、京都所司代に拘束されたとの情報が届いたのである。大文字屋当主比喜多五三郎亡き後、跡を継いだ息子の比喜多源二までもが捕まったと聞かされたのだ。
京都所司代は、京都での出来事が短時日の間に福岡の攘夷論者の許に届き、福岡の情勢が京都の反体制派に届いている、そのカラクリを徹底的に追求した。人脈を手繰っていくと、馬場文英が平野国臣を匿った事実まで突き止めたのだった。
馬場の捕縛は、幕府が第二次長州征討を打ち出した時期と重なる。馬場と比喜多源二は、京都周辺に滞留していた平野国臣と同じく、六角の牢獄に封じ込まれた。そこで、望東尼と馬場の連絡ルートは完全に断ち切られることになった。
「ここも、無事ではいられませんよ」、と孫の助作が望東尼に耳打ちした。尊攘派の志士たちの思想的柱である家老の加藤司書だって、無事ではいられまい。
藩庁から睨まれているだろう志士たちは、どの者も、国を憂い、正しい道を導き出すために運動してきた若者である。もし、藩庁から尋問を受けることがあれば、正々堂々と自分らの正義の考えを述べれば済むこと。例え尊攘派に理解を示さない役人でも、そのうちに分かってくれるはず。望東尼は、そう信じ、必要以上に怖れることはないと、助作に言い聞かせた。
時代が慶応元(1865)年に入ると、福岡藩尊攘派弾圧の波はそこまで押し寄せていたのであった。

望東尼の気持ちは落ち込むばかりであった。気晴らしに、曾孫と戯れようと野村本家に出かけた。やがて夏を迎える時期である。
近くの神社でひとしきり遊んだ頃、玉垣の向こうから野村家の女中が駆け込んできた。何事かと問うても、口もとを震わせるばかりで、はっきりしたことを言わない。とりあえず、幼な子を彼女に預けて家に戻った。
帰るなり、嫁から一通の書状を見せられた。それは本家を継いでいる助作に対する藩庁からの召し文(呼出状)だった。「戒めがある故出頭せよ」とだけ書いてある。座敷に入ると、助作が既に身支度を済ませて祖母の帰りを待っていた。召し文に書かれている「戒め」の意味が分からないと、助作はぼやいている。しばらく経って助作は、実家の浦野吉之助と連れだって出かけていった。
大詰めを迎えた歌集『向陵集』の編纂も気になるが、ここは当主助作の祖母として野村家を護らなければならない。親類の者が続々集まってくる中で、夜中になっても戻らない孫をひたすら待ち続けた。
夜明けも近くなる時刻、吉之助が一人で戻ってきた。右手に藩庁から渡された仰せ文を握っている。誰に対する文かと見てびっくり。対象は、助作ではなく望東尼自身だった。
「疑いの義あり。次なる沙汰があるまで、親族の家で謹慎するように」とのこと。その間、望東尼を身内の者がしっかり見張るようにとのお達しであった。仰天する望東尼は、このときの心境を日記「夢かぞえ」に書き記している。
世を捨てし身にさしかかるうき草の濡れ衣、墨の衣に引き重ねつる事ども、いと畏(かしこ)しとも思いわきがたし
頭を丸め、仏門に入った我が身に、思いもよらぬ濡れ衣が掛けられようとは。それも、信頼する福岡藩からのお達しである。とても、畏まって承服できることではない。怒りは心頭に達した。その後助作を待つ時間の長かったこと。たったの半日が、1年にも思えた。
東の空が白みかける時刻、助作が戻ってきた。助作は、祖母への謹慎言い渡しを知らされていないらしく、まずは自らの今後について語った。自身にも謹慎を言い渡されたというのである。助作は現役の藩士であるため、見張りも公の守人がつくと言う。
「謹慎を受けるのは、そなたと私だけではなかろう」
祖母の問いには答えず、助作はそのまま寝間に入っていった。

夜が明けて、望東尼は実家の浦野家に移された。慶応元年(1865)年8月15日である。
久しぶりの実家なのだが、懐かしさや親兄弟への思い出など感傷は湧いてこない。実家の跡取り浦野吉之助が見張り役となり、二人は複雑な面持ちで向き合った。
「嫌疑がかかる者を、身内の甥っこに見晴らせるとは情けない藩庁だね。だって、私に何かあったら、おまえらのせいにするって言うことだろう」
望東尼は、藩への恨みを吐き出した。今回厳しい「戒め」を受けるのは、名前を挙げるだけでも半端な人数ではなかった。
月形洗蔵、筑紫衛、鷹取養巴、森安平、万代安之丞、江上栄之進、伊能茂次郎、海津亦八、伊丹真一郎、今中作兵衛、真藤善八、尾崎逸蔵など。
山荘で我が子同様に接してきた者ばかりである。この日、藩に拘束された武士は、望東尼と助作を加えて総勢14名に上った。その他足軽などを含めると、39名が「戒め」を受けることになった。
悲しいことに、望東尼を頼って和歌の弟子入りをした、瀬口三兵衛まで連れて行かれたという。三兵衛は、今朝も、山荘の庭に咲く草花を届けてくれたばかりである。
「どうして? なぜなの?」
自分の周囲にいた人たちが、ことごとくしょっ引かれたと聞くと、望東尼の頭は真っ白になり、ただ座敷に額を付けて呻くばかりであった。
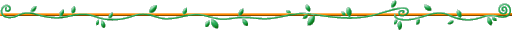
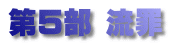

御馬屋後(おうまやのうしろ)(現中央区赤坂3丁目付近)に建つ浦野家での謹慎暮らしが始まった。「謹慎」と言えばまだ聞こえはよいが、実態は「座敷牢獄」と同じようなもの。ここは、自身が嫁入り前まで暮らした家である。藩庁からのきつい申し渡しもあり、勝手に外出することは許されない。広い座敷で、見張り役の総領吉之助と二人が睨めっこしているばかりであった。
「伯母上・・・」
退屈そうな伯母に、吉之助が語りかける。
.gif)
望東尼生誕地付近(福岡中央区赤坂)
「どこにどのような目があるかも知れぬ」と、望東尼が小声で遮った。
「吉之助よ、たまには外に出て、弓射場(ゆみいば)でも覗いてみたいの」
今度は、伯母の方から話しかけた。するとすぐに、吉之助が身構える。
「駄目ですよ。伯母上が変な気でも起こしたら、浦野家はたちどころに取り潰しですからね。しばらくの辛抱です、我慢しましょう」
「分かっていますよ。ただ、おまえの名前を呼んでみたかっただけ」
それだけの会話を交わすのにも、気を遣わなければならない窮屈な自宅謹慎であった。

福岡城内堀
謹慎中も、藩庁から取り調べの達しが届く。取り調べの場所は、お城を半周して、博多湾に向かったところの中名島町である。おおよそ半里(2㌔)の道のりを駕籠に乗せられて行くことに。体力に自信がない望東尼は、駕籠に揺られるだけでもすぐに疲れる。付き添いの吉之助にねだって、海の見える日陰で一休みすることにした。現在の長浜公園あたりだろうか。湾からの風が気持ちよく、いつまでもここにいたいと駄々をこねたくもなる。
取り調べは、年老いた尼僧を気遣ってか、部屋の中で淡々と進められた。
「今回取り調べを受けている者は、いずれも、包み隠さず素直に答えておる。貴僧も、お仲間を思う心があるのなら包み隠さず答えられよ」
「何をお訊きになりたいのです?」
と応じたところで、役人の声色はますます優しさを増した。
「山荘に出入りしておった者の名前を聞かせてくれまいか。それから、中村円太の枡木屋脱走について、知っていることがあればすべて教えてほしい」
「申し上げたら、いま捕らわれている者たちを、自由の身にしてくれますか」と、念を押した。
「貴僧の願いを聞いてくれるよう、お奉行に申し伝える故」
そこで望東尼は、平尾山荘に出入りしていた若者の名前を連ねた。そのことが、後の大弾圧に直結する誘導尋問であろうとは微塵も考えず、知りうることをすべて申し立てた。

高杉晋作の帰国後、長州藩では俗論派(佐幕派)の勢いが衰え、正義派つまり倒幕思想が勢いを増すことになっていた。そんな尊攘派の勢いを削ぐべく、幕府は総司令官に将軍德川家茂(いえもち)を据えて、第二次長州征討に打って出たのである。
第二次長州征討を知らされた福岡藩主・黒田長溥は、謹慎を申し渡している志士たちを即刻処分するよう言い渡した。世に言う乙丑の獄(いっちゅうのごく)本番の始まりである。

加藤司書像
尊攘派が拠り所にしている家老の加藤司書や月形洗蔵ら21名に切腹及び斬罪が言い渡された。その他16名には流罪が。併せて100名を超える志士に対する処分も断行された。
中でも加藤司書への断罪の報は、福岡藩中に衝撃が伝わり、志士らの間に動揺が深まった。
それは、慶応元(1865)年10月23日の夕刻であった。加藤司書は中老の隅田清左衛門屋敷にお預けの身となった。隅田家では、急遽設えた座敷牢に司書を迎えることに。屋敷の周辺には、警備の役人が多数配備された。
2日後、切腹決行の夜である。墨田家では、最大級のご馳走を司書に差し出し、これまでの働きを労った。夜遅く大目付がやってきて、「天福寺にて切腹」の君命を言い渡した。そこで加藤司書は、墨田清左衛門に対して深々と頭を下げた後、護送用の網駕籠に乗せられて死出の旅路についたのであった。
一方、望東尼の孫・野村助作には、流罪の判決が言い渡された。流される先は宗像沖の大島だと聞かされた。
そして望東尼には、「姫島流罪牢居」の刑が告げられた。望東尼は、判決文を聞かされて涙が止まらなくなった。取り調べの際に、あれほど同士に対する罪はないことにして欲しいと頼んだのに。正直に事実を述べれば、許してくれると信じていたのに。全身全霊を傾けての訴えは、黒田のお殿さまにまでは届かなかったのか。まして他の同志に比べて自分への罪が死罪でないのはどうしたことか。打ち首ではなく島流しということでほっとするどころではない。恥ずべきことだとも思えた。
そしてもう一つびっくりしたのは、流される先が筑前の姫島だと聞かされた時だ。福岡藩は、死罪に次ぐ罪人に設けた「流罪先」として、姫島・玄海島・大島・小呂島など、近郊の離島に牢獄を設けた。
姫島には望東尼自身何度か足を踏み入れていたことがある。今は亡き弟桑野嘉右衛門が姫島勤務だったときのこと。誘われて姫島に渡った時、和歌の師匠である大隈言道と二人連れだった。
玄界灘に浮かぶ姫島は、岐志港から7㌔西に浮かぶ離島である。周囲3.8㌔、面積0.75平方キロほどの小さな離れ島であった。
あのとき望東尼と言道は、愛宕神社下の海岸を、港まで語り合いながらの旅であった。海が荒れていて船を出せないという船頭に従って、村長(庄屋)の屋敷に泊めてもらうことになった。望東尼はそのときの心境を詠んでいる。
旅ごろも香月の浦にいつまでか立うらぶれん波もわがみも
ようやくたどり着いた姫島では、漁師や家族とのふれあいなど、楽しい思い出が詰まった旅となった。この姫島に、次は自身が囚人となって、荒波を渡ることになろうとは・・・。

福岡長浜海岸

慶応元年(1865年)11月14日の夕刻であった。浦野家門前に唐丸籠が運び込まれた。唐丸籠とは、囚人を載せて護送するための駕籠のこと。「籐丸籠」とも書くそうだ。籐を編んで作った、闘鶏用のシャモを飼う籠に似ているところから付けられた名前だとか。
赤坂(あかさか)御馬屋後(おうまやのうしろ)の実家から岐志の港までの8里(30キロ強)を、夜を通して望東尼を護送する。岐志港に到着後は、船で姫島まで運ぶことになる。籠の舁き手は前後に二人の守人。囚人は、最初から最後まで籠の中。排便も籠の底に開けられた小穴を大小共通で使う。外から物珍しそうに見つめる目もお構いなし。これ以上ない惨めな晒しものである。気位の高い400石取りのご新造さんには残酷過ぎる。顔から火が出るような羞恥心も関係なく、籠は西方に向かって歩き出した。
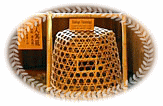
唐丸籠
「せめて港まででも…」見送りたいと訴える者には、「後の祟りが恐ろしいから」と、吉之助が押しとどめた。結局、身内から5人が、籠の後を着いていくことになった。籠は唐人町から唐津街道に出た。
室見川を渡って振り返ると、川向こうから城下の灯が見送ってくれている。生まれてこの方馴染んできた、お城や福岡の街とも今生のお別れになるかも知れぬ。多くの志士らと出会った平尾山荘を、今後誰が面倒見てくれることやら。月形洗蔵-平野国臣など、山荘に出入りした面々が脳裏を駆け巡る。亡き夫貞貫と、「ここでのんびり和歌を詠もう」と誓った山小屋である。夫の幻影が浮かんだ途端、もう一人が顔を出した。10日間だけ山荘に匿った、優男ながら眼光の鋭い高杉晋作である。
籠は彼女の感傷も知らぬげに、海岸通りから愛宕下へ、更に生の松原を経て博多湾へと進んでいった。風が出たのか、海岸に打ち付ける飛沫が頬を濡らした。拭き取ることもままならず、目を閉じたままで我慢した。それより、師走間近の海辺は、頬を殴る風が耐えられないほどに痛い。
一行が岐志の港に着いた時、東の空では大きな星が休みなく瞬いていた。一行は、船乗り場からほど近い庄屋の家で、しばし休息をとることになった。以前師匠の大隈言道と連れだって姫島に渡った折立ち寄ったのも、この庄屋の屋敷であった。そのとき、庄屋に頼まれて和歌を贈ったことを思い出した。
.gif)
岐志の港
役人は、守人に厳重な警護を言い渡すと、自分だけさっさと眠りこけた。後ろから付いてくる身内は、ここから今来た道を戻っていった。
静かな寝息を立てる守人の隙を見て、庄屋が筆と紙を差し出した。「今のお気持ちを一句」詠んでいただきたいとの願いである。
舟でするきしの浦波立かへりまたこの家にやどるよもがな
目を覚ました役人が、守人の頭を叩いた。「凪いでいる間に船を出すぞ」と声をかけ、望東尼を再び唐丸籠に押し込んだ。桟橋まで見送ってきた庄屋とその家族が、「お身体をお大事に」と手を振っている。行く末を察知しているかのように、声は上ずりがちであった。
桟橋を出るとき凪いでいた引津湾は、出港後玄界灘に出た途端、うねる波が襲いかかる荒海と変じていた。
「大丈夫だって、こんくれえの波じゃひっくり返ることはなかけん」
艪を漕ぐ船頭は、荒波に揺さぶられる様を楽しんでいる風にも見える。船酔いがひどい望東尼は、籠の中とあって横になることもできずにもがいた。
「夜が明けますぜ」と船頭が叫んだ。お盆を伏せたような姫島が、目に飛び込んできた。まさしく、これからの辛苦を予告するような島影であった。
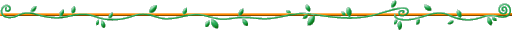
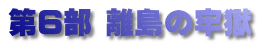

姫島全景 アカ□=姫島牢獄 アオ○=姫島漁港


望東尼を乗せた船が姫島の桟橋に着いた。夜が明けて間もないというのに、数人の島民が唐丸籠を取り巻いた。中には、見覚えのある女房や娘の顔も確認できた。
唐丸籠が浜定番(はまじょうばん)屋敷に入った。暫時屋根の下で待たされる。そこで出された冷や飯も、白湯だけでは喉を通りそうにない。昼過ぎから裏庭の白州に引き出され、藁茣蓙(わらござ)に座らされた。
「ここに直れ」。屋敷の小役人が指さした。しばらく待つと、上方からかすれ声が降ってきた。「面(おもて)を上げい」と叫んでいる。自分を見下ろしているのは、かつて弟の部下であった小島源五右衛門であった。小島は、望東尼に挨拶をしたいような眼差しを向けた。だが、すぐに険しい顔に戻り、「流刑囚の心得」を形式的に読みあげて、さっさと奥に引っ込んだ。
小役人に両脇を抱えられ、再び唐丸籠に押し込まれた。連れて行かれた先は山の中腹に建てられた粗末な獄舎である。降りたって南方を眺めると、眼下に白波の立つ海が見える。玄界灘である。慶応元(1865)年11月15日。晩秋の真昼時であった。
これから寝起きする獄舎は、まさしく囚人が住むに相応しい小屋である。四角い建物の屋根には、薄っぺらな瓦が置いてあるだけ。縦1間半(2.7㍍)、横2間(3.6㍍)の広さに、寝起きするための畳が1枚と敷板が置かれている。そのすぐ隣に雪隠(せっちん)(便所)があり、またその隣が警護室になっている。
a.gif)
姫島獄舎跡(望東尼御堂)
護送してきた役人は、望東尼の身辺を念入りに調べた。自殺の恐れのある刃物や、火災のもとになりそうな蝋燭などを隠していないか点検するためである。望東尼を獄に閉じ込めた後、役人は外から頑丈な錠前をかけたあとすぐに立ち去った。役人が警固室に寝泊まりしないことを知り、安堵した。
長かった一日が終わりに近づき海岸線に陽が沈むと、月明かりが板戸の隙間から差し込んでくる。表の草むらで鳴く虫の音や、頭上から聞こえる梟の鳴き声がもの悲しい。「痛い!」思わず自身の声が獄中に籠もった。忍び込んできたコオロギが、脛に食いついたのだ。与えられた薄い布団と周囲の茣蓙を重ね合わせて身にまとった。寒さを偲ぶためである。牢屋に忍び寄る虫や残り蚊に悩まされながら、一睡も出来ない夜が過ぎていった。
東の空が明るくなると、村人らしい中年の男がやってきて板戸を開けた。彼方に見える波頭が、目に飛び込んできて眩しい。村民との接触は、役所が委嘱している食事を運ぶ村の女が一人だけ。それも、無用な会話は許されていないらしく、用を済ますとさっさと獄舎を離れていった。格子戸から眺める対岸は、福吉あたりの唐津街道筋か。その奥に浮嶽(うきだけ)(805㍍)が、気持ちよさそうに居座っている。点在する藁葺き屋根の家屋から聞こえる牛や雄鶏(おんどり)の鳴き声がうるさい。
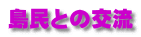
2.gif)
姫島漁村風景
いかに役人が村人との間を裂こうとも、時間が囚人との距離を縮めるもの。島の女たちは、魚の天日干しなど仕事の合間に獄舎の前庭に集まって来る。そこでは、子供のことや亭主の稼ぎについて自慢し合っている。最初は小声で、そのうちに他人の耳など気にしなくなった。武家屋敷では、おおよそなかった下世話の話まで飛び出して、大口開けて笑い合う女たち。
しばらく経つと、朝晩食事を運ぶ村の女・シノとも会話を交わすようになった。最近顔色が良くなったと言って嬉しそうに語りかけてくる。望東尼は、シノに頼んで筆立てを用意してもらった。姫島での日記を書くためである。
入牢して二十日が経過した頃、獄中の柱に書き込んだ心境が残っている。

次にこの獄舎に入る人よ、耐えがたく辛いと思うのは最初の二十日間だけのことですよと、いとも前向きな歌である。
この頃、囚われの身であった馬場文英が京都の牢獄から釈放されたと、見回りに来た小役人が耳打ちしてくれた。そのうちに、野村の本家からも、差し入れが届くようになった。
「これ、ババには甘すぎて駄目だから、お子たちに食べさせて」
朝食を運んでくる際、シノに差し入れられた駄菓子を差し出した。ある時は、シノが桑野喜右衛門という以前の役人を覚えていると言い出した。
「その者はこの尼の三つ違いの弟だよ」と応えると、「あらまあ」の連発。後は、以前からの知り合いでもあるように、口が軽くなった。厳重に禁止されているはずの蝋燭を、「書き物に必要だろうから」と、こっそり敷き布団の下にしのばせた。夜になって火を灯すと、世界が変わったかのように明るくなった。この句は、人との繋がりの大切さを仏の光に見立てて詠んだ句である。
暗きよの人やに得たるともし火はまこと仏の光なりけり
時間は過ぎていく。狭いながらも獄舎が以前からの住処であるような、居心地に変わるものかと我ながらびっくりする。シノに限らず、寄ってくる主婦や娘とも格子越しに、会話するようになった。一日に一度の役人の見回りさえ気をつけておけば、彼女らとの間に、獄舎の壁はあってないようなものになっていった。
.gif)
姫島の村落
ある日、別の獄に繋がれている囚人が、二人連れでやってきた。脱獄の恐れの少ない囚人に対しては、監視も緩やかになっているらしい。無精髭が顔中を覆う男は、望東尼が旧友ででもあるように、親しげに話しかけてきた。島を囲む海は、何にも増して頑丈な監獄塀の役目を担っているのだ。
ある時は漁師の男がやってきて、釣り船の進水を祝った和歌を詠んでくれとねだった。望東尼は、新しい舟の航海の安全と豊漁を祈念して、和歌を贈った。
望東尼が唐丸籠に乗せられて上陸した際、桟橋で見かけた女の子も気安く話しかけてきた。名前をウメと言い、望東尼のことを「おばあちゃん」と呼んだ。あどけない幼女が、本当の孫のように思えてきた。年が明けると島人たちは、シノを通じて海の幸・山の幸が入った雑煮を運んでくれた。
獄舎には、いろいろな生き物が侵入してくる。ねずみ、百足、蜘蛛、蟻など。いちいち怖れたり怖がっていたら、ここでは生きていけない。彼らも大切な仲間なのだと割り切って、安全な場所に逃がしてやったりもした。

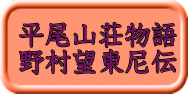
入獄から半年ほど過ぎた慶応2(1866)年6月。幕府による15万の軍勢を擁しての第2次長州征伐が始まった。だがこのとき長州藩にとって、「八月十八日の変」では敵方にあった薩摩藩との間に薩長連合(同盟)が成立していた。そのため、長州征伐の幕府からの命令が出ても、薩摩藩は動こうとしなかった。それでも幕府軍は、四方(小倉口・石州口・大島口・芸州口)から長州軍を攻めたてた。だが攻める幕府軍も、旧式装備では7千の長州軍に勝つことは出来ない。そこで幕府は、将軍家茂の死去を機に征討を中止することにしたのだった。
その時、小倉口の戦いで指揮を執っていたのが高杉晋作であった。
12.gif)
小倉城から持ち帰った戦利品の大太鼓
(下関厳島神社)
時は更に過ぎて行く。慶応2年(1866年)の9月。福岡藩を脱藩した後、長州下関にいた藤 四郎が病床の高杉晋作に告げた。
「平尾山荘の主である望東尼が、筑前姫島の牢に入れられています。いつ何時命を奪われるかも知れません」
老尼の救助を願い出た。玄界島に流された同士2名が、突然首を斬り落とされたことが、藤 四郎の焦りを誘っていたのである。
四郎の差し迫った訴えを聞いた高杉は、望東尼救出を決意した。高杉にとって、わずか10日間の滞在ではあったが、望東尼は命の危機を救ってくれた恩人である。別れ際には、「お世話になったご恩はけっして忘れません」と誓ったうえで、気持ちを吐露する漢詩も置いてきた。望東尼からは、山荘を出る際一晩かけて縫い上げた旅衣を着せてくれた。
山荘を出る際高杉は、福岡藩や長州の俗論派から命を狙われていた。その際、月形洗蔵が主導して福岡藩領から脱出させ、無事長州の同士に引き渡してくれた。長州の正義派は、高杉の帰国後、すぐさま俗論派を追放することに成功したのであった。
藤 四郎から望東尼救出の相談を受けた高杉は、直ちに作戦に必要な同士を集めさせた。まずは、姫島と周辺海域に詳しく、海流や海路、風向きなどに長けた者、脱出に必要な船舶と船頭を都合できる者など、作戦に必要な要員の確保である。
「脱出後は、海の流れと風が頼りだ。対馬藩の浜崎領に行けば、そこには船問屋が2軒あるはず。対馬の同志に手頃な船と船頭を調達するように」
高杉は、頭に浮かぶことを次々に口に出した。
「姫島に上陸する以前に、獄にいる望東尼殿に知らせる必要がある」とも指示した。突然牢獄に突入すれば、望東尼本人も驚くだろうし、救出隊が味方なのか敵なのかさえ疑われるだろう。藤 四郎は、言われた役目を果たせる同志を思い浮かべた。

夏の盛りも過ぎた8月の末。陽が落ちて、出入り口の戸を叩く音がする。望東尼が振り向くと、戸の隙間から紙切れが1枚。「9月10日夕刻、救助に参上 四郎」と書かれていた。「まさか、あの四郎では」と直感する望東尼の心が躍った。慶応2(1866)年9月10日の夕刻であった。
船幅いっぱいに帆を張った船が、姫島の船着場に碇を下ろした。夕飯支度の時刻であり、海辺に人影はない。船から下りたのは男が6人。船には2人の船頭が残った。
1.gif)
牢獄前の庭
男らは、上陸すると3人ずつの二手に分かれて、島の中央に座る鎮山に向かう急坂を登っていった。藤 四郎と博多商人の権藤幸助、それに長州藩士の泉三津蔵は望東尼が入っている獄舎へ。権藤幸助は商人だが、攘夷派の藩士との交わりが深く、藤
四郎に誘われて作戦に参加している。事前に脱獄の予告文を投げ入れたのもこの男である。泉三津蔵は、日頃高杉晋作に仕える長州藩士で、玄界灘の海流や季節風に詳しいことから指名された。
望東尼が繋がれている獄舎に到着した藤 四郎は。周囲の様子をうかがった後、獄中に向かって声をかけた。
「ハハウエ、お迎えにあがりました」。中から呻くような声が返ってきた。
藤 四郎ら3人は、持参した木槌で錠前を叩き壊した。
「おお、四郎かえ」
先を競うようにして侵入してきた3人を迎えた望東尼が、真っ先に質した。
「長州の高杉晋作どのの計らいで、ハハウエを救いに参りました。ここにいるのは、同志の権藤幸助と泉三津蔵です。細かいことは後ほどゆっくりと…。手荷物は最小限にして、さあ、参りますぞ」
促されて望東尼が立ち上がろうとするが、膝に力が入らない。
「おつかまりください、手前の肩に」と、権藤幸助。
船着場まで歩けと言われても、1年近くも座りっぱなしで、足が萎えていて思うように動かない。背中を向けた権藤には、かすかながら見覚えがあった。いつしか平尾山荘に志士らと連れだってやってきたことがある。その時、珍しい茶菓子を差し入れてくれた。
「して…、私をこれからどこに連れて行くのですか?」
「長州の下関まで」
「長州」と聞かされても、そこがどんなに遠いところなのかさえ、考えが及ばない。
陽が唐津の海に落ちていく。近所の民家から漏れているわずかの灯りと、遠くで点滅する漁り火が道標(みちしるべ)であった。背負われて急坂を下りていく際、下から上ってくる女とすれ違った。獄に夕飯を届けに行くシノであった。
「あのう」、見知らぬ男の背中に負われている望東尼に声をかけた。
「おシノさん、もうご飯はいらないよ。わたしはこれから遠いところに行くけれど、心配いらないからね。島のみなさんに、くれぐれもよろしゅう伝えて」
事情を察したシノは、桟橋に急ぐ望東尼を、声を押し殺すようにして見送った。
一方、定番屋敷に向かった小藤平蔵と多田荘蔵、吉野応四郎の3人。小藤は福岡藩を脱藩し、多田と吉野は対馬藩を脱藩した、いずれも長州領内に居留する志士である。定番屋敷に着くなり、小藤平蔵が屋敷の表戸を叩いた。玄関に現れた定番役の坂田が、しきりと小首を傾げている。
「我らは、藩奉行の命により参上いたした。この度、朝廷からの命令があり、入獄している野村望東を釈放するために参上した。尼僧の身柄は、当方で城まで届ける故、心配ご無用」
小藤が、声を大にして相手を威嚇した。眠気覚めやらぬ坂田は、何事が起こったのかさえはっきりしない様子。
「そんなはずはない。囚人の管理は定番役の拙者の仕事。しばし待たれよ。当方より真偽のほどを確かめる故」
「何を申すか!この期に及んで…」
小藤は、坂田と押し問答しながらも、一向に慌てる風はない。
その時である。港の方から「ズドーン」と、銃砲の轟音が響き渡った。
「何事じゃ、あの音は?」
坂田が庭番に質すがはっきりしない。
「困ったご仁じゃ」
小藤は、坂田嘉左衛門を睨み付けた後、多田と吉野を促すと、いっせいに山裾めがけて駆け下りていった。
「どうもおかしい。あの者らは、本当に奉行の遣いなのだろうか。もう一度問い詰めなければ…」
坂田は着替えた後に、目をこすりながら出て行った。坂田が小役人と一緒に船着き場に駆けつけたとき、望東尼らを乗せた帆船は、暮れかかった彼方の仏崎岬に隠れるところであった。
.gif)
姫島から仏崎岬望む
「しまった、遅かったか!」
地団駄踏む坂田嘉左衛門。こうして藤 四郎らによる望東尼救出作戦は成功した。高杉晋作が組み立てた作戦と藤 四郎らの実行力が、見事に的中したのであった。
藤 四郎らは、鎮山の頂が見えなくなって、ようやく帆掛け船の舳先で胸をなで下ろすのだった。
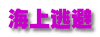
望東尼は、用意されていた布団に横たわったまま、頭上で点滅する星座に魅入っていた。
「こんな一本柱の帆掛け船で、波の荒い玄界灘を乗り切れるのかね。風だって、必ず順風とは限らないでしょう」
「そこは心配ご無用に願います。船は、南から北へ流れる対馬海流に乗っております。それに今は都合のよい南西の風が吹いております故」
藤 四郎が説明した。
「この船に乗っているのは、誰と誰?」
望東尼の問いに藤 四郎は、一人一人を指さしながら答えた。
.gif)
玄界灘
藤 四郎・小藤平蔵(以上福岡藩脱藩者)、多田莊蔵・吉野応四郎(以上対馬藩脱藩者)
泉 三津蔵(長州藩士)、権藤幸助(博多商人)の名前を挙げた。
「今、船はどの辺を走っているの?」
船頭が口を挟んだ。
「先ほど先方で大きな船が横切ったから、玄界島を通過したところですかね」
しばらく沈黙が続いた。気がつけば望東尼は、俯いたまま寝息をかいている。
藤 四郎が声を上げた。
「ハハウエ、拙者はこれから宗像沖の大島に上がります」
「何のために?」
望東尼には訳の分からないことである。
「大島の牢獄に捕らえられている、助作殿を救い出すためです」
「孫の助作ですか?会いたいな」
突然の話に、すっかり目を覚ました望東尼が起き上がった。
「肝心の牢獄が何処にあるのか、わかっているの?」
「それも心配ご無用です。拙者は6年前に、脱藩の罪で大島の牢獄に繋がれたことがありますから」
大島には、宗像大社の中津宮が祀られている。牢獄は、この島の北東部に造られていると言う。
藤 四郎は、権藤幸助を伴って下船した。間もなく戻ってきた時、助作ではないほかの男を連れていた。
「どうしたの、うちの孫は?」と、激しく問い質す望東尼。
「この者の話だと、助作殿は流罪ではなかったのです。城下の枡木屋に入れられたままだそうです。この者は、やはり脱藩の罪で流罪になった澄川洗蔵と言います。脱獄を望んだので連れて行くことにしました。ハハウエには、期待だけ持たせて、お気の毒です」
一同、うなだれる老尼を励ますばかりであった。
大島を離岸した船は、再び波荒い玄界灘に出た。南西の強い風を受けて、時を待たずに響灘へと突き進んだ。
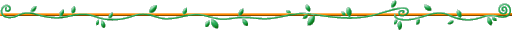
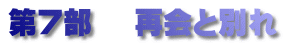

望東尼らを乗せた帆船は、波荒い玄界灘から穏やかな響灘へ。更に馬関海峡(関門海峡)から吐き出されてくる船群を横目に、その先の小瀬戸へと進入していった。
「もうすぐですけん、辛抱してください」
藤 四郎が、望東尼の背中をさすりながら励ました。慶応2年9月17日の夜中である。船は長州藩士の泉三津蔵に先導されて、竹崎の港に着岸した。丸一昼夜の船旅であった。着いた船着場は、白石正一郎邸の浜門(裏門)であった。
.gif)
下関竹崎の港
白石正一郎とは、下関界隈で荷受け問屋を営む豪商である。白石のもう一つの顔は、尊王攘夷派の志士たちの強力な後ろ盾でもあった。白石が世話した主な者をあげるだけでも、西郷吉之助(隆盛)や高杉晋作、坂本龍馬、平野国臣などそうそうたる顔ぶれである。
白石正一郎は、夜中であることも厭わず望東尼らを出迎えた。
「ようおいでなさった。尼どののことは、高杉さんからも、くれぐれもよろしゅうと頼まれております。遠慮なさらず、まずはお身体をお労りください」
主人は、日頃客人が使う離れの間に案内させた。聞きつけて集まってきた若い志士らも、長期の獄中暮らしで弱りきった望東尼に対し、必要以上に気を遣った。
望東尼は、そこにいるはずの人がいないことが気になった。平尾山荘で別れた高杉晋作のことである。高杉は、既に近くの商人入江和作の家に移動していた後だった。
その瞬間も、長州軍は馬関海峡を渡った向こうの小倉口で、幕府軍と激戦中であった。長州藩の指揮を執っていた高杉晋作は、疲労も重なり急遽戦列を離れて下関に戻っていた。望東尼らが白石邸に到着する数日前である。

旧白石邸の門構え
白石邸の女たちが、総動員で望東尼の入浴や着替えを手伝った。虫けらのような扱いを受けた姫島での獄中暮らしが、作り話ででもあったかのように思える待遇である。用意してくれた布団に横たわった途端、意識は遠い夢の世界に迷い込んでいった。気がつけば、陽は真上に上がっていた。枕元には藤
四郎が座っている。
「気がつかれましたか、ハハウエ。相当にお疲れでしたね」
望東尼が2日間眠ったままであったことを、藤 四郎が告げた。
.gif)
白石正一郎邸跡
「ここはどこ?」
下関の白石邸に着いたこともすっかり忘却の彼方に遠ざかっている。姫島での島民との語らいや、土間に茣蓙1枚の寝床を敷いて過ごした1年間。獄中に忍び込んでくる蜘蛛や蠅などとも、殺生を避けながらうまく付き合ってきたこと。遠くに見える対岸の灯りや居座る浮嶽の姿が、走馬灯のように脳裏を駆け巡った。大島での助作奪還の失敗も、下関上陸後白石邸の主人が親切に出迎えてくれたことも、女たちに体を洗ってもらったこともはっきりとした記憶から遠ざかっている。
「ここは、竹崎の浦(現下関市竹崎町)で荷受け問屋を商う小倉屋さんのお屋敷ですよ。脱獄を指導してくれた高杉さんの口利きで泊めてくださったのです。ご主人の白石さんは、ただ今遠方にお出かけだそうです」
白石邸は、この時代商家には珍しい書院造りの建物であった。
「それで、あなた方は、どのようにして私を助け出したのですか」
藤 四郎らは、望東尼を救い出すことに必死で、これまで肝心のことを本人には伝えていなかった。
「実はですね」と前置きして、高杉晋作の枕元に藤 四郎ら6人の実行部隊が集まったことから話し始めた。
「6人は、長州を出て浜崎(現唐津市)の対馬藩領内宿屋に集合しました。決行の6日前です」
浜崎領は、幕府にとって江戸・大坂への積み出し港として重要な藩領の役目を担っていた。そのため、港から鏡山に向かって商家が連なっていた。
対馬藩の尊皇攘夷派同志は、10人以上が乗船できる帆船と海流と風を読み取れる船頭2名を調達した。浜崎の港からは、天気さえよければ、姫島が見通せる位置にある。彼らは、島影が確認できる日を待って出帆した。

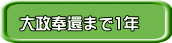
「して…、高杉さんは今どこに?」
望東尼が一番知りたいことであった。
「最近まで、高杉どのもこの白石さまのお屋敷におられました。先の幕府との戦い(小倉口)で陣頭指揮を執られましたが、途中病がひどくなって、やむなく帰ってこられたのです。拙者ら6人に、ハハウエの救出作戦を指導なさった場所はこのお屋敷でした。その後、ここを離れて、桜山と言うところで療養なさっておられます」
「して、高杉さまの看護はどなたがなさっているのかしら」
.gif)
高杉晋作療養の地
聞きづらいことを聞いていると、望東尼自身は気づいていた。
「今一緒におられるのは、おウノさんというお方です。齢は22才だと聞いています。医者の石田精逸さまののおすすめで、桜山付近の『東行庵(とうぎょうあん)』にお住まいだそうです。東行とは、高杉殿の別の名前です」
そこまで聞いたところで、頭痛が激しくなって話は途切れた。獄中や脱獄の際の長船旅での疲れで寝込むことになり、望東尼は高杉を訪ねる気力さえ失せかけていた。
下関に着いて1ヶ月が経った10月中旬。平尾山荘から高杉を送り出してから2年が経過している。
そんな折、白石邸に滞在する望東尼を珍客が訪ねてきた。来訪者は小田村文助と名乗る武士である。対面しても、すぐに誰だか思い出せなかった。
「太宰府の延寿王院の門前でお会いした折り…」
そこまで言われて、記憶が蘇った。あれは、1年半ほど以前で、境内の梅が咲き始めた頃であった。延寿王院に幽閉中の三条実美卿に挨拶を済ませて表門に出たところで、見知らぬ武士に声をかけられた。男は長州藩士の小田村文助と名乗っていた。その時の侍である。
「本日は、藩主からご下命を受けた件をお伝えするために伺いました」
突然、「藩主」と言われても、返答のしようがない。
「藩主より、お尼どのに特別の配慮をなすようにとの命を受けました故」
藩主よりの配慮の命とは、「望東尼に応分の待遇を与えること。身の回りの世話をする娘をつけること」であった。地獄から天国へとはこういうことを指すのか。長州藩主の意図を完全に理解しきれないまま、申し出をありがたくお受けすることにした。小田村文助は、翌年9月、藩命により「楫取素彦(かじとりもとひこ)」と改名している。高杉亡き後の楫取は、明治時代を代表する官僚であり政治家となって後世に名を残した。特に群馬県政(知事)として富岡製糸場を見事に立ち直らせた実績は、後の世まで語り継がれることになる。
「尼どのから受けたご恩は、長州藩として決して忘れてはならないことです」
小田村は、深々と頭を垂れた後去って行った。小田村が告げた望東尼に対する長州藩からの「応分の待遇」は、後日「二人扶持」支給ということになり、生活の保障を約束するものである。


下関上陸から1ヶ月経った慶応2年9月末頃、望東尼はようやく疲れと頭痛から解放された。そこで思い切って、高杉を訪ねることにした。もちろん、高杉に寄り添うウノとは初対面である。未だ娘盛りの面影を残す、色白で小柄な美人であった。
「お体の案配はいかがですか?」
これからの暮らしのことなどを話題にしているうちに、場がほぐれていった。高杉は、一通りの挨拶を済ました後、今後のことなどについて話しだした。
「今住んでいる桜山には、僕の発案で昨年完成した招魂社があります。ここは、世を変えるために命を惜しまなかった奇兵隊諸君の霊魂を祀るためのお社です。奇兵隊の働きがあってはじめて、長州は幕府の悪性を正すまでの力を持ったのですからな。その陰には、福岡藩や対馬藩諸君の力添えがあったことを忘れてはいけないのです。楫取素彦君にも、その点をくれぐれもと申し伝えております」
望東尼はその時、自分が高杉の看病に尽くすべきだと決心した。
時代は、德川時代の終焉を迎えようとする劇的な転換期にあった。皮肉にもこのとき、高杉晋作の命は幾ばくもなかった。
慶応3(1867)年。270年間続いた德川幕府が崩壊する年に突入したのである。春本番を迎えた2月、望東尼に対して長州藩主毛利敬親から、「二人扶持」を支給する旨正式に伝えられた。これで、異国の地で暮らしていける目途が立ったと一安心する。
去年今年(こぞことし)かなたこなたにまどひつつ徒(いたずら)にのみすぐす春かな
そうなると、筑前国から渡ってきて安全な場所にいる我が身が、もったいないような気持ちにもなる。藤 四郎から得た情報では、孫の助作は大島ではなく、当初から福岡城下の枡木屋の獄に縛られていたらしいとのこと。
望東尼は、白石邸を離れて商家入江和作邸の離れに移った。これも、高杉が声をかけてくれたものであった。高杉も街中の妙蓮寺そばに建つ林算九郎宅の離れに移り住むことになった。高杉晋作、人生最終の居住地である。
111.gif)
高杉最期の居住地
望東尼は、高杉看護のために、林算九郎宅に泊まり込むことにした。それからは、ウノと二人がかりの看病に明け暮れる毎日が続くことになった。
.gif)
高杉辞世の句碑(防府天満宮境内)
だが望東尼の願いも叶わず、高杉の最期の時がきた。望東尼は、枕元に座り込んで、高杉の口もとに耳を近づけた。
高杉は、枯れ枝の如くか細くなった自らの手に筆を載せさせ、辞世の句を詠んだ。

そこまで読み終えて、あとの句を望東尼に託した。

「面白くもないこの世にあって、それでも面白く生きていくにはどうしたらよいものか」と望東尼に問うた。返ってきた句は、「周りがどうあろうと、あなたならどう思うかが大切なことですよ」と応えたのである。あなたは、こんなにボロボロになった身体でも、よくぞこれまで頑張りました、と結んだのだった。
重篤の知らせを聞きつけて、多くの同志が集まってきた。慶応3年4月13日。高杉晋作は大勢の同志に見守られながら、静かに息を引き取った。享年29歳であった。倒幕と「大政奉還」の夢が叶うまで、残すところ半年である。そばで大泣きする同士や望東尼から離れて、愛人ウノは別室で一人すすり泣いていた。

高杉は、多くの同士に見守られて、黄泉の国へ旅立った。夜空のもと下関から小月を経て吉田村まで、6里に及ぶ野辺の送りが始まった。このコースと墓所はすべて、高杉晋作本人の遺言によるものであった。参列者は3000人。全員が松明をかざしての行進であった。清水村の清水山に設えられた墓地に棺が到着したのは、出発から5時間後の夜10時を過ぎていた。
望東尼も、列から遅れまいと必死でついていったが、途中で息切れしてしまった。行列の進む先々で、高杉の死を悼む人々が見送った。望東尼にとって高杉の死は、夫貞貫との永久の別れの儀式とも重なった。
足を引きずりながら入江宅に戻った望東尼は、翌日から呆然と時を過ごす日々が続いた。夫貞貫の死から10年。この間に掛け替えのない人を、何人送り出したことか。そして、自分一人がこの世に取り残されている。
ウノ(出家して梅処尼)は、愛するお方の供養を生涯の務めと決心して仏門に入った。彼女が書き残した文がある。

出家後のウノ(梅居尼)
「高杉は自分にとって「命の親様」である望東尼殿のために、部屋をきれいにしつらえ、何の不足もないようにしました。私は当時二十二、三歳でしたが、既に六十歳を越えていた望東尼殿を母親のように慕い、貴女さまの指示に従って高杉を看病致しました。最期は三人で住んでいましたが、望東尼どのが風邪を引いて寝込んだときなど、三階に望東尼どのが、一階には高杉が寝ていました。私は、高杉と望東尼どのが寝込んだまま詩と歌のやりとりをするので、階段を昇ったり降りたりして、さすがに足が疲れました」
高杉の死後、望東尼は高杉夫人のマサに、次の歌を棺に入れてほしいと託した。
奥つ城(おくつき)のもとに吾が身はとどまれど別れて去(い)ぬる君をしぞ思う
だがマサ夫人は、預かった歌を棺には入れなかった。夫人にも、他人には絶対に見せたくない意地のようなものが存在したのであろう。
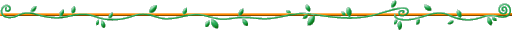
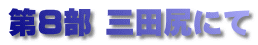

高杉の死後、望東尼はただぼんやりとした日を過ごしていた。楫取素彦が手配してくれた手伝いの娘・トキとの世間話が、唯一の安らぎの時間にもなっていた。
「谷梅(高杉の別名)さんが逝って、もう10日だね。待っていなさるだろうね、わたしが会いに来るのを。早く行かなきゃ」
うつろな目で庭を眺めながら呟いた。そばにいるトキが反応した。
「出かけましょうよ、お供しますから」
1.gif)
高杉晋作の墓所
高杉が眠る吉田村(現下関市大字吉田)まで北へ6里、男の足でも5時間はかかる。若いトキの体力を頼りに朝早く出立して、長府の茶店で昼ご飯をいただいた。宿泊先は、吉田村の庄屋・野原清之助宅。これも、楫取の手回しである。庄屋の家に着いたのは、陽も完全に沈んだ時刻であった。
翌朝、庄屋に案内されて、高杉の墓前に額づいた。
「やっとお会いできましたよ。貴方がいなくなって、本当に寂しゅうございます」
そばにいる庄屋にもトキにも悟られないように、俯いたままで10日ぶりの再会を告げた。事前の心配とは逆に、不思議と涙は出てこなかった。
墓標と敷地は、山県有朋が高杉の愛妾・ウノに贈ったものである。東行の墓名は、高杉晋作の号名。
※山県有朋:明治・大正時代の政治家。元奇兵隊の幹部を経て、維新後首相となる。
高杉晋作亡き後、途方に暮れる望東尼を支えたのは楫取素彦とヒサ夫妻である。病床にあった高杉は、難を逃れて長州に来た望東尼の面倒を、楫取に託していたのであった。楫取は、藩主毛利敬親(もうりたかちか)のそばにあって、藩(国)事に奔走する毎日である。
.gif)
楫取素彦の墓(防府市)
高杉の四十九日法要も過ぎた頃、望東尼のもとに楫取がやってきた。楫取は彼女がより安心して過ごせる場所として、居を山口(現在の山口市)に移すよう促した。「ここなら、妻のヒサも十分にお世話ができる」からとも言ってくれた。山口からだと、萩往還(国道262号)を北へ10里進んだところに萩城が建つ。
山口における滞在先は、湯田温泉郷の吉田屋であった。吉田屋は、この地にあって由緒ある家柄である。身に余る厚遇であると、改めて高杉に感謝するのであった。
吉田屋に落ち着いて間もなく、今度は藩主敬親の遣いが現れた。正装である。遣いは、十三代藩主からだと、一服の反物を差し出した。姫島の牢獄から一転して、藩主からの下賜を授かるとは、想像すらしなかった栄誉であると望東尼は感謝した。
湯田の郷を出て、西へ1里も歩くと鼓の滝に行き着く。名前の通り、飛沫を跳ね上げながら落ちる水のさまは、鼓に合わせて踊る龍のごときである。心行くまで自然の美を楽しみながら、歌人としてこの上ない贅沢な時を過ごした。
わすられぬ心づくしのなかりせば湯田のたゆたに物を思はじ
この歌は、身に余る藩主からの恵みを受けて、湯田の里に落ち着いた気持ちを詠んだものである。
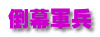
心に落ち着きを取り戻すとすぐに、在りし日の平尾山荘と若き同士たちのことが気にかかる。
特に孫の助作のことが心配でならなかった。だが願いも空しく、助作は城下に造られた獄中で帰らぬ人になったと知らされた。助作の獄中生活は2年近くに及んだと言う。
浮雲はまだ晴れやらぬ身なれども露の心は世には残さず
助作の辞世の句である。嫌疑が晴れないままの身ではあるが、少しも心をこの世には残すまいと詠んでいる。助作に続いて実姉の吉田タカも没したと知らせが届いた。続けさまの故郷での不幸を聞いても、駆けつけられないこの身がもどかしい。
その間にも、世の中の動きは激しさを増していた。倒幕派雄藩と幕府存続を唱える藩が日本列島を二分したまま、一触即発の緊張状態が続いていたのだ。270年もの間続いた德川の世である、それも当然の成り行きなのかも知れない。
慶応3(1867)年9月19日。江戸時代最後の時節となった。野村望東尼は62歳になっている。
坂本龍馬らの仲介もあって、薩摩と長州藩が手を結び、倒幕のための密議が熱を帯びていた。討議に加わったのは薩摩側が大久保利通や西郷隆盛であり、高杉亡き後の長州からは桂小五郎らであった。その密議で、倒幕のための出兵に関する合意がなされた。薩摩藩兵は、9月25日までに三田尻の港に到着し、長州軍と合流する。その後は共に東上して、幕府の主要人物が集まる大坂城を攻める算段であった。長州藩はお隣の安芸藩にも働きかけ、薩長芸の三藩連合軍の出兵という予定もできあがりつつあった。
※薩長同盟:幕末1866年。薩摩・長州両藩が結んだ同盟。両藩は1863年8月18日の政変以来反目していたが、第2次長州征伐の頃から、大久保利通・西郷隆盛ら討幕派が藩論を動かした。土佐藩の坂本龍馬らの仲介により、長州藩の木戸孝充らと折衝して同盟が成立。幕府に対抗して両藩の相互援助を約し、以後武力討幕派の勢力が台頭。
9月23日。望東尼は、三田尻港に向かう長州兵を見送るべく、萩往還に赴いた。倒幕を目指して進む若者らは、かつて平尾山荘に出入りしていた福岡藩の若者と重なる。もう少し自身が若ければ…、自分が病弱でなければ…、それより何より、この身が男であったなら。「間違いなくこのような部隊に身を置いていたであろうに。そして幕府を、この手で打ち負かす役の一翼を担っていたろうに」と、声を震わせながら若い兵士らを励ました。

湯田郷に戻った望東尼を、内儀風女性が待っていた。楫取素彦夫人のヒサである。初対面である彼女、実は高杉晋作や桂小五郎などが学んだ松下塾吉田松陰の実妹であった。
「早くお訪ねするようにと、主人から言われていたのですが…」
遠慮深そうに挨拶する姿は、いかにも楫取素彦の夫人に似つかわしいと感じる。
1.gif)
湯田温泉井上公園(七卿滞在地)
「私も、三田尻におられる荒瀬百合子先生に習って、少しばかりですが…」
和歌を勉強中であると、ヒサは自己紹介した。
「荒瀬先生も、貴女にお会いしたいとおっしゃっていました」
三田尻は、長州軍が薩摩軍と合流する予定の港町である。長州軍の参謀には、ヒサの夫である楫取素彦が任じられているとも聞かされていた。
望東尼は、出来ることなら自分も三田尻まで出かけて、若い兵士らを見送りたいと思っている。三田尻では、防府の天満宮に額づいて、彼らの戦勝を祈願するつもりであった。心を込めて詠んだ和歌を、信仰する天神さま(菅原道真)に捧げて祈願したかった。
「きっと、荒瀬先生も喜ばれますわ。早速使いを出して、その旨伝えておきます」
近々再会することを約束して、ヒサは帰って行った。
9月25日早朝。望東尼は、藤 四郎にも告げず萩往還に向かった。藤四郎に言えば、「ご自身の歳をいくつだとお思いか」、「病み上がりだということをお忘れか」ときつく叱られるに相違ない。自身、年齢や病弱のことを気にしていないわけではない。それよりも、杖一本を頼りの一人旅では、心細くないわけがない。それでも、湯田郷で倒幕の吉報を待つだけでは、その方が耐えがたい。「もしも私が若かったら…、男だったら…」の気持ちがそうさせるのである。
往還に出て鰐石橋を渡る頃には陽も昇り、川底から吹き上げてくる風が冷たかった。萩往還は、日本海側の萩城を起点として、瀬戸内海の三田尻まで、ほぼ直線的に結ばれている。この道は、大名行列のためだけではなく、一般庶民にとっても、「陰陽連絡道」として重要な役割を果たしてきた。

往還を行き交う人々も、商人風であったり武士であったり、百姓や遊び人風まで様々である。一里塚や茶店などもそれなりに整備されていて、老女の一人歩きもさほど心配ではなかった。吉田屋を出て3里ほど歩いて、景勝地の鳴滝に着いた。そこで疲れをとっている間も、日暮れが気になる。途中いくつかの峠道を越えるときなど、足が重くて道ばたに座り込むこともしばしば。夕刻が迫っての、勝坂峠の上りはさすがに堪えた。座り込んでいるところを、通りがかりの百姓の荷車に乗せてもらった。
a.gif)
萩往還勝坂峠
百姓と別れた後は、また一人旅になる。ここで留まっていては、天満宮まで行き着くことなどおぼつかない。気持ちを高めて、また歩き出した。茶をすすりたいが、次の茶店がなかなか近づかない。そんな時は道端を流れる小川の水がありがたかった。老体を心配してくれて、道中の話し相手をしてくれる娘に手を取ってもらうこともあった。
次の峠道にさしかかったとき、追い越してくる屈強な男に「大丈夫かい」と声をかけられた。「松崎の天神さま(防府天満宮)まであとどのくらい?」。力ない声で尋ねると、「3里ほどかな」。男は、「もとは侍だったが、今は浪人」だと断りながら、手を引いてくれた。
「あんたはお坊さんらしいが、その言葉だと地のもんじゃないね」と、男が問うた。「筑前の博多の出ですよ。生業は和歌を詠む歌人ですがね。見ての通り仏に仕える身ながら、なかなか俗世とも縁が切れなくて…」
そんな会話も長くは続かず、分かれ道が来たら男は別の方に走り去った。再び一人旅に戻ると、両の足が絡まって先に進まなくなった。泣きたくなって座り込むと、なぜだか福岡城下の平尾山荘が瞼の裏に浮かんでくる。助作亡き後、野村本家は取り潰しになったのだろうか。早く帰って、私がなんとかしなければ」と、気持ちが空回りする。考えることは、兄弟喧嘩や塾の師に叱られたことなど、遠い昔の出来事ばかり。目の前がぼやけて、膝から崩れかかったところまでは覚えている。
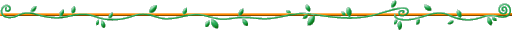
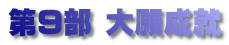


.gif)
防府天満宮
「気がつかれましたか?」
優しい女の声で目が覚めた。だが、声をかけた人が誰だか見当がつかない。
「荒瀬百合子です。楫取(かとり)さまからお知らせを受けて、お迎えに参りました」
「ここは…」
「松崎の天神(防府天満宮)さまですよ」
3日前だったか、楫取素彦夫人のヒサが湯田の吉田屋を訪ねてきた際、防府天満宮にお参りする旨を伝えておいた。その後、荒瀬百合子女史の自宅を訪ねるとも。楫取夫人が早速、連絡してくれていたのだろう。

七日詣での際一日一首奉納した短冊
起き上がった望東尼は、挨拶を済ますとすぐ拝殿に向かった。吉田屋を出る際、心に決めていた「七日詣で」の初日分を実行するためである。
本日9月25日から7日間、欠かさず天神さまに「戦勝祈願」を行い、和歌を一首ずつ奉納することを決めていたのである。神前に深々と頭を垂れた後、道中詠んで書き留めておいた句を神官に差し出した。
もののふのあだにかつ坂かけつつもいのるねぎごと受させたまえ
朱に染められた本殿は、太宰府や京都の北野天満宮とはひと味趣を異にしている。拝殿に上がると、今にも眼前に天神さま(菅原道真)が顔を出しそう。本殿から見下ろす向こうには、町のシンボルである桑山(くわのやま)が居座っていた。更にその向こうに広がる海が、三田尻の港であろうか。
望東尼は、荒瀬百合子が手配した駕籠に乗り、半里先の荒瀬宅に向かった。百合子の夫はかつて商人だったが、先に亡くなっている。残された夫人は58歳。現在歌人として活躍中であった。
百合子は、望東尼に不自由なく過ごしてもらえるよう、離れの間を提供した。望東尼は、疲れをとる間もなく、翌朝から天満宮通いを始めた。境内の手水鉢で身を清めた後、拝殿に上がり精神を統一して二日目の和歌を詠んだ。

薩長盟約によれば、薩摩兵を乗せた船は、9月25日か26日には三田尻の港に到着するはずである。だが、いくら港を望んでも、それらしき船影は現れなかった。荒瀬家の離れで知らせを待つ気持ちも落ち着かなかった。
山口の湯田温泉から遙々三田尻までやってきたのに、見送るべき長州兵が、いつ戦場に赴くのか見当もつかない。望東尼は、案内役として若くて力持ちの使用人友三を付けてくれた。桑山(標高107㍍)登りを手伝ってもらうためである。
「あちらに見えるのが三田尻の港で、その向こう側が中之関です」
「それで、佐賀関は?九州と四国の間の…」
友三の指先を頼りに、視界を巡らせていく。港の向こうが向島。いくつかの小島を飛ばして、その向こうにかすかに見えるのが四国の佐多岬である。目を見開いて眺めたが、薩摩兵を乗せた軍船らしいものはなかった。
.gif)
現在の三田尻港
「やっぱり駄目だね」
深いため息をつくが、薩長盟約のことなど知らされていない友三には、彼女の気持ちを察することは出来ない。
ちぎりおきて帆かげも見えぬ薩摩舟またうき波や立ちかえるらむ
9月28日、荒瀬宅に楫取素彦が山田市之丞と一緒にやってきた。二人は、三田尻に居を構えて、薩摩兵の到着を待っているのだと言う。
「遅いですね、薩摩のお方たち」
.gif)
望東尼が身を寄せた荒瀬家
(現在桑山麓に移築されている)
出迎えた望東尼が呟くと、楫取は「そんなこともあるさ」と、焦っている風にも見えない。「八月十八日の変」以来、長州藩内に漂う「薩摩不審」が、頭をもたげていたのかも知れない。訪問者は、和歌の詠みあいなどした後帰って行った。それから6日経った夕刻、友三が駆け込んできた。
「薩摩の船が中之関に入ったらしいです」と。慌てて身支度を済ますと、再び荷車に乗せられて桑山山頂へ。
「あれが、待ちに待った薩摩船ですか」
桑ノ山の頂上から眼下に見える船を見て、足下が不安定になるほどに気が抜けた。見下ろした向こうに見える船には、薩摩兵が400人乗っている。それから三日後には、更に859人の藩兵が到着したと知らされた。

望東尼は、桑山山頂より薩摩軍船の姿を見届けたあと荒瀬宅に戻ってきた。いかに友三の助けがあっても、62歳という年齢からくる体力には限界がある。床につくと、間もなく始まる新しい世への期待も薄れてしまい眠りこけた。
「どうしましたか、嬉しいはずなのに」
百合子とヒサが部屋に入ってきて声をかけた。眠っているわけでもないのに、すぐには返事ができない。
みよひらくたよりや菊の花ならんあきつむしさへゆたにやどれり
天皇の御代が始まるという知らせを聞くのは、菊の花であろうか、あきつむし(とんぼ)さえゆったりと止っている。
客人の異常を感じ取った百合子は、受け取った歌の清書をヒサに頼んだ。
「頑張ってくださいよ、貴女が命をかけて戦い取ろうとする新しい世が、すぐそこまで来ているのですから」
百合子は、叱るような口調で望東尼を抱き起こした。
間もなく長州藩主から、反物と菓子の見舞い品が届いた。追いかけるように、藩主が指名した開業医師3人が、交代で枕元に付き添うようになった。
「まだまだ、そんなに早くは逝きませんから…」
この期に及んで、望東尼は強がりを忘れていなかった。
望東尼が体調を崩して寝込んでいるその瞬間も、世界はすさまじい勢いで動いていた。まさしく地殻変動である。
長州藩主父子に下されていた官位剥奪の処罰が、天皇の名のもとに取り消された。慶応3(1867)年10月13日である。将軍德川慶喜は京都の二条城にあって、上洛中の諸大名らに大政奉還についての意見を訊いた。そして翌日には、朝廷に対して大政奉還の上表を提出した。
世の動きは、年でもなければ月でもない。日・時刻単位で急変していくのである。薩摩と土佐藩が盟約を結んだ後、土佐藩主の山内豊信(容堂)が、大政奉還の建白書を幕府に提出した。間を置かずして10月15日、朝廷は幕府からの大政奉還上表を受理する。ここに、権力機構としての江戸幕府の使命は、実質的に終了するのである。
望東尼が、死に際まで気をもんでいた「倒幕」と「天皇による治世」の実現は、黄泉の世界に旅立つわずか10日前に実現したのであった。

望東尼は、息を引き取る寸前まで、和歌を詠むことにこだわった。次が、人生最期の歌である。
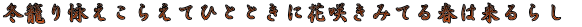
冬籠もりをして、こらえにこらえていた花が一斉に咲き満ちる春の到来です。(防府野村望東尼会=解釈)
駆けつけた藤 四郎の手を握り締めて望東尼は、絞り出すような声で訴えた。
「死ぬ間際に、四郎に言い残したいことがあります」
そこまで言って、喉が詰まり咳き込んでしまった。それでも藤 四郎は、辛抱強く次なる言葉を待った。
「私が死んだら後の遺体は、桑山の麓に埋めておくれ。これは、お世話になった長州への、せめてもの私の気持ちです」
望東尼は、生前博多の妙光寺に自分の墓を建てている。妙光寺は、野村家の菩提寺であり、夫貞貫が死んだ折、そばに置いてくれるよう住職に頼んで建てたものであった。それでも、自分の骨を野村家の菩提寺まで運んでくれとは言わなかった。
「私は、高杉さまや長州の方々から受けたご恩を決して忘れませんから」と言いたかったのだろう。
「それから…もう一つ。叶うものなら、死ぬ前に一度、海の向こう(九州)のお国に戻りたかった。あの平尾山荘の畳の上で死にたかった。喧しいほどの小鳥たちの鳴き声を聞きながら…。これだけは、かつて福岡の地で過ごした四郎にだけ言い残しておきたかったことです」
そこでまた、望東尼の声が止った。
「ハハウエには、もうしばらく生きていて欲しいです。貴女の願った夜明けは、すぐそこまで来ているのですから」
11.gif) .gif)
望東尼辞世の句碑(防府市桑山麓)
小刻みに震える望東尼の手を握り締めながら、藤 四郎が呟いた。そこにヒサが入ってきて、話は途切れた。二人だけの会話は、筑前の福岡藩で過ごした者にしか通じない情感であったろう。地獄だった筑前姫島の牢獄から救い出された後。長州に来てからは、一挙に天国に昇ったような待遇をいただいた。こちらの皆さまに、これ以上の贅沢を言える立場などあろうはずもない。でも本音は、死ぬときくらい、身内の者たちに囲まれていたかった。それが偽りのない気持ちでもあった。
「必ず、必ず、私が馬関海峡(関門海峡)の向こうまでお連れしますから。その間、あまり遠くへ行かないで、待っていてください」
藤 四郎は、向かい側に座っている荒瀬百合子と楫取ヒサに気づかれないよう、俯いたままで望東尼に話しかけた。
荒瀬百合子と楫取ヒサの献身的看護もあって、望東尼の容態は奇跡的に快復するかに見えた。が、すぐに危篤に陥る。その繰り返しが幾度も続いた。そして、周囲の者の問いかけにも反応しなくなる。慶応3(1867)年11月6日夜の五つ半(午後9時頃)だった。つきっきりの医者が首を横に2度振った。望東尼が永遠の眠りについたのである。62年の生涯であった。
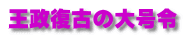
望東尼の死後7日経って(11月13日)、薩摩藩主・島津忠義は、西郷隆盛以下3000人の藩兵を従えてお国を出立した。4日後の17日には、三田尻港に着岸して、先着の軍兵と合流する。11月23日には、錦の御旗をおっ立てて京都に入ったのである。
薩長同盟成立を仲立ちした坂本龍馬と中岡慎太郎が、京都河原町の近江屋で暗殺されたのは、その少し以前の慶応3年11月15日であった。
一方長州藩の軍兵は、1200人を乗せて三田尻港を出港し、西宮に留まって陣を構えた。続いて安芸藩も、11月28日に300人の軍兵が京都に入っている。
運命の12月9日は、十五代将軍德川慶喜が朝廷に対して政権を返上する歴史的な日になった。御前会議を開いて王政復古の大号令が発布された。ここに、江戸幕府の消滅と明治維新・新政府の第一段階が始まった。望東尼が死去して1ヶ月後のことである。
幕府による政権返上のその内容とは…
幕府・将軍職の辞職
京都守護職の廃止
摂生・関白の廃止
新たに、総裁・議定・参与の設置
というものであった。
望東尼は、浄土への道すがら、どのあたりでこの「大号令」を聞かされたのであろうか。そしてもう一つ。心から気にしていた、三条実美以下七卿は。慶応3(1868)年12月27日にすべての罪が許され、太宰府を発って京都に帰還したのであった。

国家体制が大きく変動する中、望東尼の葬儀は、桑ノ山麓の正福寺(禅寺)で執り行われた。故人に付けられた法号は、「始本院向陵望東大姉」。棺は多くの長州藩士や関係者に見守られて、桑山へと向かった。遺言通り遺体は火葬にはせず、桑山山麓に埋められた。これらすべての行事は長州藩の仕切りで進み、費用も長州藩主の毛利家が負担したとのこと。
12.gif)
野村望東尼の墓(桑山山麓)
その後、桑山大楽寺境内に、「正五位野村望東尼之墓」と刻した華々しい墓碑が建てられた。彼女が死去した後も、高杉の危機を救ってくれた恩を忘れない、長州人の心意気であったろう。
.gif)
下関から門司港望む
時は更に進んで、明治20年代の中頃。歳の頃なら五十半ばの男が、徳山からの連絡船に乗り込んだ。船は穏やかな関門海峡を門司港に向かっている。心地よい海風を受けているのは、望東尼の最期を看取った藤
四郎であった。
息を引き取る間際に交わした、「必ず、馬関海峡(関門海峡)の向こうまでお連れしますから」の約束を果たすべく、ふるさと筑前への旅であった。望東尼の死後今日までの藤 四郎は、既に故人となった高杉晋作や楫取素彦などに、少しなりとも恩返しをと務めてきた年月であった。
顔を上げると、前方に門司の港が見えてきた。
「さあ、貴女が待ち望んだ筑前に着きますよ」と、手元の小箱に話しかけた。白布に包まれた小箱の中には、桑山山麓の土と彼女の辞世の句が納められていた。おわり
|