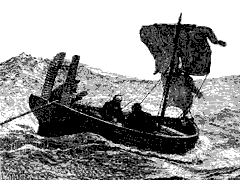
救命ボート上の惨劇
『空飛ぶモンティパイソン』の第2シーズンは、女王陛下に人肉食をぶつけるというトンデモなくブラックな回で幕を下ろすが、その中の、救命ボート上で「俺を喰え」「いいや、俺を喰え」と乗組員が云い争うスケッチの元ネタが、このミニョネット号の事件である。
1884年5月19日、ミニョネット号というヨットがサザンプトンを出帆した。行き先はオーストラリアのシドニーである。
このヨットは在オーストラリアの実業家J・H・ウォントが故郷イングランドとの間を往復するために購入したもので、このたびは試験的な処女航海だった。乗組員は4人。ダドリー船長とスティーヴンとブルックスの船員2人、そして、まだ17歳の給仕リチャード・パーカーである。
航海は当初は順調だったが、喜望峰を経由したあたりから雲行きが怪しくなり、やがて激しい嵐に襲われた。小さなヨットはまるで木の葉のようにいたぶられて浸水、4人は辛うじて救命ボートで脱出した。
本当の災いはここから始まる。どうにか持ち込んだ食料はカブの缶詰2個だけだった。それも4日で喰い尽くし、飲み水も雨に頼るありさまだった。やがて嵐が去ると天日干しの地獄の日々が訪れた。
漂流生活16日目のことである。給仕のパーカーが喉の渇きに堪えられず、海水をガブガブ飲んでひっくり返った。痙攣しながら身悶えている。明らかに瀕死だった。これを為すすべもなく見守っていたダドリー船長がまず切り出した。
「彼はもう助からないだろう。だから、我々だけでも助かるために、彼を食べようじゃないか」
これにブルックスが猛反対した。そんな人の道を踏み外すようなこと、出来る筈がないじゃないですか。
「船長としては全滅させるわけには行かないんだ。それに考えてもみたまえ。君たちには扶養家族がいる。子供たちのためにも生き延びなければならないんだよ」
スティーヴンは渋々ながらも同意したが、ブルックスは頑なに拒み続けた。ところが、ダドリー船長が祈りを捧げてパーカーの喉を掻き切ると、吹き出す血をブルックスも飲んだ。肉も食べたのだ。
彼らがドイツの貨物船モンテスマ号に救助されたのは、5日後の7月28日のことである。
船長たちはパーカーの殺害を隠蔽することも出来たのだが、それは良心が許さなかった。潔くすべてを告白し、ダドリー船長とスティーヴンは殺人の罪で起訴された。一方、ブルックスは不起訴となった。彼はパーカーの肉を食べただけで、殺人には加担していなかったからだ。
弁護人のコリンズは二人をこのように弁護した。
「二人は理由なく殺したわけではありません。必要性に迫られていたのです。それはまさに極限的なものでした。死から逃れる唯一の方法が、一人を犠牲にすることだったのです。他に取るべき道がなかったのです」
彼はまた、黒板に「一人しか支えられない板につかまる溺れた二人の男」の絵を書いて、ギリシャの哲学者カルネアデスの言葉を引用した。
「もし、一人がもう一人を押し退けて溺れさせたとしたら、彼は殺人者でしょうか? そうではないでしょう。彼は自分が助かるために必死だったのです。そして、これと同じことが救命ボートの上でも行われていたのです」
いわゆる「カルネアデスの板」である。これに基づき近代刑法学は「緊急避難」の理論を構築した。すなわち「犯罪に該当する行為であっても、危難を避けるために已むを得ずにした行為であれば違法ではない」という理論である。今日では殆どの法治国家で採用されている。ところが、当時はまだこの理論は論争の真っ只中にあり、確立した通説もなければ判例もなかったのだ(その要件、特に「法益の均衡」に関して争いがあったのだが、その詳細については法律論になってしまうので割愛する)。
結局、イギリス最高法院は法律論よりも倫理的な判断を優先し、被告に死刑を宣告したが、ヴィクトリア女王の特赦により6ケ月の禁固刑に減刑された。妥当な結論と云えよう。