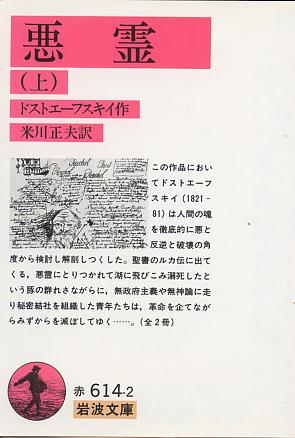
|
『罪と罰』を読んでそれ以上にとりつきにくいそうな『悪霊』を読んでみましょうと思い立ちました。そこで岩波文庫、米川正夫訳を読もうとしたのですが上巻の半分も進まないうちに嫌気がさしてきたのです。自分の読み方が悪いことを棚に上げ、訳者の翻訳がいけないからこうもわかりにくいのだと思ったものですからこんどは新潮文庫、江川卓訳に挑戦しました。あまり代わり映えがしないものだと気がつきましたが、これも放棄するのはあまりにももったいないことなので、ぼちぼちと通り一遍ですが読み終えたのが半年ほど前のことです。
『罪と罰』も三回読んでようやく自分なりの読み方ができたとの気分に到達した経験からこれもやはりもう一度読む必要があります。その前にどうして難解であったのかについて整理しておくことが理解を進めるような気がしました。
もっとも基本的な過ちはこの作品の「あらすじ」をはき違えて読んだことにあったんじゃないか。
たとえば岩波文庫版(上)の表紙にあるコピーにはこう書かれている。
この作品においてドストエフスキー(1821ー81)は人間の魂を徹底的に悪と反逆と破壊の角度から検討し、解剖しつくした。聖書のルカ伝にでてくる、悪霊にとりつかれて湖に飛びこみ溺死したという豚の群さながらに、無政府主義や無神論に走り秘密結社を組織した青年たちは、革命を企てながらみずからを滅ぼしてゆく
たとえば新潮文庫(下)の裏表紙はこうだ。
ドストエフスキーは、組織の結束を図るため転向者を殺害した「ネチャーエフ事件」を素材に、組織を背後で動かす悪魔的超人スタヴローギンを創造した。悪徳と虚無の中にしか生きられずついに自ら命を絶つスタヴローギンは、世界文学が生んだもっとも深刻な人間像であり、“ロシア的”なものの悲劇性を結晶させた本書は、ドストエフスキーの思想的文学的探求の頂点に位置する大作である
日頃、血なまぐさい猟奇的殺人事件が日常化し週刊誌なども興味深く読んでいる私には、このキャッチコピーはその延長線にあって刺激的であり読む意欲がむくむくと湧いてきたわけだ。しかも邪悪の権化、破壊の魔神、悪魔の超人であるスタヴローギンの人格を想像し、サイコホラーの人格分析にもあれこれ通じている自信があるものだからとてつもない魅力であって、大いに期待することになったのは仕方がなかった。
読み始める。そりゃあ、スタートからこのエキセントリックな本筋にはいるわけはないからはじめはさらさらと入ってさてどこからこの山の入り口にたどり着くのだろうとどんどんどんどんページを繰るのでした。仲間割れの「陳腐な殺人事件」がでてきたわいと気がついた時には終わっていたというのが実感でしたね。
「ロシア的な風土なかで生煮えの西洋革命思想が自滅する」というようなキャッチコピーであれば端からこんな読み方はしなかったと反省しましたよ。もっともこんなコピーではわれわれ俗人が手を伸ばすチャンスがあまりないでしょうがね。
読み方にあった問題のもう一つは主人公がスタヴローギンだと思いこんでしまったところにあったようです。
2005/10/06
こんなお便りをいただきました
ブログ村経由で辿りついたイーゲルと申します。『悪霊』は9度目の挑戦でようやく一周読んだ程度、もう「ナナカマド以下」という位置づけで息切れしながら読みました。
私が読んだのは新潮文庫版なのですが、文庫裏の作品紹介だと、どエライ悪の権化スタヴローギンが何かやらかしてくれるのかと期待して読んでいたら…あら?という感じでしたね。
2005/10/07
ところで『悪霊』の主人公はだれだ?それはスタヴローギンに違いはない。
だから、岩波文庫(下)の表紙にはこうある。
非凡な頭脳と繊細な感受性そして超人的な体力に恵まれながら、思想も感情も分裂し、悪徳と虚無に生きる呪われた男スタヴローギンを主人公に狂信的革命主義者ピョートル、ロシア正教に根ざす民族主義者シャートフ、徹底した反宗教的個人主義に生きるキリーロフら、革命思想に憑かれた人間たちの破滅を描く現代の黙示録。
|
ここには破滅するひとたちの代表が4人あげられています。このキャッチコピーを作文した専門家にとっては常識なのかもしれませんが、さらりと読んだ私は「悪徳と虚無に生きる」とか「狂信的革命主義者」とか「ロシア正教に根ざす民族主義者」そして「反宗教的個人主義」といわれてもそんな都合の良い類型化した表現は作品の中で見あたりませんでした。これは後の時代の人が後に時代に定着した概念をくっつけたものでその当時はここまで断定的に言えるような思想ではなかったんでしょう。そのせいか、実際の小説の中では主人公たちのイメージがキャッチコピーどおりではないようで、そんなにわかりやすいものではないのです。
もっともわかりにくい人格はスタヴローギンでして狂人なのか狂人をよそおい陰で組織を動かす冷徹な革命家なのか、最後まで理解することができません。
むしろ主人公たちのバックにある登場人物、作品の冒頭から登場するスタヴローギンの母親・ワルワーラ夫人やその腰巾着となっているなんともだらしない進歩的文化人・ステパン・ヴェルホーヴェンスキーたちに焦点を当てその時代の一方を代表する主人公として読んだほうが現代に通じるおかしさがあって作品の一片鱗かもしれないのだけれど、理解が進むような気がしました。
新潮文庫(上)の裏表紙はこうだ。
1961年の農奴解放令によっていっさいの旧価値観が崩壊し、動揺と混乱を深める過渡期ロシア。青年たちは、無政府主義や無神論に走り秘密結社を組織してロシアの転覆を企てる。聖書に、悪霊に憑かれた豚の群が湖に飛びこんで溺死するという記述があるが、、本書は、無神論革命思想を悪霊に見立て、それに憑かれた人々とその破滅を、実在の事件をもとに描いたものである。
読んでいると彼ら数人の手で本気で「ロシアの転覆を企て」ていたとはとうてい思えないのだ。せいぜい地方都市でちょっと暴走した程度のお騒がせなんですね。日本でもよくあるじゃないですか、せっかくの成人式を茶化して酒の勢いでぶちこわしにする非常識な若者が。それはお仕着せの官主導セレモニーに対する政治的抵抗なんてもんじゃない、単なる場違いの目立ちたがり根性でしょう。それとこれとを同じにしちゃあいけないかもしれませんがね。そして彼らを動かすインタナショナルな秘密結社が背後に存在するのか、それは幻想なのかもしれず、とにかくはっきりとは描かれていません。
だから彼らの革命とか陰謀とかに着目して読むと消化不良になるのです。
そしてもっともわかりにくくしているのはドストエフスキーのこの物語(とくにスタヴローギンの人格)を描く姿勢にあることがわかる。
2005/10/07
|

|
イーゲルさんからこんなコメントをいただきました。
ブログ村経由で辿りついたイーゲルと申します。『悪霊』は9度目の挑戦でようやく一周読んだ程度、もう「ナナカマド以下」という位置づけで息切れしながら読みました。
私が読んだのは新潮文庫版なのですが、文庫裏の作品紹介だと、どエライ悪の権化スタヴローギンが何かやらかしてくれるのかと期待して読んでいたら…あら?という感じでしたね。
やっぱりね。
わかりにくくさせている一つに語り手の「私」があって、いったいぜんたい「私」って何なのかと戸惑わせるんですね。
このストーリーは「私」という一人称の語りで進行しているようなんですが、「私」ってなんていう名前の人かしらと気になるんです。しばらくしてどうやら「G氏」として登場していることがわかる。G氏は進歩的文化人・ステパン・ヴェルホーヴェンスキーのもっとも親しい友人なのだが、「語り部」として読者にむかって登場しているだけでこの物語の出来事には何の影響力も与えない透明な存在なのです。
ミステリーを好んで読書している私は一人称叙述であるとすぐ叙述にひそめたトリックに思い当たり、その語りようにはとても神経質になってしまうんですね。たとえばG氏の、これは断定口調であるから事実を述べているんだ、こっちは「らしい」と推定口調だから事実ではないかもしれない、これは実際に別人が語ったことを自分できいた事実を述べているのだがその語ったことが事実であるとは限らない………とこんな具合になっちゃうんです。ミステリーじゃないのだからなにもそこまで厳密に考えなくともいいじゃないかと思われる方もあるでしょうが、そうすべき理由がないではない。悪霊の化身であるスタヴローギンの人となりはほとんどが「私」が別の人から聞いたそれも噂やさらに人づてに聞いた伝承であって、その表現方法によってスタヴローギンを謎の男にしているわけですが、読み手としましては
「事実はなんなんだ」とか
「ドストエフスキー自身はどういう人物だと述べているんだ」
と突っ込まざるをえないんですね。
それでもよくわからない。
イーゲルさんはこんな推定をしています。
ピョートルがスタヴローギンの奇行に目を付け伝説のイワン王子として祭り上げているだけで、スタヴローギン自身は「マゾ」だと思います。お偉いさんに狼藉を働き、半狂乱(?)の娘と婚約したりと禁忌を破る快感に酔っているだけなのではないでしょうか。
私はなるほどそうかもしれないと思うのですが………。つまりはわかりにくいってことなんですね。そういう読者がいて安心しています。
「私」がクセモノなのはそれだけでないのです。
はじめのうちは出来事そのものに臨場して「私」は語っているのです。ところが
「ここで物語の先行きを考えて読者に予備知識を与えて」
あげましょうなんて読者にもったいぶったサービスのヒントをくれたりするものだから、余計にまぎらわしくなっちゃうんです。
さらに
「私はつぎに、それにつづく諸事件を、今度はいわば事情に精通したものとして、つまり、すべてが解き明かされた現在の立場から書いていく形で、私はこの記録を続けたいと思う」
と突然「私の視点」を変えたりするんです。
そんなら結論を先に教えてくれと叫びたくなる。そして完成された記録の結末を読めばすべては解き明かされると思ってしまう。実はそれは間違いであって「私」は所詮、私に過ぎないのだから、神様ではないのだから、わからないことはわかりませんとして読者を放りっぱなしにするんですね。
読者としての私は普通の小説作法であれば「私」の立場は一貫しているはずなのにと思うわけです。まあ「私」が単にG氏ではなくてドストエフスキーその人の顔が時々出てくるものだと考察はしますがね。変幻自在のドストエフスキーの表現と持ち上げる人はいるようですが、私にとってはそれは消化不良の元ですね。
結局、ドストエフスキーさんよアンタハ何をイイタイノって疑問と同じことなのかもしれません。
再々読するにあたってこれまでの経験からえたこれらいくつかの要点をじっくり心しておきたい。
しかし読み出す前に時代背景だけは勉強しておこうと思います。
2005/10/10
|
時代背景<農奴解放令>
物語は1869年の秋から冬にかけてロシアのある地方都市とその郊外にあるスクヴォレ−シニキという領地を舞台に展開する。この大領地を所有者し、地方政治にも強い影響力を持つ資産家がスタヴローギン家の女主人ワルワーラ夫人である。この地方都市でワルワーラ夫人を中心にやはり大地主の夫人や県知事夫人などカカア天下の上流階級の暮らしぶり、社交界の喧騒、ロシア帝政の末期的動揺が戯画的に描かれる。
彼らの栄華の終焉をつげるかのような農奴解放令が発布されたのが1861年であった。
クリミア戦争での敗北はロシアの後進性を露呈させたが,加えて国内には経済的矛盾と社会的不安が高まっていた。そうしたなかで皇帝アレクサンドル2世政府は,貴族領主の大半が強く反対するなかで,自らイニシアティブをとって農奴制の廃止に踏み切った。しかしこの改革は不十分なものであり、解放後も農民は,重い負担と土地不足に苦しみ、共同体の枠組みにはめこまれ,加えてこの共同体の活動に対する領主側の監督もさまざまな形で存続した。
ワルワーラ夫人たち領主側は収入が減少し、暴動への不安が高まるなど流動化しつつある環境の中で、いまだ地方自治の特権の座でどうにかあぐらをかいていられたというそんな時期である。
なおドストエフスキー(1821−81)の父は1839年、領地の農奴に殺害されている。
余談ですがこれは『罪と罰』を読んだときも感じたことなのだが、登場する女性の意識のレベルが驚くほど高いんですね。日本で言えば江戸末期から明治初期ですよね。カカア天下というレベルじゃあない。単に財力があって婿養子を支配している、その程度ではないことです。若い娘さん、女中、狂女までもが自分の主張を第三者に堂々と発信できるところまで自己確立がすすんでいるんです。フィクションだからってもんじゃないでしょうね。
2005/10/11
|
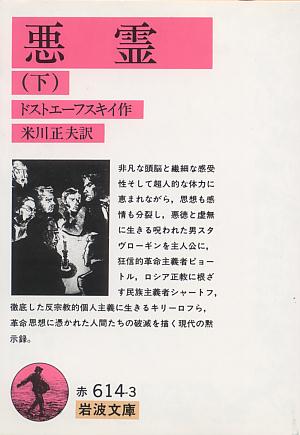
|
時代背景<革命運動>
ロシアの革命思想といえばせいぜい20世紀初頭のボルシェビキ政権を樹立したマルクスレーニン主義を思いつく程度だから、その前夜にあたるこの当時の反政府思想にいたってはまるで見当もつかない。ところがこの小説ではいろいろな登場人物がいろいろな考えを激論し、あげくの果てに内ゲバまで起こる、しかもそれをドストエフスキーのシニカルな色眼鏡をとおして語るのを読むのですから、大変つらいものがあります。
とはいえ革命運動を重要な題材として取り上げているのですから、我流にでも勉強して大筋だけはつかんでおいた方がいいと思いました。
農奴解放令を発布したアレクサンドル2世は先進西欧の合理主義・科学主義による経済発展、つまりロシアの資本主義化をトップダウンで押し進めようとしたんです。西欧化はピョートル大帝以来の潮流で、フランスやドイツ思想の流入に密接にかかわっていたのですが、その動きを批判的にうけとめる知識人が登場するんですね。インテリゲンチャ。ロシア語が語源です。
西欧文明に絶望している政治的人間たちから、ナロ−ドニキ主義という革命思想が生まれていました。この小説でははっきりとは見あたらなかった運動名ですが、物語の背景にあるのだろうと思います。
ナロードニキ主義とは、後進国ロシアが先進資本主義、自由主義的西欧を拒否し、ロシアの共同体的伝統を手がかりとして、これに先進西欧の生み出した社会主義思想を結合することによって、資本主義発展の道を通らないでも、一挙に社会主義に進みうるし、進まねばならないとする思想です。
『悪霊』は1872年に書かれています。この運動は1861年以後の農奴解放の実施期に展開され,これが広範なひろがりをもち、一世代の青年・学生の運動となったのが1870年代だそうですから、まさに『悪霊』が書かれた時期にあたります。この運動が先鋭化すると強固な秘密結社を各地の農村に組織し工作宣伝活動を活発に行うようになるのですが、『悪霊』はこの組織を強くイメージしているところがあります。
さらに過激な分子は権力との直接闘争を主張し、アレクサンダー2世を暗殺するのですが、これは1881年のドストエフスキーが亡くなった歳にあたります。1972年に書かれた『悪霊』が後に「革命運動の果てにある地獄図を予言した書」などともっともらしい評価がでてくる端緒でもあったわけです。
そういえば、若いころの学生運動とかかわりがあった当時を思い出しますな。
ところで『悪霊』では革命運動、革命思想を批判的にとらえるのが一つのテーマだとする見解があるが、必ずしもそうとはいえないのじゃあないか。
先進西欧の合理主義・科学主義をそのまま受け入れる大きな流れがある。、一方それとはなじまない慣れ親しんだ農耕文化、すなわちロシアの国民性がある。後者は前者に飲み込まれようとしている。ロシアを愛するものたちはどうすればいいのか。どうしようもないところにある苦悩。ここが肝心なところではないかと今予感するわけです。
2005/10/12 |
こうした反政府思想の広範なたかまりの中で文壇デビューまもない20代のドストエフスキーが直接巻き込まれた政府による弾圧事件がありました。ペトラシェフスキー事件です。
外務省翻訳官・ペトラシェフスキーの家に若いインテリゲンチャが集まって、フランスの空想的社会主義者フーリエやドイツの進歩的哲学者フォイエルバハの著書などで議論していただけだったようです。メンバーは役人、教師、作家、芸術家、学生、将校など、この小説でいえばトホホ人間のステパン先生の周囲で集まったお友達の蘊蓄披露の会がイメージできます。そこにはドストエフスキーが加わり『悪霊』の主役・スタヴローギンのモデルになったスペシネフも参加していたのです。ドストエフスキーはここでロシア正教を批判したベリンスキーの手紙を朗読している。
しばらくして一部の急進的やつらが農民蜂起や秘密文書の印刷、配布ってなことまで論じるようになったものだから、1849年、密告からペトラシェフスキーはじめ大勢のメンバーが逮捕されてしまった。テロ行為などの直接行動を起こしていないにもかかわらずです。ドストエフスキーまでもがロシア正教批判程度の咎で死刑の判決を受ける事件になった。最終的には銃殺刑執行の直前、皇帝ニコライ2世の命により、4年間のシベリア徒刑とその後の兵役に減刑される。
どうやらあらかじめ政府のこしらえた筋書きだったようで反政府活動に対する取締りを今後は厳しくするぞとの警告だったのですね。
このような過酷な精神的、肉体的苦痛が彼のこころをどれほど歪めたことか。そしてこの体験がその後の文学作品へと結晶していくのです。
ところで私の父親のことなのですが、若いころ治安維持法違反容疑で特高に逮捕されたという話を思い出します。ジャンバルジャン物語という紙芝居を子どもたちに見せていたのだそうですが、これは当局を愚弄し、貧乏人を糾合させて世の平穏を乱そうとするたくらみだと解釈されたらしい。一月ほど拘留され、立件不能で釈放されたのですが、この間ひどい拷問にあって半狂乱、しばらく精神病院に入院したそうです。
次ページへ |

